おすすめのメール誤送信対策ソフト8選|選ぶ際の比較ポイントも解説
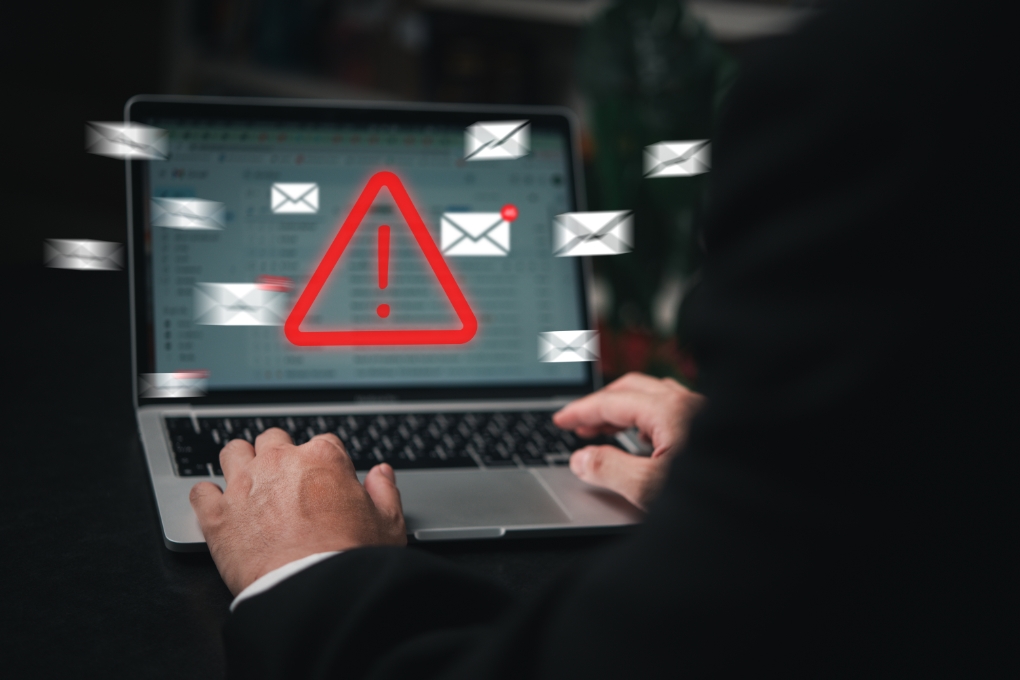
Check!
- メール誤送信対策ソフトは、機能やメールシステムへの対応可否を確認して選ぶ
- 多くの社員が利用するため、簡単な操作性やモバイル対応の可否も確認するのがおすすめ
- 導入後はメール送信業務が煩雑になることもあるため、仕組みや使い方を周知する
メール誤送信対策ソフトを利用すれば、メール誤送信による情報漏洩やセキュリティインシデントを防止し、メール業務の安全性を向上できます。この記事では、おすすめのメール誤送信対策ソフトや選ぶ際の比較ポイント、導入時の注意点などを解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
メール誤送信対策ソフトでメール業務の安全性を向上

メール誤送信対策ソフトは、メールの送信時に起こりうる誤りを未然に防ぐためのツールです。送信先の宛先や添付ファイルが正しいかどうかの確認や、送信ミスを防ぐためのポップアップ表示など、様々な機能を備えています。
このソフトを導入することで、情報漏洩やセキュリティインシデントを防止し、メール業務全体の安全性を向上できます。この記事では、おすすめのメール誤送信対策ソフトや選ぶ際の比較ポイント、導入時の注意点などを解説します。

メール誤送信対策ソフトとは?機能やメリット、比較のポイントも解説
メール誤送信対策ソフトとは、その名の通りメールの誤送信を対策するためのソフトです。この記事では、メール誤送信対策ソフトの機能や導入のメリット・デメリット、ツールを選定する際の比較ポイントなどについても詳しく解説していきます。
メールの誤送信が発生するパターン
メールの誤送信は誰にでも起こりうることですが、特に生じやすいパターンとして、送信先が異なっていたり、社内のセキュリティポリシーに違反しているケースが挙げられます。以下では、これらについて詳しく解説します。
送信先の誤り
メールの宛先がそもそも間違えていると、気付かずに誤送信が発生する可能性が高いです。例えば、名刺などを見ながらメールアドレスを手入力する場合、打ち間違いによって、別のアドレスに送信してしまうリスクがあります。
また、宛先を途中まで入力すると自動でサジェストしてくれる機能は、よく確認しないと異なる宛先を選択してしまうケースも多いです。サジェスト機能は、誤送信を招きやすいメールソフトの機能でもあるため、送信する前に必ずチェックをすることが大切です。
社内のセキュリティポリシー違反
添付ファイルや重大な内容のメールを送信する際に、ファイルの暗号化や承認フローといったルールを設けている企業は少なくありません。
しかし、メールを早く送信しなければならないといった理由でこれらを省略してしまうと、社内のセキュリティポリシー違反に触れるだけでなく、個人情報や機密情報を削除しないまま誤送信してしまうリスクがあります。
これは情報漏洩にも繋がり、企業の信頼性にも悪影響を及ぼします。誤送信を防ぐためには、メールの送信に余裕を持ち、社内で決められたルールを厳守することが重要です。
メール誤送信対策ソフトのメリット
メール誤送信対策ソフトを導入することで、ヒューマンエラーの防止に繋がります。上述したように、メールの誤送信は送信者の人的ミスによって発生するケースが多く、注意していても完全に防ぐことは難しいものです。
しかし、メール誤送信対策ソフトには、宛先やメールの本文確認機能が標準で備わっているため、ヒューマンエラーの発生を最小限に抑えられます。また、送信後でも一定の時間内なら送信を取り消せる機能もあり、万が一誤送信してしまった場合でも安心できます。
メールを誤送信してしまうと、取引先への連絡や謝罪といった対応に追われ、人的コストや手間などがかかります。メール誤送信対策ソフトは、誤送信を防ぐことでこれらのコストカットも図れるため、費用対効果の高いツールと言えます。
メール誤送信対策ソフトは機能や自社環境への適合性で選ぶ

メール誤送信対策ソフトを選ぶ際には、必要な機能を備えているか、利用中のメールシステムに対応しているか、自社のセキュリティ要件を満たしているかの3つのポイントを確認することが重要です。
これらのポイントを押さえて、ソフトが実際に自社で適切に機能するかどうかを判断しましょう。次の章では、これら3つのポイントについてそれぞれ詳しく解説していきます。
【重要なポイント3つ】
- 必要な機能を備えているか
- 利用中のメールシステムに対応しているか
- 自社のセキュリティ要件を満たしているか
【その他の比較ポイント】
- 簡単に操作できるか
- モバイルに対応しているか
- 十分な費用対効果が見込めそうか
メール誤送信対策ソフトの選び方で重要な3つのポイント

メール誤送信対策ソフトを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。以下では、これらの重要なポイントについて詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
メール誤送信対策ソフトの選び方で重要な3つのポイント
必要な機能を備えているか
メール誤送信対策ソフトに必要な機能が備わっているかを確認することは非常に重要です。主な機能として、宛先や本文の確認、送信後の取り消し、送信先に関する注意喚起などが挙げられます。
必要な機能が揃っているかを確認して、適切なソフトを選びましょう。以下の表は主な機能の概要です。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 宛先確認 | メール送信ボタンを押すと、本文や宛先、CC、BCC、添付ファイルの内容が自動的に確認され、宛先を再確認 |
| 本文確認 | メールの本文をチェックし、ポリシー違反があれば送信をブロック |
| 送信後の取り消し | 送信後でも一定時間内であればメールを取り消せる |
| 送信先に関する注意喚起 | メール送信前に確認手順を追加し、ポップアップを表示 |
| 送信制限 | フリーメールや特定の条件を満たすアドレスへの送信を制限 |
| 開封制限 | メールを開封できる受信者の数やそのタイミングを制限 |
| 自動BCC | 一斉送信時に自動的にBCCに追加して、個人情報の漏洩を防ぐ |
| 添付ファイルの暗号化 | 添付ファイルを自動的に圧縮・暗号化 |
| 承認 | 上長やセキュリティ担当者が内容を確認・承認後に送信 |
| 多言語対応 | 日本語、英語、中国語など複数の言語に対応 |
利用中のメールシステムに対応しているか
メール誤送信対策ソフトを選ぶ際は、現在利用しているメールシステムに対応しているかを確認することも大切です。例えば、OutlookやGmailなどは多くの企業で利用されていますが、互換性がないとソフトが正しく機能しない恐れがあります。
自社で採用しているメールシステムに対応していない場合、メールの誤送信対策が十分に行えない可能性もあります。そのため、導入前には必ずベンダーに確認し、使用中のメールシステムとスムーズに連携できるかどうかをチェックしておくことが重要です。
自社のセキュリティ要件を満たしているか
メール誤送信対策ソフトを選定する場合、自社のセキュリティ要件を満たしているかどうかも確認する必要があります。どんなに便利な機能を備えていても、ソフトウェア自体が十分なセキュリティ対策を講じていなければ、情報が漏洩するリスクがあります。
特に、ベンダーがどのような体制でデータ保護を行っているかや、セキュリティ対策が自社のポリシーに適合しているかを確認しましょう。適切な対策が施されているソフトを選ぶことで、より安全な業務運用につながります。
メール誤送信対策ソフトのその他の比較ポイント

メール誤送信対策ソフトを選ぶ際、操作のしやすさやコストパフォーマンスも重要な比較ポイントです。ここからは、メール誤送信対策ソフトのその他の比較ポイントについて詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
メール誤送信対策ソフトのその他の比較ポイント
簡単に操作できるか
メール誤送信対策ソフトは、多くの社員が日常的に使用するため、誰でも簡単に操作できることが非常に重要です。操作が複雑なソフトウェアを選んでしまうと、誤操作が増えるリスクが高まり、かえって業務の効率を下げてしまう可能性もあります。
また、部署や社員によっては、大量のメールを送信・返信しなければならないことも少なくありません。毎日の業務で使うツールが扱いにくいとストレスがたまり、社員の負担も増えてしまいます。
例えば、ファイルの暗号化を簡単にできる機能があれば、メールのやり取りが多い場合にも手間を抑えられるでしょう。直感的に操作できるシンプルな設計のソフトを選ぶことで、結果として人的ミスの削減にも繋がります。
モバイルに対応しているか
最近では、外出先や自宅からモバイル端末でメールを送信する機会も増えています。そのため、メール誤送信対策ソフトがモバイル対応していると社員の利便性向上に繋がります。
モバイル対応しているメール誤送信対策ソフトを選ぶことで、スマートフォンやタブレットからも誤送信防止機能が適切に働き、宛先確認や送信内容のチェックなどがスムーズに行えます。
モバイル環境でも簡単に使えるソフトを導入すれば、どこにいても安心してメール業務が行え、業務の効率化も図れます。柔軟な働き方をサポートするためにも、モバイル対応かどうかを確認することが大切です。
十分な費用対効果が見込めそうか
メール誤送信対策ソフトは、月額や年額で料金が発生するため、予算に対して十分な費用対効果が見込めるかどうかを確認しましょう。どれだけ優れた機能を備えていても、企業の予算に合わなければ導入は難しくなります。
ソフトの導入によって、どの程度のリスク削減や業務効率化が見込めるかを具体的に考え、コストと効果のバランスを見極めましょう。
たとえば、ソフトの導入で日常的なメール業務が効率化すると、長期的には業務時間の短縮にもつながり、結果的に高い費用対効果に期待できます。予算に見合ったコストパフォーマンスの良いソフトを選ぶことが大切です。
おすすめのメール誤送信対策ソフト8選
株式会社インゲージ
Re:lation
ここがおすすめ!
- 送信前チェック機能や脱PPAP対策・セキュリティ対策などの機能が充実
- メール誤送信対策だけでなく、案件管理や顧客管理も行える
- 業務改善につながる分析や返信までにかかった時間などの評価機能を搭載
ここが少し気になる…
- メール誤送信特化型ではなく、問合せを一元管理したい方向け
HENNGE株式会社
HENNGE One
ここがおすすめ!
- 添付ファイルのクラウドストレージ格納やBox格納など「脱PPAP対策」に対応
- 条件に応じ、一時保留や承認・削除が行える
- 大容量ファイルの送受信やクラウドストレージの外部共有コンテンツ管理が行える
ここが少し気になる…
- アクセス管理や標準型メール攻撃訓練機能が欲しい場合は別途契約が必要
株式会社USEN ICT Solutions
メール誤送信防止
ここがおすすめ!
- 添付ファイル忘れなどに気付いた際に送信キャンセルが可能
- 添付ファイルの暗号化にし、その後パスワードを別メールで送信する機能が自動で行える
- 宛先をBCCに強制書き換えが可能
ここが少し気になる…
- 特性や詳しい情報を知りたい際は問い合わせが必要
株式会社ケイティケイソリューションズ
@Securemail Plus Filter
ここがおすすめ!
- 多彩なフィルタリング機能を備え、細かくルール設定ができる
- ゲートウェイ型を採用しており、導入期間を短縮して素早い利用を実現
- 添付ファイルをメール本文から切り離したWEBダウンロード化にも対応
ここが少し気になる…
- 初期費用が必要になり、月額費用は10アカウント単位での契約
NTTテクノクロス株式会社
CipherCraft Mail
ここがおすすめ!
- 確実性による安心感・低コストで導入しやすい
- メールによる情報漏えいを未然に防止することが可能
- 直感的に操作が行えるシンプルなインターフェースで使いやすい
ここが少し気になる…
- 導入する製品によって利用できる機能が異なる
アイマトリックス株式会社
matriXDLP
ここがおすすめ!
- メール送信時に他者、または自身による承認の実行が可能
- 柔軟なポリシー制御や組織情報と連携した承認設定が備わっている
- 先進的な個人情報フィルターによって緻密なチェックと運用・管理負荷の低減を実現
ここが少し気になる…
- 料金を確認するには問い合わせが必要
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
GUARDIANWALL MailSuite
ここがおすすめ!
- メールセキュリティの課題をトータル支援してくれる
- 1ヶ月間無償で利用でき、その後正規版に切り替えられる
- 「MailFilter」「MailConvert 」「MailArchive」を組み合わせた製品
ここが少し気になる…
- 見積もり依頼をしたい際には問い合わせが必要
株式会社クオリティア
Active! gate SS
ここがおすすめ!
- 利用シーンに合わせて最適な機能を選択できる
- オンラインから30日間の無料トライアルをすぐに試せる
- クラウド型で豊富な機能が揃っている上、低コストで導入できる
ここが少し気になる…
- 利用できるメールアドレス数は10まで
メール誤送信対策ソフトの導入フローと注意点

メール誤送信対策ソフトを導入する際には、明確なフローを持つことが重要です。適切なソフトを選ぶと、誤送信による情報漏洩やセキュリティインシデントを防ぎ、メール業務の安全性を高められます。
以下では、導入のステップを詳しく解説し、注意点について解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
メール誤送信対策ソフトの導入フローと注意点
1. 導入目的に合った製品を選ぶ
メール誤送信対策ソフトを選ぶ際には、まず導入の目的を明確にすることが非常に重要です。例えば、単に送信ミスを防止したいのか、それとも特定の受信者に対してメールを制限したいのかによって、必要となる機能は異なります。
例えば、宛先のミスを防ぎたい場合は送信先の再確認機能、本文確認を効率化したい場合はメール本文の内容チェック機能など、企業によって求められる機能は多様です。そのため、自社の業務フローや課題を把握し、適した機能を持つソフトを選ぶことがポイントです。
2. 無料トライアルで試してから導入する
メール誤送信対策ソフトでは、無料トライアルが提供されている場合もあり、導入前に実際の使いやすさや操作性を確認できます。このトライアル期間を活用して、ソフトが直感的で使いやすいか、社内のスタッフがスムーズに利用できるかをチェックしましょう。
特にメール送信業務が複雑化することなく、効率的に進められるかどうかを見極めるのが大切です。また、トライアル中に得られたフィードバックを基に、製品が自社のニーズに合っているかを再度検討すると、導入後の失敗を最小限に抑えられるでしょう。
事前にソフトの使い勝手を把握しておくことで、社員はいち早くソフトに慣れることができ、社内に定着しやすくなります。
3. 社内に使い方を周知する
メール誤送信対策ソフトを導入した後は、社内のメンバー全員に使い方をしっかりと周知することが大切です。新しいソフトを導入すると、最初はメール送信業務が煩雑になったり、作業効率が低下したりする場合も考えられます。
これらのリスクを防ぐには、社員全員がスムーズにソフトを活用できるように、操作方法や注意点を明確に伝えましょう。特に誤操作や余計な手順が増えないよう、効率的に使いこなすためのトレーニングセッションを実施するのも効果的です。
社員に使い方や仕組みを適切に理解してもらうことで、業務の混乱を防げます。また、導入後のフォローがしっかり行われれば、ソフトの利便性を十分に活かし、メール送信の安全性を確保しながら業務の効率化も図れます。
まとめ

メール誤送信対策ソフトを活用することで、メール誤送信による情報漏洩を防ぎ、業務の安全性を高められます。ソフトを選ぶ際には、必要な機能や使用しているメールシステムに対応しているかをしっかり確認しましょう。
また、誰でも簡単に操作できるものや、外出先でも安心して使えるようにモバイル対応しているソフトを選ぶことも大切です。導入後は、業務が煩雑にならないように社内で使い方を周知し、スムーズに運用できるよう工夫しましょう。
本記事で紹介した内容を参考に、適切なメール誤送信対策ソフトを導入し、メール業務の安全性と効率を向上させましょう。





