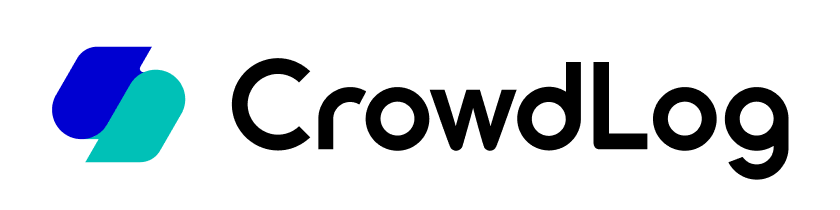おすすめのプロジェクト管理ツール10選|選ぶ際のポイントも解説

Check!
- プロジェクト管理ツールは、搭載機能・導入形態・費用を重視して選ぶ
- 操作性やテンプレートの充実度、日本語対応の可否も確認すると選びやすい
- 導入の際は、従業員へのトレーニングや運用ルールの策定を計画的に行うことが重要
プロジェクト管理ツールとは、プロジェクトの業務進行を可視化・管理するためのツールです。プロジェクト管理を効率化するさまざまな機能を備えています。本記事では、プロジェクト管理ツールを選ぶ際のポイントを交えておすすめのツールを紹介し、導入時の注意点も解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
プロジェクト管理ツールで進捗管理を効率化

プロジェクト管理ツールとは、プロジェクトの業務進行を可視化・管理するためのツールです。プロジェクト管理ツールでは誰が何の作業をしているのか、期限はいつなのかといった情報を一目で確認できます。
プロジェクトが複雑になるほど、プロジェクト管理ツールの効果を発揮します。本記事では、プロジェクト管理ツールを選ぶ際のポイントを交えておすすめのツールを紹介し、導入時の注意点も解説します。

プロジェクト管理ツールとは?ガントチャートなどの手法解説やメリット、ツール選びの失敗しないポイントも
プロジェクトでは「人・もの・お金・時間・情報」など多くのリソースを適切に管理する必要があり、成功率を高めるため、プロジェクト管理ツールの利用が一般化しました。本記事では、プロジェクト管理ツールの基本機能やメリットをご紹介。失敗しないツール選びで着目すべきポイントや導入手順をおさえ、業績向上をバックアップします。
プロジェクト管理ツールは機能・導入形態・費用で選ぶ

プロジェクト管理ツールを選ぶときは、「機能」「導入形態」「費用」の3つを中心に比較するのがポイントです。 プロジェクト管理ツールには多種多様な種類があり、それぞれに特徴や強みがあります。
どのツールを選ぶかによって、業務の進めやすさやチームの生産性に大きな差が出ます。次章では、この3つの観点を1つずつ詳しく解説します。
【重要なポイント3つ】
- 目的に合った機能を搭載しているか
- ツールの導入形態を確認
- 料金体系と費用を確認
【その他の比較ポイント】
- 使いやすいインターフェースか
- テンプレートは豊富か
- 日本語に対応しているか
プロジェクト管理ツールの選び方で重要な3つのポイント

プロジェクト管理ツールを選ぶときは、目的に合った機能があるか・導入形態は適しているか・料金体系は妥当かの3点が重要です。どのような機能を重視するかは、プロジェクトの内容によって変わります。
また、クラウド型やオンプレミス型など導入形態の違いによって、使い勝手やセキュリティ対策も異なります。さらに、ツールごとに料金体系が異なり、コスト面の比較も重要です。この章では、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
プロジェクト管理ツールの選び方で重要な3つのポイント
目的に合った機能を搭載しているか
プロジェクト管理ツールにはさまざまなタイプがあり、すべてのツールが同じ機能を備えているわけではありません。たとえば、チーム全体の進捗を管理したい場合と、個人単位でタスクを整理したい場合では、必要な機能が異なります。
ツールは大きく分けて「多機能型」「タスク管理特化型」「業界・業種特化型」の3つのタイプに分類できます。自分たちのプロジェクトの規模や内容をよく把握した上で、それに合った機能が備わっているツールを選びましょう。
合わないツールを選ぶと、逆に手間が増える原因になるため、目的との一致が大切です。
多機能型
多機能型は、プロジェクト全体を細かく管理したいチームにおすすめです。多機能型のツールには、プロジェクトに必要なあらゆる管理機能がそろっています。主な機能には以下のようなものがあります。
- タスク管理
- メンバー管理
- 予実管理
- 原価管理
- スケジュール共有
- チャットや掲示板などのコミュニケーション機能
- ファイル共有
このように多機能型は、一つのツールでプロジェクト全体を一元管理できる点が特徴です。ただし、操作がやや複雑になりがちなので、小規模なプロジェクトやシンプルな管理を求める場合は、かえって不向きな場合もあります。
導入前にチーム全体で必要な機能を明確にしておくことがポイントです。
タスク管理特化型
タスクを整理して見える化したい場合は、タスク管理特化型が最適です。タスク管理特化型のツールは、個々の作業の進捗を分かりやすく管理できる点が魅力です。
タスクの登録や期限設定、担当者の割り当てなどが簡単にでき、カンバン方式(カードを並べて管理)で表示できるものも多く、直感的な操作が可能です。複雑な機能はなく、使い方もシンプルなため、誰でもすぐに使い始められます。
そのため、小規模なプロジェクトや日々の業務整理、個人のタスク管理などに向いています。ただし、ガントチャートやコスト管理などの高度な機能はない場合が多いため、チームでの大規模な進行管理には向きません。
業界・業種特化型
業界に特化したツールは、専門的な業務管理をスムーズに行いたい場合に向いています。業界・業種特化型のプロジェクト管理ツールは、特定の業界でよく使われる機能を備えており、専門的なプロジェクトの進行に役立ちます。
たとえば、IT業界向けのツールは、バグ管理機能や開発の進捗確認機能、製造業向けでは、部品管理や在庫管理といった機能が用意されています。これらのツールは、一般的な管理ツールではカバーしきれないニーズに対応できるのが強みです。
導入する際は、自社の業務内容とツールの機能が一致しているかどうかをしっかり確認しましょう。特定業種に最適化されているため、業界の慣習に合った管理がしやすくなります。
ツールの導入形態を確認
クラウド型かオンプレミス型かを選ぶことで、運用の自由度や管理体制が大きく変わります。 プロジェクト管理ツールには、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型があります。
手軽に導入してすぐに使いたい場合はクラウド型、セキュリティを最優先したい場合はオンプレミス型が適していることが多いです。導入したい業務や規模、予算などに合わせて選びましょう。
次の項目では、それぞれの導入形態の特徴・メリット・デメリットについて詳しく解説します。
クラウド型
手軽に使いたいならクラウド型がおすすめです。 クラウド型のプロジェクト管理ツールは、インターネット上でサービスが提供されており、PCやスマートフォンがあれば場所を選ばずに利用できます。
ソフトのインストールが不要なため、導入が短い期間で簡単に行えて、常に最新版の機能を使えるのが大きな魅力です。さらに、初期費用を抑えて始められるため、スモールスタートに適しており、導入に失敗するリスクを抑えられます。
また、共有作業やリアルタイム更新にも強く、テレワークなどのリモート業務との相性が良いのも特徴です。ただし、インターネット環境が必須であること、そして機密情報を扱う場合はセキュリティ対策に注意が必要です。
オンプレミス型
カスタマイズやセキュリティを重視するならオンプレミス型が向いています。 オンプレミス型は、自社のサーバーやパソコンにソフトウェアをインストールして使うタイプです。
自社の運用体制やセキュリティポリシーに合わせて細かく設定・管理ができるため、機密性の高いデータを扱う企業におすすめです。また、ネットワークに依存せず安定して使えるのも魅力です。
一方で、導入にはサーバーの準備やシステム構築が必要となるため、初期費用が高くなりやすい傾向にあります。
料金体系と費用を確認
プロジェクト管理ツールを選ぶ際は、コストと使い勝手のバランスを見極めることが大切です。 プロジェクト管理ツールの料金体系は、クラウド型とオンプレミス型で異なるため、慎重な検討がおすすめです。
クラウド型の場合は、一般的に月額固定制と従量課金制があります。月額固定制は、利用人数に応じた一定の金額を毎月支払うタイプで、予算を立てやすいのが特長です。一方、従量課金制は利用した分だけ課金されるため、利用頻度が少ない企業に向いています。
また、オンプレミス型は初期導入費用が高く、運用や保守に関するコストもかかりますが、長期的に見れば安定した運用が可能です。それぞれの特徴を把握して、自社の予算と利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
無料で利用できるツールもある
コストを抑えたいなら無料ツールやオープンソースも選択肢になります。 プロジェクト管理ツールには、無料で使えるクラウド型ツールや、誰でも自由に使えるオープンソースのソフトも存在します。
たとえば、無料プランでは利用人数や機能に制限があるものの、基本的なタスク管理や進捗管理機能は十分に利用できます。そのため、小規模なプロジェクトやお試し導入にも適しています。
オープンソースのツールは、自社でカスタマイズできる柔軟性がありますが、導入や保守にある程度の知識が必要です。まずは無料プランから試して、自社の運用に合うかを確認したうえで有料版への切り替えを検討するのもおすすめです。

おすすめのOSS型プロジェクト管理ツール|メリットなども解説
OSS(オープンソースソフトウェア)とは、無料で公開されているプログラムのソースコードのことであり、自由にカスタマイズして利用できます。本記事では、おすすめのOSS型プロジェクト管理ツールやその選び方、利用するメリットや注意点を解説しています。
プロジェクト管理ツールのその他の比較ポイント

ツールの機能だけでなく「使いやすさ」や「サポート体制」なども重要です。プロジェクト管理ツールを選ぶ際は、基本機能や料金だけでなく、実際に使いこなせるかどうかも大切な判断材料です。
ここでは、見落としがちな比較ポイントを詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
プロジェクト管理ツールのその他の比較ポイント
使いやすいインターフェースか
プロジェクト管理ツールはチーム全員が使うものであるため、操作がわかりやすいことが非常に重要です。ボタンの配置や画面の見やすさ、操作の流れなどが直感的であれば、ITが苦手な人でもすぐに使いこなせるでしょう。
具体的には、マニュアルを読まなくても操作できるくらいのわかりやすさが理想です。また、外出先でも進捗を確認できるように、スマートフォンやタブレットでも使える「モバイル対応」かどうかもチェックポイントです。
使いやすいツールは、業務のスピードや正確さにもつながります。
テンプレートは豊富か
プロジェクト管理ツールにプロジェクトのテンプレートが備わっていれば、初期設定の手間が大きく減ります。たとえば、「新商品開発用」や「イベント運営用」など、目的に応じたテンプレートがあれば、それをベースに必要なタスクを調整するだけで準備が整います。
テンプレートは、タスクの流れやチェック項目があらかじめ組まれているため、経験が少ない人でも安心して進められるのが魅力です。また、テンプレートを使うことで、チーム全体の仕事の流れを統一でき、抜け漏れ防止にもなります。
日本語に対応しているか
日本語で操作・サポートが受けられるツールを選ぶと安心です。プロジェクト管理ツールには海外製も多くありますが、すべてが日本語に対応しているとは限りません。
メニューが英語表示だったり、困ったときのサポートが英語対応のみというケースもあります。英語が得意でない人にとっては、トラブルや疑問点に迅速に対応できなくなるため、導入前に「操作画面が日本語対応か」「サポート窓口は日本語か」を必ず確認しましょう。
特に全社的に導入する場合、日本語でスムーズに使えるかどうかは、日々の業務に大きな差を生みます。
おすすめのプロジェクト管理ツール10選
株式会社クラウドワークス
クラウドログ
株式会社アジャイルウェア
Lychee Redmine
ここがおすすめ!
- 出来高管理・コストマネジメントなどの管理機能を標準装備
- 進捗はリアルタイムで確認できて、遅延の確認も簡単に行える
- 負荷状況の把握がしやすく、無理のない計画を立てられる
ここが少し気になる…
- 機械管理を利用したい場合はオプション扱い

株式会社ギャプライズ
monday.com

ここがおすすめ!
- ボード上でコミュニケーションが簡単に取れるため、クライアントにも進捗状況を把握してもらえる
- 管理ボードのスタイル・項目・色など、自社の用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズできる
- 無料プランはクレジットカードの入力が不要なため、手軽にお試しできる
ここが少し気になる…
- 導入の際は3ユーザー以上の契約が必要になる

Asana Japan 株式会社
Asana
株式会社PR TIMES
jooto
Wrike Japan株式会社
Wrike
アトラシアン株式会社
Jira Software
ここがおすすめ!
- プロジェクトが一元管理でき、チームの連携が高まる
- すぐに使用できるテンプレートが各種用意されているため、簡単に始められる
- 企業やチームの規模に合った豊富なプランの中から選べる
ここが少し気になる…
- 初心者には複雑な使用感で最初はつまずきやすい

ファーエンドテクノロジー株式会社
Redmine
プロジェクト管理ツールの導入フローと注意点

プロジェクト管理ツールは便利ですが、ただ導入するだけではうまく活用できません。スムーズに定着させるためには、導入スケジュールの策定や、従業員のトレーニング、運用ルールの整備など、いくつかのステップを踏む必要があります。
また、導入後の効果をしっかりと測定し、必要に応じて改善していく仕組みも大切です。以下で各ポイントを詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
プロジェクト管理ツールの導入フローと注意点
1.導入のスケジュールを策定する
プロジェクト管理ツールの導入は、チームの業務のやり方を大きく変える可能性があります。そのため、思いつきで急に始めるのではなく、導入時期やステップをしっかり計画することが大切です。
たとえば「テスト導入→本番導入→定着支援」というように段階を分け、社内の混乱を防ぐスケジュールにする必要があります。導入のタイミングも繁忙期を避けるなど、現場の状況に合わせて計画することで、よりスムーズにスタートできます。
2.従業員へのトレーニング計画を策定する
どれだけ高機能なツールでも、使う人が操作方法を理解していなければ効果は出ません。そのため、導入と同時に従業員向けのトレーニング期間を設けましょう。初心者でもわかるマニュアルを作ったり、簡単な使い方セミナーを実施したりするなどの工夫が効果的です。
ツールに慣れるまでのサポート体制を整えることで、社員が自信を持ってツールを活用できるようになります。
3.運用ルールを定める
プロジェクト管理ツールを導入したあと、誰がどう使うかがバラバラでは意味がありません。たとえば、「いつタスクを更新するか」「誰が管理するか」「通知設定のルールはどうするか」など、事前に運用ルールを決めておく必要があります。
こうしたルールがあることで、全員が共通のやり方でツールを使えるようになり、チーム全体の効率が上がります。また、ルールがあれば、万が一トラブルが起きたときにもスムーズに対処できます。
4.導入効果を測定する仕組みを整える
プロジェクト管理ツールは導入して終わりではなく、その後どれだけ役立っているかをきちんと把握することが大切です。
具体的には、「納期遵守率が上がったか」「コミュニケーションの量が増えたか」などの定量的な数値と、「使いやすいか」「業務が楽になったか」といった定性的な意見の両方をチェックします。
そして、問題点があれば再トレーニングや機能追加を行い、より使いやすい環境を整えていきましょう。振り返りを続けることで、導入効果が最大化され、費用対効果の高い運用に繋がります。
まとめ

プロジェクト管理ツールを活用するには、ただ導入するだけでなく「いつ・どうやって導入するか」「使う人が理解しているか」「共通のルールで運用されているか」をしっかり整えることが大切です。
また、導入しただけで満足せず、効果を測りながら改善していくことで、長期的にメリットを感じられるようになります。本記事を参考に自社に適したプロジェクト管理ツールを導入し、自社に合った運用を考えてみましょう。