サイバー攻撃対策ソフトとは?セキュリティソフトとの違いも解説

Check!
- サイバー攻撃対策ソフトは、サイバー攻撃の監視や対策を行うためのソフトウェアである
- サイバー攻撃対策ソフトの導入で、攻撃による被害を最小限に抑えることが可能になる
- サイバー攻撃対策ソフトを選ぶ際は、自社のセキュリティの弱みを補えるか確認が必要
システム破壊やデータ流出などを引き起こすサイバー攻撃を受けると、事業の継続が難しくなるなどのリスクがあります。サイバー攻撃の対策・監視を行うなら、サイバー攻撃対策ソフトの導入がおすすめです。本記事では、サイバー攻撃対策ソフトのメリットなどを解説しています。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
サイバー攻撃対策ソフトとは

サイバー攻撃対策ソフトは、サイバーセキュリティに特化したソフトを指します。サイバーセキュリティとはサイバー攻撃からシステムやネットワークを保護することで、インターネットが普及した現代では、企業や個人の重要な情報を守るうえで必要不可欠なものです。
サイバーセキュリティを強化するためには、サイバー攻撃対策ソフトの導入が有効です。このソフトウェアは、マルウェアの検知・ブロック、不正アクセスの防止、ネットワークの監視などが主な役割となります。
セキュリティ対策の一環として企業や個人がサイバー攻撃対策ソフトを導入することで、重要な情報を守れます。
サイバー攻撃対策ソフトとセキュリティソフトの違い

従来のセキュリティソフト(セキュリティ対策ソフトウェア)は、既知のウイルスやマルウェアに対して効果を発揮しますが、新たに出現した未知のウイルスに対する対策は難しい場合があります。
一方、サイバー攻撃対策ソフトは未知の脅威に対応するために、先読みして対策を行えるのが特徴的です。
サイバー攻撃対策ソフトは、過去の攻撃データを元に、未知のウイルスの特徴を分析し、類似した攻撃を未然に防ぎます。また、インターネット上の不審なアクティビティを監視し、異常な挙動を検知することで、未知のウイルスを発見し、ブロックすることができます。
サイバー攻撃の主な種類

サイバー攻撃とは、コンピューターやネットワークなどの情報通信インフラを標的にする攻撃の総称です。インターネットの普及に伴ってサイバー攻撃は増加し、その手法も多様化しています。
組織や個人に対して重要な情報を盗む目的で行われる場合もあれば、システムを停止させることで混乱を引き起こす目的で行われることもあります。また、不正ログインを目的としたパスワードリスト攻撃や、サービスの停止や遅延を引き起こすDoS攻撃などもあります。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
マルウェア
マルウェアは、悪意のあるソフトウェアの総称です。コンピュータやネットワークに侵入し、不正な活動を行うことで、被害をもたらします。マルウェアには様々な種類があり、ウイルス、トロイの木馬、ワーム、スパイウェア、ランサムウェアなどが含まれます。
マルウェアの感染経路も様々で、不正なメールの添付ファイルやリンクをクリックしたり、感染したWebサイトにアクセスしたりすることでコンピューターに侵入されます。
感染したコンピューターは個人情報や機密データの盗難、システムの乗っ取り、ネットワークのダウンなどの被害に遭遇することがあります。
総当たり攻撃
総当たり攻撃は、主にログイン画面などの認証が必要な場面において行われる攻撃手法です。自動化されたプログラムやスクリプトを使用して、大量のパスワードや認証情報の組み合わせを試行し、正しい組み合わせを見つけ出します。
以前は手間のかかる非効率な手法として認知されていましたが、最近は自動ツールの利用により、時間をかければかなりの確率で解読が可能であると言われています。強力なパスワードや認証手法が設定されていない場合は、容易に侵入されてしまう可能性があります。
標的型攻撃
標的型攻撃は、特定の組織や個人を狙った攻撃手法です。攻撃者は事前に徹底的な情報収集を行い、ターゲットに合わせた攻撃を仕掛けます。そのため、総当たり攻撃に比べて高度なテクニックが使われるのが特徴です。
攻撃対象は企業の重要な機密情報や顧客データ、財務情報などです。攻撃者は、組織のセキュリティシステムの脆弱性を見極め、標的を特定して個別に攻撃を仕掛けることで、攻撃の成功率を高めようと試みます。
パスワードリスト攻撃
パスワードリスト攻撃は、事前に用意されたパスワードリストを使ってログインを試みる攻撃手法です。攻撃者は、何らかの方法で入手したIDとパスワードのリストを用いて、インターネット上のサービスにおける特定のアカウントに対しての不正なログインを試みます。
対策として、定期的なパスワードの変更、多要素認証の導入などを行うことでリスクを最小限に抑えられます。また、システムやサービスの管理者は不正なログインを監視し、異常なアクティビティを検知した際に適切な対応を行うことも重要です。
DoS攻撃
DoS攻撃は、悪意のある攻撃者が特定のサーバーやネットワークに、過剰なトラフィックを引き起こすことで、サービスの停止や遅延を引き起こす攻撃手法です。
攻撃対象のシステムは、その処理能力を超えるほどのデータやリクエストを送信されるため、サーバーは混雑します。これにより、サービス提供が困難になり、ウェブサイトの表示が遅くなったり、アプリケーションの動作が停止するなどの影響が出ます。
一般的に一人の攻撃者から行われますが、「DDoS攻撃」として複数の攻撃者が協力して攻撃を行うこともあります。この場合、より大規模な攻撃が可能となり、より広範な影響をもたらす可能性があります。

DoS攻撃とは?意味やDDoS攻撃との違い、対策などをわかりやすく解説
DoS攻撃とは、1台のパソコンを使ってサーバーに負荷をかける攻撃のことを言います。DoS攻撃を受けることで、サーバーダウンや社会的信頼性の低下といったリスクがあるため、十分に対策を行う必要があります。本記事では、DoS攻撃の種類や対策について解説しています。

DDoS攻撃とは?攻撃の目的・起こり得る被害や対策について解説
DDoS攻撃とは、多数の端末でアクセス要求を行い、Webサイトなどのサーバーに負荷をかけて処理能力を停止させるサイバー攻撃を指します。本記事では、DDoS攻撃の意味や概要を交え、DDoS攻撃を行う目的や起こり得る被害、対策などについてわかりやすく解説します。
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃は、メーカーがセキュリティの脆弱性を修正する前に、その脆弱性を悪用して攻撃を行う手法です。OSやソフトウェアでは、稀にプログラムのミスや欠陥によって、セキュリティが不十分な状態になっていることがあります。
この場合、メーカーは修正プログラムなどを配布して対処しますが、攻撃者は対処法がリリースされる前に攻撃を仕掛けるため、対策が遅れて大きな被害を受けてしまうことがあります。攻撃者は常にこのようなセキュリティの穴を狙っているのです。
サイバー攻撃における主な対策

サイバー攻撃から身を守るためには、適切な対策が必要です。主な対策としては、侵入経路を塞ぐ入口対策、攻撃を受けた際に素早く検知するための内部対策、また、外部から攻撃に対しての支援を受ける外部対策などがあります。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
入口対策
入口対策は、攻撃者がシステムに侵入する前に、その侵入経路を塞ぐ対策です。主な取り組みとしては、ファイアウォールの設置や侵入検知システムの導入、メールやWebサイトへの不正アクセスを防ぐためのセキュリティソフトの活用などが挙げられます。
また、従業員への教育・啓蒙活動も重要であり、不正なリンクをクリックしたり、不審なメールの添付ファイルを開かないよう意識づけることが必要です。

ファイアウォールとは?種類や機能やを初心者にも分かりやすく解説
ファイアウォールとは、ネットワーク通信において外部からの侵入や攻撃を防ぎ、内部からの不正なアクセスを禁止することで、悪意のある通信から保護するシステムです。この記事では、ファイアウォールの機能や導入のメリット・デメリットを分かりやすく解説していきます。
内部対策
内部対策は、既にシステムに侵入してしまった攻撃者を検知・防御する対策です。この対策は企業や組織のネットワークやシステム内に侵入した攻撃者を検知し、その動きを追跡することで被害を防ぎます。
具体的には、セキュリティ監視システムを導入し、ネットワークやサーバーの通信を監視し、不審なアクティビティを検知します。また、ログの収集・分析を行い、異常なアクセスや操作を素早く発見します。
また、バックアップやシステムの隔離など、事前に計画を立てておくことで、侵入を制限し、システムの回復をスムーズに行えるようにする必要があります。
出口対策
出口対策は、万が一サイバー攻撃の結果ネットワーク内部に侵入されても、データを外部に持ち出されないようにする対策です。攻撃は情報を漏洩させるために行われることも多いため、こうした対策も重要です。
例えば、ネットワーク内部から外部に向かう通信を監視して不審な動きを検知・ブロックするといった方法が考えられます。出口対策を行うことで、何らかの方法で入口対策を突破されてしまっても、個人情報や機密情報の漏洩を防ぐことができます。
サイバー攻撃対策ソフトの機能
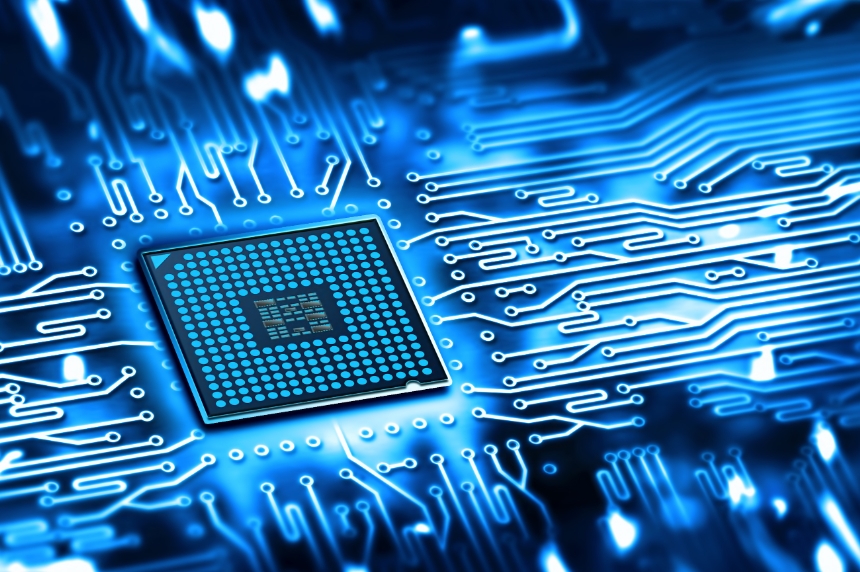
サイバー攻撃対策ソフトには、上記の入口対策・内部対策・出口対策に該当するさまざまな機能が搭載されています。主な機能は、下の表のとおりです。
ただし、サイバー攻撃対策ソフトと一口に言っても多くのソフトが存在しているため、ソフトごとに実際にどのような機能が搭載されているかよく確認する必要があります。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| マルウェア対策 | マルウェアを検知・排除 |
| 不正アクセス検知・防御 | 不正なアクセスや不審なアクセスを検知・防御 |
| ファイアウォール | ネットワークの入り口で通信を監視・制御 |
| 改ざん検知 | 第三者による不正なデータの改ざんを検知 |
| エンドポイント監視 | 各デバイスの状況を監視 |
| 脆弱性チェック | システムやソフトウェアの脆弱性を検知 |
| ログ管理 | ネットワークやシステムのログを収集・分析 |
サイバー攻撃対策ソフトを導入するメリット

サイバー攻撃の脅威はますます高度化しており、企業や組織はセキュリティ対策を強化する必要があります。ここでは、サイバー攻撃対策ソフトを導入することによって、セキュリティ対策の面でどのようなメリットがあるのか解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
サイバー攻撃対策ソフトを導入するメリット
被害を最小限に抑えられる
サイバー攻撃は、企業や組織に対してシステムの破壊や機密情報の漏洩などの深刻な被害をもたらす可能性があります。
サイバー攻撃対策ソフトを導入することで、未知のウイルスやマルウェアに対応し、攻撃を事前に予防したり、攻撃を検知・ブロックしたりすることが可能です。そのため、被害を最小限に抑えられます。
信頼できる企業であることをアピールできる
サイバー攻撃を受けてしまった場合、重要な情報などの漏洩により、社会的信頼を失うリスクも否定できません。また、サイバーセキュリティの重要性が高まる中、取引先や顧客はセキュリティ対策が十分になされている企業との取引を求める傾向にあります。
サイバー攻撃対策ソフトの導入は、その企業がセキュリティに対して真摯に取り組んでいることをアピールする手段となります。信頼性の向上により、競合他社との差別化や新規顧客の獲得にも繋がります。
セキュリティに関する知識が不要
従来のセキュリティ対策は、専門的な知識やスキルを要することが一般的でした。その点、サイバー攻撃対策ソフトは、セキュリティに関する専門知識がない人でも簡単に操作・管理できるようになっています。
セットアップや設定は自動化され、複雑な技術や用語がわからなくても扱えます。また、定期的なアップデートやパッチ適用も自動で行われるため、大きな手間もかかりません。
さらに、従来必要だったセキュリティ対策を担当する専門家の人件費や、教育コストを削減することも可能です。
サイバー攻撃対策ソフトを導入するデメリット

サイバー攻撃対策ソフトの導入には多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。特に、ソフトウェアごとにコストが大きく異なり、相場が分かりづらいことが挙げられます。無料のものから高額なものまで、さまざまな価格帯があります。
そのため、企業や組織ごとに求めるセキュリティレベルや予算に応じて、適切なソフトを選択することが重要です。ただし、価格が高いからといって優れた性能を持つとは限りません。
導入前に無料トライアルが提供されている場合は、それを利用して実際にソフトの動作や機能を試してみることがおすすめです。実際に手に触れてみることで、自社に適したソフトウェアを見極めることができます。
サイバー攻撃対策ソフトを選ぶ際のポイント

サイバー攻撃対策ソフトを選ぶ際には、いくつかのポイントがあります。機能だけでなく、監視サービスの有無や、サポート体制なども重視しましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
サイバー攻撃対策ソフトを選ぶ際のポイント
自社のセキュリティの弱みを補える機能が備わっているか
サイバー攻撃対策ソフトを導入する際には、自社のシステムやサービスのセキュリティの弱みを把握することが重要です。そのうえで、ソフトウェアがどのような攻撃に対応できるのか、既存のセキュリティ対策とどのように連携するのかを確認しましょう。
自社のセキュリティに合わせたカスタマイズが可能なソフトウェアであれば、より効果的な対策が可能となります。
監視サービスがあるか
中小企業や個人事業主などでは、セキュリティ部門を設けることが難しく、サイバー攻撃への対応が不十分となることが多いです。このような場合は、サイバー攻撃対策ソフトに、監視サービスが含まれているソフトウェアの導入をおすすめします。
このサービスでは、専門のセキュリティチームが24時間365日体制で監視を行い、異常な通信や攻撃の検知を行うため、早期に対処できます。監視が不十分な状態でサイバー攻撃を受けた場合、攻撃の検知が遅れるなどのデメリットが生じる可能性があります。
初心者にも使いやすいか
サイバー攻撃対策ソフトは、複雑な設定や操作が必要な場合があります。ソフトによって運用難易度は異なるので、自社の担当者のスキルレベルに合わせて使いやすいソフトウェアを選ぶことで、担当者の負担やセキュリティの抜け漏れを軽減できます。
初心者でも使いやすいソフトは簡単な操作で効果的な対策が行えるため、セキュリティ対策に費やす時間とコストが削減できます。操作に慣れていない従業員でも、ストレスなく利用できるサイバー攻撃対策ソフトを選びましょう。
24時間365日サポートしてくれるか
サイバー攻撃は、24時間365日発生する可能性があります。万が一の際に迅速な対応が求められるため、24時間365日体制でサポートを提供してくれるソフトウェアを選ぶことが重要です。
問題発生時に専門家によるサポートを受けることで、迅速かつ適切な対応が可能となります。セキュリティに関する安心感を持つためにも、サポート体制の確認は欠かせません。
オンプレミス型かクラウド型か
サイバー攻撃対策ソフトの提供形態も重要なポイントです。自社のネットワークやシステム内で展開するオンプレミス型は、拡張性が高く自社の悩みをピンポイントで解決しやすいのが特徴です。ただし、費用は高額になることが多く、使用開始までに日数もかかります。
一方、インターネットを介して利用するクラウド型は、契約後すぐに利用が始められ、アップデートもサービス会社が行ってくれるため手間がかかりません。しかし、拡張性は低く、利用する間は利用料が発生し続けます。
このように、提供形態によってメリットとデメリットがあるため、導入前にしっかり確認しておくことが大切です。
費用は妥当か
サイバー攻撃対策ソフトの導入には、当然ながらコストがかかります。オンプレミス型の場合は導入時の初期費用、クラウド型の場合は初期費用と月額費用が主な費用になりますが、ソフトによって具体的な金額は大きく変わります。
クラウド型のベーシックなプランでも、料金相場は月額2,000円〜10,000円程度と幅があります。機能の充実性のみならず、企業規模によっても料金が変わることがあるので、事前によく確認しておくことが重要です。
まとめ

サイバー攻撃対策ソフトは、未知のウイルスやマルウェアに対応し、攻撃を検知・ブロックするツールです。このソフトを導入することで、攻撃による被害を最小限に抑えられます。
万が一攻撃されてしまった場合は、企業の信頼を失いかねません。安心して事業展開を行い、サイバーセキュリティを確保するために、自社に合った使いやすいサイバー攻撃対策ソフトの導入を検討してください。

