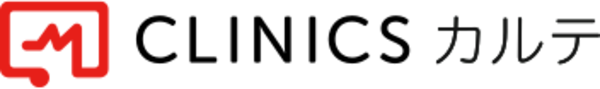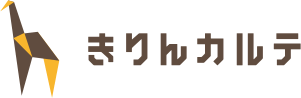電子カルテシステムおすすめ10選|選び方も解説

Check!
- 電子カルテシステムは、レセコン一体化型かレセコン分離型かどうかを確認する
- 大規模病院や訪問診療などで利用する場合には、クラウド型・モバイル対応がおすすめ
- システム導入では院内の診療フローと運用課題を把握し、導入計画を策定する必要がある
電子カルテシステムを導入することで、従来までの紙のカルテをデジタル化し、システム上で一元管理できます。患者情報にアクセスしやすくなり、診療の効率化やスムーズな情報共有が可能です。本記事では、電子カルテシステムのおすすめや選び方などを解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
電子カルテシステムで診療の効率化を図ろう

電子カルテシステムは、診療の効率を大きく高めてくれる重要なシステムです。紙のカルテと違い、パソコン上で患者の情報をまとめて管理できるため、過去の診療記録や検査結果をすぐに確認できます。
また、情報共有がスムーズになるため、医師だけでなく看護師や受付スタッフも業務がしやすくなります。診療所や中小病院など、どんな規模の医療機関でも役立つのが電子カルテの魅力です。
本記事では、電子カルテシステムの特徴や選ぶポイント、導入時の注意点などをわかりやすく紹介していきます。
電子カルテシステムは形態・連携性・機能で選ぶ

電子カルテシステムを選ぶ際は、ただ便利そうという理由だけで選ぶのではなく、自院の運用に合っているかを見極めることが大切です。
特に重要となるのは、「レセコンとの一体型か分離型か」「他システムや医療機器との連携性」「自院の規模や診療科目に合った機能が備わっているか」の3つのポイントです。
これらを事前に確認しておくことで、導入後に「使いにくい」「欲しい機能がなかった」といったトラブルを避けやすくなります。次の章では、この3つのポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。
【重要なポイント3つ】
- レセコン一体型・分離型から選ぶ
- 他システム・機器との連携性を確認
- 自院の規模・診療科目に適しているか
【その他の比較ポイント】
- 導入実績と現場の評価を確認
- クラウド型かオンプレミス型か
- モバイル対応で安全にアクセスできるか
- サポート体制と安定性を確認
- 法改正への対応スピードを確認
電子カルテシステムの選び方で重要な3つのポイント

電子カルテシステムを選ぶときに重要なのは、「どのタイプか」「ほかの機器やシステムと連携できるか」「自院の規模や診療内容に合っているか」という3つの視点です。
どれか一つでも合わないと、せっかく導入しても使いにくくなったり、業務がかえって煩雑になったりする可能性があります。以下では、電子カルテシステムの選び方で重要なポイントについて詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
電子カルテシステムの選び方で重要な3つのポイント
レセコン一体型・分離型から選ぶ
電子カルテを選ぶ際は、「レセコン一体型」か「レセコン分離型」かを必ず確認しましょう。レセコンとは診療報酬を計算し、請求をするための診療報酬請求明細書(レセプト)の作成・管理を行うシステムのことです。
一体型は、電子カルテとレセコンが一つの画面で連携して動作するため、診察内容を入力すればそのまま会計処理に反映されます。入力ミスが減ることから、特にクリニックのように少人数で効率を重視したい施設に向いています。
一方で分離型は電子カルテとレセコンが別々に動くため、すでに使っているレセコンをそのまま活用できます。システム障害が起きても片方だけで済むなどの利点もあります。
どちらが自院の診療スタイルやIT環境に合っているか、実際の運用をイメージしながら比較検討することが大切です。
自院の規模・診療科目に適しているか
電子カルテシステムは自院の規模や診療科目に合っているかを確認することが重要です。内科・皮膚科・整形外科など、それぞれの診療内容に適したテンプレートや入力項目が用意されているかどうかで、業務効率が大きく変わります。
また、クリニック向けと病院向けでは、想定される患者数やスタッフ数も違うため、操作画面の構成や導入費用などにも差があります。
自院に合っていないシステムを選んでしまうと、無駄な機能が多くなったり、必要な情報が扱えない恐れもあるため、導入前にしっかりと検討しましょう。
他システム・機器との連携性を確認
電子カルテは単体で使うだけでなく、すでに利用している機器やシステムと連携できるかが重要なチェックポイントです。血圧計や心電図モニター、検査機器のデータが自動でカルテに取り込まれると、手入力の手間が省けて記録ミスも減らせます。
また、予約システムや会計ソフト、電子薬歴などと連携できれば、院内全体の業務効率がさらに高まります。一方、連携ができない場合は情報の入力が二重になり、手間もかかってしまいます。
電子カルテシステムの導入を検討する際は、今使っているシステムと連携できるかどうかを必ず確認しておくことが大切です。
電子カルテシステムのその他の比較ポイント

電子カルテシステムを選ぶ際には、基本機能や連携性だけでなく、実際の導入実績や使いやすさ、セキュリティ面、法改正への対応といった点も重要です。以下で、比較すべき具体的なポイントを順番に解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
電子カルテシステムのその他の比較ポイント
導入実績と現場の評価を確認
自院と似た医療機関での導入実績が多い電子カルテを選ぶと安心です。内科クリニックで多く使われている製品なら、同じような診療フローを想定して作られているため、自院でもスムーズに運用しやすくなります。
さらに、現場の医師やスタッフの声も重要です。「入力しやすい」「サポートが丁寧」「トラブルが少ない」といった口コミや導入事例を確認することで、実際に使ったときのイメージがわきやすくなります。
自院と似た環境の評価を参考にすることで、導入後のミスマッチを防げるでしょう。
クラウド型かオンプレミス型か
電子カルテシステムは、大きくクラウド型とオンプレミス型に分かれます。結論から言うと、初期費用を抑えたい・外部からも使いたいならクラウド型、インターネット環境に頼らず安定性を重視するならオンプレミス型が向いています。
クラウド型はインターネットを通じて利用するため、PCやタブレットからどこでもアクセスできて便利ですが、通信環境が悪いと使いにくいという弱点があります。
オンプレミス型は院内のサーバーにインストールする方式で、安定性は高いですが初期投資が大きくなります。自院のIT環境やセキュリティ方針に合わせて選ぶことが重要です。
スタッフが操作しやすいか
電子カルテは、医師だけでなく看護師や受付スタッフも使うため、誰でも使いやすい設計かどうかがとても重要です。複雑で使いにくいと、入力ミスが増えたり、操作に時間がかかってしまったりします。
そのため、導入前に無料トライアルやデモを利用して、実際に触ってみることがおすすめです。「画面が見やすいか」「入力操作が直感的か」「マニュアルがわかりやすいか」などを確認すると、導入後の混乱を防ぎ、いち早く業務に慣れることができるでしょう。
モバイル対応で安全にアクセスできるか
外出先や訪問診療で使うことがあるなら、スマホやタブレットに対応し、安全にアクセスできる電子カルテを選ぶべきです。モバイル対応があると、病院の外でも患者情報を確認したり、入力したりできるため、業務の幅が広がります。
ただし、外部からアクセスする場合はセキュリティが重要になります。データ通信の暗号化や、二段階認証などの対策がとられているかを必ず確認しましょう。モバイルでも安心して使えるシステムは、今後の働き方に柔軟に対応できる強みとなります。
サポート体制と安定性を確認
電子カルテは医療現場で毎日使うシステムのため、安定して動くかどうか、困ったときにすぐ相談できるかが非常に大切です。診療中にシステムが停止すると、業務に大きな支障が出るだけでなく、患者対応にも影響が出てしまいます。
そこで、提供会社のサポート体制を確認しましょう。「土日も対応してくれるか」「電話での問い合わせが可能か」など、運用時間に合った支援があると安心です。
また、過去の障害情報や稼働実績を確認し、安定性の高いサービスを選ぶことで、トラブルを未然に防げます。
法改正への対応スピードを確認
医療業界は、診療報酬や制度の改定が頻繁に行われる分野です。そのため、システムが新しい法制度にすばやく対応できるかどうかは、とても重要な比較ポイントです。
診療報酬の改定に対応が遅れると、正確な請求ができなくなり、収入に影響が出てしまうおそれもあります。電子カルテを選ぶときには、過去の法改正への対応実績や、改定後のサポート体制について事前に確認することが大切です。
常に最新の制度に合わせて使える電子カルテを選ぶことが、安定した医療運営につながります。
電子カルテシステムおすすめ10選
電子カルテシステムの導入フローと注意点
【クリニック向け】電子カルテシステムおすすめ7選
株式会社メドレー
CLINICSカルテ
ここがおすすめ!
- Web予約やレセコンなどの独立したシステムを一元管理できる
- 医師だけでなく受付担当も効率よく使える機能を標準装備
- 買い替えやメンテナンス不要で使え、初期費用を抑えた導入を実現
ここが少し気になる…
- スマホの対応可否やオプションの費用は問い合わせで確認
エムスリーデジカル株式会社
エムスリーデジカル
ここがおすすめ!
- あらゆる手間を解決できる機能を標準装備
- iPad・スマホ対応や会計連携などでよりスムーズな業務を実現
- 専門のスタッフが対応し、ニーズにあわせてサポートプランが選べる
ここが少し気になる…
- iPadの手描きカルテや処方監査などはオプションの扱い
ここがおすすめ!
- 豊富な機能を搭載し、「システム利用料」が無料で使える
- 基本的な機能はもちろん、予約システム・在宅医療向け機能も用意
- 導入がスムーズな「クラウド型」かつ、iPadにも対応
ここが少し気になる…
- すべての医科診療科に対応しているが、入院機能は非搭載
ウィーメックス株式会社
Medicom-HRf Hybrid Cloud
ここがおすすめ!
- 「独自のノウハウ」により、スピーディーな操作性を実現
- 予約や精算など、170社の機器とシームレスな連携が行える
- 「ハイブリッド型」のため、訪問診療や院外にも対応
ここが少し気になる…
- 導入費用やサポート費用は問い合わせで確認
株式会社EMシステムズ
MAPs for CLINIC
ここがおすすめ!
- 「オールインワン」でスムーズな診療と業務を目指せる
- 職員だけでなく、患者の目線でも使いやすい機能を標準装備
- オンプレ並の「高機能・安心感」とクラウドの「気軽さ」を提供
ここが少し気になる…
- 他社連携サービスやスマホ対応の可否は問い合わせで確認
株式会社DONUTS
CLIUS
ここがおすすめ!
- 「AI機能」により診察の効率化が行え、開業コストの削減につながる
- ほぼ全ての診療科に対応しており、利用施設間連携でも稼働を確認
- セットアップ時はスタッフが直接訪問し、不安なく導入可能
ここが少し気になる…
- レセコン・ORCAの初期費用、サポート費用・利用料は別途
ウィーメックス ヘルスケアシステムズ株式会社
Hi-SEEDW3EX
ここがおすすめ!
- レセプトチェックシステム「べてらん君collaboration Plus」を搭載
- 直感的かつシンプルな画面設計で、不慣れでも扱いやすい
- 「オンライン資格確認」や「オンラインサポート」に対応
ここが少し気になる…
- 導入費用や保守・サポート費用は問い合わせで確認
【中小規模病院向け】電子カルテシステムおすすめ3選
ウィーメックス株式会社
Medicom-CKⅡ
ここがおすすめ!
- 「クラウド」と「オンプレミス」の2種から導入方法を選べる
- 電子カルテに不慣れでも直感的に操作が可能な使いやすい画面
- マルチデバイス・ブラウザ対応で、状況にあわせて使える
ここが少し気になる…
- 導入費用や保守・サポート費用は問い合わせで確認
株式会社医療情報システム
ウェブカルテⅡ
ここがおすすめ!
- 初めてでも操作しやすく、インターネット感覚で入力できる
- マルチベンダー方式を採用し、シームレスな連携を実現
- バックアップサーバを標準構成し、障害が発生しても業務が可能
ここが少し気になる…
- 無床・有床診療所向けの機能や製品の取り扱いはない
富士通株式会社
HOPE LifeMark-HX
ここがおすすめ!
- 必要な情報は1つの画面で集約し、二重入力防止対策も行える
- 蓄積されたデータは可視化でき、抽出・分析により活用にも効果的
- 作業を止めることなくシステムの導入ができ、職員の負担を軽減
ここが少し気になる…
- 導入の初期費用や保守費用などはと合わせで確認
電子カルテシステムの導入フローと注意点

電子カルテシステムを導入する際には、いきなりシステムを入れるのではなく、まずは現状の業務を見直し、導入のタイミングや運用方法をしっかり計画することが重要です。以下では、導入の具体的なステップと注意点を順に解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
電子カルテシステムの導入フローと注意点
1. 院内の診療フローと運用課題を把握
まず現状における院内の診療フローを把握し、紙カルテでの運用課題を整理しましょう。どのように受付を行い、どのタイミングでカルテを記入し、会計まで進むのかという診療フローを明確にすることで、何が課題かが見えてきます。
たとえば「紙カルテの保管が大変」「情報共有に時間がかかる」といった問題がある場合、電子カルテでどう改善できるかを考えやすくなります。現場のスタッフの声を聞きながら、今の運用方法を整理しておくと、導入後もスムーズに移行できるようになります。
2. 診療に支障が出ない導入計画を策定
電子カルテの導入は、できるだけ診療に影響が出ないタイミングを選びましょう。特に繁忙期や人手不足の時期に導入すると、操作に慣れないことで混乱が起きやすくなります。
そのため、業務の落ち着いている時期を選び、余裕を持ったスケジュールで導入準備を進めることが重要です。また、切り替え当日だけでなく、数週間単位でのトレーニング期間を設けておくと、スタッフも安心して対応できます。
こうした計画を立ててから契約や設定を進めると、現場に混乱を与えず、スムーズに運用を始められます。
3. バックアップとセキュリティ対策
電子カルテには、患者の個人情報や診療記録など、非常に重要なデータが含まれています。そのため、万が一のトラブルに備えて、バックアップ体制を整えることが欠かせません。
たとえば、クラウドに定期的に自動保存する仕組みや、外部のサーバーにデータを複製しておくなどの方法があります。また、外部からの不正アクセスを防ぐために、パスワード管理やアクセス制限、ウイルス対策などのセキュリティ対策も必須です。
トラブルが発生してからでは遅いため、導入前から万全の準備をしておくことが求められます。
まとめ

電子カルテの導入を成功させるためには、事前の診療フローの見直しと業務課題の整理、診療に支障が出ないタイミングでの導入、そしてデータの安全性を確保する対策が必要です。
事前に現在の業務の流れを整理し、どんな課題があるのかを把握することで、必要な機能が明確になります。また、個人情報を多く扱うため、バックアップやセキュリティ体制もしっかり整えておきましょう。
電子カルテシステムは導入して終わりではなく、運用後も定期的な見直しと改善が必要です。この記事を参考に、自院に合った電子カルテを導入し、より良い診療体制の構築を目指してみてください。