ストレスチェックサービスおすすめ8選|選ぶ際のポイントや注意点も解説

Check!
- ストレスチェックサービスは、受検方法の選択肢やサービスの範囲を比較することが重要
- 設問数の柔軟性や回答しやすさ、ストレスチェック以外への対応も大切なポイント
- サービスを利用する際はトータルコストを確認し、従業員にも実施目的などを周知する
ストレスチェックは多くの企業で義務付けられていますが、ストレスチェックサービスの利用によって、法令に準拠したストレスチェックの実施や職場環境の改善に繋げられます。本記事では、ストレスチェックサービスのおすすめや選ぶ際のポイント、注意点などを解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
職場改善を図るならストレスチェックサービスがおすすめ

ストレスチェックサービスを活用すれば、企業は従業員の心の健康を守りながら、より良い職場環境をつくることができます。
企業には労働安全衛生法によって、年1回のストレスチェックを実施する義務があります。ストレスチェックサービスを導入することで、その手続きをスムーズに行えるだけでなく、集めたデータを分析して職場環境の改善も図れるでしょう。
ストレスチェックでは、従業員一人ひとりのストレス状態を数値化し、その原因や傾向を見える化できます。チェック方法には、質問票によるアンケート調査が一般的ですが、近年では生体反応や行動パターンの分析を取り入れたサービスも登場しています。
この記事では、ストレスチェックサービスを選ぶ際のポイントを交えて、おすすめのサービスを紹介していきます。
ストレスチェックサービスを導入するメリット
ストレスチェックサービスを導入することで、法令に準拠できたり、迅速なストレス要因の対処に繋がります。以下では、これらのメリットについて詳しく解説します。
法令に適したストレスチェックを実施できる
ストレスチェックを行う際は、ストレスチェック制度に準拠して進めることが重要です。特に実施後は、労働基準監督署に向けて報告書の提出が必要になり、これを怠ると労働安全衛生法によって50万円以下の罰金を課される恐れがあります。
そのため、特にストレスチェック制度が義務化されている場合は、制度に従った適切な運用が求められます。多くのストレスチェックサービスでは、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」に準拠したテスト機能が提供されています。
これによって、専門知識がなくても制度に沿った形でストレスチェックを実施でき、法令に適した運用を安心して進められるでしょう。ひいては、リスクの回避だけでなく、従業員のストレス状況を正確に把握し、ストレス要因の対処にも繋がります。
迅速な職場環境の改善やフォローアップが可能
休職や離職の原因として、業務量の負担や人間関係によるストレスが大きく影響するケースは少なくありません。ストレスチェックサービスでは、従業員のストレス状態以外にも年代や性別によるグループ分けや、ストレス要因の分析を行えます。
そのため、分析結果をもとに問題点を特定でき、ストレスが高い従業員への迅速なフォローや、職場環境の改善を図れます。また、定期的なストレスチェックによって、継続的に労働環境の見直しや従業員との面談も行えるため、問題が深刻化する前に対処できるでしょう。
その結果、従業員が安心して働ける環境づくりが進み、組織全体の健全性向上も期待できます。
ストレスチェックサービスは受検方法・フォロー・セキュリティで選ぶ

ストレスチェックサービスを導入する際には、自社の目的や体制に合ったものを選ぶことが重要です。サービスによって、受検の方法やサポート体制、セキュリティのレベルには違いがあるため、選び方を間違えると効果的な職場改善につながらない可能性があります。
特に注目したいのは、どのような方法で受検できるか・実施に必要な業務をどこまで代行してもらえるか・実施後のフォローアップがどれだけ充実しているかという3つのポイントです。
これらを十分に確認して選ぶことで、収集したデータや分析結果を効果的に活用できるでしょう。次の章からは、ストレスチェックサービスを選ぶうえで押さえておくべきこの3つのポイントについて、詳しく解説していきます。
【重要なポイント3つ】
- ニーズに合った受検方法か
- 実施者や実施事務従事者の代行が可能か
- 実施後のフォローアップに役立つか
【その他の比較ポイント】
- 設問数を自由に変更できるか
- 簡単に回答できる操作性か
- 多言語対応のサービスか
- ストレスチェック以外にも対応できるか
- セキュリティ体制・プライバシー保護は万全か
ストレスチェックサービスの選び方で重要な3つのポイント
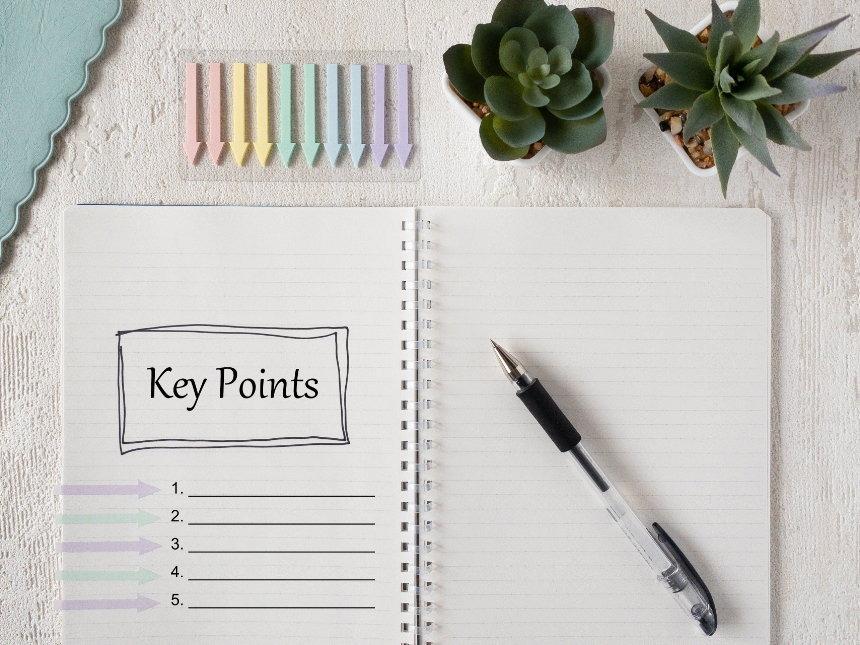
ストレスチェックサービスを導入する際には、どのサービスを選ぶかがとても重要です。数多くのサービスがある中で、自社のニーズに合ったものを選ばなければ、せっかく導入しても効果的に活用できないことがあります。
以下では、ストレスチェックサービスの選び方で重要な3つのポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
ストレスチェックサービスの選び方で重要な3つのポイント
ニーズに合った受検方法か
ストレスチェックサービスを選ぶ際、まず大切なのは従業員が受検しやすい方法が用意されているかどうかです。ストレスチェックの受検方法には、パソコンやスマートフォン、タブレットを使うオンライン形式のほか、紙で回答する方法が挙げられます。
オフィスワーク中心の企業ではオンライン形式が便利ですが、現場作業や高齢の従業員が多い職場では、紙の回答形式が適している場合もあります。
受検方法が実際の働き方に合っていないと、従業員がうまく回答できなかったり、受検率が下がったりすることが考えられます。そのため、自社の業種や勤務形態、従業員層に合った受検方法を選び、スムーズに回答できる環境を整えることが重要です。
実施者や実施事務従事者の代行が可能か
ストレスチェックを実施するには、医師や保健師、精神保健福祉士、公認心理師などの専門資格を持つ実施者と、その業務をサポートする実施事務従事者が必要です。しかし、多くの企業では社内にこうした専門職がいないか、担当者の手が足りないこともあります。
そこで役立つのが、実施者や実施事務従事者の業務を外部に委託できるストレスチェックサービスです。ストレスチェックの実施だけでなく、高いストレスを示す従業員への面談手配や結果のレポート作成、さらには管理職向けの教育支援まで幅広く対応してくれます。
ストレスチェックサービスの活用によって、自社の負担を軽減しながら、法律に則った適切な実施が可能になるため、委託できる範囲やサービス内容を事前にしっかり確認して選ぶことが大切です。
実施後のフォローアップに役立つか
ストレスチェックは、実施して終わりではなく、結果をもとに職場改善につなげることが本来の目的です。ストレスの数値が高い従業員には保健師との面談案内や、部署ごとの集計データから組織全体のストレス傾向を把握するなど、適切な対応が求められます。
こうした実施後のフォローアップを手助けしてくれるサービスを選ぶことで、改善に向けた施策もスムーズに対応できます。たとえば、わかりやすいレポートを作ってくれる機能や、メンタルヘルスの改善に向けたアドバイスをしてくれるサービスもあります。
フォロー体制がしっかりしていることで、ストレスチェックの効果を最大限に活かし、働きやすい職場環境も整えられるでしょう。
ストレスチェックサービスのその他の比較ポイント
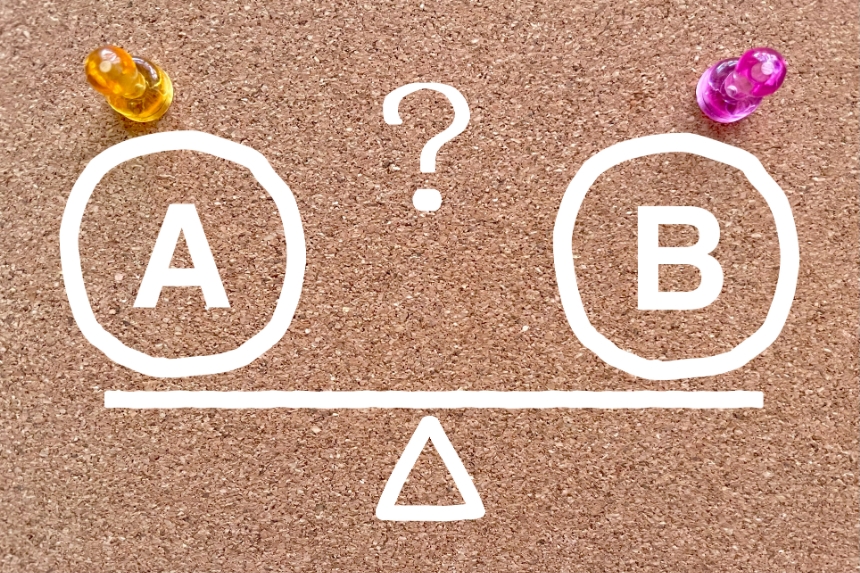
ストレスチェックサービスを選ぶ際は、受検方法や実施体制だけでなく、細かい機能や対応範囲もチェックしておくことがとても大切です。
自社のニーズにぴったり合うサービスを選ぶためには、設問の自由度や操作のしやすさ、多言語対応、他の健康管理との連携、セキュリティの体制なども忘れずに確認しましょう。ここでは、そうした比較ポイントをひとつずつ詳しく説明していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
ストレスチェックサービスのその他の比較ポイント
設問数を自由に変更できるか
自社の課題に合わせて設問数をカスタマイズできるかどうかは、ストレスチェックサービスを選ぶうえで重要なポイントです。例えば、厚生労働省が推奨している「職業性ストレス簡易調査票」は57項目で構成され、基本的なストレス状況を把握するには十分と言えます。
しかし、57項目だけではカバーしきれない職場の問題が存在するケースもあります。そこで活用できるのが、設問数を自由に追加・編集できるサービスです。企業が抱える課題に応じて設問を調整することで、より実態に即したストレス要因を把握できるでしょう。
具体的には、より詳細に分析できる調査票である「80項目版」では、ハラスメントの有無や上司との関係、働きがいなどの要素も評価できます。
企業ごとに抱える課題は異なるため、より実態に即した調査を行いたい場合は、こうした設問のカスタマイズ性が高いサービスがおすすめです。
簡単に回答できる操作性か
ストレスチェックは、従業員が負担なく回答できることが重要です。そのため、サービスの画面が分かりやすく、操作が簡単かどうかも比較ポイントになります。
例えば、スマートフォンやタブレットでもストレスなく操作できるか、途中で回答を保存できるか、質問に対して直感的に答えられるかなどを確認しておきましょう。
また、無料トライアルを提供しているサービスも多いため、実際に使ってみて操作性を確かめるのもおすすめです。操作しやすいシステムを導入すれば、受検率の向上にもつながり、より多くの従業員のストレス状況を正確に把握することができます。
多言語対応のサービスか
外国籍の従業員がいる職場では、多言語に対応しているストレスチェックサービスを選ぶのがおすすめです。せっかく優れたサービスを導入しても日本語のみ対応している場合、内容を正しく理解できず、適切に回答できない人が出てしまう可能性があります。
多国籍従業員が多い場合は英語だけでなく、中国語やベトナム語などそれぞれの言語に対応しているかどうかも確認しておきましょう。
多言語に対応しているサービスであれば、すべての従業員が平等にストレスチェックを受けられるため、会社全体のメンタルヘルスの状態を正確に把握できます。文化や言語の壁を取り除くことで、より働きやすい職場づくりにもつながります。
ストレスチェック以外にも対応できるか
ストレスチェックだけでなく、他の健康管理や職場支援に対応しているかもサービス選びの大切なポイントです。
例えば、健康診断の結果を一緒に管理できたり、従業員エンゲージメント調査や勤怠・休暇管理なども一括で対応できるシステムであれば、業務効率が大きく向上します。また、従業員の体調やメンタルの変化を総合的に把握できることで、迅速な対応が行えるでしょう。
サービスによっては、レポート機能や分析機能が充実しているため、経営層への報告資料作成にも活用できます。できるだけ一つのシステムに情報をまとめられるサービスを選ぶと、情報の分散や重複を防げるため、管理の手間を大きく減らせます。
セキュリティ体制・プライバシー保護は万全か
ストレスチェックで最も大切なのは、従業員の個人情報や回答内容がしっかり守られることです。ストレスに関する情報は非常にデリケートなため、サービスのセキュリティ体制やプライバシー保護の仕組みを必ず確認しましょう。
法律では回答は匿名で集計され、本人の同意なしに個人が特定されることは禁止されています。従業員が安心して正直に回答できる環境を整備するためにも、サービス導入時にはセキュリティポリシーや情報の取り扱いルールをしっかり確認しましょう。
また、ストレスチェックの結果が人事評価などに不当に使われないよう、実施に関わるメンバーは人事や総務から分けて体制を整えることも重要です。こうした対策があるサービスを選ぶことで、従業員のプライバシーを守りながら効果的なストレス管理が可能になります。
ストレスチェックサービスおすすめ8選
ここがおすすめ!
- フィードバックやパーソナルなど、各種レポートが細かくて手厚い
- 性格や地頭といった先天的な資質を判定できる
- 結果は即座にチェック可能で時間の削減にも効果的
ここが少し気になる…
- スマホは適性検査しか対応しておらず、タブレットは動作環境に対応していない場合も
株式会社マネジメントベース
HRベース適性検査
ここがおすすめ!
- 性格・気力・知的能力など「働く価値観」を見える化できる
- メンタル不調が発症するリスクに着目した検査が行え、休職や離職の防止にも効果的
- 1社にあたり3名までサンプル診断を試せるため、導入に当たりじっくり検討できる
ここが少し気になる…
- スマホブラウザに対応していない
株式会社アドバンテッジ リスクマネジメント
アドバンテッジインサイト
ここがおすすめ!
- 日本国内で唯一「EQ能力」の測定が行え、性格ではなく能力で判断できる
- 17の視点からストレス耐性を計測し、潜在的な要素だけでなく現在の状態も可視化する
- 得点が高いほどいい判定なため、面接担当者がすぐに分かる
ここが少し気になる…
- 「ストレス耐性」に特化した検査のため、その他にフォーカスした検査を行いたい場合には不向き
株式会社フォスターネット
CPAG・CPAB適性検査
ここがおすすめ!
- CPAGは主に新卒採用候補者を対象に、基礎的な学力・メンタルヘルス・ストレス耐性・行動特性などの基礎能力を合わせて診断可能
- CPABでは中途採用候補者や従業員を対象に、基礎能力・メンタルヘルス・ストレス状態の把握や企業文化とのマッチングを診断できる
- WEB受験が可能なため検査が手軽に行いやすい
ここが少し気になる…
- 対象者に合わせて2種の検査を使い分ける必要があるため場合によってはコストがかかることも
株式会社ダイヤモンド社
DIST
ここがおすすめ!
- ストレス耐性に特化した測定内容で、自分で対処する資質を可視化
- 個人の変化・組織の現状を実施者が把握できる
- 利用環境に合わせて診断形式の選択が可能
ここが少し気になる…
- 大量受検者向けプランでは、別途導入費用がかかる
株式会社ベクトル
PET II
ここがおすすめ!
- 独自のコンピテンシーモデルに基づいて開発
- 受検者の組織人材としての適性を多面的視点から診断し、可視化
- 採用・人材育成・カウンセリング等の場面で役立つ
ここが少し気になる…
- 年間での使い放題プランについての詳細や料金は問い合わせが必要
株式会社ダイヤモンド社
I-Dats
ここがおすすめ!
- 職場適応性DPI、ストレス耐性DIST、基礎知的能力DBITのWeb検査を一度で受検・採点可能
- それぞれのテストで別々の診断表が作成されるため情報量が多く活用しやすい
- 企業担当者、受検者ともに複数回実施の試験より負担が少なく効率的
ここが少し気になる…
- 複数試験をおこなうため1人あたりの価格が高価になる
株式会社トライアンフ
採用適性検査CUBIC TRIUMPH ver.
ここがおすすめ!
- 豊富な項目から選べる「職務適正」「設定基準結果」など、細かな設定が行えて自社にあった人材を見抜ける
- 応募者の共感を得やすい動機付けが行える「キャリア志向」の可視化
ここが少し気になる…
- プランの種類や価格は問い合わせて確認
ストレスチェックサービスを利用する際の注意点

ストレスチェックサービスを導入すれば安心と思ってしまいがちですが、利用する上で注意すべき点がいくつかあります。特に、費用の確認や従業員への説明、結果の活用方法などを考えておかないと、せっかく取り組んでも十分に効果を発揮しないことも考えられます。
ここでは、ストレスチェックサービスを使うときに気をつけるべき3つのポイントについて、順番にわかりやすく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
ストレスチェックサービスを利用する際の注意点
トータルコストを確認しておく
ストレスチェックサービスを利用する際は、あらかじめトータルコストを確認しておきましょう。ストレスチェック自体は1人あたり300円〜1000円程度が一般的ですが、フォローアップや分析レポートの作成まで依頼する場合は、別途費用がかかることがあります。
また、従業員数が多い企業や複数拠点に対応する場合は、導入コストがさらに高くなることにも留意が必要です。サービスによっては料金体系がわかりづらいこともあるため、基本料金のみか、オプション費用はどれくらいかかるのかなど、契約前に詳細を確認しましょう。
もし費用をなるべく抑えたい場合は、厚生労働省が無料で提供しているストレスチェック実施プログラムを使うという選択肢もあります。
従業員への周知と理解促進に努める
ストレスチェックを行う前は、従業員に対してしっかりと説明を行い、安心して受けてもらうことが重要です。
なぜストレスチェックを実施するのか、結果は誰が見るのか、個人情報はどう守られるのかなどを丁寧に伝えなければ、従業員に不安を抱かせるリスクがあります。特にチェック結果が人事評価に使われたり、上司に知られたりするのではと心配する従業員も多いです。
法的な面でも、結果は個人の同意なしに第三者に提供してはいけないと決まっているため、その点を明確に伝えることが信頼につながります。周知のためには、説明会の実施や社内向けの資料を配布するといった工夫も必要です。
実施だけでなく結果の活用が重要
ストレスチェックは実施すること自体がゴールではありません。最も重要なのは、その結果をもとに職場環境の改善や従業員へのサポートに活かすことです。制度が義務化されてから、多くの企業が形だけのチェックにとどまってしまうケースも少なくありません。
しかし、それではメンタルヘルスの向上にはつながらず、ストレスが高い従業員への適切なフォローも難しいです。そのため、チェック後は集団ごとのストレス傾向を分析し、特定の部署で問題がある場合は、その原因を特定して改善策に反映させることが求められます。
また、高ストレスと判定された従業員には、産業医との面談や専門的な支援を提供するなど、個別対応も必要です。チェックの結果を放置せず、どう活用するかに焦点を当てることで、はじめて意味のある取り組みになります。
まとめ

ストレスチェックサービスとは、従業員一人ひとりのストレス状態を数値化し、その原因や傾向を見える化できるサービスです。サービスを選ぶ際は、自社に適した受検方法や実施者の代行有無、フォローアップにまで対応してくれるかを確認することが重要です。
ただし、ストレスチェックは単に実施するだけでなく、費用の全体像を把握し、従業員に対して目的や個人情報の取り扱いを丁寧に説明することも大切です。また、チェック結果を活かして、職場環境を改善する仕組みを整えることも必要です。
そのため、ストレスチェックサービスの機能や料金だけでなく、運用体制や従業員が安心して受検できる仕組みづくりも大切です。この記事を参考に、細かなポイントに注意して最適なサービスを選び、効果的に活用しましょう。





