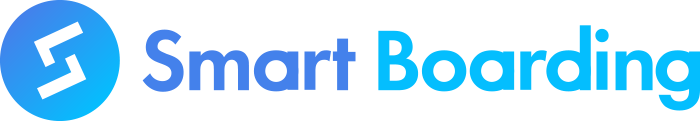おすすめのLMS(学習管理システム)12選|選ぶ際のポイントも解説

Check!
- LMSは、自社に合った機能や必要なコンテンツがあるかなどを確認して選ぶ
- オンライン研修だけでなく、集合研修も一元的に管理できるものがおすすめ
- LMSの導入後は、従業員に使い方を説明し、運用体制を整える必要がある
LMSとは、学習コンテンツの配信や受講者の管理を行うためのシステムです。主に社内研修を目的として多くの企業で導入が進んでいますが、多数のシステムがあるため、自社の用途に合わせて選ぶことが重要です。この記事では、おすすめのLMSや選ぶ際のポイントを解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
LMS(学習管理システム)で社内外の教育・研修を効率化

LMSとは「Learning Management System」の略称で、日本語では「学習管理システム」と訳されます。eラーニングの学習教材を一元管理できるツールであり、教育機関をはじめ、近年は企業における社内研修や資格取得を目的にした利用も増えています。
LMSを企業に導入すると、従業員の学習状況をシステム上で一元管理できるだけでなく、従業員側も自身の学習成果を把握しやすくなるなど、管理者・受講者双方にメリットがあります。
なお、LMSによってできること・強みを持つ分野が異なるため、導入効果を高めるためには、自社の用途に合わせて選ぶことが大切です。本記事では、LMSの選び方のポイントや、おすすめの製品について解説します。

LMS(学習管理システム)とは|eラーニングを効率化する基本機能から失敗しないための選定ポイントも徹底解説
LMSは従来のeラーニングにおける課題を解決するために誕生し、従業員個々の学習管理を可能にします。本記事では、LMSの機能・種類・メリットなどの基礎性能に加え、最適な選定ポイントを解説。従業員のスキルアップや学習環境に課題を抱えている企業は必見です。
LMS(学習管理システム)は機能と教材の充実度で選ぶ

LMSを選ぶ際は、「必要な機能があるか」「自社のオリジナル教材は利用できるか」「自社に合った教材があるか」の3つに注目しましょう。これによって、自社の用途に合ったLMSを導入でき、効果的な人材教育にもつなげやすくなります。
あわせて、操作性や集合研修への対応可否、費用、セキュリティ・サポート体制にも注目するのがおすすめです。それぞれのポイントについて、次の章から詳しく解説していきます。
【重要なポイント3つ】
- 必要な機能があるか
- 自社で作った教材を利用できるか
- 自社に合った教材が用意されているか
【その他の比較ポイント】
- 誰でも使いやすいか
- 集合研修の管理も可能か
- 費用は適正か
- セキュリティ・サポート体制を確認
LMS(学習管理システム)の選び方で重要な3つのポイント
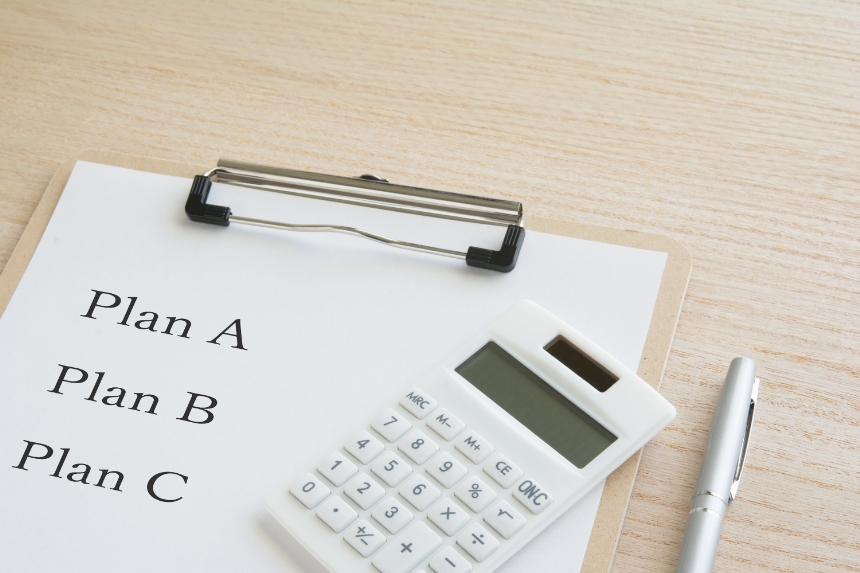
搭載機能や利用できる教材の種類はLMSによって異なります。自社の希望に近い学習体制を実現するためにも、必要とする機能や教材が揃っているかを確認しましょう。ここでは、LMSの選び方で重要な3つのポイントを解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
LMS(学習管理システム)の選び方で重要な3つのポイント
必要な機能があるか
LMSによって搭載機能が異なるため、自社に必要な機能の有無を確認しましょう。例えば、学習管理に関する機能といっても進捗管理や学習履歴分析など、目的に合わせて機能が細分化しています。
これらの機能はLMSの使い勝手や導入効果に直結するため、どのような機能があるかは詳細に確認すべき事項です。ここからは、LMSにあると便利な機能の例について、目的別に紹介していきます。
受講者の学習管理
受講者ごとの学習進捗や、教材別の受講状況を一目で確認できる機能があると、大量の学習者がいる場合でも効率的な受講管理が可能です。あわせて、学習履歴の分析機能があれば、受講者ごとの習熟度を見える化でき、適切なフィードバックにつなげやすいです。
受講者の学習管理に関する機能には、この他にもオリジナルの学習コースの設定、学習者ごとの教材の割り当て、グループごとのレポート出力などもあります。
また、学習者自身で学習履歴や成績を確認できるLMSは、それぞれが自身の進捗を把握しやすく、自主的な学習やレベルアップを自然に促せます。
コミュニケーション機能
オンラインでの学習は、疑問を講師に質問する場がなく、分からないことが分からないままになるケースも少なくありません。さらに、基本的に個別学習であるため、孤独感を感じやすく、モチベーション維持が難しいのも課題です。
これらの解決に役立つのが、LMSのコミュニケーション機能です。講師と受講者あるいは受講者同士の双方向での交流が可能となり、疑問をその場で解消しやすく、他の受講者と切磋琢磨しあえる環境を構築できます。
講師と受講者の交流に役立つ機能として、ライブ配信機能やチャット機能が代表的です。また、掲示板やグループディスカッション機能は、受講者同士の活発な交流も促せます。LMSごとのコミュニケーション機能の詳細を確認し、自社に適したものを導入しましょう。
多言語対応
近年は、外国人従業員を積極的に採用する企業も増えています。受講者が日本語話者に限らない場合は、必要な言語に対応したLMSを導入する必要があります。また、言語の種類だけでなく、設定の自由度も注目すべきポイントです。
例えば、言語の切り替えを管理者が一括で管理するLMSや、学習者ごとに設定できる機能を備えたものなど、製品によって言語設定の方法が異なります。管理者の負担や安全な運用ができるかに配慮した上で、最適なツールを検討しましょう。
自社で作った教材を利用できるか
教材を自社で作成すると、自社の理想に近い教育施策が可能になり、さらに教材の調達コストも抑えられます。オリジナルの学習教材を利用したい場合は、自作教材の配信ができるLMSを選びましょう。
なお、教材作成機能を備えたものは、教材の作成から配布・管理までをシステム上で一本化でき、教材管理がさらに効率化します。また、LMSの中には、自作した教材の社外販売に対応したものもあります。
業界全体でのスキル向上や自社の収益につなげたい場合は、これらの機能の有無にも注目しましょう。
配信できる教材の形式も確認
LMSによって、動画・スライド・PDFなど対応する教材の形式はさまざまです。つまり、教材を自作する場合には、自社が求める教材形式の作成・配信に対応したLMSを選ぶ必要があります。
これらの確認作業により、自社の方針に合わせた教材作成が可能になり、教育施策の自由度も高まります。また、受講者にとって利便性の高い教材を利用することで、学習の満足度を高められるメリットもあります。
自社に合った教材が用意されているか
既製品の教材を利用したい場合は、LMSごとのコンテンツのラインナップに注目する必要があります。自社が求めるコンテンツを提供していない場合、ツールの導入効果が低減する恐れがあるためです。
一般的に、コンテンツ数が豊富なLMSは多分野を網羅的にカバーしており、業種・業態に関係なく利用しやすいです。ただし、教材数が多いほど費用も高額化しやすいため、必要なコンテンツだけを組み合わせて利用できるかどうかにも注目しましょう。
LMS(学習管理システム)のその他の比較ポイント

LMSは、上記のポイントに加えて、使いやすさ・集合研修の管理の可否・費用・セキュリティやサポート体制にも注目するのがおすすめです。ここからは、LMSのその他の比較ポイントについて解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
LMS(学習管理システム)のその他の比較ポイント
誰でも使いやすいか
LMSは従業員全員で利用することが多いため、誰でも操作しやすいツールを選びましょう。操作が難しいものは受講へのハードルが高く、社内に浸透しない恐れがあります。結果として、人材育成の質の低下にもつながりかねません。
ITツールに不慣れな従業員の割合が大きい場合は、直感的に操作できるUI/UXのツールがおすすめです。シンプルな画面デザインのものは、誰でも比較的使いやすいでしょう。
集合研修の管理も可能か
LMSによっては、集合研修の管理にも対応しています。特に介護や医療といった技術系の業種では集合研修の実施頻度が高いため、集合研修もまとめて管理できるツールを検討しましょう。
例えば、集合研修の受付・出欠確認・受講履歴ができるツールなどがおすすめです。オンライン研修と集合研修を1つのシステム上で管理できることにより、従業員ごとのスキルや習熟度が一目で分かり、人材育成のさらなる効率化が見込めます。
費用は適正か
LMSは長期にわたる運用が想定されるため、無理なく運用し続けられる価格帯のツールを導入しましょう。企業の成長や従業員の増加に合わせて、段階的に機能拡張やコンテンツの追加ができるツールであれば、必要最小限のコストでの運用が可能です。
なお、LMSの運用費用は、大きく分けて初期費用と月額利用料の2種類があります。また、クラウド型のLMSは、一律料金で利用できる「月額固定制」と、ユーザー数などに応じて料金が変動する「従量課金制」に分化します。
サービスごとの料金体系を確認し、自社の予算に見合ったLMSを導入しましょう。
セキュリティ・サポート体制を確認
セキュリティ対策やサポート体制も、LMSを選ぶ上で重要なポイントです。特にクラウド型のツールはインターネットを介して利用するため、情報漏洩のリスクが比較的高く、社外秘の教材が外部に漏洩する恐れもあります。
これらのリスクをできる限り小さくするためにも、万全のサポート対策を備えているかを確認しましょう。例えば、通信の暗号化や多段階認証、ユーザー別のアクセス権限設定の有無に注目するのがおすすめです。
あわせて、万が一の緊急時にどのようなサポートが受けられるかも確認が必要です。また、ITツールの操作・運用に不安がある場合は、基本操作などのレクチャーが受けられるサービスを検討しましょう。
おすすめのLMS(学習管理システム)12選
株式会社プラスアルファ・コンサルティング
タレントパレット

株式会社プラスアルファ・コンサルティング
タレントパレット
採用から育成までをワンプラットフォームで!受講管理の手間を削減したい方におすすめ
ここがおすすめ!
- 多様な人材データに基づいて人材管理
- 活用が可能人事と従業員にとって使いやすいデザインと操作性
- 人事評価や労務管理をはじめ、幅広い領域の「人事DX」を実現
- 採用から育成・研修はもちろん、労務や最適配置、健康管理など幅広い機能をワンプラットフォームで行える
- 未受講者へのリマインド・テスト採点・研修レコメンドなどあらゆる管理作業を自動化
- 研修内容に対するレビュー機能で、教材の見直し・改善が図れる
ここが少し気になる…
- 教材やカリキュラム設計は自社で行う必要がある
- 提供教材はビジネスの必須カテゴリメインなので内容が浅く感じることも
-

人事考査を一定の役職以上が評価において管理できるメリットがある。一般社員からするとブラックボックス化していることになるが、評価側は見えない点がよいため、管理設定しやすいメリットがある。
-

上司との面談の際は、こちらのツールをみながらフィードバックなどをもらっています。考課の際は進捗状況などこちらを確認すればOKです。オンライン研修もできるのは便利だと思いました。
-

自身のスキルや経験を可視化できるため、これまで意識していなかった強みやキャリアの方向性を客観的に見直すきっかけになりました。 また、性格テストから自分の仕事観等が分かり、新たな発見も期待できる点、メンバーの仕事の価値観も参照すれば、どのように接してほしいか等のヒントが見つかるかもしれない点がメリットかもしれないです。



Smart Boardingとの比較はこちら

【2026年最新】LearnO vs Smart Boardingを徹底比較|どちらがあなたに合う?評判・機能・料金で検証!
今、eラーニングシステムを導入する企業が増えています。特に「LearnO」と「Smart Boarding」は2大人気サービスで、評価を見てもどちらが本当に自社に合うサービスなのか悩んでいる方も少なくありません。本記事では、徹底比較したビジコン編集部が目的別・使い方別に違いを明確に解説します。
ここがおすすめ!
- 企業の規模に合わせた料金体系があり、どれだけ費用が掛かってくるか予算を立てやすい
- 年に4回以上のアップデートが行われており、PCの最新のOSにも対応できる
- デザインの選択やロゴの登録が可能で、オリジナル感ある資料が作れる
- 独自の教材をアップロードし、自由に設定した価格でエンドユーザーへ再販売することができる「OEM制度」も展開している
ここが少し気になる…
- 教材は自社で作成する必要があるため、1から始める場合は時間や労力が掛かる可能性も
株式会社Oyster
OneCompliance(ワンコンプライアンス)

株式会社Oyster
OneCompliance(ワンコンプライアンス)
コンプライアンスに特化!上場準備中/IPO準備中、上場企業、大手グループ会社、監査法人、金融機関/フィンテック、中堅/中小企業の方に特におすすめ

ここがおすすめ!
- 上場準備中/IPO準備中の企業にも最適
- ダッシュボードや自動リマインダーなど管理工数を最小化
- 初期費用なし、受講人数に合わせた料金体系のためコストを最適化
ここが少し気になる…
- 費用は人数に応じた課金体系のため、問い合わせで確認



LearnOとの比較はこちら

【2026年最新】LearnO vs Smart Boardingを徹底比較|どちらがあなたに合う?評判・機能・料金で検証!
今、eラーニングシステムを導入する企業が増えています。特に「LearnO」と「Smart Boarding」は2大人気サービスで、評価を見てもどちらが本当に自社に合うサービスなのか悩んでいる方も少なくありません。本記事では、徹底比較したビジコン編集部が目的別・使い方別に違いを明確に解説します。
ここがおすすめ!
- 内定者・新人教育からリーダー・管理職育成まであらゆるシーンで活用
- 属人化を防いでいつでも何回でも学習できる環境を実現
- 自社オリジナルコースの作成や学習進捗管理も行える
ここが少し気になる…
- 電話やメール相談、教育プログラム設計といった手厚いサポートを受けられるのは「充実サポートプラン」のみ
株式会社EdulinX
Reallyenglish
ここがおすすめ!
- 「総合力向上」「スピーキング」「ライティング」「TOEIC対策」など、コースが充実!
- 個々の英語レベルに合わせてカリキュラムを自動で生成するため、効率よく学べる(一部のコース)
- オンライン英会話は業界内で評判のいい「QQEnglish」が提供
ここが少し気になる…
- 期間内にコースを修了しなければならない(別途料金を払えば延長可能)
コードキャンプ株式会社
CodeCamp
株式会社イー・コミュニケーションズ
SAKU-SAKU Testing

株式会社イー・コミュニケーションズ
SAKU-SAKU Testing
初心者にも◎受講者の管理をスムーズに行いたい方におすすめ
ここがおすすめ!
- 不慣れな方でも作成・登録しやすいコンテンツ機能を多数搭載
- あらゆる企業ですぐに役立つ実践的な内容のコンテンツを厳選して用意
- ユーザー管理機能を備えているため、より細かな対象でカテゴリーやグループを紐づけられる
ここが少し気になる…
- 事務局運営やカスタマーデスクを利用する場合はオプション扱いとなる
株式会社Schoo
Schoo for Business
ここがおすすめ!
- 7,000本以上の動画が見放題かつ、普段の生活にも役立つプログラムが豊富なためスキルアップにつながる
- スマホからでも動画を視聴することができ、移動をしている際でも効率よく学ぶことが可能
ここが少し気になる…
- 研修のような基礎的な動画が多いため、内容が浅いと感じてしまう可能性も
-

管理画面の操作がシンプルでわかりやすく、生配信(時間指定配信)がある為、社内でのschoo活用が浸透させやすい仕組みが整っている。
-

たくさんのコンテンツがあり、自発的に利用する人が増えた。これまでの研修は時間を決めて行う必要があり、業務の都合上参加できないことも多かったが、時間や場所を気にする必要がなくなった。
-

興味のある分野を動画でわかりやすく学習することができた
アルー株式会社
etudes Plus

ここがおすすめ!
- 階層やテーマに合わせて学ぶべき教材があらかじめセットになっているため、受講コース決定がスムーズ
- 自社教材のアップロード数は無制限で、動画やテストを組み合わせたオリジナルコース作成も可能
ここが少し気になる…
- 階層・テーマ別セットなど提供教材を利用するには「etudes Plus」プランを契約する必要がある
KIYOラーニング株式会社
AirCourse

ここがおすすめ!
- 定額制では750コース・4,500本以上の動画を備えており、コンテンツ不足解消にもうってつけ
- 1つの動画は5分程度で終わるため、隙間時間の活用にもなる
ここが少し気になる…
- 自社コースでコンテンツ不足になった場合はコンテンツプラスプランへの切り替えが必要
-

・好きなタイミングで講義動画を視聴できる点が大きなメリットでした。倍速再生や途中からの再開機能もあり、限られた時間の中でも効率的に学習を進められました。また、受講履歴が一目で分かるため、学習の進捗管理もしやすく、目標達成に向けた計画的な学習が可能でした。 ・別料金ですが、参考書の配布があったのが良かったです。
株式会社テクノカルチャー
e学びばこ

ここがおすすめ!
- パソコンに慣れていない方でも使いやすい機能とUI
- 販売している教材コンテンツは修正・加工が自由で自社に合わせて使える
ここが少し気になる…
- 教材コンテンツは別途購入の必要あり
- 「同時接続数管理」「IPアドレス制限」「多言語化」などはオプションでカスタマイズが必要
-

マニュアルだけではなかなか浸透しなかった運用ルールなどを、オンラインでの教育教材として研修に利用。進捗状況や理解度なども判定、管理できるので、人材育成ツールとしてもメリットが大きい
-

メリットはやはりユーザー数に制限がなく無制限というところが一番大きい。 サポート体制も電話メールで他に比べると対応してもらえるので助かっている。 オンプレ対応なのでセキュリティが厳しい業界にも強いところもメリットである。
-

誰にとっても使いやすいシンプルな設計で、直感的に操作できます。初めて使う人でも迷わず使えるため、年齢やITスキルに関係なく安心して活用できます。
株式会社ITBee
SpeedLMS Pro

ここがおすすめ!
- 医療業界や官公庁など幅広い分野での導入実績があり、操作性や画面デザインまでカスタマイズできるためITリテラシーが高くない現場にも◎
- 一からのシステム開発ではないため安価で、環境構築費用も不要
ここが少し気になる…
- カスタマイズして利用する場合は、すぐに運用開始できないため注意
LMS(学習管理システム)の導入フローと注意点

LMSを効果的に運用するには、試験運用した上で最適な運用フローを考案することが大切です。ここでは、LMSの導入フローと各段階の注意点について解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
LMS(学習管理システム)の導入フローと注意点
1. 無料トライアルで試用する
LMSを導入するには、まず複数のシステムを試験運用し比較したうえで、自社にとって使いやすいツールを選ぶのがおすすめです。無料トライアルやデモを提供するLMSもあるため、これらから優先的に試験運用しましょう。
従業員にとって使いやすいツールを選ぶために、現場の声を集めることが重要です。ITスキルは従業員によって大きな差があるため、ITツールに不慣れな従業員のスキルに合わせると、スムーズな運用開始に期待できます。
試験運用をすることで、本格運用開始後のイメージを具体的に描けるため、導入前にやるべき要件整理や運用準備も効率化します。
2. 運用体制を整える
次に本格的な運用開始に向けて、運用体制を整える必要があります。具体的には、管理担当者の選定や管理マニュアルの策定、運用フローの決定などを行いましょう。また、従業員に割り当てるID・パスワードの準備も必要です。
同時に、従業員に改めて操作方法や使い方について周知を行います。これらの準備を入念に行うことで、運用開始後のトラブルや混乱が発生しにくくなります。
3. LMSと対面学習の併用を検討する
業種・業態に応じて、LMSと対面学習の併用を検討しましょう。例えば、医療系・工事系といった技術職や、接客・サービス業においては、実技トレーニングが求められることもあります。
LMSだけでは学べない分野については、積極的に対面学習を行いながら、従業員の質の向上に務めましょう。集合研修や対面学習もまとめて管理できるLMSであれば、管理者の業務負担を減らしつつ、従業員管理の効率化にもつなげられます。
まとめ

LMSとは、eラーニングの学習教材の一元管理ができるツールです。受講者の学習管理や教材管理に加えて、オリジナル教材の作成・配布や、講師と受講者・受講者同士のコミュニケーションに役立つ機能を備えたものが登場しています。
近年は多言語対応のLMSも多く、グローバルな人材育成にも役立てられます。集合研修や対面研修もまとめて管理できるLMSであれば、実技研修が必要な業種・業態でも運用しやすいでしょう。
LMSは長期にわたって運用することが多いため、費用・セキュリティ・サポート体制にも注目し、安心安全に運用できるツールを選ぶことが大切です。本記事を参考に、自社の運用に適したLMSを導入し、社内研修や従業員の資格取得の効率化につなげましょう。