契約日と契約締結日の違いとは?決め方や注意点についても解説

Check!
- 契約書の日付は「締結日」と「作成日」の2つであり、「契約日」の明確な定義はない
- 契約開始日が契約締結日であることが多いが、同日ではないケースもある
- 契約書を作成する際はバックデートを避け、日付を空欄にしないよう注意する
契約書の日付は「契約締結日」と「契約書の作成日」の2つであり、実は「契約日」という言葉に明確な定義はなく違いも説明できません。また契約締結日は契約開始日と同日でない場合もあります。この記事では契約書の日付の考え方や期間の指定方法、注意点などを詳しく解説します。
\おすすめの電子契約システムをご紹介/
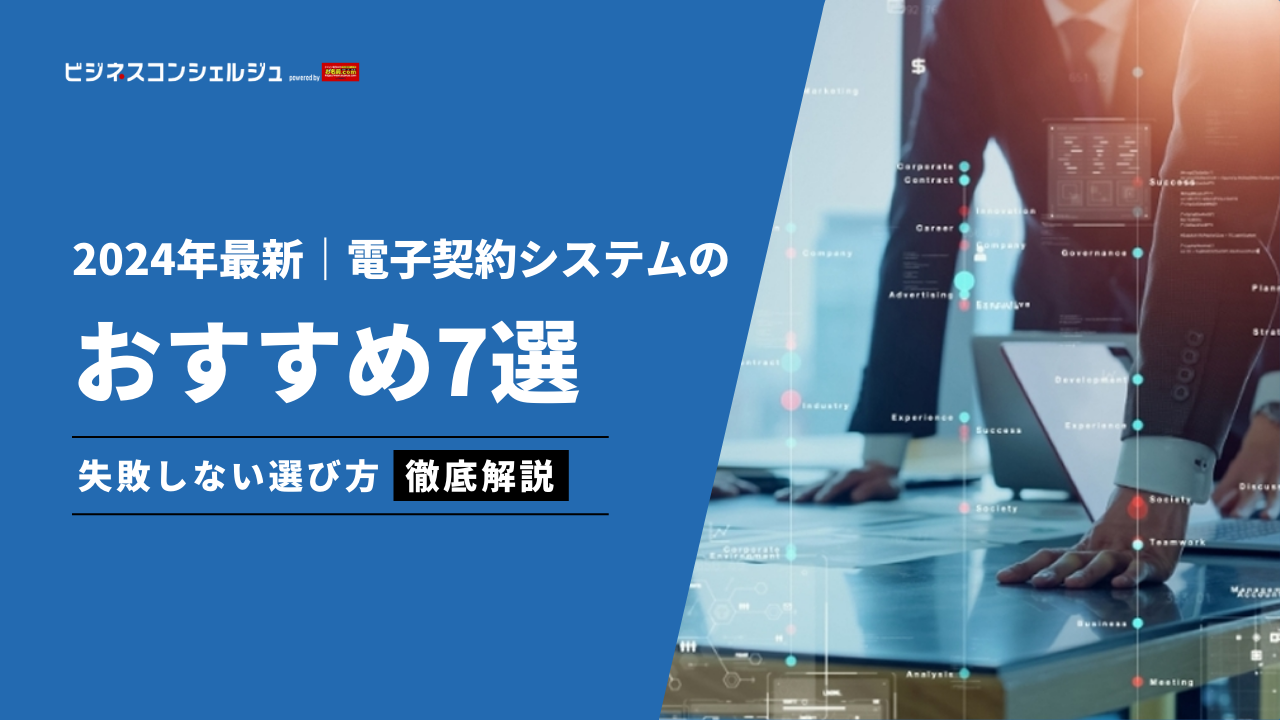
おすすめ電子契約システム7選(全46製品)を比較!【2024年最新/比較表付】
この記事を読めば、あなたの目的に合ったおすすめの電子契約サービスがわかる!電子契約ツールを法令への対応可否、機能性、サポートなどの観点から厳選しました。電子契約システムを導入したくても、種類が多すぎてわからない…そんなあなたにぴったりな電子契約システムを見つけましょう!
おすすめ記事
契約日と契約締結日の違いとは

契約書には日付の記入が必要ですが、一般的に「契約締結日」と「契約書の作成日」の2つがあります。「契約日」という言葉には明確な定義が存在しないため、契約者同士で認識を合わせて契約を結ぶことが求められます。
書き方に不備がある場合、後のトラブルに発展する可能性も考えられるでしょう。契約書の日付の考え方や注意点を抑えておくことが大切です。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
契約書締結日とは
契約書締結日とは、法的効力が発生する日(契約開始日)です。双方の契約当事者同士が署名・押印が完了した日のことを意味します。契約者が複数人いる場合は、最後に署名・押印された日が契約締結日になります。
契約書の日付と契約締結日が異なる日付の場合は、法的に認められるのは契約締結日です。ただ、郵送などでのやり取りになる場合、相手が日付を書かずトラブルになることもあります。契約締結日をいつにするのかは、契約を交渉する段階で決めておくことが必要です。
契約書の作成日とは
契約書の作成日は、契約書を作成した日です。また、一方の当事者が契約内容を記入する日として「記入日」と呼ばれることもあります。業務内容や支払額への影響を考えると、2つの日付は同じ日であることが望ましいと言えるでしょう。
契約書の作成日と締結日を同じ日にしたい場合は、契約当事者同士で事前に打ち合わせを行い、日付を揃えることも可能です。
契約締結日と契約開始日を変える場合

契約締結日は契約開始日(効力が発生する日)と同日ではない場合もあります。契約内容の効力が発生するより前もって締結する場合が多いためです。逆に、遡って適用が必要となる場合もあります。
契約開始日を過去にする場合
すでにプロジェクトが開始しており、後から契約を結ぶ場合に過去の特定の日付を契約開始日にすることができます。このように契約開始日を契約締結日よりも過去の日付にすることを「遡及契約」や「遡及適用」と呼びます。
契約開始日と契約締結日が異なる場合は契約書の条項の中に記載しておく必要があります。例としては、「本契約は、〇年〇月〇日に遡って通用する」などと記載しましょう。
契約開始日を未来にする場合
プロジェクトが開始する前に契約を結ぶ場合に、未来の特定の日付を契約開始日にすることができます。この場合も「本契約は、〇年〇月〇日から有効になる」のように契約書の条項の中に記載しておきましょう。
契約期間の指定も可能
契約内容の記載方法次第では、契約期間を指定することもできます。その際、「契約期間は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする」などの条文を入れることが必要です。
契約期間を指定する場合、契約書の作成日と契約期間は乖離することも珍しくありません。契約期間の計算や初日不算入の原則の必要性が出てくる場合もあるため、期間を決める際には注意が必要です。
契約締結日の決め方

契約締結日は、まず双方の合意の上で決めることが前提となります。契約締結日の決め方にも以下のようないくつかの方法があります。
- 契約開始日に契約締結日を合わせる
- 全ての契約当事者が契約内容に合意した日を締結日とする
- 契約当事者の間で最初に署名された日を契約締結日とする
- 契約当事者の間で最後に署名された日を契約締結日とする
トラブルの発生を防止するためには、契約の締結日に加えて何をもって契約を締結とするか、当事者間で明確にしておくことが必要です。
契約締結日と押印の関係
契約締結の際には、押印または署名が必要です。定期借地権の設定のための契約や任意後見契約などの一部を除くと、契約締結に署名捺印が必ずしも必要とされないことがあります。
しかし、トラブルの発生を防止するためには押印か、それに準ずる仕組みを採用することが望ましいと言えます。
契約書の日付に関する注意点

契約書の日付には、注意しなければいけないこともあります。ここでは、契約書の日付に関する注意点を解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
契約書の日付に関する2つの注意点
バックデートは避ける
契約締結をする際は、バックデートにならないよう注意が必要です。バックデートとは、実際に契約を締結した日よりも過去の日付を締結日として契約書に記載することです。
実際に契約締結した日という事実は異なるため、虚偽の情報を契約書に記載することになります。必ずしもトラブルに繋がるわけではありませんが、コンプライアンス上の問題が発生する可能性もあるため、基本的には避けるべきです。
日付を空欄にしない
契約内容の日付欄は空欄にしないよう注意しましょう。空欄になっていると契約が成立したか分からなくなります。また、勝手に書き加えられてしまいトラブルに発展するリスクもあるため、記入漏れのないよう注意が必要です。
電子契約システムを使えば契約締結もスムーズに

電子契約システムを利用すれば、スムーズに契約締結ができるようになります。電子契約システムとは、インターネット上の電子ファイルに署名・押印して契約を締結できるシステムです。
書類上で契約を交わす必要がないため、契約に関する複雑な日付の管理におけるミスを減らしたり、ペーパーレス化できたりなどのメリットがあります。

電子契約システムとは、企業などが契約時に交わす署名や押印等の書類でのやり取りを電子上で行うことができるシステムです。この記事では、電子契約システムの仕組みや、メリット・デメリット、選び方や導入する際の注意点などを解説します。
まとめ

契約日に明確な定義はなく、効力が発生する「契約締結日」と契約書を作成または記入する日にあたる「契約書の作成日」があります。しかし、契約締結日が契約内容に正しく記載されれば、効力が発生する日を将来または過去に適用させることも可能です。
ただ、契約締結日を実際の締結日より前の日付で記載するバックデートを行うと、トラブルに繋がるリスクもあるため、やむを得ない場合を除いて注意が必要です。
インターネット上で契約を締結できる電子契約システムは、複雑な日付管理やペーパーレス化による業務効率の向上ができます。メリットが大きいと感じる場合は場合は、電子契約システムの導入を検討しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

