Slackと連携できるおすすめのWeb社内報ツール|注意点も解説

Check!
- Web社内報ツールにはSlackと連携できるものもあり、より円滑な情報共有を可能にする
- Slackはスマホで利用する従業員も多く、どこにいてもWeb社内報の通知を受け取れる
- Web社内報ツールを選ぶ際は、セキュリティ対策や機能、サポート体制などを確認する
Web社内報ツールには、チャットツールのSlackと連携できるものもあります。Slackと連携することで、よりスピーディーな情報共有が可能です。この記事では、Slackと連携できるおすすめのWeb社内報ツールや選ぶ際のポイントなどを解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
Web社内報ツールとSlackを連携して情報共有を円滑化

Web社内報ツールをSlackと連携することで、よりスピーディーな情報共有が可能です。Web社内報ツールは、紙やPDFではなくオンライン上で社内報を配信・管理できる仕組みであり、従業員がスマホやPCから手軽に閲覧できる点が特徴です。
Web社内報ツールにSlackの連携機能を組み合わせると、新しい記事の公開や更新情報をSlack上で自動通知できます。特にSlackを日常的に業務連絡の基盤として使っている企業では、社内報と業務の情報が一元化されるため、情報伝達のスピードが格段に向上します。
この記事では、Slackと連携できるおすすめのWeb社内報ツールや選ぶ際のポイントなどを解説します。

Web社内報とは?メリット・デメリット、運営のポイントを解説
Web社内報は、社内報をWeb上で展開することで、作成の効率化・リアルタイムでの情報共有が行えます。テレワークや働き方改革の影響をきっかけに、社内報をデジタル化する企業が増えています。本記事では、Web社内報のメリットやツールの選び方を解説しています。
Slackとは
Slackは単なるチャットアプリではなく、企業のチームワークを支える包括的なビジネス用プラットフォームです。Slackの特徴は、会話をテーマやプロジェクトごとにチャンネルに分けて整理できる点にあります。
メールのように情報が埋もれる心配が少なく、コミュニケーションの効率が大幅に向上します。また、テキストチャットに加え、ファイル共有やビデオ通話・外部サービスとの連携など多彩な機能を持っているのが強みです。
特に、さまざまなビジネスツールとの統合機能により、Google Driveやカレンダーはもちろん、Web社内報ツールとも連携できます。つまり、Slackは単なるチャットではなく、効率的に仕事を進めるための基盤であり、Web社内報との相性も非常に良いツールです。
Web社内報ツールとSlackを連携するメリット

Web社内報ツールとSlackを連携させることで、さまざまなメリットがあります。ここからは、Web社内報ツールとSlackを連携させるメリットについて詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
Web社内報ツールとSlackを連携するメリット
リアルタイムな情報共有が可能になる
Web社内報ツールとSlackを連携する魅力は、記事投稿が自動で通知され、リアルタイムに情報を共有できる点にあります。リアルタイム性を強化することは、従業員の情報格差を減らし、どこにいても公平に最新情報に触れられる環境を整える効果があります。
確認漏れを防げる
従来は「更新されたことに気づかない」「読むタイミングを逃す」といった問題がありましたが、Slackの通知を活用すればこれらのリスクを軽減できます。特にSlackはスマートフォンで利用している従業員が多いため、外出先や在宅勤務中でも即座に通知を受け取れます。
たとえば、経営層からの重要メッセージや緊急の社内連絡も、Slack通知によって確実に届きやすくなります。また、通知からそのまま記事にアクセスできるため、社内報を「読むために探す」手間も不要です。
普段から従業員がSlackを活用していることで、社内報の更新が周知された際も、スムーズな情報共有が可能です。
Web社内報運用の手間を削減できる
記事を公開したあと、全従業員に周知するためにメールや社内チャットでリンクを手動配信するのは、時間も労力もかかる作業です。しかし、Slack連携により、Web社内報の運用担当者にとっても大きな負担軽減につながります。
社内への周知が楽になる
Slack連携を導入すれば、記事が投稿されたタイミングで自動的に通知が配信されるため、告知作業を繰り返す必要がなくなります。
Slack連携をせずにメールやSlackのみで共有をする場合は、遡って見返す必要がありますが、Slack連携をしておけば情報の整理も簡単です。また、周知が楽になるだけでなく、ナレッジの蓄積としても役立ちます。
周知や情報の更新漏れを防げる
Slack連携により通知が統一されることで、伝達漏れや周知のタイムラグも防止できます。Web社内報のツールによっては、更新されたタイミングでSlackに通知が飛ぶように設定ができる機能もあり、従業員への周知漏れ防止に役立ちます。
また、社内報の更新日が明確になるため、「いつから更新されていないのか」も一目でわかります。つまり、Web社内報とSlackを連携させることにより、定期的な情報の発信にもつながります。
Web社内報ツールとSlackを連携する際の注意点

Web社内報ツールとSlackの連携は大きなメリットをもたらす一方で、正しく運用するためにはいくつかの注意点を押さえる必要があります。
便利さだけに目を向けて導入すると、情報の過多による混乱やセキュリティリスクが発生する恐れがあるため、事前に体制を整えておくことが重要です。以下では、具体的な注意点を解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
Web社内報ツールとSlackを連携する際の注意点
セキュリティ対策を確認する
Slack連携を導入する際は、まずセキュリティ面の確認が重要です。連携を行うことで、Web社内報ツールにSlack内の情報へのアクセス権限を付与することになるため、不適切な設定やセキュリティ不足があると情報漏洩のリスクにつながります。
特に社内報には、経営情報や従業員に向けた重要な連絡が含まれる場合もあり、外部に流出してしまうと企業にとって大きな損害になります。そのため、導入時にはツール提供会社のセキュリティ対策が十分であるかを必ず確認する必要があります。
また、権限設定を最小限にとどめ、不要な情報へのアクセスが発生しないように管理することも大切です。
使い方のルールを決めておく
Web社内報ツールとSlackを連携する際には、利用方法に関するルールを事前に決めておきましょう。通知が無秩序に送られてしまうと、重要な情報を見逃したり通知疲れを起こしたりする原因になりかねません。
たとえば、社内報通知専用のSlackチャンネルを設けることで、情報が分散せず一元的に確認できるようになります。また、既読した際にはスタンプやリアクションで反応するなど、従業員全員が共通して取り組めるルールを設ければ、周知状況の把握もしやすくなります。
さらに、通知の頻度や内容についてもガイドラインを作成しておくと、効率的に投稿できるようになります。こうしたルールづくりは、一見手間に見えても長期的には社内報を「確実に読まれる情報発信ツール」として機能させるための基盤となります。
Slackと連携できるおすすめのWeb社内報ツール
ウォンテッドリー株式会社
Story
評判・口コミを紹介
Storyを導入してからというもの、社内報へのコメントやいいね機能を通して社内コミュニケーションが活性化したと感じています。更新の告知はチャットツールで行っていますが、社内報を楽しみにしてくれている人が増えたので、メンバーのチャットに対するレスポンスがよくなりました。育成の現場では、講座への質問数が増えたという嬉しい声もあがっています。
利用事例(株式会社LULL)|ウォンテッドリー株式会社
ここがおすすめ!
- 洗練されたフォーマットにより、手軽におしゃれな投稿ができる
- 手間のかかるサイト構築の必要がなく、権限があれば誰でも執筆・公開が可能
- 書けたらすぐに投稿ができるシンプルな機能で使いやすい
ここが少し気になる…
- シンプルな仕組みのため搭載している機能が少ない
その他のWeb社内報ツールの選び方

Web社内報ツールを選ぶ際には、Slack連携の可否や料金だけでなく、自社の利用環境や目的に合致しているかを判断する必要があります。特に重要なのは次の3つのポイントです。まず「ツールのタイプが自社に合っているか」を確認することです。
記事型・動画型・ハイブリッド型など、社内報の発信スタイルに適したツールを選ぶことが効果的な運用につながります。次に自社に必要な機能が備わっているかを見極めましょう。
閲覧率の分析や検索機能、アンケート機能など、自社の課題解決に直結する機能が揃っているかがポイントです。そしてマルチデバイス・アプリ対応があることも欠かせません。
その他にも以下のような比較ポイントを確認すると自社に適したWeb社内報ツールを選べるでしょう。
【重要なポイント3つ】
- ツールのタイプが自社に合っているか
- 自社に必要な機能が備わっているか
- マルチデバイス・アプリに対応しているか
【その他の比較ポイント】
- 担当者が作成・運用しやすいか
- サポート体制が充実しているか
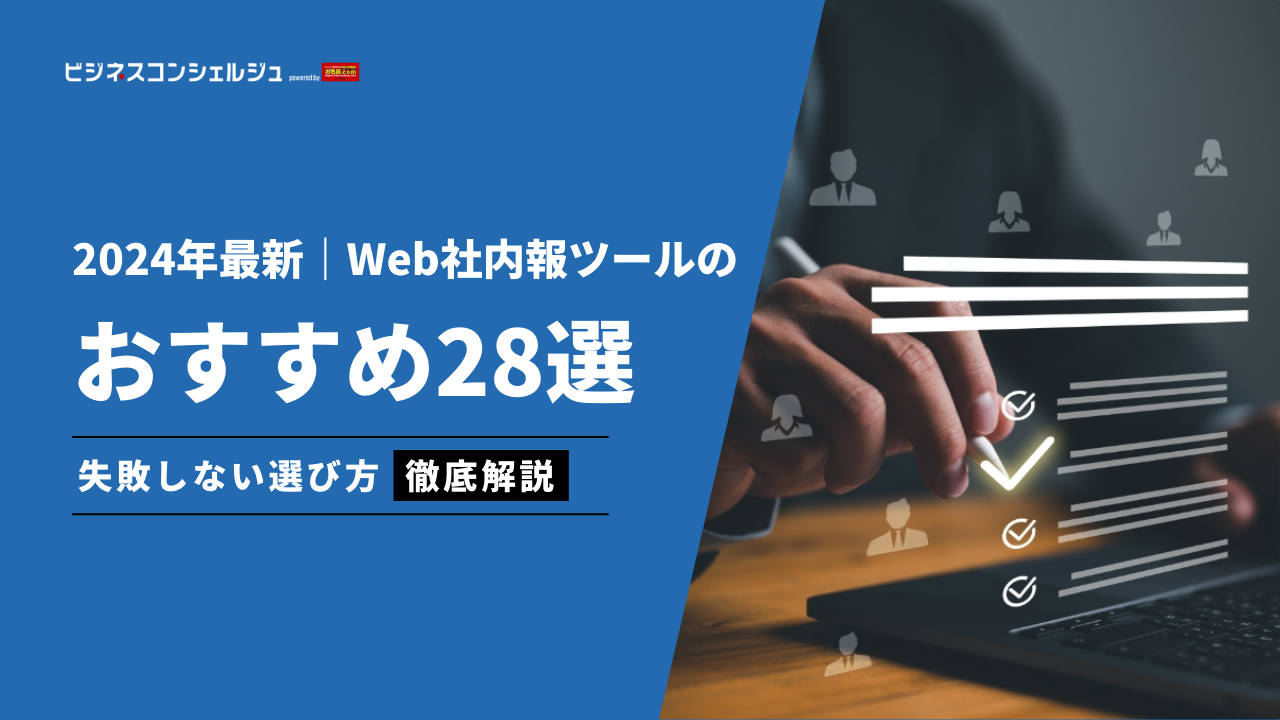
Web社内報ツールおすすめ10選(全28選)を徹底比較!選定のポイントや導入時の注意点を解説
Web社内報ツールとは、システム上で社内報を作成・更新・修正などができるツールです。紙媒体と違って、リアルタイムで共有できて物理コストが発生しないことから、近年多くの企業で社内報のデジタル化が進んでいます。本記事では、徹底比較したおすすめのWeb社内報ツールや選び方などを詳しく解説します。
まとめ

Web社内報ツールとSlackを連携させることで、社内の情報共有は格段に効率化し、従業員が必要な情報をリアルタイムで受け取れる環境を整えられます。また、スマートフォンで利用している従業員も多いため、オフィスにいない状況でも情報をキャッチできます。
特にSlackは多くの従業員が日常的に利用しているため、社内報の記事が公開されると自動的に通知される仕組みを作れます。しかし、重要な情報を見逃さず即座に確認できる一方で、セキュリティ対策の確認や使い方のルールを整えることも重要です。
そのため、本記事の内容を参考に自社に合ったツールを導入し、Slackとの連携でスピーディーな情報共有に役立ててください。

