eラーニングと通信教育は何が違う?両者の違いやメリットを解説
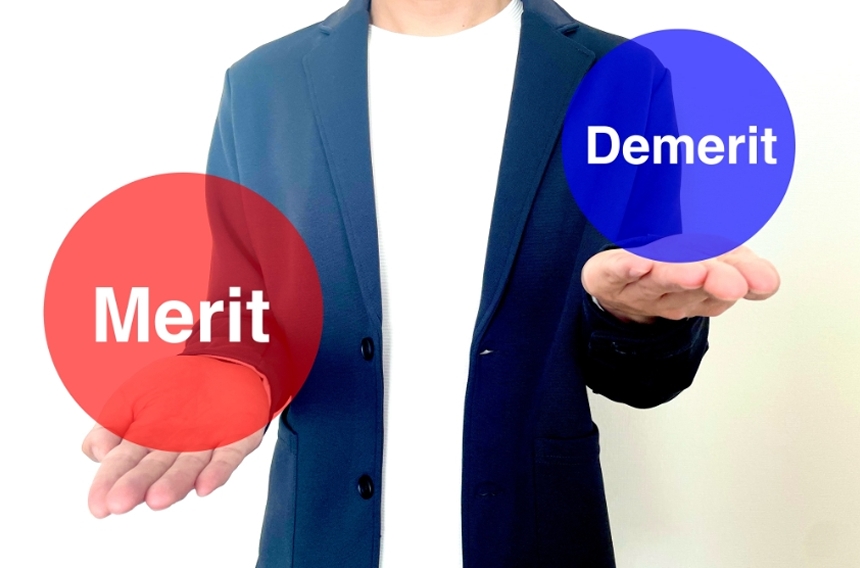
Check!
- eラーニングは、ブロードバンド化やスマホ・タブレットの普及により加速した
- eラーニングでは、通信教育では管理しにくい個人の学習状況を把握することができる
- eラーニングを導入するなら、eラーニングシステムがおすすめである
eラーニングは、時代の変化と共に通信教育が進化したもので、現在の主流はeラーニングになっています。本記事では、eラーニングが普及した背景となっている歴史を紹介し、通信教育との違いやそれぞれのメリット・デメリット、導入準備などについて解説します。
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
eラーニングと通信教育の違い

eラーニングと通信教育の最も大きな違いは、教材が紙か電子かです。そもそもeラーニングとは、インターネットを通じた学習法です。パソコンやスマートフォンを使い、インターネット上で提供されている教材(コンテンツ)で学習を進めます。
近年では会社の研修・スキルアップなど幅広い学習の場に普及し、多くの企業がeラーニングを導入しています。
対して通信教育とは、指定された紙の教材(教科書・ワークなど)を使って学習する方法で、主に自己啓発的な学習で活用されています。課題(ワーク・テストなど)は郵送で主催元に送付し、添削されたものが郵送で手元に戻ってきます。
従来の自宅学習は紙教材を使った通信教育が主流でしたが、インターネットが普及した現代では、より利便性の高いeラーニングが主流になっています。
eラーニングとオンライン研修の違い
インターネットを通じた教育には、eラーニングのほかにオンライン研修もあります。両者はよく似ていますが、リアルタイムかどうかという点が異なります。
オンライン研修とは、講師による研修をリアルタイムで配信するものです。対してeラーニングでは、録画された研修を配信・視聴するスタイルが一般的です。
また、オンライン研修とeラーニングでは、目的にもやや違いがみられます。オンライン研修が主に知識の定着を目的とするのに対し、eラーニングは知識の共有・インプットのために行われます。
オンライン研修はリアルタイムの研修であり、マイクとカメラをつなげば不明点や疑問点をその場で講師に質問できます。インプットとアウトプットの両方が可能であるため、知識の定着を進めたい場合に適しています。
一方、eラーニングは録画コンテンツを視聴するものが多く、講師への質問はできません。インプットのみの学習となるため、定着よりも知識の共有に適しています。
通信教育からeラーニングに進化した歴史

自宅学習が従来の通信環境からeラーニングに進化する過程には、さまざまなターニングポイントがありました。eラーニングへの理解を深めるためにも、その歴史についてもある程度知識を持っておきましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
通信教育からeラーニングに進化した3つの歴史
CD-ROM搭載PCの普及
前述の通り、従来の通信教育は紙の教材を利用していました。しかし1990年代の終わり頃にCD-ROM搭載PCが誕生したことにより、教材にCD/DVD-ROMを利用した通信教育が誕生しました。これが通信教育の電子化、eラーニングの始まりといえます。
講師の講義を録音・録画で受講でき、中には教科書をパソコン上で閲覧できるものもあります。従来の紙面のみで行っていた講義に比べ、「ライブ感」のある教育が可能となり、大幅な学習効果の向上がみられました。
インターネットのブロードバンド化
インターネットのブロードバンド化に伴い、eラーニングの進化もスピードアップします。ブロードバンド化とは、簡潔にいえば通信回線の高速化です。インターネットのブロードバンド化により、大容量データの送受信が可能となりました。
たとえば従来はCD/DVD-ROMで行っていたコンテンツ視聴をインターネット上で行えるようになったほか、課題の提出もインターネット経由となりました。また、提出した課題の採点もオンラインで行え、その場ですぐに点数や習熟度が判明します。
加えて従来のような教材や課題の郵送の手間もなくなり、学習の利便性がより高まりました。
スマホ・タブレットの普及
スマートフォンやタブレットといったスマート端末の普及も、eラーニングの発展に深い関係があります。それまでeラーニングはパソコンでしか行えず、学習はパソコンがある場所でしか行えませんでした。
しかしスマート端末の登場により、パソコンと同クオリティの映像・音声・データを持つコンテンツを、場所に制限されず利用できるようになりました。
たとえば、従来は自宅でしか視聴できなかったコンテンツが、通勤や通学のすきま時間を利用して視聴できるように変化しました。より手軽さが増したことからeラーニングの利用者が急増し、現代のような盛況ぶりを見せています。
通信教育のメリット

従来の通信教育には、eラーニングと形態が異なっているからこそのメリットがあります。eラーニングと比較しながら、また自社・自身の学習スタイルにも置き換えながら理解を深めましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
通信教育のメリット
学習が形に残る
通信教育では紙媒体の教材を用いるため、学習が形に残る点がメリットです。たとえば、テキストの書き込み・マーカーといった足跡が残せるため、後から見直しをしたいときにも便利です。学習の達成感を得やすい点も、紙媒体の教材ならではの魅力でしょう。
記述式でアウトプットできる
通信教育では、課題やレポートは記述式で取り組みます。インプットした情報を自分の言葉で整理・系統立ててアウトプットできるため、知識の定着を促せます。
見るだけでなく実際に問題を解く、書くといったアウトプットは理解を深めます。見るだけの学習は手軽ではあるものの、知識の定着にはやや向かないため、通信教育の記述式である点は身になる学習が期待できます。
学習環境の設備が簡単
通信教育は、どのような学習環境でも行える点がメリットです。基本的に教材やノートを広げる場所さえあれば学習を進められ、eラーニングのようにパソコンの設置・通信環境の確保といった手間やコストはかかりません。
eラーニングの学習環境整備に必要なコストと比較すると非常に安価な点も、通信教育の大きなメリットといえます。
通信教育のデメリット

通信教育には、学習状況の把握が難しく、タイムラグが発生するといったデメリットも存在します。それぞれの内容を解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
通信教育のデメリット
個人の学習状況を把握しづらい
通信教育では、主催者が各受講者の学習状況を把握しづらいという課題があります。基本的に受講者の状況が知れるのは、提出されてきた課題を受け取ったときのみです。
課題は科目を一定程度履修する度に発生し、主催元や講師は課題を受け取ることで「この受講者はこの科目まで学習が進んでいる」と推測できます。定期的に課題が提出される場合は問題ありませんが、提出が途絶える・遅くなると、今の学習状況を知ることはできません。
計画的に研修や教育を進めたい場合、各受講者の状況をリアルタイムで把握できないことは大きなデメリットとなります。
タイムラグが発生する
通信教育は、課題を郵送で提出・添削されたものが郵送されるため、提出から結果がわかるまでに一定程度のタイムラグが発生します。
学習スピードにも多少なりとも影響を及ぼすため、学習へのモチベーション低下を招きかねません。また、課題の提出や返却ごとに郵送代がかかる点もデメリットです。
eラーニングのメリット

通信教育が抱える課題を解決したのがeラーニングです。通信教育と比較した場合のeラーニングのメリットについて、企業側(主催元)と受講者側に分けてそれぞれ解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
企業側のメリット
eラーニングの導入により、企業側は学習状況の把握が容易・低コストで実施できる・受講者とコミュニケーションが取れるといったメリットを得られます。
コストは抑えつつ、より効果的な学習環境を整備できるため、従業員のスキル・知識の向上や人材の育成につなげられます。
学習状況を把握しやすい
eラーニングシステムは、各受講者の学習状況の把握に優れています。多くのeラーニングシステムは受講管理機能を備えており、コンテンツの利用履歴などを元に、誰が・どの学習コンテンツを・どれほど学習したかをリアルタイムで把握できます。
また、eラーニングシステムでは、科目の履修ごとにテストやアンケートを配布でき、その結果によって習熟度や理解度が可視化されます。理解が進んでいない箇所については個別にアドバイスやフィードバックを与えられるため、着実な成長を促せます。
低コストで行える
eラーニングシステムの導入により、教育にかかるコストを低減できます。たとえば集合型の研修と比べて、eラーニングでは次のようなコストをカットが可能です。
- 会場費
- 資料の印刷代
- 講師代
- (講師の)交通費・昼食代・宿泊費
- 資料の印刷の手間
- 会場確保の手間
- 会場設営・資料準備の手間
- (講師の)交通手段・昼食・宿泊施設手配の手間
通信教育と比べた場合、紙の教材を使用しないため、紙代・印刷代のほか、印刷や資料配付の手間を削減できます。
特に従業員規模が大きい企業は、会場代や資料の印刷代が莫大になりやすいため、インターネット上で個別に学習を進められるeラーニングの導入には大きな意義があります。
コミュニケーション機能を使える
eラーニングシステムによっては、コミュニケーション機能を搭載したものがあります。たとえば、チャットやビデオ通話を利用した講師・生徒の双方向のコミュニケーションが代表的です。質問や疑問点をその場で解消できる点がメリットです。
あるいは日記の公開機能や友達機能を備えたシステムもあり、自分の学習状況や学習に対する思いを他者と共有できます。互いに励まし合ったり、アドバイスを与え合ったりできるため、学習へのモチベーションの維持・向上を促せます。
eラーニングは基本的に録画コンテンツを各自で視聴するスタイルであり、孤独感を感じやすい側面があります。孤独感はモチベーションの低下につながりやすいため、講師・生徒間のコミュニケーションを促す機能を備えたシステムの導入は重要です。
受講者側のメリット
eラーニングシステムは、受講者にとっても大きなメリットがあります。代表的なメリットは、場所・時間にとらわれずに自分のペースで学習を進められる点です。
集合型の講義は、講義の日時に合わせて会場に足を運ぶ必要がありました。講義にあわせてスケジュールを調整せねばならず、移動に時間・交通費がかかる点も難点です。さらに、他の学習者と学習スピードを合わせなければならない点も課題でした。
一方、eラーニングシステムでは自分のスケジュールにあわせて、好きな時間・場所で録画コンテンツを視聴できます。移動の手間や交通費は必要なく、一度で理解が追いつかない内容については、繰り返しコンテンツを確認できます。
集合型の講義のように他者の学習スピードに合わせる必要がないため、着実な学習成果を上げられます。また、通信教育と異なり、学習の進捗に合わせてリアルタイムでアドバイス・フィードバックを受けられる点もメリットです。
eラーニングのデメリット

eラーニングは多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。場合によっては通信教育のほうが適していることもあるため、デメリットを把握した上でどちらを利用するか選択しましょう。
受講環境の整備が必要
eラーニングの代表的なデメリットは、受講環境を整備する必要がある点です。eラーニングはインターネット環境がなければ利用できないため、次のような設備を企業・受講者が各自で整える必要があります。
- パソコン・タブレットなどのデバイス
- 通信環境
- マイク・カメラ
- 教材の作成・準備
なお、 eラーニングシステムの中には、上記のような環境整備を支援するサービスを有したものもあります。主に企業向けのサービスで、導入にかかる手間や時間を削減したい場合におすすめです。
運用側はシステムを十分に使いこなす必要がある
eラーニングには受講者のモチベーションを維持するための機能など、さまざまな機能が搭載されています。そのため、運用側がシステムを十分に使いこなしていないと、受講者の学習効果が十分に得られません。
また、自社で学習コンテンツを追加する際にもたついてしまうと、受講者は学習を始めることができず、研修などに遅延が発生します。
eラーニングの導入に必要なもの

eラーニングの導入にあたっては、最低限次のような3つのポイントを揃える必要があります。各ポイントを正しく理解し、eラーニングの円滑な導入・運用につなげましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
LMS
LMSはeラーニングプラットフォームを指し、簡潔にいえばeラーニングシステムの基盤となるものです。LMSを利用すれば、一からeラーニングシステムを構築する必要がないため、プログラミングなどの知識がなくてもeラーニングシステムを運用できます。
さまざまなベンダーから多彩なLMSがリリースされており、それぞれ講座内容・使用教材・搭載機能が異なります。自社が実施したい講習や研修を実現できる機能・特徴を備えたLMSを選択しましょう。
学習教材
eラーニングで使用するコンテンツには、資料・音声・動画・パワーポイントなど、さまざまなものがあります。
多くのeラーニングシステムは講座内容にあわせた学習教材の提供を行っており、自社で独自に準備する必要はありません。自社独自のオリジナル教材を作成したい場合は、作成支援やアップロードに対応してくれるシステムも多くあります。
教材の数や質は、eラーニングシステムによって異なります。受講者に求める習熟度レベルをあらかじめ設定し、そのレベルを実現できる教材を備えたシステムを選びましょう。
学習の支援者
学習の支援者とは、各受講者の学習を支援してくれる人材です。「チューター」「学習サポーター」などと呼ばれます。
自主学習であるeラーニングは、質問ができない・モチベーションの維持が難しいといった課題を課題を抱えています。学習の支援者は、これらの課題を解決するための存在です。
学習の支援者は講師の代わりに質問や相談に答えたり、時には学習内容や教材の提案・アドバイスをしたりします。簡潔にいえば、学習者に寄り添うことで、学習へのモチベーションを保ちつつ、継続的な学習を促すのが支援者の役割です。
1人で学習を進めるのが難しい受講者にとって、支援者の存在は大きな意味があるでしょう。
自社に合ったeラーニングを選定する

eラーニングは、自社が実施したい研修や講習に対応したものを選びましょう。各業界・業種に特化した企業向けのサービスも多くあり、それぞれ習得できる知識・スキルや使用コンテンツなどが異なります。自社に適したシステムを選ぶためのポイントは、次の通りです。
自社に適したシステムを選ぶためのポイントは次の通りです。
- 希望する講座内容の有無
- 既存の教材or自社作成の教材
- 使いやすさ
- 導入費用
- システム利用料金
- 提供形態(オンプレミス型orクラウド型)
- 利用人数
使いやすさは業務効率・学習効率を左右する重要なポイントです。使いにくいシステムは、やはり学習へのモチベーションが下がりやすくなります。また管理者にとっても、業務が煩雑になる・負担が大きくなるといったデメリットが発生します。
導入費用やシステム利用料金は、主に提供形態によって大きく異なります。一般的にオンプレミス型は導入費用が高く、クラウド型は継続的なシステム利用料金が発生するため割高になりやすいです。
上記にあわせて、一度に利用できるユーザー数についても必ず確認しておきましょう。大規模な研修や講習に利用する場合は、当然ながら大人数の利用に対応したシステムの導入が必要になります。

おすすめのeラーニングシステム7選|選び方や注意点を詳しく解説
eラーニングシステムとは、インターネットを活用したオンライン学習システムのことを言います。eラーニングシステムは法人向けから個人向けまで種類が多く、自社に適したものを選ぶのが困難です。本記事では、おすすめのeラーニングシステムやその選び方などを解説します。
まとめ

紙の教材や課題を郵送でやりとりしていた通信教育に代わり、現代ではコンテンツの配信・視聴や課題の提出・添削をすべてインターネット上で行えるeラーニングが主流になっています。
eラーニングは資料準備や会場確保にかかる費用・手間を削減できるほか、各受講者の学習状況を一目で把握できる点も、従来の通信教育にはないメリットです。一方、導入の際は環境整備などにコストがかかるため、導入支援があるシステムの利用がおすすめです。
eラーニングは、主にLMS・学習教材・学習の支援者の有無を基準に選定することが大切です。自社に適したeラーニングシステムを導入し、従業員の自主学習を促すことで、より効果的に優秀な人材の育成を進めましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

