BOMとは?管理方法や課題、BOMシステムをわかりやすく解説
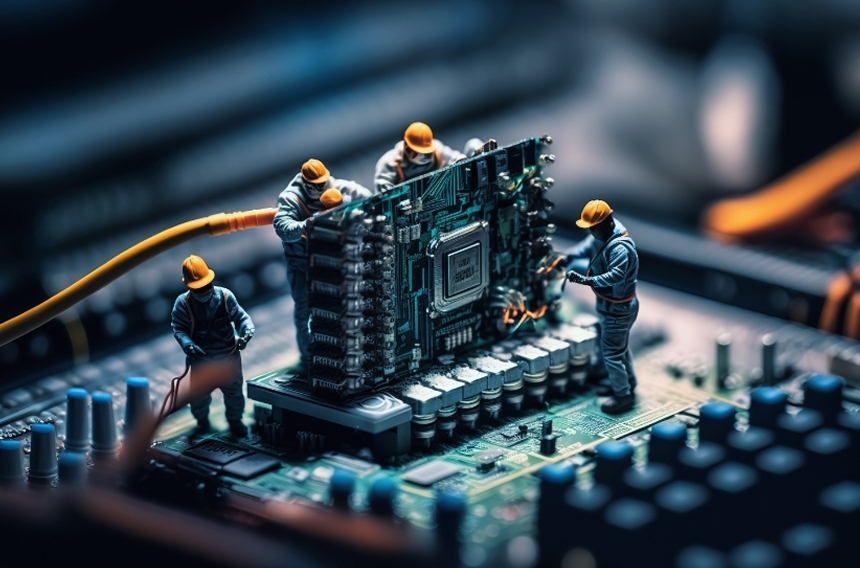
Check!
- BOMは、製品製造に必要な部品を効率的に管理し、生産管理全体を効率化するのが目的
- BOM管理には、情報の入力ミスや転記ミスなどのヒューマンエラーに関する課題がある
- BOMシステムで全部門のBOMを管理すると、業務効率化や情報共有の迅速化に繋がる
BOMとは、日本語で「部品表」を意味し、製品を作るのに必要な部品一覧を指します。BOM管理には、人的ミスやBOM統合が難しいといった課題があり、その解決にはBOMシステムがおすすめです。本記事では、BOM管理における課題やBOMシステムについて解説します。
おすすめ記事
BOMとは
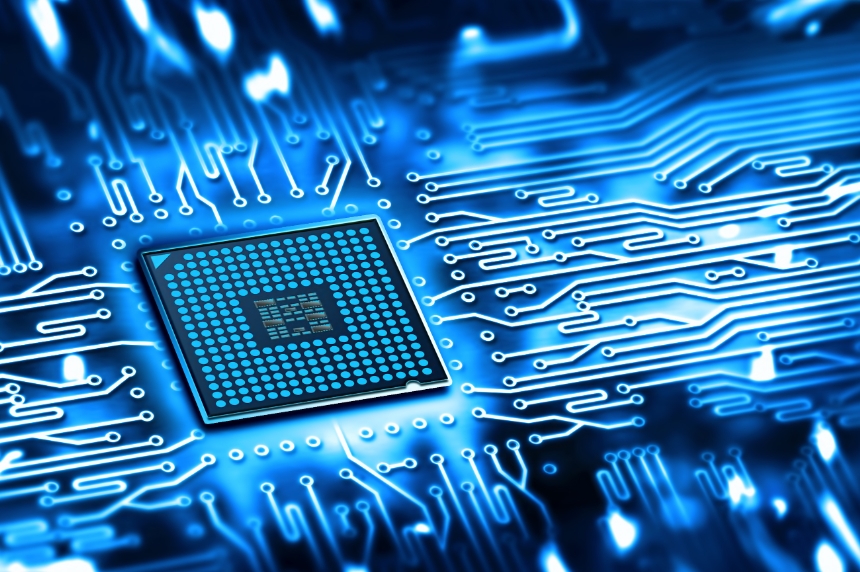
BOM(ボム)とは「Bill Of Materials」の略称で、製造業で用いる「部品表」を意味します。部品表とは、製品の製造に必要な部品や組み立ての仕方を一覧表にしたもの、という読み方もできます。
BOMは製造部門だけでなく、製品に必要な部品を調達する調達部門・製品の組み立てを行う組み立て部門などでも活用されます。つまり、製品を適切に製造するためには欠かせない書類といえます。
BOMの目的
BOMの主な目的は、製品製造に必要な部品を効率的に管理することです。例えば、次のような項目をリストアップすることで、部品不足・手配漏れなどを防ぎ、生産管理を効率化します。
- 製品に必要な部品の種類
- 必要な数
- 在庫
- 手配時期
- 納品日
BOMはさまざまな部門で活用されますが、求められる情報は部門によって異なります。
BOMの種類

BOMは利用される目的・部門によって、種類が異なります。BOMの代表的な種類と特徴を理解し、適切なBOM管理を行いましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
E-BOM(設計部品表)
E-BOMは「Engineering-BOM」の略称で、製品の仕様を満たす部品構成情報をリスト化したものです。例えば部品やモジュールの仕様・部品の必要数量・設計図面・技術情報などを表わします。
製品の製造に必要な各部品の仕様や、製造に必要な技術を一目で把握できるのが特徴です。E-BOMは主に設計部門で活用されます。
M-BOM(製造部品表)
M-BOMとは、E-BOMに部品の組立順序・加工工程などの情報を追記したものです。「Manufacturing-BOM」の略称で、主に製造部門で活用されます。
M-BOMは主に生産のスケジューリングや進捗管理に用いられます。例えば生産指示・工程管理のほか、生産スケジュールに合わせた部品の発注に役立てられます。
P-BOM(購買部品表)
P-BOMは「Purchasing-BOM」の略称で、資材・調達部門での部品調達に用いられます。具体的には、部品の発注の際に必要となる部品表です。P-BOMでは、部品ごとの手配数・仕様・価格のほか、仕入先情報などがリスト化されています。
S-BOM(サービス)
S-BOMとは、製品の保守・サポート・メンテナンスといった業務に用いる部品表です。正式には「Service-BOM」といい、製品のメンテナンス情報・メンテナンスに必要な部品を顧客ごとにまとめるのが一般的です。
BOMの管理方法

BOMの管理方法は3つに大別できます。自社に最適な管理方法を選択するためにも、それぞれの特徴や強みを理解しましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
サマリ型
サマリ型は、製品の製造に必要な部品を並列にまとめる方法です。製品の加工過程・組立順序は関係なく、必要な部品の種類と数のみに重点が置かれます。
例えば、製品Aを製造するのに、中間製品Bが3個・部品Cが2個必要と仮定します。なお、中間製品Bの製造には部品Cが3個必要です。この場合におけるサマリ型では、製品A1個に対して必要なのは、部品C11個であると表します。
サマリ型BOMのメリットは、必要な部品の総数が一目で分かるため、部品の追加・仕様の変更にも柔軟に対応できる点です。主に資材・調達部門で活用されます。
ストラクチャ型
ストラクチャ型は、次の2つの項目を製品の製造過程に沿って階層構造的(ツリー形式)で表したものです。
- 部品の組立順序
- 部品の親子関係(親部品・子部品・孫部品)
ストラクチャ型では、製品製造の各工程ごとに・どの部品が必要かが一目で把握できます。製品の加工順序・工数を可視化できるため、作業着手から製品完成までの時間(リードタイム)が計算しやすい点がメリットです。
中間工程を詳細に管理できるため、製品の仕様に変更が出た場合も、影響範囲・原価計算が容易になります。ストラクチャ型は主に製造部門で活用されます。
パラメトリック型
パラメトリック型は、基本の製造仕様からさまざまなパターンを予測し、各仕様を満たす部品を自動生成するBOMです。具体的には、色違い・サイズ違いといった複数のパターンを持つ製品の製造管理に適しています。
BOM管理における課題

従来のBOM管理は、紙・Excelを利用して手動で行うのが一般的でした。手動でのBOM管理には特別なツールやシステムが不要であり、コストを抑えて行える点がメリットです。一方、従来のBOM管理には以下のような課題があります。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
BOM管理における課題
ヒューマンエラーの発生
Excelや紙を使った手動管理で発生するのが、入力ミス・転記ミスといったヒューマンエラーです。特に、管理すべき部品が膨大であるほどミスも起こりやすくなるでしょう。
また、製品の仕様に変更が生じた場合、それに伴って部品も変更されます。部品変更に伴う原価計算や影響範囲の測定も手動で行わなくてはならず、この作業は非常に煩雑なため、ヒューマンエラーのリスク増大に繋がります。
当然、ヒューマンエラーは努力次第で防止できます。しかし、全てのヒューマンエラーを防ぐには細心の注意が必要なため、業務担当者に大きな負担がかかるほか、業務遂行にも多くの時間を費やすことになります。
管理工数の増加
手動でのBOM管理は、管理すべき製品・工程が増える度にBOMにも新規で登録しなければならず、管理工数が増大した際に対応がしきれない恐れがあります。つまり、BOM管理に多くの手間と時間が必要になるため、手動の作業では限界があります。
特に、現代は消費者ニーズが複雑化・多様化しており、それに併せて製品・サービスも多様化している時代です。そのため、製品の仕様変更・工程数の増加は頻繁に起こる現象であり、これら全てに業務担当者の努力だけで対応していくのは、現実的ではありません。
また、ERPや生産計画などのシステムでは、M-BOMで必要とする情報が異なり、登録にも多くの手間が発生してしまいます。
BOMの共有が停滞化する
BOMはさまざまな部門で活用されますが、その種類や管理方法は各部門で異なります。特にExcelや紙でのBOM管理は、業務担当者によって内容・質が大きく異なり、部門を横断しての情報共有が困難です。
部門間でBOMの共有が停滞すると、業務の非効率化や生産性の低下の原因となります。例えば設計部門で作成したBOMを調達部門に回覧する際は、調達部門でも管理しやすい仕様に作り直さなければなりません。
これには時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを含んでいます。
対策としては、全部門でBOM管理を統一する方法があります。1つのBOMを全ての部門で回覧できるため、部門ごとに作り直す必要がなく、業務の効率化を図れます。ヒューマンエラーのリスクも低減できるでしょう。
BOMの統一化が困難
BOMの統一化はBOM管理における1つの対策ですが、その方法にも課題があります。それは、BOMに使われる部品コードは部門によって異なることが多く、BOMの統一化にあたっては、まず部品コードの整理・標準化といった工程が必要だからです。
この工程だけでも莫大な工程数を費やすため、通常業務と並行して行う場合、業務担当者の負担はさらに大きくなるでしょう。よって、1つの課題に対する対策が、返って業務負担の増加に繋がってしまう恐れがあります。
BOM管理にはBOMシステムがおすすめ

手動でのBOM管理の課題解決として注目されているのが、IT技術を活用したBOMシステムです。BOMシステムは、BOMの管理・運用を効率的に行うためのシステムとして、次のような機能を備えていることが一般的です。
- BOM管理機能:BOMを部門ごとに区別して管理する
- BOM更新機能:BOMの変更履歴(製品の仕様変更履歴)を自動で更新・管理する
- 在庫管理機能:製品の製造工程に沿ってBOMや部品を管理する
- 製品管理機能:製品と部品表・組み立て表を特徴・属性別に系統立てて管理する
BOMシステムの導入により、企業は次のようなメリットを期待できます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
BOMシステムのメリット
ヒューマンエラーの削減
BOMシステムの導入により、ヒューマンエラーの削減が期待できます。従来の手動のBOM管理の場合、部門ごとにBOM情報を入力し直さなければならないため、転記ミスや入力ミスといったヒューマンエラーが起こりがちでした。
一方、BOMシステムにはBOM管理機能・更新機能が備わっており、1つの部門で登録した情報は自動的に全部門で共有されます。これにより、手動での転記・入力といった工程を最小限に減らせるため、ヒューマンエラーのリスクも小さくなります。
ヒューマンエラーの削減により、部門間での情報のミスマッチが起こりにくくなるため、業務の効率化や生産性の向上が見込めるでしょう。
BOM情報を一元管理できる
BOMシステムの導入により、BOM情報を一元管理できるようになります。例えばBOMに用いられる部品コードなどは部門によって異なることが多く、部品を探す際にはまず部品コードの照合から始めなければなりませんでした。
一方、BOMシステムでは異なる部品コードも体系立てて一元的に管理できます。これにより、部品の検索性が向上し、従来のようにコードを突き合わせて確認する必要がなくなります。必要な情報をすぐに取り出せるため、業務の効率化に繋がるでしょう。
ただし、BOMを一元管理するには、導入前に部品コードを整理しておく必要があります。
情報共有の迅速化
BOMシステムの導入により、部門間の情報共有が迅速になります。それは、BOMシステムを確認すれば、別部門で登録・更新された情報もリアルタイムで閲覧できるためです。
情報共有の迅速化によって、部門間のスムーズな連携が可能となり、効率性・生産性の向上を見込めるでしょう。例えば、部品の在庫状況を製造部門と調達部門でリアルタイムで共有すれば、部品の在庫切れといったトラブルを防止しやすくなります。
また、製品の仕様変更の際は、部品の種類や調達先・組み立て順序にも変更が出ることが多いですが、組織全体で情報をリアルタイムで共有しておけば、各部門が即座に必要な対応を行うことができるでしょう。
生産管理システムとの連携
BOM管理システムの中には、生産管理システムとの連携が可能なものが存在します。生産管理システムとの連携が行えると、E-BOMをBOM管理システムで構築してから、生産管理システムでM-BOMやP-BOMを構築することができます。
これにより、効果的なBOM連携が行えると共に、設計から生産までの情報共有も密なものとなり、設計の段階から見直しをすることもできます。
BOMシステムを導入する際の注意点

BOMシステムの導入にあたっては、注意すべきポイントも存在します。スムーズなBOMシステムの導入・運用に繋げるためにも、次の2つのポイントを留意しておきましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
BOMシステムを導入する際の注意点
品目コードの統一が必要
BOMシステムの導入にあたり、多くの企業が直面する課題が品目コードの統一です。基本的に、BOMの品目コードは、部門や業務担当者によってバラつきがあることが多いです。
そのため、BOMシステム導入においては、バラバラの品目コードを1つの品目に紐づけるといった作業が必要になります。管理すべき製品や部品が多いほど、整理作業にかかる時間と手間も大きくなるでしょう。
E-BOMやM-BOMの連携が難しい
BOMシステムの導入の際は、E-BOMとM-BOMの連携に苦慮する企業が多くみられます。主な理由には次のようなものがあります。
- 設計部門(E-BOM)と製造部門(E-BOM)では使用する部品コードが異なる
- E-BOMは部品だけを扱うのに対し、M-BOMには副資材や梱包材料も含まれる
- E-BOMは常に最新の構成・部品を扱うのに対し、M-BOMには古い情報も含まれる
上記のような課題を解決するには、まず全部門で部品コードを統一することが大切です。また、生産管理システムとの連携やCSVデータの活用により、上記のような課題を解決する方法もあります。
まとめ

BOMは製造業における部品表のことです。ただし設計部門・調達部門・製造部門などによって、使用するBOMの種類や管理方法は異なります。
従来のBOM管理は、Excelや紙を利用することがほとんどであり、ヒューマンエラーのリスクや業務が非効率的であること、部品コードの照合が難しい、などの課題がありました。こういった課題解決に役立つのがBOMシステムです。
BOMシステムの導入によって、製造工程の一元管理と業務の効率化に期待できます。また、システムに登録された情報は、全部門でリアルタイムに共有できる点もメリットです。
一方、BOMシステムの導入にあたっては部品コードの統一化が必要といった課題もあります。よって、E-BOMとM-BOMの連携に問題がある場合は、生産管理システムとの連携も視野に入れながら、自社にとって運用しやすいBOMシステムを構築しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

