原価の意味とは?分類別の費用や原価計算の目的・方法も解説

Check!
- 原価とは製品やサービスを生産するための費用のことで、製造原価と売上原価がある
- 原価は、目的別・視点別・変動の有無によって分類ができる
- 原価計算の目的には、財務諸表の作成やコスト削減、予算計画の策定などがある
原価とは、製品やサービスを生産するためにかかる費用のことを指します。原材料の購入費・労働賃金・製造に関する諸経費などが含まれます。この記事では、原価の意味や分類別の費用、原価を計算する目的や計算方法の種類、計算手順などを解説します。
原価の意味とは
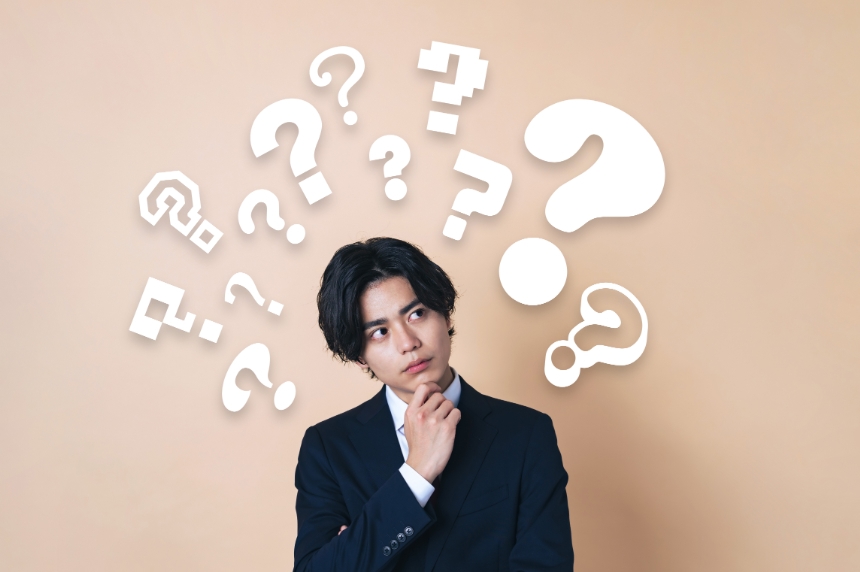
原価とは、企業が商品を製造したりサービスを提供したりする際にかかるコストの総称です。企業が製品やサービスを提供するためには、原材料の購入費用、労働力のコスト、設備の運用費用など、さまざまな要因にコストが発生します。
原価管理は、これらのコストを正確に計算し、企業が収益や利益を最適化するために活用されます。
原価と費用の違い
原価は、製造や提供にかかったコストであるのに対し、費用は、商品を売るために支払うコストのことを指します。費用には原価の他に、従業員の賃金も含まれます。原価と費用は、どちらも商品やサービスを売るために必要なコストです。
原価の2つのカテゴリー

原価は大きく分けて、「製造原価」と「売上原価」の2つにカテゴライズできます。以下では、それぞれについて詳しく紹介します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
製造原価
製造原価とは、具体的な製品を製造するために必要なコストです。製造原価を正確に計算して理解することは、企業がその製品の価格を適切に設定し、収益を最大化するために重要です。
要するに、製造原価は製品を作るのにかかる総費用です。原材料を買うためのお金、労働者を雇うためのお金、機械や設備を維持するためのお金、さらには製品を市場に送るためのお金などが含まれます。
企業はこれらのコストを正確に把握し、利益を得るための戦略を立てることができます。
売上原価
売上原価とは、実際に商品を販売したりサービスを提供したりする際にかかるコストです。具体的には、製品の製造にかかる費用に加えて、販売やマーケティングに関連する経費、商品を顧客に届けるための輸送費などが含まれます。
売上原価を正確に計算して理解することは、価格設定や収益分析において非常に重要な役割を果たします。簡単に言えば、売上原価は商品やサービスを提供するのにかかる総費用のことです。
これには、製品を作るためのコストだけでなく、その商品やサービスを市場に出し、顧客に提供するための費用も含まれます。
仕入れ原価との違い
仕入れ原価とは、商品を提供するために他社から購入した製品にかかるコストを指します。カフェなどの飲食店の場合は、料理を作るために購入した食材などが対象です。
売上原価と仕入れ原価の違いは、売れ残った商品にかかった仕入れ額を含むかどうかです。売上原価は、その年度に売れた商品の仕入れ額のみが含まれます。一方の仕入れ原価は、商品が売れた・売れなかったに関わらず、その年度に仕入れた全ての額が含まれます。
原価の分類

原価は、ビジネスや会計の世界において非常に重要な概念であり、様々な方法で分類できます。ここからは、原価の分類方法に焦点を当て、目的別・視点別・変動の有無による分類について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
原価の分類
目的別の分類
目的別の分類では、原価を特定のビジネス目的に合わせて分類します。目的別の分類は、原価がどのように使用されるかに応じて異なる方法で計算され、分析されます。以下に、目的別の分類について詳しく解説します。
材料費
材料費は、製品やサービスを提供するために必要な原材料や部品の購入にかかるコストです。具体的な例として、建設業界ではコンクリートや鉄骨などの建材が必要です。
また、製造業では電子製品を製造するために、マイクロチップやプラスチックなどの材料が必要です。原材料の価格は市場の変動に左右され、その変動に合わせて材料費も変化します。供給の安定性も考慮しなければなりません。
材料費は製品の原価計算においてコストを最適化するために重要な要素です。
労務費
労務費は、企業が従業員に支払う給与や賃金、社会保険料など、人件費に関連するコストです。例えば、給与、ボーナス、手当、退職金、健康保険、労災保険などが含まれます。
労務費には、従業員の雇用や給与の計算といった雇用契約を管理するための多くのプロセスが関わっています。また、企業の規模や業界によっても大きく異なり、従業員のスキルや役職に応じても変動します。労務費は、組織の人材戦略や給与体系の設計に影響を与えます。
経費
経費は、企業の日常的な運営や業務にかかる費用で、特定の製品やサービスには直接関係しないコストです。例えば、オフィスの賃料、光熱費、事務用具、交通費、宣伝費、法的コンサルティング費用などが含まれます。
経費は、組織全体の効率性や生産性に影響を与えます。経費は一般的に、固定経費(例:賃料)と可変経費(例:交通費)に分けられ、企業の収益や利益に与える影響が異なります。
簡単に言えば、材料費や労働費が直接製品にかかる費用なのに対し、経費は企業全体の運営や事務作業に関する費用です。
視点別の分類
視点別の分類では、原価を異なる視点から捉えます。特定の製品や部門がコストにどのように影響しているかを理解し、戦略的な意思決定を行うのに役立ちます。
直接費
直接費とは、特定の製品やサービスに直接関連するコストです。具体的な直接費には、原材料費、労務費、輸送費、製造費などが含まれます。
このような費用は、特定のプロジェクトや製品の原価計算に直接組み込まれ、その製品やサービスの価格設定に影響を与えます。例えば、ある製品を生産する際に必要な原材料のコストや、その製品を製造するためにかかる労働力の費用が直接費に含まれます。
直接費は、生産ラインやサービス提供に直接関連付けられるため、個別のコストとして追跡でき、特定の製品やサービスの利益計算に用いられます。つまり、直接費は、企業が特定の製品やサービスにかかるコストを正確に把握するために活用されます。
間接費
間接費とは、特定の製品やサービスに直接関連しないコストです。これらの費用は、組織全体の運営や管理に関連し、製品やサービスごとに特定の金額に割り当てることが難しい場合が多いです。
具体例として、オフィスの賃料、電気代、従業員の給与手当、オフィス用具の購入費などが挙げられます。これらの費用は組織全体で共有され、各製品やサービスに割り当てることが難しいため、通常は組織全体のコストとして計算されます。
変動の有無による分類
変動の有無による分類は、原価がどの程度変動するかに基づいて原価を分類します。固定原価は時間の経過とともに変化せず、変動原価は生産量や販売量に応じて変動します。これらの分類は、コスト構造を理解し、利益計画を策定する際に重要な役割を果たします。
変動費
変動費は、企業の生産量や活動レベルに応じて変動するコストです。具体的には、生産や売上が増減すると、変動費も増減する費用のことです。変動費は、生産や販売の活動に直接関連し、生産量や売上の変動に合わせて柔軟に増減する特徴があります。
例えば、ある工場が製品を生産する際に生産が増加すれば、原材料の需要も増え、その結果、原材料の購入費用も増加します。反対に生産が減少すれば、原材料の購入費用も減少します。
変動費は、企業が生産や販売活動の規模を変更する際に、コスト変動を考慮するための重要な要素です。
固定費
固定費は、企業の生産量や活動レベルに関係なく、一定の金額で発生するコストです。具体的な例として、賃貸料や給与が挙げられます。このような費用は、生産や売上が増減しても、支払額が一定で変化しない点が特徴です。
例えば、企業がオフィススペースを借りている場合、賃貸料は毎月一定の金額で支払われます。生産が増えたり減ったりしても、賃貸料自体は変動しません。同様に、給与も一定期間ごとに支払われるため、生産の変動には影響されません。
固定費は、企業の経営者が比較的予測しやすい費用であり、事業計画や予算作成において安定した支出を見積もる際に重要です。また、生産量や売上が一時的に減少した場合でも、固定費は一定であるため、企業の安定性を保つのに役立ちます。
原価を計算する目的

原価計算は、経営者や経営陣が企業の健全な運営と成長を実現するために必要な情報を提供します。原価計算の目的は多岐にわたり、その主な目的を解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
財務諸表を作成するため
財務諸表は、企業の1年間の財務状態や業績をまとめて報告する決算書です。これらの文書を作成する主な目的は、企業の経済的な健全性を評価し、内外のステークホルダーに情報を提供することです。
財務諸表の主要な種類には、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などがあります。これらの財務諸表の作成は、企業法や会計基準によって法的に義務付けられています。
財務諸表を通じて、企業は経営状況を透明化し、株主・投資家・債権者・関係取引先などの関係者に対して正確な情報を提供します。これにより、信頼性のある企業であることを示すことができます。
参考:「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 の取扱いに関する留意事項について|金融庁
適正な価格設定を行うため
価格設定は企業にとって極めて重要で、適切な価格設定ができないと収益に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、適正な価格設定を行うには、原価計算が欠かせません。
原価計算は、製品やサービスを提供する際にかかるコストを正確に把握するための手段です。これには、原材料費、人件費、輸送費、設備の償却費など、製品やサービスを生み出すためにかかるあらゆるコスト要因が含まれます。
価格が高すぎると顧客から敬遠され、低すぎると収益が減少する可能性があります。原価計算を通じて正確なコスト情報を得ることで、競合他社の価格や市場の需要と供給を考慮に入れ、適正な価格を設定できるでしょう。
無駄なコストを把握・削減するため
無駄なコストを把握・削減するためには、サービス原価を把握することが必要です。サービス原価とは、提供されるサービスごとにかかるコストを正確に計算し、把握することを指します。
サービス原価を計算することで、適切な価格設定が可能となります。顧客に提供するサービスの価格は、コストをカバーして、利益を上げる必要があります。サービス原価を知らないと、過少または過大な価格設定につながりかねません。
サービス原価を把握することで、無駄なコストや効率を改善できるポイントを特定できます。効果的なコスト管理により、サービス提供のコストを削減し、競争力を高めることが可能です。
損益分岐点を把握するため
損益分岐点は、ある特定のレベルの売上が必要なポイントです。これを超える売上を達成すれば、企業は利益を上げることができ、損失を回避できます。
具体的には、ある商品やサービスを提供するためにかかるコスト(原材料、人件費、輸送費、広告費など)と、その商品やサービスの売上収入がちょうど相殺され、利益がゼロになるポイントを指します。
損益分岐点を計算することで、企業は最低限の売上目標を設定し、収益を最大化することが可能となります。
予算計画を作成するため
予算計画は企業の財務戦略や運営計画の基盤となります。原価計算によって、製品やサービスの生産にかかる具体的なコストが把握でき、予算の精度が向上します。そのため、収益目標や利益率を達成するための具体的な行動計画が立てられます。
原価計算は、費用の評価に不可欠です。企業は予算を立案する際に、どの部分でどれだけの費用がかかるかを理解する必要があります。原価計算を通じて、材料費、人件費、間接費などの各コスト要因を明確にして、予算内での支出を管理できます。
原価計算方法の種類

原価計算にはいくつかの異なる方法があり、それぞれ異なるアプローチや用途があります。主な原価計算方法として、標準原価計算・実際原価計算・直接原価計算などがあります。ここからは、それぞれの原価計算方法の特徴や利用ケースについて詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
標準原価計算
標準原価計算は、事前に設定された標準的な費用や価格を基に計算されます。この方法では、製品やサービスごとにあらかじめ設定された「標準コスト」と呼ばれる材料費、労働費、間接費などの費用が使用されます。
例えば、ある製品の標準材料費が1万円、労働費が5,000円、間接費が3,000円と設定されている場合、この製品の標準原価は合計で1万8,000円になります。
実際に製品を生産する際には、実際の材料費や労働費などを計算し、標準原価と比較します。例えば、実際の材料費が1万2,000円、労働費が6,000円、間接費が3,500円だった場合、実際の原価は2万1,500円となります。
このとき、標準原価と実際の原価との差異は3,500円(2万1,500円 – 1万8,000円)です。この差異分析を通じて、企業はどの部分で予算と実績がずれているかを把握し、コストの効率化や改善のポイントを見つけることができます。
実際原価計算
実際原価計算は、実際に製品を生産したりサービスを提供した際に発生したコストをもとに、その製品やサービスの原価を計算する方法です。
具体的には、製品の製造過程やサービス提供に関連する材料費、労働費、輸送費、間接費など、実際にかかった費用を記録し、これらの実際の費用を合計して原価を算出します。
例えば、ある製品を生産するために、実際にかかった材料費が5,000円、労働費が3,000円、輸送費が1,000円、間接費が2,000円だった場合、その製品の実際原価は、これらの費用を合計した11,000円になります。
実際原価計算は、過去の取引データや実績に基づいて原価を計算するため、特定の期間や取引におけるコストを正確に把握するのに役立ちます。
直接原価計算
直接原価計算は、製品やサービスに直接関連するコストのみを考慮して、その製品やサービスの原価を計算する方法です。具体的には、製品を生産したりサービスを提供するために直接必要な費用、つまり材料費や直接労働費などが含まれます。
しかし、オフィスの賃料や経理部門の給与といった経費や間接費は、直接原価計算には含まれません。この方法は、特定の製品やサービスの原価を素早く把握するために役立ちます。
企業は製品の価格設定や収益性を評価する際に、その製品ごとの直接原価を計算し、適切な価格を設定するのに利用します。また、どの製品やサービスが収益を上げているかを把握し、経営戦略の評価にも活用できます。
原価の計算手順

原価計算は企業にとって非常に重要なプロセスであり、通常、次の3つの段階を踏んで行います。ここからは、それぞれの段階について説明します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
費目別原価計算
費目別原価計算は、企業がコストを異なる費用の種類に分類して計算するプロセスです。この段階では、例えば材料費、労務費、輸送費、設備の償却費などのコストがどのカテゴリに属するかを明確にします。
具体的には、各費用項目の金額を収集し、それぞれのカテゴリに合計します。これにより、企業はどの部分で主要なコストが発生しているかを理解しやすくなります。
これによって、企業がどれだけの材料費を支払っているか、またはどれだけの人件費がかかっているかを費目別に把握できます。企業のコスト構造を理解しやすくする重要なステップです。
部門別原価計算
部門別原価計算は、企業が異なる部門やセクションごとに原価を計算するプロセスです。例えば、生産部門、営業部門、研究開発部門など、各部門ごとに発生する原価を把握します。
この部門別原価計算によって、どの部門がコストを引き起こしているか、またどの部門が収益を生み出しているかが明らかになります。
例えば、生産部門の原価と営業部門の原価を比較することで、どちらの部門が収益に対して多くのコストを負担しているかがわかります。
製品別原価計算
製品別原価計算は、企業が提供する個々の製品やサービスごとに原価を計算するプロセスです。各製品が材料、労務、間接費などのコストをどれだけかけているかを詳細に把握できます。
例えば、ある企業がスマートフォンの製造とタブレットの製造を行っているとします。製品別原価計算を実施すると、それぞれの製品が材料費、労働費、間接費などのコストがどれだけかかっているかが分かります。
その結果、スマートフォンの方がタブレットよりも原価が高いことが明らかになった場合、企業はスマートフォンの価格設定や生産プロセスの最適化を考えることができます。
製品別原価計算を通じて、どの製品やサービスが最も収益性が高いか、どの製品に改善の余地があるかが分かり、製品ラインの戦略的な管理が可能となります。
原価管理システムなら損益の計算も簡単に
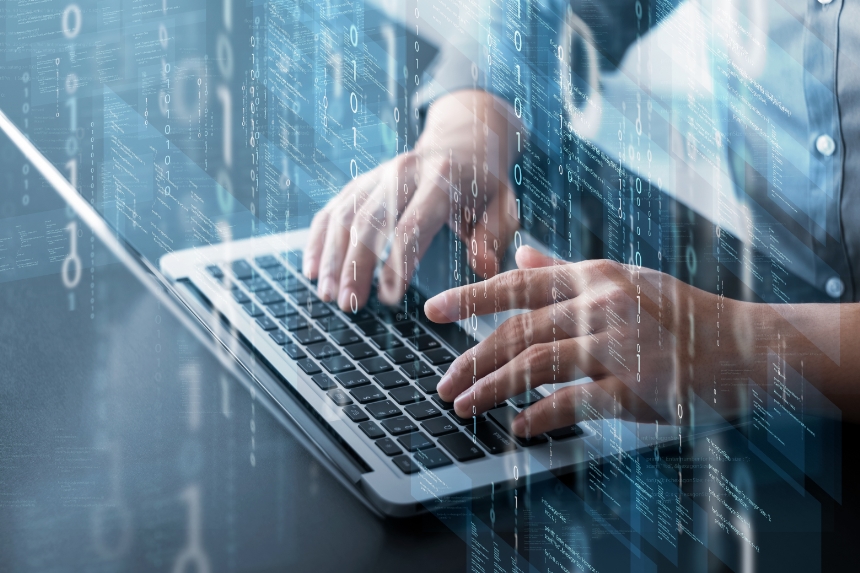
原価管理システムは、企業が原価情報を効率的に管理するためのツールです。このシステムを導入することで、原材料の価格、労働者の給与、輸送費など、製品やサービスを提供するためにかかるコストに関するデータを正確に算出できます。
このシステムは手動でデータを入力する必要がなく、データの誤りやヒューマンエラーの削減に役立ちます。また、組織がどの部分でコストが発生しているかを把握して、無駄なコストを見つけ出すこともできます。
原価管理システムは、原価計算をより簡単にし、組織全体の収益性や効率性を向上させる重要なツールです。

原価管理システムとは?主な機能やメリット・選ぶポイントを解説
原価管理システムとは、原価計算や損益分析、原価シミュレーションなどの複雑な計算を効率的に行えるシステムです。この記事では、原価管理システムの基本的な機能やシステム導入によるメリット、導入前・導入時にそれぞれ考えるべきポイントについて詳しく解説します。
まとめ

原価とは、企業が製品やサービスを提供する際にかかるコストのことです。原価計算は、このコストを正確に把握するための手段であり、財務諸表の作成や価格設定、コスト削減、収益最大化のために不可欠です。
原価計算には標準原価計算、実際原価計算、直接原価計算などいくつかの方法があり、各種の情報を提供します。原価は目的や視点に応じて分類され、部門別、製品別、費目別などで計算されます。
また、原価管理システムの導入は、データ収集や分析を効率化し、組織の効率性と競争力を向上させます。これにより、無駄なコストの発見と削減、予算計画の策定、損益分岐点の把握などが可能になります。
原価管理の正確性を向上させ、効率化させたい場合は、原価管理システムの導入を検討しましょう。

