資産除去債務とは|会計基準・仕訳・計算方法をわかりやすく解説

Check!
- 資産除去債務は、撤去・除去が義務付けられている有形固定資産を取得した際に発生する
- 資産除去債務は、国際会計基準との整合性をとるために計上されるようになった
- 資産除去債務などの会計処理を効率的に行うには、システムの導入がおすすめである
資産除去債務とは、有形固定資産を取得するときに発生する負債のことで、有形固定資産を除去するときに見込まれる費用を計上します。本記事では、資産除去債務が取り入れられた背景に触れ、資産除去債務の計算・仕訳方法や、システム導入がおすすめな理由を解説します。
資産除去債務とは

資産除去債務とは、企業が将来的にその資産を撤去や除去することが義務付けられている有形固定資産を取得する場合に、その撤去・除去で発生すると見込まれる費用を現在価値で計上する負債のことを指します。
例えば、企業が原発やガスプラントなどの大型施設を建設した場合、将来的にその施設を撤去する義務が生じることが多いです。このような撤去義務に関連する将来の支出を現在の金額で計上することで、真実の財務状況を反映させることが目的となっています。
この資産除去債務は、企業の財務諸表上での負債として計上され、その後の経営活動や投資判断に影響を与える要素です。資産除去債務の計上は、企業の財務健全性を示す指標としても利用されるため、経営者や投資家にとっても重要な情報となっています。
資産除去債務が発生する具体例
資産除去債務は、特定の有形固定資産の取得や利用に伴い、将来的な撤去や除去の義務が発生する場合に計上されます。
例えば、原子力発電所の建設においては、将来的にその施設を解体し、廃棄物を適切に処理する義務が発生します。この解体や廃棄物処理にかかる費用が資産除去債務として計上されることが一般的です。
また、油田やガス田の開発のケースでは、開発後、資源の採掘が終了すると、その場所を元の自然環境に近い状態に復元する義務が生じることが多いです。この復元作業に必要な費用が資産除去債務として認識されることがあります。
資産除去債務の会計基準
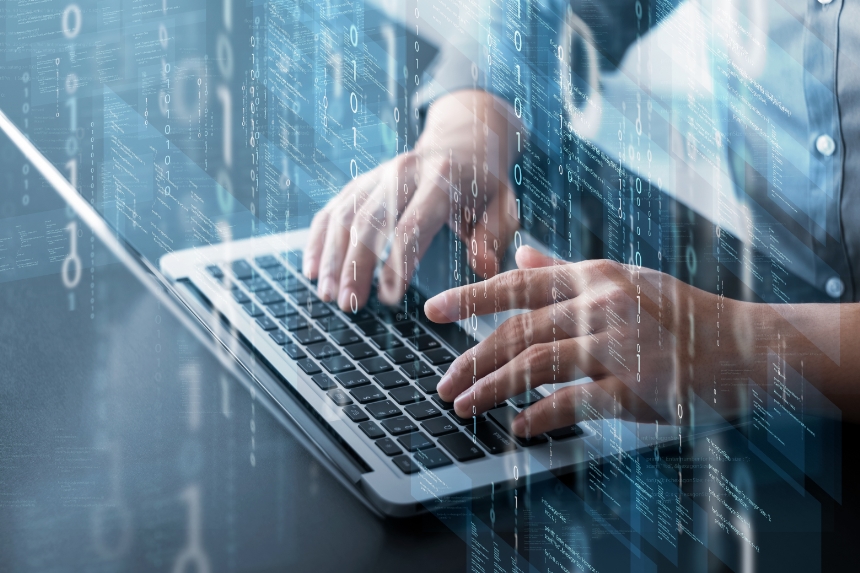
資産除去債務は、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」により定義されています。この基準は、資産除去債務の定義、会計処理、および開示に関する指針を明示しています。
資産除去債務に関連する除去費用は、資産除去債務を負債として計上したときに、その計上額と同額を帳簿価額に加えることとされています。この除去費用は、減価償却を通じて、関連する有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分されます。
また、会計上と税法上の処理の差異をなくすためには、税効果会計の導入が必要です。税効果会計は、会計上の利益と税法上の所得の間の一時的な差異を調整するための会計処理を指します。
なぜ資産除去債務が取り入れられたのか

資産除去債務の導入は、国際的な会計標準の一致を目指す流れを汲み、企業の環境に対する責任を強化するための措置として始まりました。
資産除去債務は、IFRSでも取り扱われているテーマであり、日本の会計基準がこれを取り入れることで、国際的な基準との一致を図る動きが強まりました。また、企業の環境への責任感の高まりも資産除去債務導入の大きな要因です。
環境問題への関心の高まりとともに、事業の終息後の環境修復の義務が増えてきました。これらの義務を未来に果たすためのコストを、現在の事業活動と並行して計上することで、企業の実際の財務状態をより明確に示すことが可能となります。
資産除去債務の計算・仕訳方法

資産除去債務は、有形固定資産の取得時に将来発生すると予想される撤去や処分に関する費用を現在価値で計上するものです。そのため、有形固定資産の購入時や決算時、資産を除去した際などに仕分けが必要になります。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
資産除去債務の計算・仕訳方法
有形固定資産を購入した時
資産の購入は単なる取得だけで終わりではありません。特に有形固定資産の場合、その後の処理や撤去にかかる費用も考慮する必要があります。この撤去や処分にかかる費用の概算を、資産除去債務として計上します。
例えば、新しい工場を建設する場合、その工場の寿命が尽きたときにどれくらいの費用がかかるのかを予測し、その額を現在の価値に換算して計上します。
この算出の際のポイントとしては、将来の撤去方法や処分方法を具体的に想定し、それに伴う費用や使用される技術の進化、さらには割引率の設定など、多岐にわたる要因を考慮する必要があります。
決算時
決算の時期が近づくと、企業は資産除去債務の調整額の計算や減価償却の計算を行う必要があります。これは、資産の価値が時間とともに変動するため、その会計基準変動を正確に反映させるためのものです。
資産除去債務の調整額の計算では、前回の計算からの変動分や新たな撤去費用の見積もり、割引率の変動などを考慮して、新たな資産除去債務の額を算出します。一方、減価償却の計算では、資産の取得価格や残存価値、使用年数を基に、その年度での償却額を計算します。
2年目以降の決算時
初年度に計上した資産除去債務の額は、その後の経過年数や市場の変動、技術の進歩などによって変動する可能性があります。
そのため、2年目以降の決算時には、前年度の資産除去債務の残高を確認し、新たな撤去費用の見積もりや割引率の変動、さらにはインフレーションの影響などを考慮して、資産除去債務の調整を行う必要があります。
資産を除去した時
有形固定資産の寿命が尽きたり、使用目的がなくなったりした場合、その資産を撤去する必要が生じます。特に3年経過した後に撤去を行う場合、計画や見積もりだけでなく、実際にかかった撤去費用の計上が不可欠となります。
この実際の撤去費用と、初めに計上していた資産除去債務との間に差額が生じた場合、企業の財務諸表上で調整しなければいけません。さらに、撤去作業に関連して外部の業者に支払いを行う場合、その支払いに伴う消費税も計上する必要があります。
会計処理を効率的に行うならシステムの導入がおすすめ

会計処理は、多くの企業にとって欠かせない業務の一つです。しかし、資産除去債務のような特定の計算や仕訳が必要な項目は、専門的な知識や経験が求められるため、人材不足や属人化の問題が生じやすいです。
さらに、人の手による作業は、人為的ミスのリスクも高まります。このような課題を解決するためには、固定資産管理システムの導入がおすすめです。システムを使用することで、計算や仕訳の自動化が可能となり、作業の効率化やミスのリスクの低減が期待できます。
また、システムには、最新の会計基準や税法の変更情報が更新されるため、常に正確な情報に基づいた計算が行えるのもメリットです。自社に必要な機能が搭載されていることも大切なポイントです。
搭載されていると便利なおすすめの機能に、リース資産管理機能と他システムへの連携機能があります。以下で、それら2点の機能の概要とメリットを解説します。
リース資産管理機能
リース資産管理機能では、リース契約の期間や条件、支払い管理、資産の価値などの複雑な管理を一元化でき、コストを正確に把握してリース資産の最適な利用ができます。
さらに、監査対応の際にも、必要なリース契約に関する情報を迅速に提供でき、リース契約の自動更新日をアラートで通知できるため、正確な契約の自動更新管理にも役立ちます。
他システム連携機能
固定資産管理システムと他システムとの連携機能があると、企業内での情報の一元化や業務の効率化を図れます。会計システムとの連携では、資産の取得や売却、減価償却費のデータを会計処理をする際に取り込むことで、二重入力などのミスを防ぐ効果があります。
また、人事・給与計算システムとの連携では、社員の入退社に伴い、個別に割り当てられた固定資産・リース資産の情報を自動更新できます。なお、固定資産は一般的に購買プロセスを経て取得されます。

おすすめの固定資産管理システム|選ぶ際の重要なポイントを解説
固定資産管理システムとは、企業が保有・使用する土地や建物などの固定資産の情報を適切に管理するためのシステムです。本記事では、固定資産管理システムの導入を検討している方のために、おすすめの固定資産管理システムや選び方、導入時の注意点を詳しく解説しています。
まとめ

資産除去債務は、企業が有形固定資産を取得する際に将来的に発生すると予想される撤去や処分の費用を現在価値で計上する会計処理です。この処理は、企業の財務状況をより正確に反映させるためのものであり、正確な計算や適切な仕訳が求められます。
一方、会計処理の複雑さや変動性を考慮すると、これらの作業を人の手だけで行うのは非常に手間がかかります。人材の不足や属人化の問題、さらには人為的なミスのリスクも考慮すると、固定資産管理システムの導入は欠かせません。
この記事に興味を持った方におすすめ

