リードナーチャリングとは?メリットや成果を出すポイントを解説

Check!
- リードナーチャリングとは、見込み客を成約・購入へ繋げるためのマーケティング活動
- リードナーチャリングにより、休眠顧客や購買意欲の高い顧客へのアプローチができる
- リードナーチャリングで成果を出すには、KPI設定やホットリードの明確化が重要である
リードナーチャリングとは直訳すると「見込み客の育成」という意味で、事前に集めたリード(見込み客)を購入や成約へ繋げるためのマーケティング活動のことです。この記事では、リードナーチャリングが注目される背景や実施のステップ、成果を出すポイントなどを解説します。
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは、潜在的な顧客(リード)との関係を構築して購買意欲を高めるための活動です。見込み客が購買を検討している期間に継続的なコンタクトを取ることで、商品に対する興味や関心を維持して購買に繋げることを目的としています。
リードナーチャリングは、顧客に対して中長期的なアプローチを行うため、検討に時間を要する商品において力を発揮する手法です。BtoBやBtoCなどの業態に関わらず、金融商品や不動産などの商品と相性が良いと言えます。
見込み客を購買に繋げるには、顧客への働きかけを適切に行う必要があります。本記事では、リードナーチャリングを行う際のステップや、成果を出すために効果的なポイントについてわかりやすく解説します。
BtoBマーケティングのプロセス

リードナーチャリングは、BtoBマーケティングにおける3つのプロセスの2番目に該当します。ここでは、リードナーチャリングを含む3つのプロセスを取り上げ、それぞれについて詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
BtoBマーケティングのプロセス
リードジェネレーション
リードジェネレーションとは、見込み顧客の情報を獲得するためのプロセスです。情報発信によって自社商品の認知度を高め、興味を持ってくれそうな顧客の情報を収集します。
リードジェネレーションの具体的な方法としては、展示会・メルマガ・コンテンツマーケティングなどが挙げられます。
リードジェネレーションはBtoBマーケティングにおける最初の段階であり、成果に繋げるための重要なステップです。ターゲットを明確に定め、自社のサービスや商品に適した方法でアプローチを行いましょう。
リードナーチャリング
リードジェネレーションで獲得した見込み顧客は、購買意欲にばらつきがあります。リードナーチャリングのプロセスでは見込み顧客の育成を行い、購買意欲を向上させます。この際、顧客の意欲段階に応じた適切な働きかけを見極めることが重要です。
リードナーチャリングの段階では、購買に繋げることを急がず、じっくりと時間をかけて顧客との関係構築を行う必要があります。セミナーやメール配信などで商品の魅力をアピールしつつ、顧客との信頼関係を深めていきましょう。
リードクオリフィケーション
リードクオリフィケーションは、BtoBマーケティングにおける最終段階です。このプロセスでは、リードナーチャリングを実施した顧客のうち、さらに購買意欲が高い顧客の選別を行います。
リードクオリフィケーションによって、購買の可能性の高い顧客だけに効率よく営業活動を行うことが可能です。このような顧客を絞り込むための手法として、個々の顧客が生む自社への価値を予測して点数化する、スコアリングという手法が用いられます。
リードナーチャリングが注目される背景

近年の消費行動の多様化に伴い、リードナーチャリングは注目を集めています。注目されている背景として、インターネットの普及や購買プロセスの複雑化に加え、休眠顧客の増加などが挙げられます。ここでは、これらの背景について解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
リードナーチャリングが注目される背景
インターネットの普及で購買行動が変化している
インターネットの普及に伴い、顧客に対するセールスをかけなくても、顧客自らが積極的に商品の情報収集を行うようになりました。また、インターネット上では多くの情報を簡単に入手できるため、商品の比較検討を重視する顧客が増加しています。
このような変化により高まりを見せているのは、自社の商品・サービスをいち早く顧客に見つけてもらうことの重要度です。また、顧客との関係性が競争力を大きく左右することから、リードナーチャリングをはじめとするマーケティング手法も注目されています。
購買プロセスが長期化・複雑化している
インターネットによって商品に関する情報収集が容易になり、顧客は複数の情報源からの情報収集や、価格・サービスの比較検討を行うようになりました。特に、BtoBにおいてはこれらの過程に複数名の担当者が関わることで、購買プロセスが長期化しています。
顧客の企業規模が大きければ大きいほど決裁の仕組みが複雑になるため、購買にかかる時間が長期に及ぶ場合があります。そのため、リードナーチャリングによって顧客と長期的な関係を築き、信頼を獲得する手法が注目されています。
休眠顧客が増加している
休眠顧客とは、過去に商品やサービスを利用した履歴があるものの、最近は取引が途絶えている顧客のことです。休眠顧客は一度自社の商品に魅力を感じて購買に至っているため、再購入の可能性が高い顧客であると言えます。
休眠顧客を放置していると、そのまま自社との関係が切れてしまう場合があります。このような状態を回避し、再び顧客になってもらうにはリードナーチャリングによるアプローチが有効です。顧客とのコンタクトを継続することで購買に繋がる可能性が高まります。
リードナーチャリングのメリット
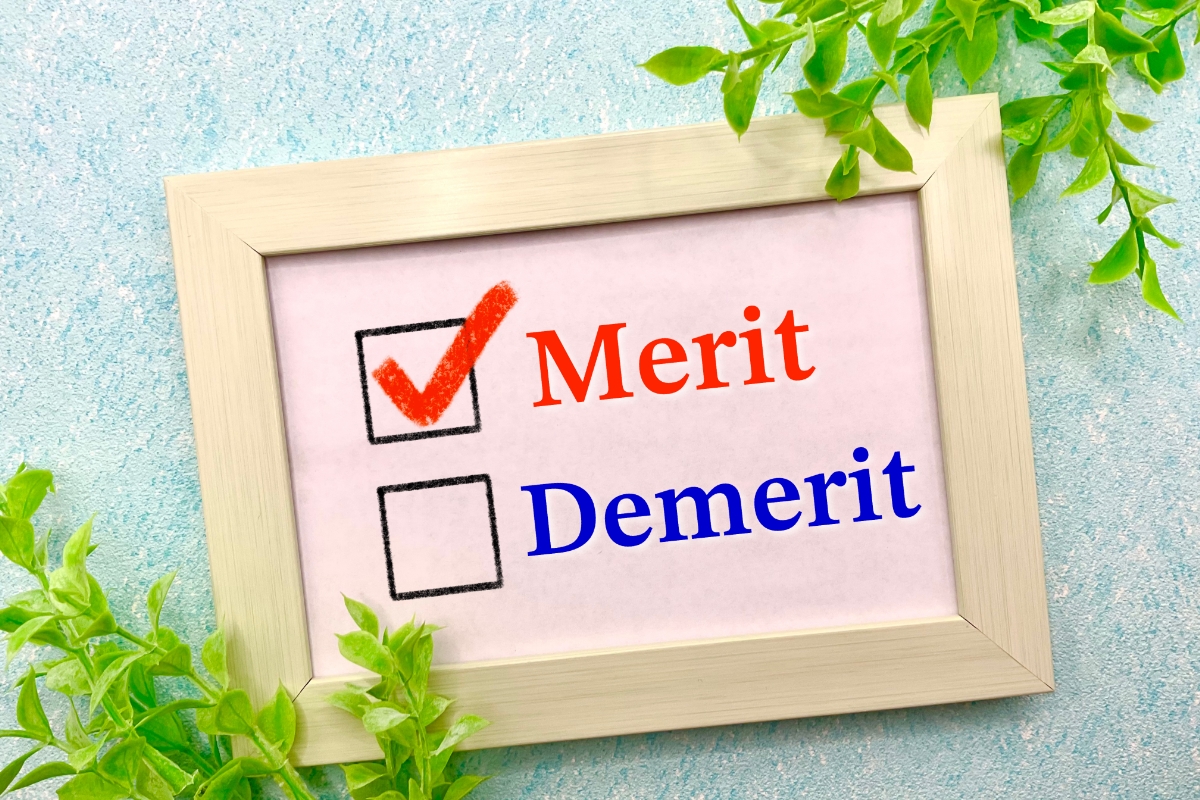
リードナーチャリングには多くのメリットがあります。リードナーチャリングによってリードを継続的にフォローし、休眠顧客の活用に繋げることが可能です。また、確度の高いリードだけに注力できます。ここでは、これらのメリットについて詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
リードナーチャリングのメリット
リードを継続的にフォローできる
リードナーチャリングを仕組み化することで、リードを継続的・長期的にフォローする体制を構築できます。これにより、リードが他社に流出してしまう事態を防ぎ、機会損失を防止する効果が見込めます。
特に、近年の長期化・複雑化した購買プロセスにおいては、リードへのフォローが欠かせません。フォローを行わなかった場合、多くの顧客は自社商品を購入せずに競合へ流れてしまうため、リードナーチャリングと営業活動との連携が重要なポイントとなります。
休眠顧客という資産を活用できる
休眠顧客へのアプローチでは、新規リードを獲得する場合に比べてコストを抑えることができます。新規リード開拓にかかるコストは利益率を圧迫してしまうため、リードナーチャリングによって、休眠顧客への働きかけに注力することが望ましいです。
新規リード獲得にかかるコストは休眠顧客の5倍にも及ぶ場合も少なくありません。さらに、休眠顧客は自社の商品に対して一定の理解を示していると考えられるため、自社にとって活用するべき資産であると言えるでしょう。
確度の高いリードに集中できる
リードナーチャリングによってリードの確度を把握できていれば、より購買意欲の高い顧客に優先的にアプローチできます。これにより、効率的な営業活動が実現して限られた人数でも大きな効果を得られるようになります。
不特定多数のリードに対して営業活動を行なっても、購買に繋がるリードはごくわずかです。営業力には限りがあるため、リードナーチャリングを用いてリードの優先順位を定め、的確な営業活動に繋げましょう。
マーケティング施策の費用対効果を高める
費用対効果とは、投じた費用に対して得られた効果のことです。マーケティングにおける費用対効果の高さとは、いかに機会損失を防ぎ、獲得したリードをコンバージョンに繋げているかを指します。
基本的に営業活動では、すぐにコンバージョンに繋げられる確度の高い見込み客が優先されます。将来的にコンバージョンが見込めるものの、育成を行う必要がある見込み客は後回しにされる傾向にあるため、結果的にリードを取りこぼしている事例も多いです。
リードナーチャリングでは、見込み客と継続的かつ長期的に付き合い、必要なタイミングでアプローチをかけられるため、このような機会損失を防ぐことができ、マーケティング施策の費用対効果が高まります。
リードナーチャリングのデメリット

さまざまなメリットをもたらすリードナーチャリングですが、注意が必要なデメリットも存在します。ここでは、デメリットを2点取り上げて解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
リードナーチャリングのデメリット
リソース・時間が必要
リードナーチャリングではリードの状態に合わせたアプローチを行うため、リードの情報管理や施策の決定に多くのリソースを要します。また、顧客を育成する過程では、効果が出るまでに多くの時間と手間がかかります。
リードの情報は常に新しい状態に保ち、担当者や関連部署間で共有されている状態が望ましいです。そのため、MAツールなどを利用せずにExcelなどで管理を行なっている場合は、情報共有にかかるリソースも確保しておきましょう。
事前に顧客獲得が必要
リードナーチャリングは、新規顧客の開拓よりも既存顧客の育成において力を発揮します。そのため、事前にある程度の顧客を確保できていない場合には不向きな手法です。
リードナーチャリングを行えないほど顧客が少ないと、成果が得られない場合がほとんどであるため、マーケティングのプロセスに従い、まずはリードジェネレーションから実施しましょう。
リードナーチャリングの代表的な手法

リードナーチャリングにはさまざまな手法があります。ここでは、リードナーチャリングの代表的な手法を7点取り上げ、それぞれについて解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
メール
メール配信によるリードナーチャリングは、一度に多くの顧客に発信でき、コストもかからないため、多くの企業で導入されている手法です。また、メールの開封率や記載されたURLへのアクセス率などの情報を取得でき、後の施策に活かすことができます。
メール配信の種類は、顧客の段階に応じた2種類です。まず、ステップメールでは、顧客のアクションに応じて段階的に一斉メールを送信します。対して、セグメントメールでは顧客の属性に基づいてパーソナライズした文面を作成し、個別の施策を盛り込みます。
SNS
SNSによってリードナーチャリングを実施する場合、企業アカウントの作成による情報発信が一般的です。Instagram・X(旧Twitter)・Facebookなどに自社商品・サービスの情報を掲載するほか、自社サイトやECサイトへの誘導を行います。
近年ではSNSの普及拡大に伴い、SNSによって商品情報を取得する顧客が増加しています。また、企業と顧客の間で双方向の交流が生まれやすく、顧客からの親近感や信頼感を得られるというメリットがあります。
SNSはサービスによって利用者の属性が異なるため、それぞれの特徴を把握することでターゲットの属性に合わせた効果的な施策に繋げることが可能です。また、SNSの情報拡散によって認知度を高める効果も期待できます。
Webコンテンツ
リードナーチャリングの目的の1つである顧客との中長期的な関係構築には、Webコンテンツの利用が有効です。リードナーチャリングにおいてはオウンドメディアによる情報発信が主流となっています。
オウンドメディアで、顧客の興味を惹く情報や自社製品と関連性の高い情報を発信することで、顧客の好感度を高められます。また、質の高い情報を提供することで、定期的にサイトを訪れるファンが増え、既存顧客のロイヤルティ向上や新規顧客の獲得も見込めます。
セミナー・イベント
自社が開催するセミナーやイベントに参加する顧客は、すでに自社に対する興味が高まっている状態です。そのため、商品のアピールポイントや魅力が伝わりやすく、リードナーチャリングの効果を得られやすいと言えます。
セミナーには、会場で行われるオフラインのセミナーに加え、オンラインセミナーも含まれます。オフラインセミナーでは、顧客と直接やりとりできるためコミュニケーションが生まれやすく、距離を縮められるというメリットがあります。
一方、オンラインセミナーでは、会場設営などの手間やコストをかけず、遠方の顧客も気軽に参加できます。いずれの場合も、商品に対する意見のヒアリングやアフターフォローなどを実施し、育成に繋げることが重要です。
リターゲティング広告
リターゲティング広告とは、過去に自社サイトへの訪問履歴がある顧客に対して配信される広告のことです。顧客にとっては一度訪れたサイトとなるため、リターゲティング広告によって再訪や購入に繋がる可能性が高まります。
リターゲティング広告では、訪問者のCookie情報を取得して広告の表示を行います。Cookieには自社サイトから発行されるファーストパーティCookieと第三者から発行されるサードパーティCookieがありますが、後者は将来的な規制が検討されています。
サードパーティCookieが規制対象となった場合、リターゲティング広告の効果が低下する可能性があることに注意が必要です。このため、近年ではCookieを使用しない広告に注目が集まっています。
DM
DMとはダイレクトメールを略した言葉で、FAX・はがき・封書などで情報発信を行う手法です。DMはオフラインによって行われるため、インターネットとの関わりが薄い顧客層にも情報を届けることができます。
郵送によるDMは、顧客に対し丁寧で特別感のある印象を与えられるため、会員限定のセールやバースデークーポンの送付などに多く用いられます。これによって、顧客との良好な関係を継続させる効果が期待できます。
また、BtoBのマーケティングにおいては、FAXによるDM送付も多く用いられます。郵送に比べてコストが抑えられるため、顧客のFAX番号を取得できている場合には有効な手段であると言えます。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーとは、見込み客に対して提供する自社の商品・サービスの情報をまとめた資料のことです。主に、公式サイトやメルマガなどで、自社の商品・サービスに興味を持った見込み客に対し、より詳細な情報を提供するために活用されます。
見込み客に資料請求・ダウンロードをしてもらう過程で、名前やメールアドレスといった情報を入力してもらい、追客を開始できるため、前述したBtoBマーケティングにおける3つのプロセスの1番目である、リードジェネレーションに適した手法です。
しかしながら、ホワイトペーパーの提供で顧客との接点を作り、潜在的な課題を認識させられる可能性もあるため、リードナーチャリングでも活用されています。
リードナーチャリングのステップ

リードナーチャリングを行う際は、ステップに沿って実施することが重要です。まずはリード情報の一元管理やペルソナ設計を行い、リードのセグメント分割を行いましょう。続いて、コンテンツの提供や施策の実行に着手します。
ここでは、これらのステップについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
リードナーチャリングのステップ
リード情報の一元管理
リードナーチャリングを行う際は、まず自社におけるリード情報を集約するところから始めましょう。リードの流入経路によって把握できる情報の種類が異なるため、すでに得られている情報を一元管理しておくことが重要です。
リード情報の一元管理を行うには、社内で顧客情報を共有し、共通のリストに整理することが効果的です。その際、リードの氏名・社名・役職などの情報に加え、流入経路やコンタクト履歴を記載しておきましょう。
この作業によって、異なる担当者からの重複連絡や不必要なアプローチを回避し、自社への信頼性を高める効果が期待できます。
ペルソナとカスタマージャーニーマップの設計
続いて、リードナーチャリングの対象となるペルソナを設定し、カスタマージャーニーマップの設計を行います。その際、なるべく具体的なペルソナを設定することで顧客のニーズを理解しやすくなります。
ペルソナに設定した顧客の目線に立って自社の商品やサービスを見直すことで、どのようなアプローチが購買に繋がるかを把握できます。顧客が自社の商品に出会ってから購買に至るまでの経緯を想定し、精度の高いカスタマージャーニーマップを設計しましょう。
リードのセグメンテーション
顧客によって自社商品への興味や購買意欲はさまざまです。リードナーチャリングでは全てのリードに対して同じ施策を行わず、あらかじめリードの属性や取引履歴などによるセグメンテーションを実施しておきましょう。
例えば、自社が想定しているペルソナと大きな乖離があるリードは、購買に繋がりにくいことが予想されます。セグメンテーションによってこのようなリードへの非効率なアプローチを避け、確度の高いリードに対して効果的な施策を打ち出すことができます。
コンテンツの作成・提供
顧客のセグメンテーションが完了したら、セグメントに応じたコンテンツの作成・提供を行います。顧客の購買意欲や商品理解の確度によって効果的なコンテンツは異なるため、顧客の段階に応じた適切なコンテンツ作成を行いましょう。
また、顧客がどの経路で自社の商品やサービスに辿り着いたのかによって、コンテンツの提供方法を工夫することも効果的です。オンライン・オフラインの手法を使い分け、顧客に合わせたコンテンツ提供を実施しましょう。
施策の実行・改善
最後に、顧客の段階に合わせた施策を実行します。施策を実行した後は、必ず施策の効果を振り返り、顧客の反応をデータとして保存しておきましょう。
これにより、効果があった点や問題点を把握し、将来の施策の改善に繋げることができます。特に、メールやSNSによるリードナーチャリングでは、顧客の反応を客観的な数値として取得できるため、さまざまな角度からの分析が可能です。
このように、施策の実行やデータの収集、問題点の改善を繰り返すことでPDCAサイクルが回り、施策の精度を高められます。部門間の連携を行って効果的な施策に繋げましょう。
リードナーチャリングの成果指標

リードナーチャリングの成果を判断するには、成果指標による分析が欠かせません。リードナーチャリングは、主に以下の3つの指標によって成果を測定することができます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
メールの開封率
メール開封率とは、配信されたメールを開封した顧客の割合のことです。開封率はURLクリック率やコンバージョン率に影響を及ぼす重要な数値であり、メールのタイトルやキャンペーン内容などを工夫することで向上に繋がります。
一般的なメールの開封率は、一斉配信されるメルマガの場合で10〜20%、セグメントメールで30〜50%程度だと言われています。
URLクリック率
URLクリック率とは、メールに記載されたURLをクリックした顧客の割合です。配信したメールの総数に対する割合と、開封率に対する割合の両方を計測する場合が多いです。
URLクリック率は業種や取り扱う商品によっても異なりますが、一般的なURLクリック率は0.8〜1.5%となっています。また、自社のメルマガにおけるクリック率では、2〜6%に達する場合もあります。
コンバージョン率
申し込みや購入など、顧客に期待する行動のことをコンバージョンといいます。コンバージョン率とは、メールに記載されたURLを通してコンバージョンに繋がった顧客の割合を指します。
コンバージョン率は、取り扱う商品の内容や施策によって幅があります。費用負担が発生しない資料請求などでは、概ね30%程度になる場合が多いでしょう。
リードナーチャリングで成果を出すためのポイント

リードナーチャリングで成果を出すためには、いくつかのポイントがあります。KPIの設定や部門間の情報共有に加え、ホットリードの定義を定めることが重要です。また、MAツールの活用も効果をもたらします。ここでは、これらのポイントについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
リードナーチャリングで成果を出すためのポイント
KPIを設定する
KPIとは、英語で「Key Performance Indicator」と表記され、その頭文字をとって略した言葉です。目標達成の過程において達成度の目安となる定量的な指標のことを指します。
リードナーチャリングで成果を出すためには、適切なKPIの設定が不可欠です。KPIは中間目標であり、現在の達成状況を測るための数値となります。そのため、最終目標から逆算した具体的な数値を設定することが重要です。
ホットリードの定義を明確にする
ホットリードとは、自社製品に興味を持っており、購入に至る可能性が高い見込み客のことです。ホットリードは成果に繋がりやすいため、それ以外の顧客と区別して優先的なアプローチを行うことが重要です。
ホットリードの定義は企業によって異なりますが、メルマガのURLをクリックしたら5点、資料請求を行なったら10点というようにリードの行動をスコアリングし、一定の点数以上に達したリードをホットリードとみなす手法が一般的です。
ホットリードの定義を明確に定めることで、打ち出すべき施策を判断しやすくなります。
部門間の情報共有を徹底する
リードナーチャリングはマーケティングの手法ですが、リードナーチャリングによって育成された顧客との実際のやりとりは営業部が行う場合も多いです。
営業部へ引き継ぎを行う際は、情報の齟齬が起こらないよう注意しなければなりません。部門間でしっかりと顧客の情報を共有することで、顧客の属性やこれまでの反応に基づいた効果的な営業活動が可能になります。
MAツールを活用する
MAツールとは、マーケティングにおけるさまざまな業務を効率化するためのサービスです。MAツールによって情報の一元化やスコアリングの自動化が実現し、リードナーチャリングのプロセスを大幅に効率化できます。MAツールのメリットは以下の通りです。

MA(マーケティングオートメーション)ツールとは、マーケティング活動を可視化し自動化できるツールを指します。本記事では、マーケティングに伴う作業を効率化してくれるMAの主な機能やシステム導入によるメリット・デメリット、導入の際に選ぶポイントを解説します。
リード情報を一元管理できる
MAツールにはリード情報を一元管理する機能が備わっています。これにより、顧客の情報や行動履歴を一箇所に集約でき、リードの状態を客観的に把握することが可能です。
リード情報の管理をExcelなどで行う場合、情報の入力や更新に多くの労力がかかっていました。MAツールの導入によって、常に最新の情報を更新・共有できるため、これらの管理にかかる時間的なコストを削減できます。
リードナーチャリングにおいては顧客の段階に合わせた施策が重要であり、MAツールによる情報の一元管理が不可欠であると言えます。
リードのスコアリングができる
多くのMAツールには、顧客の行動に応じてスコアリングを行う機能が搭載されています。スコアリングの基準をあらかじめ設定するだけで、一定の基準に到達したリードの情報を取得できるため、効率的なマーケティング活動を実現可能です。
ホットリードに対する営業活動を優先的に行うことで売上に繋がりやすくなり、業績の向上が見込めます。また、MAツールの中には計算期間の設定や属性によるフィルタリングなどの機能を備えたものもあり、顧客の状態に応じたきめ細かな施策を打ち出せます。
手作業でのスコアリングは工数が多くなって正確な算出が困難なため、MAツールによる自動化が望ましいでしょう。
部門間の情報共有をスムーズにする
リードナーチャリングでは、マーケティング部門と営業部門とのスムーズな連携が不可欠です。MAツールによって顧客の状態やKPIなどのさまざまな情報が可視化されるため、効率的かつ確実な情報共有が実現します。
また、自社で使用している他システムとの連携が可能なMAツールなら、マーケティングに必要な情報を簡単に取得できるというメリットも得られます。
まとめ

リードナーチャリングとは、見込み客への中長期的なアプローチによって商品購入に繋げる活動のことです。リードナーチャリングでは顧客のセグメンテーションを行い、それぞれの段階に応じた適切な施策を実施します。
インターネットの普及拡大に伴い、顧客の購買行動は長期化・複雑化する傾向にあります。そのため、リードナーチャリングによる顧客との継続的な関係構築を用いた手法が注目を集めています。
リードナーチャリングにおいては、顧客の情報を適切に管理し、それぞれの段階を見極めることが重要です。MAツールによるリード情報の一元管理やスコアリングを行い、効率的なリードナーチャリングを実現しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

