クリニックでマニュアル作成すべき理由とは?作成時のポイントも解説

Check!
- マニュアル作成により、クリニックにおける業務標準化や教育の負担軽減が可能になる
- マニュアルを作成する際は、読み手の知識レベルに配慮し、必要に応じて図や写真を使う
- 作成したマニュアルはいつでも閲覧できる場所に置き、定期的に内容を見直す
人材育成に関する課題が多いクリニックにおいては、業務マニュアル作成が推奨されます。マニュアル作成により、業務の標準化や教育の負担軽減を図ることができます。この記事では、クリニックでマニュアル作成すべき理由や作成時のポイントなどを解説します。
クリニックにおける人材育成の課題

クリニックでの人材教育を実施するときには、さまざまな課題が浮かび上がってきます。一般的な病院では、採用された実務経験がないスタッフは、最初から外来や病棟などに配属されて仕事をすることはありません。
まず、人事課や総務課などに研修配属された後、病院勤務に必要な基本教育が行われてから各部署に配置されます。一方でクリニックにおいては、新人スタッフの教育は一般的には院長の責任です。
スタッフの患者への応対が、直接そのクリニックの評価につながります。しかし、クリニックにおける人材教育では、離職が多いことや教育のための時間がなかなか取れないなどの問題点があります。
これらの問題をいかにクリアして、スタッフを教育するかどうかがクリニック全体の評価にもつながってきます。
クリニックでマニュアル作成すべき理由

常に忙しいクリニックでは、マニュアルの作成は後回しにされがちです。しかし、マニュアルを作成して正しく運用することで、業務の効率化や品質改善など多くのメリットを実感できます。マニュアルは、忙しい医療現場で多大な効果を発揮するといえます。
ここでは、なぜクリニックでマニュアルを作成すべきかについて解説します。
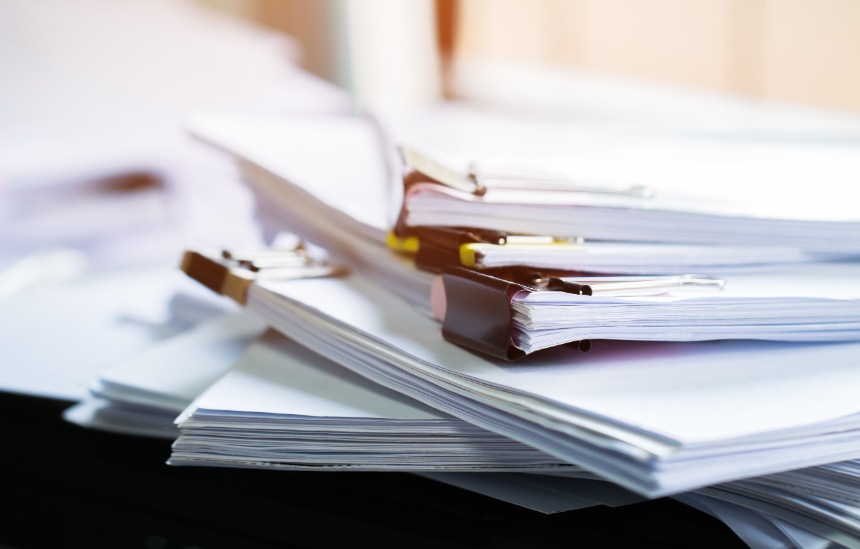
マニュアル作成とは?メリット・デメリット、ツールの選び方を解説
マニュアルを作成することで、教育コストを削減し、業務の効率化や属人化防止に効果的です。またマニュアル作成ツールを導入することで、マニュアル作成に関する課題の解決に役立ちます。本記事では、マニュアル作成の手順やマニュアル作成ツールの選び方などを解説しています。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
クリニックでマニュアル作成すべき理由
業務を標準化するため
クリニックでマニュアルを作成するメリットの1つは、作業の標準化が図れる点です。スタッフごとに作業の方法が異なっていたケースでも、マニュアル化することで解消でき、スムーズに業務が行えます。
業務をマニュアル化することは、誰が処理してもほぼ同じ結果が得られるための仕組み作りに役立ちます。例えば、スタッフの一人が急に退職する場合でも、マニュアルがあれば引き継ぎがスムーズになり、後任スタッフへの移行も日常業務に支障なく行うことができます。
どの組織においてもスタッフに長く勤めてもらい、経験を積んでスキルを高めてくれることが理想です。しかし、万が一欠員や退職者が出た際に、特定のスタッフが業務を把握していると、代わりのスタッフは手探りで業務を進めなければなりません。
このようなことを避けるためにも、クリニックでのマニュアル作成はとても重要です。
教育の手間を軽減するため
統一されたマニュアルがクリニックにあれば。新人を教育する手間と時間を軽減できます。複数のスタッフを採用する場合、さまざまなタイプの人がいて、それぞれの仕事の経験値も違います。
大雑把な人・几帳面な人・細かい点にも気が付く人・器用で覚えが早い人・作業に慣れるまでに時間がかかる人、などのように性格や能力もさまざまです。クリニックに業務のマニュアルがあれば、これを活用して実務に必要な基準の提示をすることができます。
スタッフそれぞれの判断で行っていた業務もマニュアルを参考にすることで、クリニックの方針に沿ったやり方に変えることができ、業務の標準化も期待できます。また、ベテランスタッフが教育する手間も省けます。
客観的に人事評価するため
クリニックにおいては、客観的に人事評価を行うことも重要です。マニュアルの作成により、客観的な基準を用いての評価が可能となります。また、基準がしっかりと決まっていることで、スタッフの仕事の満足度が上がることにもつながります。
スタッフは、マニュアルを参考にすることで自発的に判断して作業ができるようになります。各自の仕事の目的を明確にして、スタッフのモチベーションアップやチーム力のアップも同時に期待できる点も大きなメリットと言えます。
クリニックでマニュアル作成を行う際のポイント
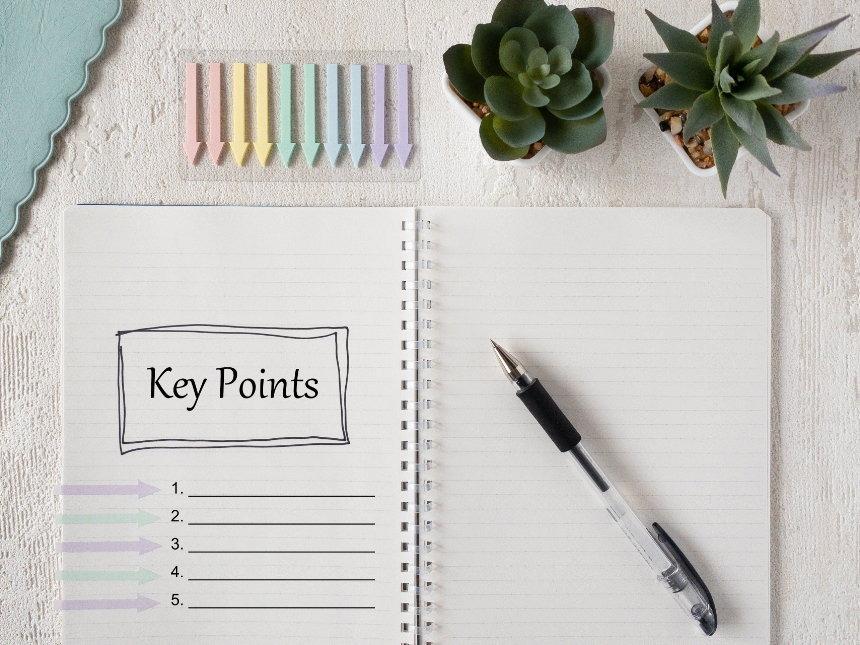
実際にクリニックでマニュアルを作成するにあたって、何から始めたらいいか分からないという担当者も多いです。誰が見ても分かりやすい内容でまとまったマニュアル作りを目指す場合は、作成する際のポイントを知っておく必要があります。
ここでは、クリニックでマニュアル作成を行う際のポイントを5項目に分けて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
クリニックでマニュアル作成を行う際のポイント
読み手の知識レベルに配慮する
クリニックに限らず、仕事のマニュアルを作成する際は、読み手の知識レベルをあらかじめ想定しましょう。読み手に合わせた文章で作成することは、分かりやすいマニュアル作りのカギとなります。
マニュアルは、使う人が理解できる言葉で書かれていなければ、意味がありません。使う人の知識レベルに合ったものであることと、必要以上に丁寧な表現になっていないかも注意しましょう。
たとえば、院内で使う専門用語についての解説は、注釈があるとより親切で分かりやすいと誤解されがちです。しかし、記載が多すぎると逆効果となることもあります。また、文章の長さも冗長的にならないよう配慮することも大事です。
作業手順は具体的に記載する
マニュアルを作成する際は、作業手順はできるだけ具体的に記載することも重要なポイントです。業務内容をより具体的に細かく記載することで、スタッフごとの作業の差を縮めることができ、失敗の軽減にもつながります。
ただし、マニュアルに記載する作業手順は、一挙手一投足指示するような内容である必要はありません。
たとえば、実際にOJTで研修するときのようなイメージで、「最初に〇〇を行う」「次に△△を」などのように業務を単位で区切る書き方にすると、読みやすいマニュアルになります。
仕事の全体像を把握できるようにする
新人が仕事を覚える際には、仕事の全体像を把握しながら各項目を理解して、実践できるレベルまで引き上げることが大事です。マニュアルは具体的な作業の工程のみならず、最終的に何が目的なのかや、全体の流れについても把握できるような内容が理想的です。
ベテランのスタッフだけでなく、新人やまだ経験が浅いスタッフが見ても分かりやすいマニュアルにするためには、全体像の記載が必須です。
新人スタッフは、なぜその作業をするかといった意味を理解できることで、より前向きな気持ちで効率的に動くことができるようになります。
必要に応じて図や写真を使う
マニュアルの内容は、文章だけでは見にくい場合があります。また、文字表現だけでは伝わりにくい機器の使い方の説明などは、図や写真・動画なども活用して作成することも有効的です。
さらに、仕事の流れなどをフローチャートで説明すると、より視覚的になり理解が深まります。
このようにマニュアルに図や写真・動画などをポイントで使うと、最初に仕事を覚えるときだけでなく、後で不明点を見返すときも探しやすくなり、確認しやすい点も大きなメリットです。
クレームやトラブルも共有する
クリニックのマニュアルは、作業の流れや機器の使い方などだけでなく、過去のクレームやトラブルなども記載しましょう。過去に起きたクレームや容や問題点を把握しておくことで、いざという時に対応する際の参考になります。
同時に過去のクレーム内容を知ることは、いかに各業務が重要であり、ミスを少なくすることが大切かについて理解することにも役立ちます。
クリニックでマニュアルを効果的に運用するために

クリニックでマニュアルをより効果的に運用するためには、マニュアルを作成した後の運用にも注意しましょう。ここでは、マニュアルをより効果的に運用するために確認しておきたい重要ポイントを3項目に分けて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
クリニックでマニュアルを効果的に運用するために
チェックリストを作る
マニュアルを作成する際は、同時にチェックリストも作成しておくと、実際の業務で非常に役に立ちます。業務内容で確認すべき点をチェックリストで示すことで、うっかりミスや見逃しなどを防ぐことができます。
チェックリストの作成は、仕事の手順の標準化にもつながり、業務の品質を常に安定させることができるメリットもあります。しかし、ミスの防止や削減のために、膨大な数のチェック項目を作る必要はありません。
チェック項目は担当者が最初にチェックし、その後に責任者がダブルチェックする項目を載せるのがおすすめです。ミスが多い箇所や必ずチェックしておきたい点に絞って載せることも大事です。
チェック項目が多い場合、そのための仕事量が増えたり、記載時間に時間がかかったりすることがあります。そのため、ミスが減らずさらなるミスが生まれるという悪循環になってしまいます。
いつでも閲覧できる場所に保管する
業務マニュアルは、担当者がいつでも閲覧できる場所に保管することも重要です。業務で使用する機器の近くやポータルサイト上など、仕事の動線を考えていつでもすぐに閲覧できる場所に置いておきましょう。
業務などにおける対応方法が分からない場合、マニュアルが遠くにあると、取りに行くために時間がかかってしまいます。また、マニュアルをどこに置いてあるかが分からないと、探すための時間も要することになります。
できるだけ早く対応する必要がある場合、スタッフのストレスが溜まるだけでなく、患者からのクレームにもつながります。
マニュアルは、常に手が届く場所に置いておくことや、端末の分かりやすい場所に保存するなど、担当者が探しやすい場所に保存し、ファイル名は複雑でないものにしておくことも大事です。
定期的に内容を見直す
マニュアルを作成した後は、定期的に内容を見直し、修正や追加をしていくことが必要です。一度マニュアルを作ったらそれで終わりではなく、定期的な内容の見直しが重要です。これにより、業務改善やミスの削減に繋げることができます。
現在のクリニック内のルールや手順は、常に見直すべき点がないかをチェックし、改善を行うことが大事です。実際にマニュアル通りに業務を行うと、もっとやりやすい方法や改善点が見つかることがあります。
また、クレームや患者からの指摘があった内容も考慮して、改善できる点は迅速に変えていくことが大切です。クレームは批判だけでなく、サービスリクエストとして考え、よりよいクリニック運営のためのアドバイスとして考えることも重要です。
まとめ

現代のクリニックにおいては、人材育成に関する課題が多いため、業務マニュアルの作成がおすすめです。マニュアルを作成することで、業務を標準化することができます。また、教育する側の負担を軽減したり、教育のための時間を有効的に使うことも可能です。
クリニックでマニュアルを作成する際は、学ぶ側の知識レベルに配慮することも大事です。必要に応じて図や写真・動画などを使うとより分かりやすくなり、有効的です。また、マニュアルだけでなく、チェックリストの添付もミス防止につながります。
作成したマニュアルは、いつでも閲覧・確認できる場所に置くことが求められます。さらに、内容を定期的に見直し、必要であれば修正し追記していくようにしましょう。本記事を参考に、誰が見ても分かりやすく、迅速に把握しやすいマニュアル作りを目指しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

