RPAを内製化|メリット・デメリット、内製化のステップも解説

Check!
- RPA導入を内製化すれば柔軟なカスタマイズが可能で、担当者はスキルを習得できる
- RPA内製化の際は社内エンジニアの負担が増えるため、周りからのサポートが必要となる
- RPAの内製化には、プログラミング言語、サーバー・ネットワークに関する知識が必要
RPAの導入には、外部委託する方法と内製化する方法があります。内製化すればコストを抑えてRPAを導入でき、自社に合わせたカスタマイズも可能です。この記事では、RPAを内製化するメリット・デメリットや内製化のステップ、注意点などを解説します。
おすすめ記事
RPAの内製化とは
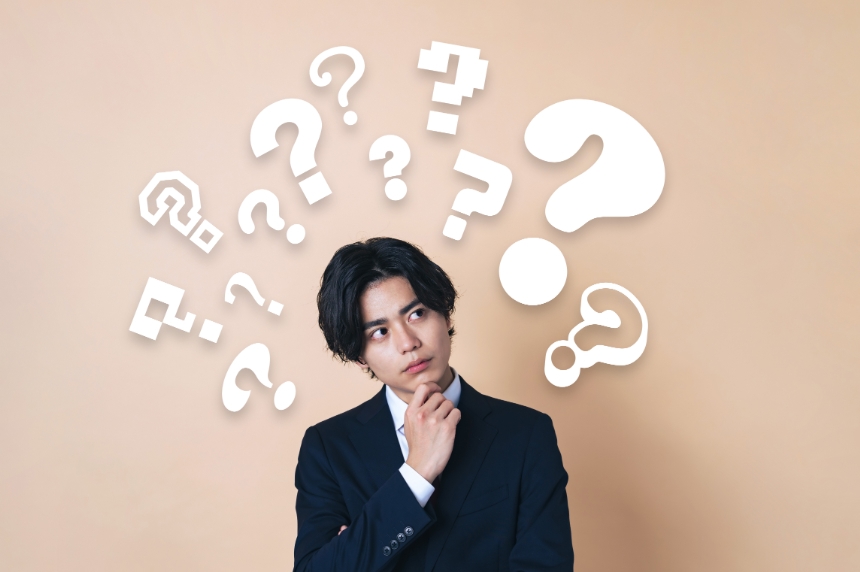
RPAとは、パソコン上の単純作業を代行するロボットです。RPAの導入により、日々の定型業務を一定程度自動化できるため、人材不足への対応・人件費の節約・人的ミスの防止などのメリットに期待できます。
RPAの開発方法には外部委託と内製化の2種類があり、このうち外部委託とは、外部の事業者が開発したツールやソフトウェアを購入して利用する方法です。一方で内製化とは、RPAを自社内で独自に開発し、導入・運用する方法を指します。
外部委託に比べて、より柔軟にツールを運用できることから、RPAの内製化を選択する企業も増えています。本記事では、RPAの内製化におけるメリットやデメリット、内製化の方法についてご紹介します。

RPAとは?メリットや向いている業務、ツールの選び方などを解説
RPAとは、定型業務をロボットを活用して自動化・効率化するシステムのことを言います。RPAを導入することで、業務処理の迅速化などに繋がりますが、対応が難しい業務もあるため注意が必要です。本記事では、RPAのメリット・デメリットや導入手順などを解説しています。
RPAを内製化するメリット

RPAを内製化することにより、コストの節約や高いカスタマイズ性などのメリットに期待できます。ここでは、RPAを内製化するメリットをご紹介します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
RPAを内製化するメリット
コストを抑えやすい
RPAを内製化することで、必要以上のコストを抑えられる可能性があります。例えば、外部委託する場合はRPAの開発費用に加えて、システム利用料金などのランニングコストが継続的に発生します。
一方、内製化では開発から運用まで自社で一貫して行うため、このような外注費用を削減できます。自社内における開発費用やRPA担当者の人件費といったコストはかかるものの、外部委託する場合に比べれば、低コストで済む可能性が高いでしょう。
カスタマイズの自由度が高い
RPAの内製化には、システムの構築や機能の拡張といったカスタマイズを自由に行えるというメリットがあります。外部委託のツールにも機能性や拡張性に富んだものは多くありますが、必ずしも自社に適合するとは限りません。
そのため、外部委託のツールを導入したものの想定外に使い勝手が悪く、費用対効果が得られないというケースもみられます。一方、RPAを内製化する場合は、自社の業務フローや作業内容に合せた柔軟なツール開発が可能です。
自社の状況にあわせて柔軟に機能をカスタマイズができる点は、RPAの内製化における大きなメリットといえるでしょう。
トラブルに迅速に対応できる
トラブル発生時に迅速に対応できる点も、RPAを内製化するメリットです。自社で開発・運用することで、RPAに関するナレッジが社内に蓄積され、これを基にした対応が可能になるためです。
RPAの故障の原因としては、業務フローや設定の変更、連携システムの障害などが代表的です。外部委託したRPAの場合、トラブル対処はベンダーが請け負うことが一般的であり、緊急時にスピーディに対応してもらえるとは限りません。
RPAの故障期間が長引けば、業務全般に重大な支障が出る可能性もあるでしょう。その点、内製化したRPAであれば自社内の人材で対応できるため、トラブル発生時にも迅速な復旧が可能です。
社内にノウハウを蓄積できる
RPAの内製化にはシステム開発に加え、シナリオ作成や初期設定、ツールの点検・保守といったさまざまなスキルが必要です。自社内でRPAを内製化することにより、担当者がこれらのスキルを習得できるメリットがあります。
また、RPAに関するノウハウを社内で蓄積することで、RPAに精通した人材を効率的に増やすことにもつながります。そして、社内全体でRPAを最大限に活用でき、業務の効率化や生産性の向上を見込めるでしょう。
情報漏洩のリスクを低減できる
RPAを内製化した場合、外部委託に比べて情報漏洩のリスクを抑えることができます。外部委託の場合は、システム開発のために、日々の業務手順や社内データを外部事業者に共有する必要があります。そのため、情報の外部漏洩のリスクは比較的高いといえます。
一方で、RPAを内製化する場合は自社内で全ての工程が完結するため、情報が外部に漏れにくい利点があります。社内の機密情報を安全に保護するには、RPAは内製化することが望ましいでしょう。
RPAを内製化するデメリット

RAPの内製化には、メリットだけでなくデメリットもあります。RPAを円滑に導入・運用するには、あらかじめデメリットを理解し、適切な対策を講じましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
RPAを内製化するデメリット
開発に時間がかかる
自社でPRAを内製化する場合、開発に時間がかかり、想定よりも導入が遅れる可能性があります。RPAの開発には高度な専門知識やスキルが必要であり、担当者が習得するのに一定の時間を要する場合があるためです。
さらに、RPAの導入に際しても、業務マニュアルや機能の設定、既存システムとの連携といった複雑な工程が膨大にあります。これらの工程に時間がかかり、RPAの運用開始がさらに遅れる可能性にも留意しておきましょう。
社内エンジニアの負担が増える
RPAの内製化は、社内のエンジニアが既存の業務と兼任することが一般的です。通常業務に加えてRPAの開発を行うことにより、担当エンジニアに大きな負担がかかる恐れがあります。
また、1人のエンジニアにRPAの内製化を任せると、業務の属人化が起こる点にも留意しましょう。この場合、担当エンジニアの急な退職などに伴い、RPAが停止する恐れがあります。
専門家の知見を得られない
RPAを外部委託する場合には、外部事業者から知見を基にしたアドバイスを受けられる可能性が高いです。例えば、RPAの導入支援や活用法の相談のほか、トラブルへの対応方法といった内容が代表的です。
しかし、内製化する場合は開発から運用を一貫して自社内で完結させるため、外部からアドバイスを得る機会がありません。そのため、RPAの開発や運用に行き詰まっても、社内の人材だけで解決する必要があります。
RPAを内製化するステップ
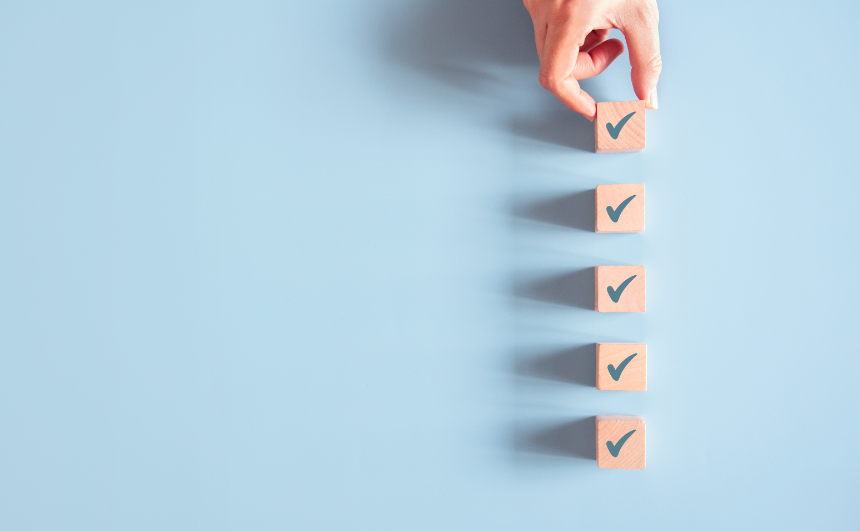
RPAを内製化するためのステップは、人材の確保・業務やプロセスの明確化・シナリオ作成・効果検証と改善といった4段階に大別できます。各ステップのポイントを押さえて、RPAの内製化を成功させましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
RPAを内製化するステップ
RPA人材を確保・育成する
RPAの開発には、専門的な知識やスキルを有した人材を確保する必要があります。社内に既存のエンジニアがいる場合は、研修や勉強会を実施してこれらを習得してもらいましょう。ただし、既存業務と兼任する場合は、業務負担が過剰になる恐れがあります。
その際は、エンジニアを新規雇用する必要があるでしょう。このとき、RPAに精通した人材を雇用すると、社内における教育コストを節約できます。
併せて、将来的にツールのトラブルなどが発生するリスクを考慮し、API・サーバー・セキュリティといった周辺知識を有する人材を確保するのが理想的です。
自動化する業務・プロセスを明確化する
RPAの内製化を成功させるには、RPAを導入する業務内容やプロセスを明確にすることが重要です。この工程により、RPAに求められる動作や機能性を具体化し、自社の求める条件を満たしたツールを開発できます。
業務内容やプロセスにそぐわないRPAを開発すると、導入後に実際の業務に対応できない可能性があり、ビジネスに大きな支障を来しかねません。なお、業務内容やプロセスを明確化する作業には、実際に現場で業務を行っている担当者との連携が不可欠です。
どの作業にRPAを投入すると業務がどの程度効率化されるか、というイメージを具体的に共有しながら、現場の状況に即したRPAの要件を定義しましょう。
シナリオを作成する
前のステップで明確化したツールの動作性・機能性に沿って、ツールのシナリオ作成を行います。シナリオ作成には、オープンソースソフトウェアを利用する方法と、プログラミング言語でゼロから自作する方法の2種類があります。
オープンソースソフトウェアを利用する場合は、システム開発にかかる手間や時間を節約できます。ただし、既存のテンプレートを基にシステムを構築する分、カスタマイズ性はやや低くなる点に留意しましょう。
一方で、プログラミング言語でゼロから自作する場合は、自社の希望に沿った柔軟なカスタマイズが可能です。高度な専門知識とスキルが求められるため、IT人材が豊富な企業に適した方法といえます。
効果検証・改善を行う
RPAの運用開始後は、定期的な効果検証と改善が必要です。実際に運用してみた結果、業務の内容やフローに対応できないといった問題が発生するケースは多く見られます。
このような課題を発見して迅速に対応するには、定期的な効果検証が欠かせません。改善を積み重ねることでRPAの精度が向上し、導入効果の最大化につながるでしょう。
併せて、トラブル発生に備えてRPAのマニュアルを作成することも大切です。マニュアル作成によって誰でもRPAの操作が可能になるため、業務の属人化の防止にもつながります。
RPAの内製化に必要な知識・スキル

RPAの開発には、幅広い分野のスキルが求められます。RPA開発において、特に重要とされるスキルについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
RPAの内製化に必要な知識・スキル
プログラミングスキル
RPAをゼロから自作する場合は、プログラミングに関するスキルが必要です。RPAの内製化に利用されるプログラミング言語には、例えば次のようなものがあります。
- C#
- JavaScript
- Visual Basic .NET
- Python
- Access
- GAS
なお、プログラミング言語のスキルは、シナリオ作成やエラー対処の際に必要になる場合もあります。そのため、オープンソースソフトウェアを利用する場合や、外部委託する場合であっても、一定のプログラミングスキルを社内に蓄積することが望ましいでしょう。
ITプラットフォームに関する知識
RPAの稼働にあたっては、サーバーの設置やネットワークの構築、セキュリティ対策を行う必要があります。そのため、RPA開発だけでなく、これらに関する知識・スキルの習得も求められます。
なお、RPAの導入形態には「サーバー型RPA」や「クラウド型RPA」などの種類があり、それぞれ利用するサーバーの特徴や管理方法が異なります。RPAツールを円滑に稼働させるには、サーバーの知識が必要不可欠なため、特に理解を深めることが望ましいでしょう。
RPAを内製化する際の注意点

RPAを内製化する際は、担当者へのサポートや余裕を持った人員の確保を行うことで、失敗のリスクを低減できます。ここでは、RPAを内製化する際の注意点をご紹介します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
RPAを内製化する際の注意点
担当者をサポートする
RPAの内製化は、エンジニアが既存業務と並行して行うことが一般的であり、担当エンジニアに過剰な業務負担がかかる恐れがあります。
また、担当エンジニアが現場業務を行う機会が減ることで、他エンジニアから厳しい目を向けられるような事態にもなりかねません。このようなリスクを回避し、担当エンジニアがRPAの内製化に専念できる環境を整備するには、周囲の理解・サポートが不可欠です。
具体的には、企業がRPA開発の重要性を周知して、担当エンジニアがRPAに注力していることを周囲に知らしめましょう。この取り組みにより、該当エンジニアの既存業務を他人員でカバーする姿勢が自然と養われます。
また、担当エンジニアは管理者と話し合い、1日の業務時間内で数時間程度、RPAに専念できる時間を確保してもらうのも良い方法です。
担当者は2名以上確保する
RPAの開発や運用・保守にあたる担当者は2名以上確保することが望ましいです。1人のエンジニアに業務が属人化すると、担当者が急に退職した場合などにRPAの運用がとん挫して、業務に多大な支障が出る恐れがあるためです。
このようなリスクを避けるには、RPAの開発や運用保守は2名以上で取り組み、RPAに関する知識・スキルをチーム内で共有することが望ましいです。
まとめ

RPAによって単純作業を自動化することで、人手不足の対応や人件費の節約などのメリットに期待できます。さらに、RPAを内製化することで、コストの節約や柔軟なカスタマイズ、社内におけるナレッジの蓄積を見込むことができます。
RPAの開発には専門的な知識やプログラミングスキルが必要なため、あらかじめ専門の人材を確保しましょう。なお、業務の属人化に伴うリスクを回避するために、RPAの内製化の担当者を2名以上設けることが望ましいです。
自社におけるRPAの内製化を推し進め、業務の効率化や生産性の向上につなげましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

