【節税ポイント付】アフィリエイト収益の確定申告方法
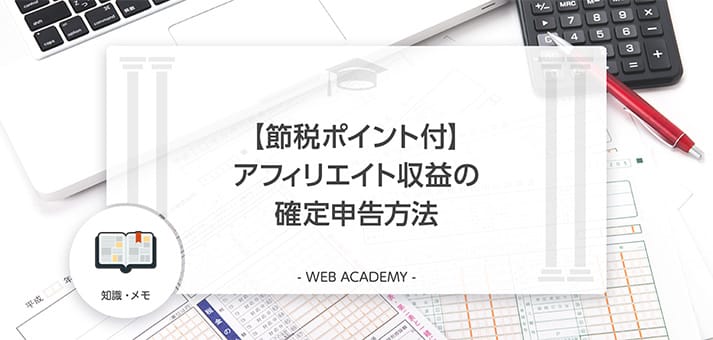
アフィリエイトで得た利益にも、当然、税金はかかってきます。
一定の金額を超えた場合には、確定申告によって自分で税務署に申告し、利益に応じた額の税金を支払わなければなりません。
今回はアフィリエイトと税金について解説します。
アフィリエイトにも税金はかかる

アフィリエイトで発生した収入の税金は、どのように納税すればいいのでしょうか。
私たちが働いて得た収入には所得税が課せられます。
会社の従業員として働いている場合は、会社が所得税を引いた後の給料を支払っているため(源泉徴収)、税の存在を意識することは少ないかもしれませんが、アフィリエイトで収入を得た場合は、自分でその売上から経費を引いた後の利益を算出し、その記録を税務署に提出した上で納税しなければなりません。
これを「確定申告」と呼びます。
確定申告が必要になるのは、会社の従業員の場合は年間20万円以上、会社に所属していない場合は年間48万円以上の利益を得た場合です。
なお、この金額は「収入」ではない点に注意が必要です。
詳しくは後述しますが、アフィリエイトの場合は、ASPから金融機関に振り込まれた金額から経費を引いた後の「利益」が、年間20万円あるいは48万円以上ということです。
確定申告とは、簡単に言ってしまえば、1月1日から12月31日までの間に発生した収入と経費と利益を全て記録して、2月16日から3月15日までの間に税務署に提出する作業です。
アフィリエイトの場合は、ASPから毎月振り込まれた収入と、サイト運営にかかった諸経費(ドメイン代やサーバー代など)の詳細を、税務署の申告用紙に記入します。
前者の収入から後者の経費を引いて、残った金額が利益となり、この利益に応じてその年の所得税が算出されます。
アフィリエイトにおける経費

毎年2月から3月にかけて、フリーランスで働いている人が「確定申告が大変」とぼやいているのを見たことがある人もいると思います。
先ほども説明したように、確定申告は前年の収入と経費を税務署に申告する作業です。
そのうち収入の把握は簡単です。
アフィリエイトの場合は、ASPから銀行口座に毎月振り込まれている収入を、12ヶ月分、合算すればいいだけです。
大変なのは出ていくお金、経費の計算です。
アフィリエイトサイトの経費は、サイトを運営していく過程で発生した、あらゆる支出が該当します。
例としては、以下のような支出です。
- ドメイン代
- サーバー代
- サイト制作費(外注した場合)
- ソフト代(Microsoft Office、AdobeCCなど)
- 有料画像素材の費用
- フォント代(MORISAWA PASSPORTなど)
- 通信費(スマホやモバイルも含む)
- パソコン本体代
- 作業用の机や椅子の費用
- 勉強用の書籍代
このほかにも、サイトのテーマに関連した出費は経費に計上できます。
例えば、ヘルスケア関連のサイトであれば健康グッズ、映画レビューサイトであれば映画のチケットなど、サイトの運営に必要であると説明できるものは全て経費で落とすことができます。
これらの費用は経費として計上すると、収益から差し引かれて、後に残った利益を小さくします。
所得税は利益に応じて算出されるため、利益が小さいと請求される税金(所得税や所得税に応じて決められる住民税)が小さくなります。
そのためサイトに関連した支出は、できる限り経費として報告した方が得になりますが、そうなると、ありとあらゆる買い物の記録を、全て領収書やレシートの形で証拠を残して、帳簿の上で合算しなければなりません。
もしこれをアナログで行うなら、1年分の領収書やレシートを山のように積んで、その支払いをひとつひとつ帳簿に手作業で入力していくということになります。
さらに、経費は「勘定科目」という基準に沿って分類する必要があります。(これを「仕分け」と呼びます)。
筆記用具なら事務用品費、電話料金なら通信費といった具合に、それぞれの支出の名目を明らかにしなければなりません。
確定申告が大変と言われるのは、この支出の計算と仕分けがあるためです。
単純な足し算と分類ではありますが、1年間のサイトに関連する全ての支出が対象になるため、数が非常に多く金額も膨らみがち。
時間がかかるし神経も使います。
数字が苦手な人にとっては煩わしい作業でしょう。
とはいえ、経費を増やせばその分、後で請求される税金が小さくなるために、わずかな支出でもサイトに関連したものなら全て経費に加えようと、頑張らざるをえないわけです。
アフィリエイト収入にかかる税金の金額

アフィリエイトで一定の収益を得たものの、そこからどれくらいの金額が税金として引かれるかが気になっている人は少なくないでしょう。
収益にかかる税金のうち、大部分を占めているのが所得税ですが、所得税は累進課税なので、収益の額に応じて税率が変化。
収入が大きくなるほど、税金として引かれる金額も大きくなります。所得税の所得金額に応じた税率と控除額は以下の表の通りです。
アフィリエイト収入にかかる税金の金額
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
-
(平成27年分以降)
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
収入が、この表の「課税される所得金額」のどの段階に該当するかによって、適用される税率を調べることができますが、注意しなければならないのが、所得金額はその年の収入の全体を含める点です。
つまり、アフィリエイト収入のほかにサラリーマンとして給与を得ている場合は、両者を合算した上で計算しなければなりません。
例えば、会社員としての年収が400万円、アフィリエイト収入が年間100万円の場合を想定してみましょう。
両者を合算した所得金額は500万円になるので、表の上から3番目の「3,300,000円~6,949,000円まで」に該当し、税率は20%が適用されます。
500万円の20%は100万円ですが、控除が42万7500円あるので、その分をマイナスして、52万2500円が所得税として引かれる計算になります。
アフィリエイトの確定申告の方法

1年間の収入と経費を計算し、経費の勘定科目への仕分けが完了したら、後はそれを確定申告用紙に記入して税務署へと提出します。
確定申告用紙は年明け頃に郵送されてくるか、あるいは税務署の窓口でも入手できます。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、それぞれ書式が違います。
最初の年は簡単な白色申告で行うといいでしょう。
白色申告は簡易式の申告方法で、税務署に事前に青色申告の届け出を行わなかった場合は、自動的に白色申告になります。
提出書類は確定申告書と、勘定科目ごとの金額が記載された収支内訳書さえあればOK。
経費を何に使ったかまでは記載しなくてよく、最終的な金額の収支さえ合っていれば認められます(ただし税務調査が入った際には、申告の根拠となる帳簿の提出が求められます)。
一方、青色申告をする場合は、青色申告承認申請書の事前の提出が必要です。
青色申告には記帳義務があり、簡易簿記あるいは複式簿記による損益計算書の提出が必要となります。
納税者の作業的な負担は大きくなりますが、その分、青色申告では65万円の特別控除が設けられていたり(複式簿記の帳簿の場合のみ)、赤字が出た年には純損失の繰越控除が行えるといったメリットがあります。
提出書類が用意できたら、2月16日〜3月15日の期間内に税務署に行って提出するか、郵送での提出、あるいはe-Taxでのオンライン申告を行います(e-Taxでの申告は1月上旬から前倒しで行えます)。
申告期間中は税務署によっては混み合うことがあり、特に期日ギリギリになると窓口に行列ができて、長時間待たされることもあります。
申告は余裕を持って行いましょう。
なお、国税局ではオンライン申告を推進しており、特に青色申告の65万円の特別控除は、オンラインの申告に限り認められています(税務署に直接提出した場合は55万円になります)。
e-Taxによるオンライン申請で必要となるのは、マイナンバーカードとICカードリーダーライタです。
マイナンバーカードは地方自治体に申請して取得しましょう。
ICカードリーダーライタは家電量販店などで2000円程度で販売されています。
もし規定以上の所得があったにも関わらず、確定申告を行っていなかったり、申告の内容を偽っていた場合にはどうなるのでしょうか。
これらは罰則の対象となり、本来の納税額に加算税と延滞税を追加されて、より多くの税金を払うことになります。
加算税は、未納のケースによって異なります。
確定申告自体を行っていなかった場合は、無申告加算税が課せられ、未納額に応じて15%から20%が加算されます。
確定申告は行っていたものの、申告額が本来の金額よりも少ない、いわゆる「申告漏れ」の場合には、過少申告加算税として、10%から15%の追徴となります。
一方、確定申告の申告内容に意図的な虚偽があった、「所得隠し」や「脱税」に該当する場合には、重加算税が加わり、35%から40%という高額な追徴を課されます。
さらに悪質とされた場合には刑事罰の対象となり、最大で10年以上の懲役もしくは1000万円以下の罰金が課せられることもあります。
確定申告の期限が過ぎた後でも、税務署の指摘を受ける前に自主的に申告した場合には、無申告加算税が免除あるいは減免される可能性があります。
もし確定申告をしていなかったことに気付いたら、すぐに税務署に相談に行きましょう。
クラウド会計ソフトを利用して省力化

近年は高度なクラウド会計ソフトが登場したことで、確定申告の作業が大幅に省力化されました。
クレジットカードと銀行口座のお金の動きを、クラウド会計ソフトが全て把握して、収入と支出を取りまとめてくれるため、以前のように領収書やレシートの内容を、表計算ソフトに入力する手間は不要になっています。
例えば、クラウド会計ソフトの「freee」では、登録したクレジットカードからの支出を全て記録して、勘定科目に自動的に分類。
1年間の収支の記録を帳簿にまとめて、そこから確定申告書や収支報告書を作成することができます。
青色申告で必要になる複式簿記による損益計算書は、簿記の経験がないと作るのは難しいと言われていましたが、freeeを利用すれば、会計の専門的知識がない人でも、申請に必要な書を作成できるようになります。
もちろん、e-Taxによるオンライン申告にも対応していて、国税局のサイトに移動しなくても、freee上から作成した申告書をe-Taxでそのまま申告することが可能です。
従来の確定申告では、青色申告は税理士に依頼するのが一般的で、簡単と言われる白色申告でも、膨大な作業が発生するため本業が圧迫されるのが当たり前でした。
しかし、クラウド会計ソフトが登場してからは、事情は大きく変わっています。
クラウド会計ソフトとe-Taxによるオンライン申告を使いこなせるようになれば、アフィリエイトサイトの確定申告にともなう負荷は大幅に軽減されます。
今後、フリーランスの税務処理には欠かせないスキルとなるのは間違いないので、アフィリエイトでの収益を見込んでいる人は、ぜひとも使い方をマスターしておきましょう。
確定申告の疑問に答えるQ&A

この章では、確定申告に関連した質問に答えるQ&Aを紹介します。
税金についての理解を深めるためにも、確定申告にまつわる疑問をここでしっかり解消しておきましょう。
住民税の確定申告は行わなくていいの?
個人の税金といえば所得税と住民税ですが、住民税は税務署ではなく居住地の区市町村の管轄になるため、そちらも別途、確定申告が必要になるのでは……?という疑問はよく耳にしますが、結論としては住民税の確定申告は必要ありません。
確定申告書を税務署に提出すると、その控えが市役所に送付されて、それを元にして市役所で住民税が算定される仕組みになっているためです。
赤字だった場合、確定申告はしなくていいの?
事業の支出が収入よりも多い、つまり収支が赤字だった場合、確定申告を行う義務はありません。
赤字の報告義務もないので、基本的には何もしなくてよいことになります。
ただし、赤字で確定申告を行わなかった場合には、いくつかのデメリットが発生します。
例えば、確定申告書がないと無所得であることを証明できないため、住宅ローンを組んだり事業資金の融資を受けたりすることができません。
ローンや融資の審査の際には、過去に遡って数年分の確定申告書の提出が求められることがあるため、そのときは良くても、後々困ることになる可能性があります。
また国民健康保険料は、無所得である場合は優遇措置が取られますが、確定申告を行っていないと、その措置の対象になりません。
さらに、青色申告を行っている場合にのみ、赤字の年の損失を翌年以降の黒字と相殺することで、課税所得を圧縮することができます。
この繰越は3年後まで行えますが、赤字で確定申告が行われていないと、当然この制度は利用できなくなります。
なお、赤字で確定申告を行わない場合も、その年の収支を記録した帳簿や領収書は必ず保存しておきましょう。
税務調査が入ったときに赤字であることを証明する必要があるためです。
領収書がない場合はどうするの?
確定申告では経費の証明として領収書が必要になりますが、必ずしも伝票形式である必要はありません。
レジで渡される通常のレシートでも領収書の代わりとなります(receiptは本来、領収書を意味する英語です)。
むしろ、手書きの領収書よりも偽装が難しく、記載されている情報量も多いため、レシートの方が信頼性は高いといえるでしょう。
領収書には印鑑が捺印されていることがありますが、商業上の慣習に過ぎないので、なくても特に問題ありません。
領収書がない場合は、購入の証拠となる記録を残しておきましょう。出金伝票、クレジットカードの記録、銀行通帳の明細、メールでの決済報告などが領収書の代替となります。
手書きのメモでも領収書の代わりとして認められるので、他に手段がない場合は書き残しておきましょう。
領収書を勝手に作ったらどうなるの?
領収書の偽装はそれほど難しくありません。
文房具屋に行けば領収書の伝票が売っているので、それを購入して架空の取引名と金額を書き入れるだけです。
ただし当然のことながら、税務署は領収書の偽造に厳しく目を光らせています。
業者が架空の場合は簡単にバレますし、実在の業者でも問い合わせれば取引があったかどうかはすぐに分かります。
年間の利益を相殺するほどの領収書は金額も大きくなるため、捏造するのはまず不可能です。
実在の領収書の金額を書き換える行為も同様で、税務署は数字の加筆や修正といった偽装を見破るのはお手の物です。
基本的に領収書関連の小細工は通用しないと考えてください。
領収書の捏造や偽装がバレた場合、ペナルティとして「過少申告加算税に代わる重加算税」が課せられ、不足分に加えて税金の35%を追加で納税しなければならなくなります。
確定申告をしないまま期日が過ぎた場合は?
所得があるにも関わらず、確定申告をしていないことに後から気付いたという場合は、速やかに税務署に行き確定申告を済ませましょう。
確定申告を行わなかったとしても、1年目や2年目であれば税務署が訪ねて来ることはまずありません。
しかしそれは税務署が気付いていないのではなく、納税額が小さいために見逃されているだけです。
そのまま未納を続けていると、未納分の金額がある程度まとまったタイミングで追徴され、一度に巨額の税金を支払う羽目になります。
確定申告をしておらず、何をどうすればいいのかも分からないという場合は、とりあえず税務署の窓口に相談に行きましょう。
税務署は自主的な納税の意思がある相手に対しては寛大で、その場で行うべき作業を全て教えてくれます。
延滞税が課せられる可能性はありますが、怒られたり叱責されたりするようなことはないので、恐れずに相談に行きましょう。
なお、2021年は確定申告の時期が新型コロナウイルスにともなう緊急事態宣言と重なった影響から、期限が1ヶ月延期され4月15日までとなっています。
サラリーマンなんだけどアフィリエイトの収益は確定申告しないとダメ?
会社に勤務するサラリーマンで、副業としてアフィリエイトサイトを運営している場合、給与以外に年間20万円以上の利益が発生した場合に、確定申告を行わなければなりません。
副業分の確定申告を行う場合もフリーランスと同様、税務署で入手できる申告書用紙に、副業で得た収益を記入して申告します。
なお、副業の場合、アフィリエイトで得た収益は「雑所得」という区分になり、青色申告はできませんので、副業の確定申告では確定申告書に、会社から給与と副業の収入を分けて記載します。
会社からの給与は、毎年会社から渡される源泉徴収票に記載されているので、その数字を給与所得、アフィリエイトで得た収入を雑所得として記入しましょう。
後は、源泉徴収票と合わせて税務署に提出すれば完了です。
隠れて副業をしていても税金で会社にバレるって本当?
こっそり副業をしていたのに会社にバレてしまった場合、原因は住民税にあることがほとんどです。
収入にかかる税金は、所得税と住民税がありますが、所得税は、副業で得た利益の確定申告を自分で行い税金を納付すれば会社には分かりません。
しかし、会社が源泉徴収を行っている住民税では、副業でトータルの年収が増えると、それに応じて額が増えるので、他の給与水準が同じ社員と比較したときに、別の収入があることが筒抜けとなります。
これを避けるためには、確定申告の際に、住民税を特別徴収ではなく普通徴収の指定にし、自力で納付する方法があります。
ただし、また自治体によってはこの方法が使えないこともあるようです。
確定申告をするとお金が戻ってくるって本当?
確定申告をすることで、払った税金の一部が戻ってくるという話を耳にしたことがある人もいると思います。
これは年末調整や確定申告によって、払いすぎていた分の税金が還付金として払い戻される制度のことを指しています。
会社からの給与や報酬は、会社側で税金分をマイナスした後の金額が支払われていますが、この仕組みを源泉徴収と呼びます。
確定申告では、源泉徴収された税金と申告した税金の照会が行われ、確定申告で申告された税金を、会社が徴収した分の税金が上回っている場合、その差額が還付されることになります。
源泉徴収される税金の算出方法は以下の通りです。
- 1回で支払う金額が100万円以下の場合
源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
- 1回で支払う金額が100万円を超える場合
源泉徴収税額 =(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円
還付金の額は、上記の方法で算出した源泉徴収額から確定申告を行った税金分を引いて、残った金額となります。
もっとも、納税者側が上記の計算を行う必要はなく、源泉徴収を行っている企業は源泉徴収票を発行する義務があり、毎年12月〜1月頃に届けられるので、それと確定申告の納税額を比較すれば、どのくらいの還付金が発生するかは見当が付くでしょう。
還付金は、確定申告から1ヶ月〜1ヶ月半後程度で給付されますが、確定申告が集中する2月〜3月は通常より時間がかかるようです。
還付金は銀行口座や郵便局への振り込みか、郵便局の窓口で受け取ることができます。
まとめ
今回はアフィリエイトと税金について解説しました。
アフィリエイトに限らず、仕事上で発生する収益とは切っても切り離せないのが税金。
ビジネスの規模が大きくなるほど、税金に関わる作業は複雑化し、支払う額も多くなっていきます。
そこで求められるのが、納税に関する正しい知識です。
それさえあれば、税金を最小限に抑え、そこで得られた分を事業の成長のための投資に回すことができるようになります。
お金は増やすだけでなく、無駄に減らさないためのノウハウも大事です。
税金について詳しくなることは、アフィリエイトの知識を増やすのと同じくらい、重要な意味を持ちます。
サイト運営にばかり目が向いて、税金対策がおざなりにならないよう、しっかりと知識を深めておきましょう。
誰でも10分!WordPressブログの始め方
ブログを始めるには、ライブドアブログやはてなブログといった無料ブログを使う方法、
あるいはWordPressなどを使用する方法があります。
まだWordPressを持っていない人でも、簡単に準備できる方法を以下の記事で解説してます。
初心者でもわずか10分で始められるので、参考にしてみてください。
合わせて読みたい
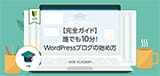
【完全ガイド】誰でも10分!WordPressブログの始め方
コロナ禍によりアフィリエイト業界が受けた影響
アフィリエイトマーケティング協会は、コロナ禍によるアフィリエイトへの影響について調査結果を公表しています。
報告によれば、全体の30.1%のアフィリエイターがコロナ禍による影響を受けたと回答しています。
そのうち、収入が増えたのが全体の43.3%で、内訳をみると100万円以上増加したユーザの割合が最も多く23.2%でした。
ジャンル別の状況では、脱毛サロン・エステ・スクール等の来店系案件が苦戦した一方で、オンライン型のサービスやVODなど巣ごもり需要と相性が良い案件が伸びたようです。
生活仕様の大きな変化に伴い、現状の生活に合わせたジャンルを選択することが成功の近道となるかもしれません。
アフィリエイトブログを始めるなら「お名前.com」
「お名前.com」は、国内No.1のドメイン登録サービス。
独自ドメインと合わせて、WordPressの自動インストールに対応したレンタルサーバーも利用できます。
WordPressや独自ドメインを一度も使ったことのない人でも、スムーズに始められるはず。
アフィリエイトに挑戦してみようと考えている方は、以下のリンクから、ぜひご利用ください。




