請求業務を効率化・自動化する方法|業務の流れや課題を交えて解説

Check!
- 従来の請求業務では、書類不備や工数の多さ、書類管理の煩雑さが共通の課題
- 2022年1月の電子帳簿保存法の法改正以降、電子請求書導入の流れがより加速
- 請求業務効率化と法令遵守には、「請求書発行システム」がおすすめ
請求業務とは、商品・サービスを提供した取引先から代金を受け取る、請求書発行から代金回収までの業務を指します。本記事では、請求業務の発行・受領フローや課題についてご紹介。請求業務におけるミスやコスト問題はどのように解消されているのか、効率化のための具体的な対策も詳しく解説します。
おすすめ記事
請求書発行システムを検討するならこのサービスがおすすめ
CRMと連携して手入力なしの請求書発行を可能に「マネーフォワード クラウド請求書Plus」
株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド請求書Plus

ここがおすすめ!
- 売上は契約期間に応じて「自動按分」で管理が行えるため、サブスク事業にも
- CRMや販売管理システムと連携でき、請求書はワンクリックでメール・郵送可能
ここが少し気になる…
- 導入まで2~3ヶ月かかり、導入を急いでいる企業には不向き

使いやすい機能やデザインで経理のウッカリ防止を月額0円からスタート「請求QUICK[発行]」
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
請求QUICK[発行]

ここがおすすめ!
- 請求書発行や自動読み取りは月に50通までなら無料で使える
- インターネットバンキングから明細取得ができる
- 「ファクタリング機能」を備え、発行した請求書を最短2営業日で資金化
ここが少し気になる…
- 郵送代行は1通ごとに285円と高め

従業員50名以下の企業に最適!簡単操作で紙保管にも対応「マネーフォワード クラウド請求書」
株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド請求書

見積書・納品書・請求書・領収書の作成が簡単に行え、ワンクリックでメール送付・郵送が完了するソフトなら、マネーフォワード クラウド請求書の導入がおすすめです。

ここがおすすめ!
- フォームに沿って入力するだけで簡単に帳票を作成できる
- インボイス制度にも対応
- 入金ステータスが一目で分かるので、請求の抜け漏れ防止にも効果的
ここが少し気になる…
- 請求書発行に特化しているものの、「入金消込」を利用するには「マネーフォワード クラウド請求書Plus」の契約が必要

請求関連業務のDX化を月契約でリーズナブルに始められる「invox発行請求書」
株式会社invox
invox発行請求書


ここがおすすめ!
- 初期費用が不要かつ「フリープラン」の提供により導入ハードルが低い
- 「カスタムレイアウト」や請求書の郵送代行・FAX送信にも対応
- 書類の発行だけでなく、入金消込や督促まで自動化できる
ここが少し気になる…
- プランにより「カスタムレイアウト」や「仕訳データ生成」「入金消込」など、一部機能の数量や利用に制限がある

請求業務とは

請求業務とは、商品などを提供した後に取引先から代金を受け取るために、請求書発行から代金回収までを行う業務のことをいいます。企業の請求においての事務作業は、一般的に経理担当が行っている場合が多いでしょう。
請求方法には、「都度請求」と「締め請求」の2種類あります。都度請求はサービスや商品を提供する度に請求を行い、締め請求は月ごとなどの限られた期間ごとに請求を行うものです。
また請求書の発行は、必ずしも行わなければならないという法的な義務はありません。基本的には、債権者と債務者間の取引内容の確認や、取引があった証明として発行されています。
請求書の役割
請求書とは、サービスや商品の対価を取引先から受け取るために、支払いの内容を確定させる文書です。
請求書の発行には法的な義務はありませんが、取引先との金銭のやり取りの証憑書類となります。例えば代金未払いのトラブルが生じた際に、請求書を提示することで取引があったことを証明することが可能です。
証憑書類とは、領収書や請求書などの、経理や会計などのビジネスシーンで取引を証明する書類のことです。証憑書類は、所得税法などで法人は法人税の申告から7年間、個人事業主は確定申告から5年間の請求が義務付けられています。
証憑書類は、上記のケースのように、会社の信頼性の確保やトラブル防止に役立ちます。税務調査や金銭的なトラブルがあった際に、適正な会計や取引であることが証明できる大切な役割があるため、適切な処理・管理が必要になります。
請求業務の基本的な流れ
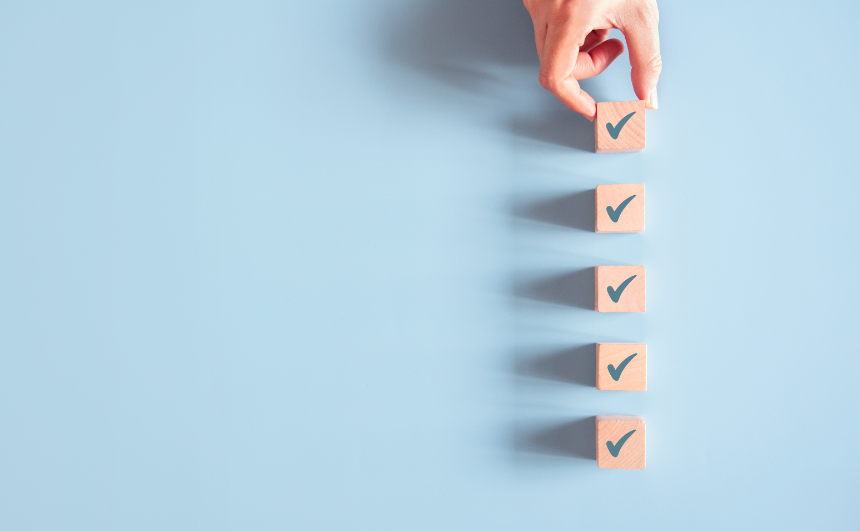
請求書は取引の流れを証明する大切な書類であるため、適切に管理する必要があります。しかし、従来の工程を改善するには、請求書業務の全体像を正確に把握することが大切です。
ここでは、請求書受け取り業務と発行業務の流れについて解説します。
請求書受け取り業務のフロー
請求書の受け取り業務は、ただ受け取って保管するだけではありません。取引先に請求書の受け取りをしたことを報告したり、代金振込確認をしたりといった業務があります。ここからは、請求書の受け取り業務の具体的なフローについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
請求書受け取り業務のフロー
請求書の受け取り
請求書の受け取りは、書面で印刷されて郵送される場合やFAX、PDF形式でデータ化してメールで送信される場合とさまざまな方法があります。
取引先の企業によっては、書面かデータかを合わせてくれる場合もあるため、自社の形式に合わせてもらえるか相談してみると良いでしょう。
請求書を受け取った後は、記載内容に不備がないか確認を行います。記載内容が条件と一致しない場合は、取引先に必ず確認しましょう。問い合わせする際は、請求書番号を控えておくと情報共有がスムーズになります。
経理への回覧と記帳
経理処理を行うために、請求書を受け取って内容を確認した後は経理部門への回覧が必要になります。その際、「支払依頼書」を作成して経理部門の承認を得ることもあります。
請求書の内容について共有された経理部門は、それを帳簿に記録します。会計システムを使用して記帳する企業も多いでしょう。
支払期日までに代金振込
支払いが確定した請求書は、設定された支払期日までに代金振込を行います。振込処理は、基本的に会計や経理担当者が行う場合が多いです。自社の代金振込の流れを確認し、請求書の内容確認、取引先に確認が済んだら、経理や会計の担当者に渡すように手配しましょう。
代金振込は、請求書に記載された支払期日当日に行われるのが一般的です。自動引き落としなどに登録しておけば、支払期日に遅れることなく引き落としが行えるため便利ですが、引き落としを自動化する場合は、残高不足などのトラブルに注意が必要です。
請求書発行業務のフロー
請求書の発行業務は、取引先に送る大切な書類であるため、記載内容に不備がないかをしっかり確認しましょう。また、受け取り業務よりも、発行業務の方が多くの業務工程があるため注意が必要です。ここからは、請求書の発行業務の流れについて具体的に解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
請求内容を確定
請求書を作成する前に、請求内容の確定をします。取引内容のサービス・商品の単価、数量、金額の情報が請求書に正しく記載されているかを確認します。特に見積もりなどを何度もやり取りした場合、請求書の金額が一致しないというケースも少なくありません。
請求書の内容にミスがあると、取引先から粗雑な仕事をする会社であると判断され、信頼性を失う恐れがあります。よって、担当者は記載ミスが起きないようにダブルチェックなどを徹底的に行い、金額や取引内容にミスがないか確認作業を怠らないようにしましょう。
請求書を作成
請求内容が確定したら、請求書の作成を行います。請求書には、以下の情報の記載が行われます。
- 請求元の情報(会社名・住所・電話番号・メールアドレス・担当者氏名など)
- 請求先の情報(請求元と同様)
- サービスや商品の内容
- 単価・数量・金額
- 支払期日
- 振込先
請求書は、エクセルやスプレッドシート、クラウドサービスなどで簡単に作成することができます。ただし、手入力の場合は入力ミスが起こりやすいため、記載内容に不備がないか十分にチェックしてから発行するようにしましょう。
また、2023年10月からはインボイス制度の開始によって、取引先との取引内容に応じて適格請求書(インボイス)の作成が義務付けられました。従来の区分記載請求書に登録番号の記載、適用税率や消費税額等の記載を必要とします。
なお、PDFなどのデータ化された請求書に関しても、記載内容の証明や、定められた期間における請求書の写しの保存・管理を必要とするため、請求書の作成には十分に気を付ける必要があります。
請求内容の承認
作成した請求書を送付するには、社内での承認が必要です。営業部門や購買部門などで作成した請求書を部門内で確認・承認した後、さらに上層部に承認を依頼する場合もあります。
部署をまたいでのフローになることや、押印が必要になるケースが多いことから、承認の作業には時間がかかることもあります。
請求書を送付
請求書を作成したら、取引先に送付します。請求書の送付方法は、紙媒体で郵送やFAXをする方法と、PDF形式でデータ化してメールなどで送付する方法があります。取引先の方針に合わせて、送付方法を選ぶようにしましょう。
メール・郵送どちらにおいても、送付先を間違えないように注意が必要です。もし、送付先を間違えたりすると、機密事項の漏洩にもつながるため、強固な管理体制を作りましょう。
また、メールなどでPDFデータを送付する場合、郵送代などのコストを削減したり、ポストに届けるなどの業務工程を無くしたりできるため、業務効率化にもつながります。よって、可能であれば、積極的に電子書類に移行するのがおすすめです。
入金確認
請求書の送付後は、支払期日までに入金されるか確認が必要です。請求書の振込は、一般的に支払期日当日に行われます。支払期日までに振込がない場合や、金額に過不足があった場合は、取引先に早めに問い合わせを行いましょう。
入金確認の問い合わせをする際は、請求書番号を控えておきましょう。電話やメールの際に、請求書番号を伝えると取引先への共有がスムーズになります。
消込処理
消込処理とは、売掛金や買掛金などの勘定科目で仕訳した残高に対し、請求書の内容通りに回収できているかをチェックし消し込み処理を行うことです。会計処理としては、売掛金として計上している時点では収益として扱われず、売掛金の消込処理を行ってから収益として計上されます。
また、売掛金の消込処理の正確さは、月次決済や締め作業に大きく影響します。取引先が多いほど、消込処理の作業も多くなるため、経理や会計担当の負担は計り知れません。消込処理は取引先との信頼性にもつながるため、なるべく金銭トラブルの発生を防ぎ、スムーズに処理できるように対策する必要があります。
取引先への再請求・催促
期日までに入金がない場合は、取引先へ催促を行う必要があります。取引先の負担を配慮して、最初は催促のメールを送付し、それでも支払いが確認できない場合は、電話・催促状・督促状の送付、の流れで取引先へ再請求を行います。
取引先に請求を催促する業務は、担当者にとって精神的な負担となるため、なるべく避けたい業務です。そのため、なるべく催促の業務を行わないためにも、自動引き落としや請求システムの活用など、催促をせずとも正しく入金が行われる環境に整備することが重要です。
請求業務を非効率化している課題

従来の請求業務には、請求金額の計算に時間がかかったり、書類不備などのミスが発生したりと課題も多いのが現状です。ここでは、請求業務の課題について詳しく解説するので、自社の請求業務についても考えながら参考にしてみてください。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
請求金額の計算に時間がかかる
従来の請求業務は、請求金額の計算に時間がかかるのが課題です。手計算する際はもちろん、エクセルなどの表計算ソフトを利用しても、取引先ごとに販売実績を照合しなければならないため、非常に集中力が必要な作業です。
また、入力ミスが起きると請求金額の合計金額が変わるため、担当者は慎重に作業しなければならず、時間と労力もかかる作業となります。取引先が多いほど経理や会計の負担が多くなるため、正確かつ迅速に対応できるシステムの導入を検討するべきでしょう。
書類不備のリスク
エクセルなどの、手入力作業で請求業務を行うと、書類不備のリスクがあります。サービス・商品の内容、単価、個数、金額などをすべて手作業で入力した場合、1つ間違えただけでも請求金額の合計金額が変わってしまうため、慎重に入力する必要があります。
請求書類に不備があると、信用に値しない会社だと判断されてしまう恐れもあり、会社自体の信用低下に繋がりかねません。
こうしたリスクを防ぐためにも、2重チェックなどで不備がないか確認を徹底したり、自動化して環境を整備したり、書類不備が起こりにくいシステム作りをすることが必要になるでしょう。
ミスの発生
取引先の数が多いほど、ミスの発生が多いのも課題です。ダブルチェックなどを行っていても、ワークフローが形骸化してしまい、一定の割合でミスが発生してしまいます。
そのため、経理担当1人に請求業務を任せるのではなく、部署ごとに金額をまとめてから経理に報告するなど、1人の業務負担を軽減するなどの対策が効果的でしょう。また、請求書発行システムなどを利用すれば、面倒な計算や請求書発行などの手間も軽減します。
時間やコストがかかる
請求業務は、時間やコストがかかるのも課題です。請求書は企業の信用性に関わるためミスが許されません。そのため、必ずダブルチェックを行うなど、請求書チェック作業を入念に行う必要があり、承認までの業務には複数の社員の確保、人件費が必要です。
また、紙ベースの請求書は都度郵送料が必要になります。その際、郵便局での手配やポストに投函する労力も必要になるため、取引先が多いほど手間がかかります。ペーパーレス化に対応するなど、できるだけ負担が少ない請求方法を検討しましょう。
書類の管理・保管が難しい
請求書は、書類の管理や保管が難しい点も課題です。請求書は証憑書類となるため、一定期間の保存が必要です。未払いなどのトラブル発生時もすぐに確認ができるように、分かりやすく整理整頓し、管理体制の強化をしておく必要があるでしょう。
また、紙媒体の請求書は、ファイルなどを保管するスペースも必要です。取引先が多いほど整理する業務や保管スペースが必要になるため、労働コストや保管スペースなども検討しなければいけません。
なお、紙ベースの保管であっても、データ化された請求書と同様、国によって保存期間が定められているため注意しましょう。
請求業務を効率化する方法

従来の請求業務では、多くの課題があることが分かりました。しかし、業務フローを改善したり、商品プロセスを簡略化したりすることによって、請求業務の効率化が可能です。ここからは、請求業務を効率化する方法について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
請求業務を効率化する方法
業務フローを改善
従来の業務フローの見直し・改善を行うことで、請求業務の効率化が可能です。自社の請求業務の一連の流れを具体的にすることで、自社の請求業務の課題と改善策が見えてきます。
担当者・業務内容などをそれぞれに分けて整理し、業務を簡素化できるものの洗い出しを行いましょう。例えば紙媒体の請求書をメール送信方法に切り替える、請求書管理・発行システムを導入するなどの方法で業務効率化を図ることができます。
自社の業務フローにおいての無駄を無くすことで、さまざまな業務効率化ができ、従業員の業務負担軽減など労働環境の整備にも繋がります。
承認プロセスを簡略化
承認プロセスを簡略化すると、スムーズに請求業務が行えます。企業によっては承認プロセスが非常に複雑になっている場合もあり、多くの労働負担がかかっている場合も少なくありません。
承認プロセスを簡略化するためには、請求書の承認のフローを自動化できる請求書管理システムの導入がおすすめです。システム上で稟議書・見積書などの管理もできるため、取引に関わる書類も参照しながら承認が行えます。
それにより、担当者が承認の度に必要な資料を確認したり、担当者ごとに直接承認を受ける必要がなくなり、業務効率化が期待できます。
アウトソーシングの活用
アウトソーシングの活用も、請求の業務効率化が図れます。アウトソーシングとは、自社の業務過程を外部に委託することを指し、請求書発行業務を外部に発注して業務効率化を目指すものです。
請求金額などのデータの準備を行い、請求書の作成・発行、郵送やメール送信業務、請求書管理・整理など、さまざまな事務作業を代行してくれます。業者によっては、入金確認や代金回収、催促業務など、従業員に精神的負担が生じる業務の委託も可能です。
ただし、請求内容の急な差し替えなどのトラブル時に、すぐに対応できない可能性があります。よって、請求確定処理を早めに行う、急な請求書の差し替えも迅速に対応してくれる業者を選ぶなどの対策が必要でしょう。
ペーパーレス化
紙媒体で請求書を管理するより、ペーパーレス化によってデータ化したやり取りの方が業務が簡素化します。紙媒体は、請求書の印刷、郵送業務、請求書の管理業務など、多数の業務負担がかかるのが難点です。
しかし、ペーパーレス化により、印刷・郵送準備などの事務作業をする必要がなくなり、請求書を保管するスペースも要りません。また、請求書をデータ化して保存できるため、内容確認や承認作業も、オンラインでスムーズに対応できるようになるのもメリットです。
請求書管理システム・請求書発行システムで業務を自動化
請求書管理・発行システムを導入すると、さまざまな業務を自動化できるのがメリットです。従来のエクセルなどの管理方法では、複雑な計算作業や入力ミスなどが課題でした。
しかし、請求書管理システム・請求書発行システムを活用すれば、請求金額の計算・承認・発行・送付・消込処理などの事務業務を自動化してくれるため、大幅な請求書管理の効率化・業務効率化が図れます。
そのため、労働コストや人的ミスの軽減も期待でき、営業や開発などのコア業務にリソースを割くことができます。また、自社の会計ソフトと連携できるものなら、会計処理まで行うことができるため、会計担当者の事務業務も軽減できるのもメリットです。
ただし、請求書管理システム・請求書発行システムにはさまざまな製品があるため、自社の課題が改善できる機能、使いやすいシステムかどうかを見極めて選定することが重要です。
\詳しくはこちらの記事をチェック/
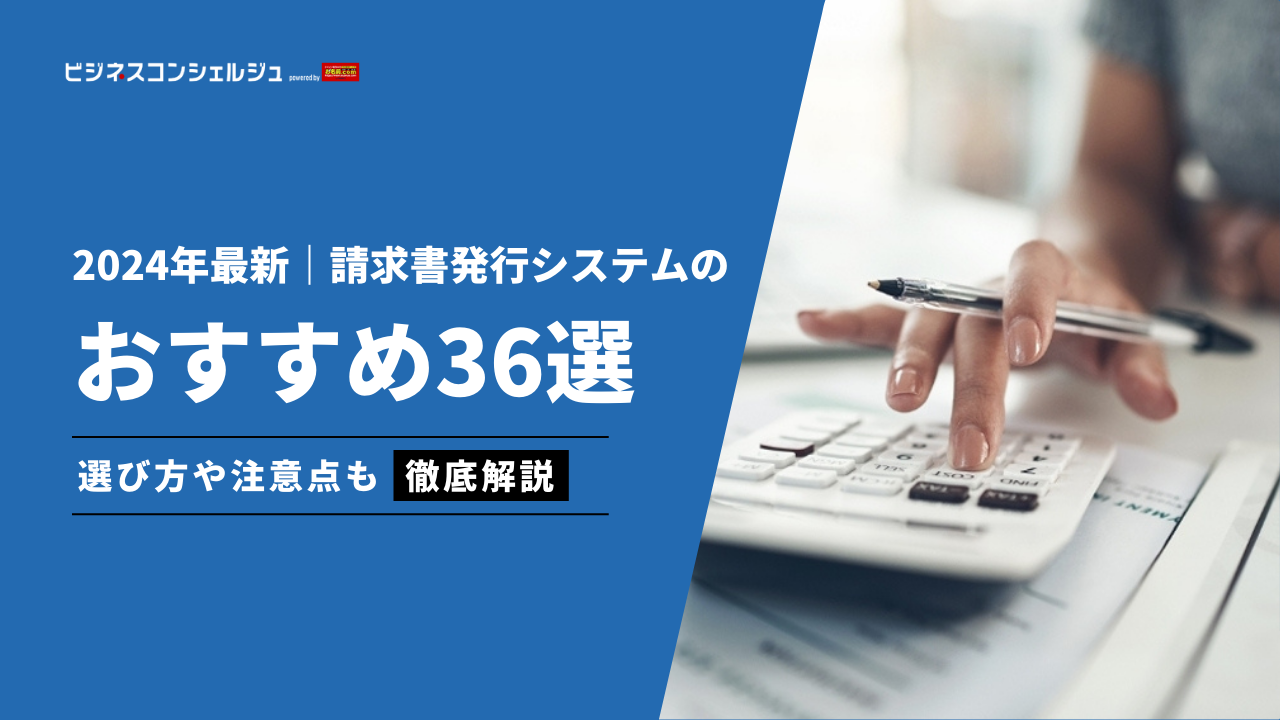
請求書発行システムおすすめ15選(全36選)を徹底比較|DX化で請求業務を80%削減!失敗しないポイントとは
請求書発行システムは、請求書の作成・発行などの業務を自動化できるITツールです。本記事では、請求書発行システムの選び方とおすすめ15選をご紹介。リサーチを重ねたポイントを比較すれば、大規模企業から個人事業主まで、ぴったりの請求書発行システムが見つかります。
まとめ

請求業務とは、商品・サービスなどを提供した取引先に代金を受け取るための、請求書発行から代金回収までの業務をいいます。しかし、紙媒体やエクセルなどを活用した従来の方法では、時間やコストがかかる、ミスが発生しやすいといった課題も多いです。
そのため、請求業務のフローを改善したり、承認プロセスを簡略化したりするなど、請求業務の効率化を図ることが重要です。請求業務を効率化するには、ペーパーレス化やアウトソーシングの活用、請求書管理・発行システムの導入などのさまざまな方法があります。
自社に合った方法を選ぶためにも、本記事の請求業務の流れ、課題などを参考に、自社の請求業務のフローを今一度見直してみてください。特に、請求書発行から管理まで一元管理できる請求書管理・発行システムを導入すると便利です。ぜひ導入を検討してみてください。
この記事に興味を持った方におすすめ


