SNS運用ガイドラインの必要性とは|作成手順や注意点も解説
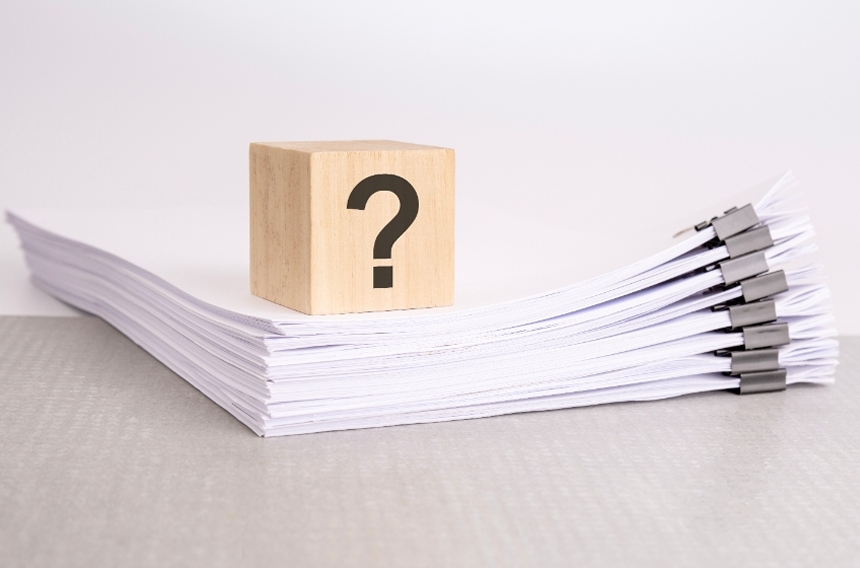
Check!
- 企業が長期的に安定したSNS運用を行うためには、ガイドラインの作成が必須
- SNS運用ガイドラインでは、基本方針・禁止事項・炎上時の対応方法などを定める
- ガイドラインの作成後は、対象者への周知徹底と定期的な見直し・更新を行う
SNSは企業の重要な情報発信ツールであり、効果的なSNS運用を行うためにはガイドラインが必要です。ガイドラインには社外向けのポリシーや社内向けの運用ルールなど、複数の種類があります。本記事では、SNS運用ガイドラインの必要性や作成手順などについて解説します。
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
企業のSNS運用にはガイドラインが必須

企業のSNS運用においてガイドラインは必須です。SNSは、顧客や社会との接点として重要な役割を果たし、情報発信やブランド価値向上に直結するツールですが、一方で誤情報の拡散や炎上などリスクも伴います。
そのため、ガイドラインを策定して運用方針を社内で共有することで、属人化を防ぎ、誰が対応しても一定の品質を保った情報発信が可能になります。
また、トラブル発生時にも対応手順を明確にしておくことで、ブランドイメージの損失を最小限に抑えられます。本記事では、SNS運用の概要に触れつつ、ガイドラインの必要性やその作成手順について詳しく解説します。
SNS運用ガイドラインの種類

SNS運用を効果的かつ安全に進めるためには、企業がルールや指針を明文化した「SNS運用ガイドライン」を複数の観点から整備することが欠かせません。以下では、それぞれのガイドラインの特徴や役割について詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
SNS運用ガイドラインの種類
SNS運用ポリシー
SNS運用におけるSNS運用ポリシーとは、企業がSNSを通じてどのような姿勢で情報発信やコミュニケーションを行うのかを社外に向けて明示するための基本指針です。
SNS運用ポリシーは、企業の信頼性を高めるための重要な要素の一つです。具体的な内容としては、「正確な情報発信を行う」「誠実かつ透明性のある対応を心がける」「差別的・攻撃的な表現を避ける」といった基本方針が盛り込まれます。
これを明文化して公開することで、ユーザーは企業がどのような考えでSNSを運営しているのかを理解できます。また、炎上や誤解を招いた際にも、ポリシーを根拠に一貫した説明や対応が可能になります。
コミュニティガイドライン
コミュニティガイドラインは、ユーザーが企業の公式SNSに関わる際に守るべきルールを定めたものです。このガイドラインを作成することで、ユーザー同士や企業とユーザー間でトラブルの防止を図れます。
具体的な内容としては、「個人情報の投稿は禁止」「誹謗中傷や差別的発言は削除対象」「宣伝目的のコメントは禁止」など、利用者の行動基準を明確にします。
このようなガイドラインを公開しておくことで、違反があった場合にも企業はルールに基づき毅然とした対応を取ることが可能です。SNSは開かれた場であるからこそ自由度は高いですが、その分、発言や行動に責任が伴います。
そのためコミュニティガイドラインの整備は、企業とユーザー双方にとって「安心・安全な交流の場」を維持するために重要です。
公式SNS運用ガイドライン
公式SNS運用ガイドラインとは、公式アカウントを運営する際に守るべきルールや手順をまとめたマニュアルのことです。このガイドラインを整備することで、属人化を防ぎ、誰が運営しても一貫したメッセージやトーンで発信ができるようになります。
ガイドラインには、投稿の作成・チェック・承認フロー、利用する画像や動画のルール、ハッシュタグの使用基準、コメント対応の手順、緊急時の連絡体制などを明確に定めます。
また、新任担当者が加わった際にもガイドラインを基に教育できるため、短期間でスキルを身につけられる点もメリットです。
社員向けSNS運用ガイドライン
社員向けSNS運用ガイドラインは、社員が個人としてSNSを利用する際の注意点をまとめたものです。このガイドラインは、社員の発言が企業全体に影響を及ぼすリスクを軽減するために必要です。
具体的には、「企業秘密や未公開情報を投稿しない」「顧客や同僚に関する個人情報を発信しない」「企業のイメージを損なうような発言を避ける」といった行動基準を設けます。
SNSでは社員個人の発言が瞬時に拡散され、企業の公式見解と誤解される可能性があるため、このようなルールを明文化しておくことが重要です。また、企業側としても、社員に自由な発信を認めつつリスクをコントロールできる体制を整えられます。
SNS運用ガイドラインで定めるべき項目

SNS運用ガイドラインには、企業が安心して効果的にSNSを活用するために押さえておくべき項目があります。以下では、SNS運用ガイドラインで定めるべき項目について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
SNS運用ガイドラインで定めるべき項目
基本方針・原則
まず定めるべきは、SNS運用の基本方針・原則です。基本方針・原則は企業がSNSを通じて何を目的とし、どのような姿勢で発信を行うかを明確にするものです。
情報発信を通じて顧客との信頼関係を構築する、企業ブランドの認知度を高めるといった目的を明文化しておくと、運用担当者は迷うことなく業務に取り組めます。
また、誠実さや透明性、迅速な対応といった基本的な姿勢や心構えも記載することで、担当者ごとの判断のブレを防げます。
機密情報の保護
SNS運用において最も避けなければならないのが、機密情報や個人情報の漏えいです。そのため、ガイドラインには情報管理に関する明確なルールを定めることが重要です。
たとえば、未発表の商品情報や取引先の契約内容、従業員の個人データなどをSNSに記載してはならないことを明示しておく必要があります。
加えて、写真や動画に無意識に社内資料や顧客情報が映り込むケースもあるため、投稿前の確認体制をルール化することが望ましいです。機密情報の保護により、企業の利益や信用を守るとともに、顧客からの信頼を失うリスクを大幅に軽減できます。
著作権に関する事項
SNSでは画像や音楽、記事など多様なコンテンツを簡単に利用できますが、他者の著作物や商標を無断で使用すると著作権侵害につながります。そのため、ガイドラインには著作権に関する事項を必ず含める必要があります。
SNSは誰でも手軽に投稿・共有できる場であるため、「少しなら大丈夫だろう」と軽い気持ちで他者のコンテンツを使ってしまうことも少なくありません。
しかし、こうした行為が企業の公式アカウントで行われた場合、企業そのものの信用失墜や損害賠償といった重大なリスクにつながります。
したがって、著作物や商標を利用する際に必ず権利者の許諾を得ること、また企業自身が保有するロゴやキャラクターなどを利用する場合のルールも、ガイドラインに明確に定めておくことが求められます。
誹謗中傷の禁止
SNSは不特定多数の人々とつながる場であるため、誹謗中傷にあたる発信を禁止することは欠かせません。特定の個人や団体を傷つける投稿が行われれば、瞬時に拡散され企業全体の評判を大きく損ねる恐れがあります。
そのため、ガイドラインでは誹謗中傷を禁止するだけでなく、どのような表現が該当するのかを具体的に示すことが大切です。
例えば、根拠のない批判や人格を否定する発言、差別的・侮辱的な表現、性的指摘やハラスメントにあたる投稿などはすべて禁止対象と明記することが有効です。
不明瞭な情報発信の禁止
SNS運用において最も重要なのは、信頼できる情報を発信することです。そのため、ガイドラインでは、根拠のない噂や未確認の情報を投稿することを明確に禁止する必要があります。
信憑性のない情報は瞬時に拡散し、後から訂正しても信用を取り戻すのは容易ではありません。特に企業アカウントは公式な情報源とみなされるため、一度でも誤った発信をするとブランド価値の低下や顧客離れにつながるリスクがあります。
そのため、投稿前には必ず情報の出所や正確性を確認し、必要に応じて複数の関係部署でチェックを行う体制を整えることが重要です。
炎上・トラブル時の対応策
SNSでは意図せず炎上やトラブルが発生することがあり、その際の対応の早さと適切さが企業の信用を左右します。そのためガイドラインには、万が一問題が起きた場合の社内対応フローを明確に定めておくことが重要です。
例えば、トラブルを発見した担当者は即座に上長や広報部門へ報告し、必要に応じて法務部とも連携する仕組みを整えると効果的です。また、公式発表の手順や発信媒体もあらかじめ決めておくと、混乱を最小限に抑えられます。
謝罪や訂正を行う際は、迅速な対応が不可欠であり、責任回避的な態度はさらに炎上を拡大させる恐れがあります。事前に具体的な対応策を策定しておくことで、企業は危機発生時でも落ち着いて行動を取れるでしょう。
発信内容の免責事項
SNS運用ガイドラインでは、発信における責任の所在を明確にする免責事項を設けることも重要です。
公式アカウントでの発信は、企業全体の意見や方針を代表するものです。しかし、担当者が誤って発信した場合の責任範囲を定めておかないと、曖昧なまま責任を押し付け合う状況に陥りかねません。
そのため、担当者にどこまでの権限と責任があるのか、また誤投稿やトラブルが発生した際に最終的な責任を負うのは誰かを明確にしておく必要があります。免責事項を設けることで、担当者自身が責任を意識し、より慎重で正確な情報発信につながります。
アカウントの管理方法
SNSアカウントの管理はガイドラインで必ず定めておくべき重要な項目です。管理体制が甘いと、不正アクセスやアカウント乗っ取りといった重大なリスクが発生し、企業の信頼を一気に失う恐れがあります。
そのため、ログイン情報は担当者以外に共有しない、定期的にパスワードを変更する、二段階認証を導入するなど具体的なルールを盛り込むことが大切です。
また、複数人で運用する場合は管理者権限を持つ人を限定し、投稿や設定変更の権限を明確に分けておくと安全性が高まります。加えて、退職や異動が発生した場合の権限削除や引き継ぎルールも記載しておくと安心です。
アカウントの適切な管理を徹底することは、企業のブランド価値や情報資産を守るうえで欠かせない取り組みといえます。
SNS運用ガイドラインの作成手順

SNS運用ガイドラインの作成には段階を踏んだ手順が必要です。ここでは、SNS運用ガイドラインを効果的に作成・導入するための手順について詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
SNS運用ガイドラインの作成手順
SNS運用状況をリサーチする
まず最初に取り組むべきは、自社のSNS運用状況を正確にリサーチすることです。現状を把握せずにガイドラインを作成すると、机上の空論となり実務に沿わないルールになりかねません。
そのため、マーケティング部門や広報部門だけでなく、人事や法務など関連部署に幅広くヒアリングを行い、どのような目的でSNSを利用しているのか、実際に抱えている課題やトラブルを整理します。
たとえば、情報発信の一貫性が保てていない、ネガティブコメントへの対応が属人的になっているといった実情を把握することで、必要なルールの方向性が明確になります。
ガイドラインの枠組みを作成する
リサーチで得た情報をもとに、SNS運用ガイドラインの全体像や基本的な枠組みを作成します。ここでは、ガイドラインに盛り込むべき主要な項目を整理することが重要です。
たとえば、投稿の基本ルール、トラブル発生時の対応フロー、情報管理や著作権に関する遵守事項、社員個人がSNSを利用する際の注意点などをガイドラインで明示するのが一般的です。
さらに、企業としてSNSを活用する目的や方針を明記することで、単なる禁止事項の列挙ではなく、従業員が前向きに活用できる指針となります。このような枠組みを固めることで、具体的な内容を肉付けする際に迷いが減ります。
この段階では、ガイドライン全体の設計図を描く工程だと捉えるとわかりやすいでしょう。
内容をブラッシュアップする
枠組みをもとに具体的な内容を作成したら、実際にガイドラインを利用する部署や担当者に確認を依頼し、内容をブラッシュアップします。現場での実務に即していない内容や、理解しづらい曖昧な表現は、この段階で修正することが重要です。
例えば、炎上リスクに関するルールが具体性を欠いている場合や、投稿基準が抽象的すぎる場合は、担当者からのフィードバックを踏まえて改善しましょう。また、利用者にとって過度な制約となってしまわないかという点もチェックする必要があります。
現場の声を反映させることで、現実的で実用性の高いガイドラインが完成し、実際に運用される中で形骸化を防げます。
対象者に周知する
完成したガイドラインは、全ての対象者に徹底して周知する必要があります。どれだけ内容が優れていても、実際に利用する社員が理解していなければ意味がありません。
そのため、配布や共有に加えて対象者への説明会や研修を行い、具体的なケースを交えて解説することが効果的です。
また、マニュアルのように堅苦しい形式ではなく、図解やQ&Aを取り入れることで理解が深まりやすくなります。このような周知と研修を徹底することで、従業員全員が安心してSNSを活用できます。
SNS運用ガイドラインを運用する際の注意点

SNS運用ガイドラインは、作成して終わりではなく、実際の運用段階で徹底して活用されてこそ意味を持ちます。どれだけ内容が充実していても、従業員が理解していなかったり、古いままのルールで運用されたりすれば、リスク管理として十分に機能しません。
そのため、ガイドラインを効果的に運用するには、対象者への周知徹底と定期的な見直し更新が欠かせません。ここでは、ガイドラインを組織に根付かせて、安全かつ時代に即した形で活用するための注意点について解説します。
対象者への周知を徹底する
SNS運用ガイドラインを導入したとしても、従業員がその存在を知らなかったり内容を理解していないと意味がありません。ガイドラインの周知を行う際は、文書を配布するほかにも、説明会や研修の場を設ける必要があります。
特に社内用のガイドラインであれば、SNSを扱う部署だけでなく全従業員を対象にすることで、全体のリスク意識を統一できます。また、新入社員研修や定期研修に組み込むと、ガイドラインが日常業務に自然と浸透していきます。
重要なのは「知っている」だけではなく、「実際に使える」状態にすることであり、そのためには繰り返しの周知と理解促進の仕組みを行いましょう。
定期的に見直し更新する
SNSは流行の変化が激しく、また法規制や社会的な価値観も常に変化しています。ガイドラインを一度作成したまま放置することは大きなリスクにつながるため、ガイドラインは定期的に見直し更新を行い、最新の状況に合わせる必要があります。
例えば、法改正による情報管理ルールの強化、あるいは新しいSNSプラットフォームの登場などに対応するためには、年に一度などの定期的なレビューを設定することが有効です。
また、更新内容は必ず全従業員に共有し、必要に応じて追加研修を実施することで、常に有効性のあるガイドラインを維持できます。
まとめ

SNSは今や企業にとって欠かせない情報発信・コミュニケーションの場であり、その運用には明確なルールが必要です。ガイドラインを整備することで、企業のブランド価値を守り、従業員やユーザーとのトラブルを未然に防ぐことができます。
ガイドラインは作成して終わりではなく、対象者への周知徹底や定期的な見直し更新を通じて運用に活かしていくことが大切です。環境や法律、トレンドの変化に対応することで、常に有効性のあるルールを維持できます。
SNSは自由度が高いからこそリスクも大きいですが、適切なガイドラインを設ければ、企業の信頼性を高めながら効果的な情報発信が可能になります。
本記事で紹介した手順や注意点を踏まえ、自社に合ったSNS運用ガイドラインを策定し、安全で持続的なSNS活用をしていきましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

