web社内報ツールの料金・費用相場とは?無料の注意点や選び方も解説

Check!
- web社内報ツールは、プラン内容やユーザー数、追加機能の有無によって料金が異なる
- web社内報ツールの料金は初期費用0〜3万円、月額利用料数千円〜数十万円程度が相場
- 無料で利用できるweb社内報ツールもあるが、容量や機能などの制限に注意する
Web社内報ツールは、社内報を簡単に作成・配信できるツールです。ツールを比較検討する際は、料金相場を押さえておくことが大切です。本記事ではWeb社内報ツールの料金・費用相場のほか、料金以外の比較ポイントや無料ツールについても解説します。
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
Web社内報ツールを導入するなら料金相場の確認が重要

Web社内報ツールは、社内報を簡単に作成・配信できるツールです。従来の紙媒体やPDFの配布よりも利便性が高く、社員が必要なときにどこからでもアクセスして、社内報の閲覧・編集を行えます。
特にインターネット上で利用できるクラウド型のサービスが主流であり、社内ネットワークに限定されず、スマートフォンやパソコンなど複数のデバイスから閲覧可能です。
Web社内報ツールを比較検討する際は、料金相場を押さえておくことが大切です。提供サービスや機能範囲によって料金が大きく異なるため、自社に必要な機能を把握したうえで、適切なコストで運用できるかを見極めましょう。
本記事ではWeb社内報ツールの料金・費用相場のほか、料金以外の比較ポイントや無料ツールについても解説します。
Web社内報ツールを導入するメリット
Web社内報ツールを導入することで、紙の社内報と比較してリアルタイム性の向上や、データ分析が可能になるといったメリットを得られます。以下では、これら2つのメリットについて詳しく解説します。
情報をリアルタイムで発信できる
Web社内報ツールを導入することで、紙の社内報と比較して情報をリアルタイムで発信できるメリットがあります。通常、紙の社内報を作成する場合、内容の執筆や編集、印刷を経て従業員が閲覧できるため、情報にタイムラグが発生することも少なくありません。
Web社内報ツールを活用すると、システム上で作成・発信ができ、従業員は気軽に社内報を閲覧できます。また、内容の修正が必要になった場合もシステム上で効率的に更新・編集ができるため、担当者の作業負担も抑えながらスピーディーに最新情報を共有可能です。
データを細かく分析できる
Web社内報ツールでは、閲覧率や読了率など従業員がどのくらい社内報を読んでいるかを細かく集計できます。紙の社内報の場合、作成・配布したら終了のため、従業員にどのくらい読んでもらえたかを把握することは難しい傾向にあります。
Web社内報ツールならデータを分析することで、従業員がどのようなコンテンツに興味を持っているか、反対に離脱率が高い内容も把握可能です。そのため、より従業員に読んでもらうための対策を講じることができ、質の高い社内報の作成に繋げられるでしょう。
Web社内報ツールの料金・費用相場

クラウド型のWeb社内報ツールを導入する際は、「初期費用」と「月額利用料」という2つのコストが主に発生します。特にクラウド型はサーバーやシステムを自社で構築する必要がなく、低コストで始められるのが魅力です。
ただし、プラン内容やユーザー数、追加機能の有無によって利用料に幅が出る点を理解しておくことが大切です。以下では、初期費用と月額利用料の相場について詳しく解説していきます。
初期費用
Web社内報ツールの初期費用は0〜30万円程度が相場です。クラウド型サービスは導入のハードルを下げるために、初期費用を無料または低額に設定しているケースが多いです。
ただし、場合によっては、初期設定の代行やデザインテンプレートのカスタマイズ、導入時のサポートなどに追加費用が発生することもあります。
そのため、単に「初期費用が無料」と記載されていても、オプションを利用することで数万円〜数十万円の費用が発生する可能性もある点に注意しましょう。どの範囲までを初期費用に含むのかを事前に確認し、予算を見積もることが重要です。
月額利用料
Web社内報ツールの月額利用料は数千円〜数十万円と幅広く、ユーザー数やオプション機能、ストレージ容量によって大きく変動します。例えば、小規模企業やスタートアップ向けのプランでは数千円から利用できる場合もあり、低コストで気軽に導入可能です。
一方で、大企業や多拠点展開している企業が利用する場合は、多くのユーザーが閲覧したり、アクセス権限管理、詳細な分析機能などの高度な機能を必要としたりします。そのため、月額費用が数十万円に及ぶことも珍しくありません。
このように単に安さだけで選ぶのではなく、自社の利用規模や目的、必要な機能を整理したうえで、最適なプランを選定することが重要です。長期利用が前提の場合は、多少高額でも必要な機能を網羅したプランを選ぶと、結果的に費用対効果が高くなるでしょう。
料金以外のWeb社内報ツールの選び方

Web社内報ツールを選ぶ際には料金だけで判断するのではなく、機能性や操作性、セキュリティ、サポート体制など複数の要素を総合的に比較することが重要です。以下では、料金以外のWeb社内報ツールの選び方について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
料金以外のWeb社内報ツールの選び方
必要な機能を備えているか
Web社内報ツールを選ぶうえで重要なのは、自社の目的に必要な機能が備わっているかどうかです。
各ツールには、記事作成や分析、コメントなど多様な機能がありますが、それらがすべての企業に必要というわけではありません。必要な機能を明確にしたうえで選ぶことで、余分なコストをかけず効率的に運用でき、費用対効果も高まります。
反対に機能が不足していると、後から追加開発や別サービス導入が必要になり、かえってコストや運用負担が増える可能性もあります。そのため、最初に目的を整理し、機能の優先度を決めて選定しましょう。
Web社内報ツールの主な機能
Web社内報ツールには、情報共有の効率化やコミュニケーションの活性化のためにさまざまな機能が備わっています。例えば、社員が「いいね」やコメントで交流できる機能や、記事の更新を知らせる機能、カテゴリやタグによる検索機能があります。
その他にも、アンケートや閲覧制限で活用範囲を広げられるのも特徴です。以下の表では、Web社内報ツールの主な機能についてまとめました。
| 機能 | 主な内容 |
|---|---|
| 記事作成・編集機能 | テンプレートやエディタを使って誰でも簡単に 記事を作成・編集できる機能 |
| データ分析機能 | 閲覧数やリアクション数を集計し、 効果測定できる機能 |
| リアクション・コメント機能 | 「いいね」やコメントを通じて社員の 参加意識を高める機能 |
| 通知機能 | 新着記事や更新情報をプッシュ通知やメールで 知らせる機能 |
| カテゴリ・タグ機能 | 記事を分類して、必要な情報を検索できる機能 |
| プロフィール機能 | 投稿者や閲覧者のプロフィールを表示し、 コミュニケーションを促す機能 |
| アンケート機能 | 記事に関連した意見や満足度を収集できる機能 |
| アクセス制限機能 | 部署や役職ごとに記事閲覧権限を制御する機能 |
マルチデバイス・アプリに対応しているか
Web社内報の効果を高めるためには、従業員がどこでも気軽に利用できる環境を整えることが重要です。そのため、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなど、マルチデバイスに対応しているツールを選ぶことがおすすめです。
特に外回りが多い営業職やリモートワーク中心の従業員にとっては、スマホアプリやモバイルブラウザからアクセスできるかどうかが社内報の閲覧率を大きく左右します。
加えて、iOSやAndroidなど複数のOSに対応していれば、従業員が自分の端末を使ってストレスなく利用できます。対応環境が限定されていると、一部の社員は社内報を閲覧できず、情報共有の効果が半減する恐れがあります。
そのため、導入前に自社の利用環境に合うマルチデバイス対応の有無を確認しましょう。
担当者が操作しやすいか
Web社内報を効率よく運用するには、記事を作成・配信する担当者が直感的に操作できるツールを選びましょう。操作が難しいシステムは、効率的に社内報の作成ができなかったり、情報の更新が滞ったりする原因となります。
そのため、分かりやすいUIや記事テンプレート、画像や動画の添付機能など、コンテンツ制作を支援する機能が整っているかが重要なポイントです。特に動画コンテンツは、経営者メッセージの発信や社内イベントの共有など、さまざまな場面で活用されやすい機能です。
動画に対応したツールであれば、より効果的な情報発信が可能になるでしょう。また、誰でも同じ手順で記事作成や配信ができるツールを導入することで、業務の属人化防止にも繋がります。
セキュリティ対策は万全か
社内報には、経営戦略や新規事業計画など、外部に漏れると大きなリスクにつながる未公開情報が含まれる場合があります。セキュリティ体制が不十分なツールを導入すると、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まり、企業の信用を損なうことも考えられます。
そのため、Web社内報ツールを選ぶ際は、セキュリティ対策が十分に施されているかどうかを確認することが重要です。例えば、通信の暗号化やアクセス制御機能が標準で搭載されているかを確認しましょう。
併せて、ISMS認証を取得しているベンダーのツールなら、より高い水準で情報管理が行われている可能性が高く、安心して利用できます。また、海外拠点や外部委託先との連携がある企業では、国際的なセキュリティ基準に準拠しているかどうかも重要です。
サポート体制は充実しているか
Web社内報ツールは導入して終わりではなく、運用を継続していく中でトラブル対応や機能活用の相談が必要になる場面が多くあります。そのため、各ベンダーのサポート体制が自社のニーズに合っているかを確認することが大切です。
サポートの範囲は、操作マニュアルやFAQの提供のみの場合や、チャットや電話での即時対応、専任担当者による運用アドバイスまで受けられるものもあります。また、対応時間が平日のみか、夜間・休日も可能かによっても利便性が変わります。
さらに、定期的なアップデートや機能改善がされるかどうかも、長期利用を考えるうえで大きな判断材料です。サポート体制が充実しているツールを選べば、運用上の不安を軽減しつつ、継続的に運用できるでしょう。
無料で利用できるWeb社内報ツールもある

Web社内報ツールの中には、無料で利用できるものも存在し、コストを抑えて情報発信を始めたい企業にとって魅力的な選択肢となります。
ただし、無料で使えるツールには、一定の機能やデータ容量を備えた無料プランや、導入前に操作性や効果を試せる無料トライアル・デモなどがあり、それぞれに特徴があります。以下では、無料で使えるツールの種類について詳しく解説します。

無料で利用できるWeb社内報アプリ・ツールおすすめ20選|選び方・注意点も解説
Web社内報は、紙の社内報と比べて情報を迅速に共有できるのが魅力です。多くのWeb社内報ツールでは、無料トライアルやデモを提供しており、無料で継続利用できるプランもあります。この記事では、無料で利用できるWeb社内報アプリ・ツール全20選や選ぶ際に注意したいポイントなどを解説します。
無料プランがあるツール
無料プランを提供するWeb社内報ツールは、運用コストが一切かからないため、予算を抑えたい企業にとって魅力的です。特に小規模組織や、まずは試験的に社内報を導入してみたいと考える企業には適しています。
しかし、無料プランには一定の制限が設けられていることが多い点に注意しましょう。例えば、記事数や保存できるデータ容量、利用できるユーザー数に上限が設けられているケースが一般的です。
そのため、コストをかけずにまずはツールを試してみたい企業や、小規模で最低限の情報共有が目的といった場合におすすめです。一方で長期的かつ本格的な利用の場合には、有料プランへの切り替えを見据えて検討することが大切です。
無料トライアル・無料デモがあるツール
無料トライアルや無料デモを利用できるWeb社内報ツールは、導入前に実際の操作感や機能を確認できる点が大きなメリットです。
トライアルでは通常、一定期間有料プランと同等の機能を利用できるため、社内報の効果や操作性を実際の環境で試せます。無料デモはベンダー側が操作画面や機能を紹介する形で、短時間で概要を把握できるのが特徴です。
これらの活用によって、自社の目的に合ったツールかどうかを事前に判断できるため、導入後に「使いづらかった」「想定していた機能がなかった」といったミスマッチを防げます。
そのため、本格導入を検討している企業は、必ず無料トライアルやデモを利用して比較検討することがおすすめです。
無料で利用できるWeb社内報ツールの注意点

無料で利用できるWeb社内報ツールは便利ではありますが、有料版と比べると制約が多い点に注意が必要です。一般的に無料プランは有料版と比べて、データ容量・ユーザー数・機能・サポートに制限があります。
そのため、特に従業員が多い企業や、画像や動画を多く載せたい企業は有料版がおすすめです。無料ツールはあくまで導入検討や小規模利用の入り口として位置付け、長期的には有料版を前提に選ぶことが賢明です。
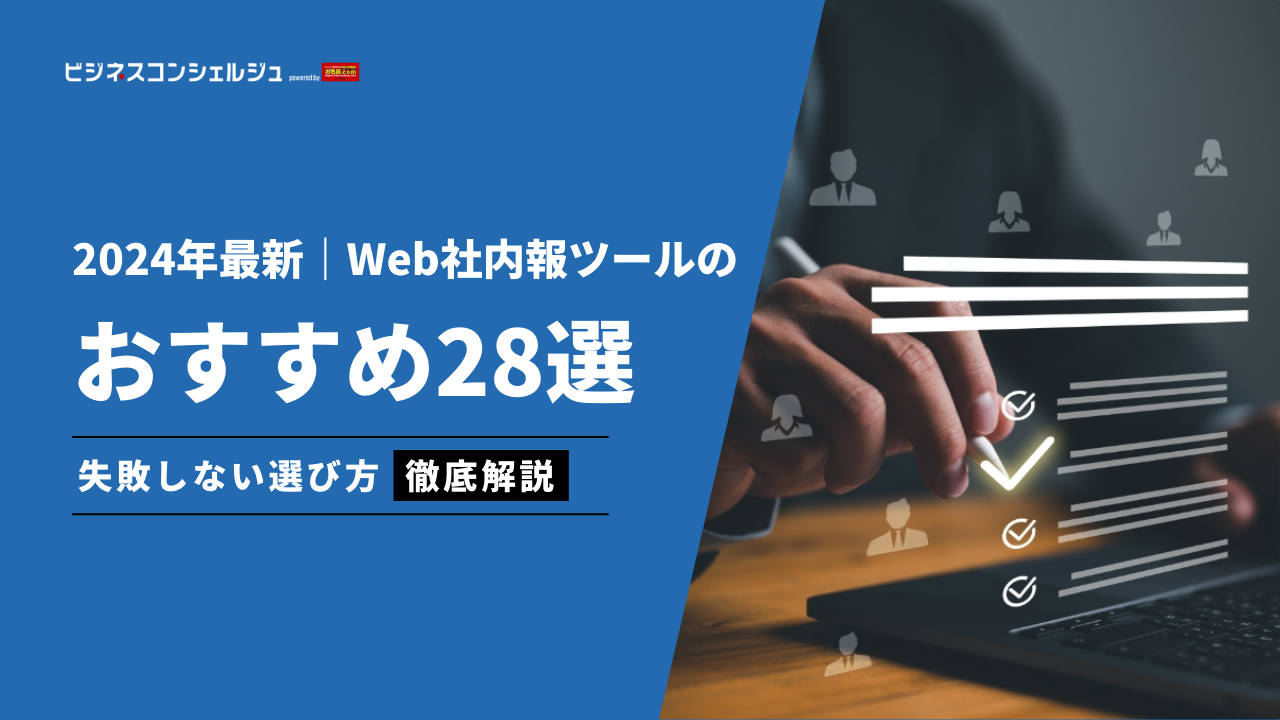
Web社内報ツールおすすめ10選(全28選)を徹底比較!選定のポイントや導入時の注意点を解説
Web社内報ツールとは、システム上で社内報を作成・更新・修正などができるツールです。紙媒体と違って、リアルタイムで共有できて物理コストが発生しないことから、近年多くの企業で社内報のデジタル化が進んでいます。本記事では、徹底比較したおすすめのWeb社内報ツールや選び方などを詳しく解説します。
まとめ

Web社内報ツールは、社内報を効率的に作成・配信し、従業員同士の情報共有やエンゲージメント向上などに役立ちます。
ただし、導入する際は、初期費用や月額利用料といった料金相場を理解することが重要です。また、必要な機能や操作性、マルチデバイス対応、セキュリティ対策、サポート体制なども比較ポイントとなります。
さらに、無料プランやトライアルを活用することでコストを抑えつつ、自社に合ったツールを見極められる点も魅力です。本記事を参考に、自社に最適なWeb社内報ツールを導入して、効果的な運用の実現を目指しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

