電話代行とは?サービス内容やメリット、選び方のポイントを解説

Check!
- 電話代行は、企業にかかってくる電話を電話代行業者に転送・対応を依頼できるサービス
- プロのオペレーターが電話対応するため、応対品質や顧客満足度向上にも繋がる
- 電話代行を選ぶ際は、対応業務やオペレーターの応対品質を事前に調べておくことが重要
電話代行は、企業にかかってきた電話をオペレーターが代わりに対応してくれるサービスです。電話代行にはメリットがある一方で注意点もあるため、よく理解して導入することが大切です。本記事では、電話代行の主なサービス内容やメリット・デメリット、選び方などについて解説します。
おすすめ記事
電話代行とは

電話代行とは、企業やお店などにかかってくる電話を代わりに取って用件を聞き、取り次ぎや返答などを行うサービスです。通話内容はメール・チャット・電話などを使って報告されるため、自社で働く事務員のような役割を果たします。
商談や会議中などで手隙の従業員がいなくても受電ができるため、電話の取り逃がしによる機会損失も防げます。人件費や教育費などのコストがかからないため、中小企業や個人事業主の方にもおすすめです。
電話代行の仕組み
電話代行は、お客様から会社にかかってきた電話を自動で転送し、プロのオペレーターに対応してもらうという仕組みです。名前や用件を確認し、内容によって緊急性が高いものは電話、急ぎでないものはメールなどで利用者に連絡が入ります。
また、利用者は必要に応じて伝言を託したり、自分の携帯電話などに取り次ぎをお願いすることもできるため、自社の事務員が電話対応をしてくれるイメージで利用できます。
電話代行と他のサービスの違い
電話代行と似たサービスに、コールセンターや秘書代行などがあります。他のサービスとの違いについても把握しておきましょう。
大きな違いは、同じ会社の事務員のように電話の受付を行い、メールや電話などで取り次ぎを行う点です。企業や会社の名前を名乗るため、お客様には内線で取り次ぎをしてくれているような感覚で話してもらえます。
また、電話代行は中小企業や個人事業主などの少ない入電数から対応可能です。低価格帯でコール数が少ないプランを提供する業者もあり、コストを抑えつつ利用できます。また、年末年始やイベントなどの一定期間のみ利用もできるのも、電話代行の特徴です。
コールセンターとの違い
コールセンターでは、専用の電話番号で予約や注文などの受付完了まで対応します。入電数の多い大手企業の通販サイトやお問い合わせセンターなどで使われ、一定数のオペレーターを確保するためにアルバイトや在宅ワーカーを採用することが多いです。
一方、電話代行では専用の番号を用意せず、自社の既存の電話番号をオペレーターに転送するかたちで用います。また、一般的に1人〜数人程度で対応できる入電数の場合に利用され、自社でオペレーターを採用する必要もないため、教育費や採用費がかかりません。
秘書代行との違い
電話代行は電話対応に特化されているのに対し、秘書代行はメールやチャットなど電話以外の対応やスケジュール管理などの秘書業務も行います。電話代行よりも事務仕事の幅が広いのが特徴です。業務範囲が広い分、電話代行よりもプラン料金も高い傾向にあります。
秘書代行では、企業のニーズに合わせて依頼業務を柔軟にカスタマイズできることも多いです。近年ではオンラインでの代行が一般的で、幅広い事務作業を任せたい場合には便利な選択肢となっています。
電話代行が注目されている背景
電話代行は、Eコマースの拡大やリモートワークの推進などに合わせて、多くの事業者が導入するようになっています。
Eコマース(Electric Commerce)とは、日本語で「電子商取引」を意味し、電子的に行われる取引全般を指します。現代では、スマートフォンを経由してネットショップを利用する消費者が増え、電話対応やカスタマーサポートなどの対応件数も拡大傾向にあります。
コールセンターを用意するほどの規模ではないが、顧客からの問い合わせに対応しきれないというケースも多く、電話代行の需要が高まっています。
また、近年はリモートワークが定着し、一般的な働き方となりました。従業員がリモートワークに切り替える中で、オフィスにかかってくる電話への対応が難しくなるケースも少なくありません。こうした課題解決に電話代行は有効です。
電話代行に依頼できる業務内容

電話代行には、ごく簡単な電話応対から、より本格的な対応まで、さまざまな業務を依頼できます。主なサービスについて具体的に解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
受電業務
受電業務では、会社にかかってきた電話を受け取り、相手の名前や要件などを記録して、自社の担当者に報告するのが基本となります。
基本の受電業務では、オペレーターが要件の詳細に踏み込むことはなく、相手との最初とのタッチポイントとしての役割のみを果たします。事務員が電話を取り、内線などで担当者に取り次ぐ、あるいは不在時の留守番電話と同じようなイメージです。
受注業務
受注業務を任せる場合、電話での商品の注文や予約の受付などを依頼できます。商品やサービスの情報や受注のしかたなどをあらかじめオペレーターに共有しておき、それに基づいて対応してもらいます。
特に小規模な事業者では担当者が常に電話に出られる状態にないことも多いため、電話代行に受注まで任せるメリットは大きいです。
問い合わせ対応
顧客からの問い合わせへの対応も電話代行が提供するサービスの一つです。商品やサービスに関する質問のほか、クレーム対応も含まれます。
この場合も、受注業務と同じく商品やサービスの情報、対応方法などをオペレーターに共有しておきます。必要に応じて自社の担当者に引き継ぐよう依頼することも可能です。
営業電話への対応
営業や勧誘の電話など事業者にとって必要のない電話がかかってきた際には、担当者に取り次ぐのではなく、断りを入れるよう依頼することもできます。断り方についても、自社の要望を反映することが可能です。
こうした電話の対応をオペレーターに任せておけば、自社の従業員が余計な電話に煩わされることもなくなるでしょう。
電話代行のメリット

電話代行を導入すると、さまざまな面でメリットを得られます。具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
従業員がコア業務に集中できる
電話代行サービスを利用することで、接客中や作業中の電話をオペレーターが受電するため、従業員はコア業務に集中できます。特に少人数で業務を行っている企業では、一日に何件も電話対応をすると業務が滞り、負担になることもあります。
また、営業電話や迷惑電話にも対応してくれるため、不必要なやり取りに時間を取られることもありません。
人件費や教育費がかからない
会社で最もコストがかかるのが人件費です。電話対応のために人材を雇う場合、採用コスト・人件費・教育コストなど、さまざまな負担が発生します。
対して、電話代行サービスであれば初期費用とプラン料金のみで利用できるため、給与や教育するためのコストと比べると少ない費用で済むことがほとんどです。また、プランも幅広く用意されており、コストの無駄を防げます。
手間をかけずに応対品質を高められる
準備期間や教育に多くの時間をかけずに、高いクオリティの電話応対を実現できるのが電話代行のメリットです。未経験者を含むアルバイトや在宅ワーカーなどを教育する手間をかけなくても、電話代行では一定以上のスキルを持ったプロが受電をしてくれます。
電話代行を提供するサービス事業者はオペレーターに対して研修を行っており、中には社員全員が秘書検定を取得しているサービスなどもあります。そのため、対応してほしい内容を共有するだけで、最初から即戦力として高いクオリティの応対が期待できます。
機会損失の防止や顧客満足度向上に繋がる
会議中や接客中、また営業時間外でもオペレーターが代わりに電話対応をしてくれるため、機会損失を防げます。どうしても電話に出られない状況が発生したり、人手が足りず電話対応まで手が回らなかったりするケースは少なくありません。
電話の取り逃がしが起きると、売上や顧客獲得のチャンスの損失に繋がり、電話が繋がらないことで顧客満足度の低下も招きかねません。電話代行によって、このようなリスクの軽減を図れます。
電話代行のデメリット
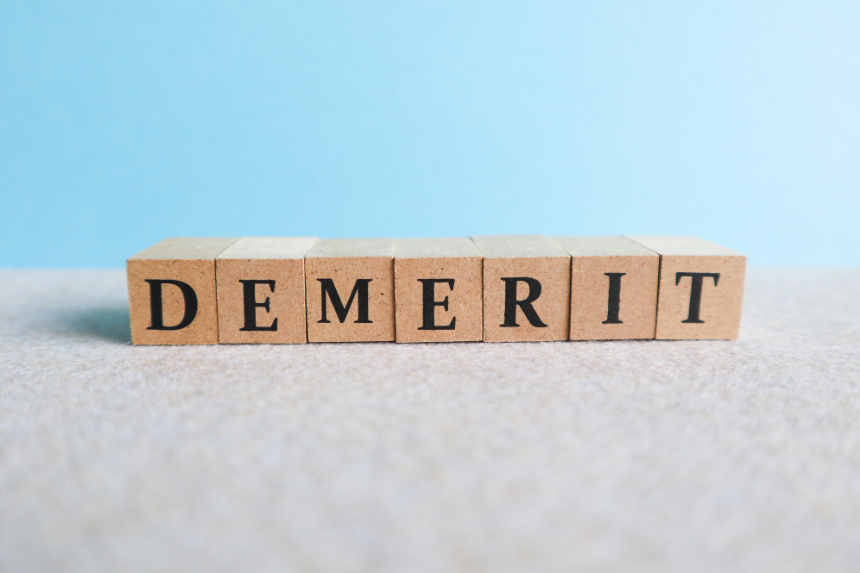
電話代行にはメリットだけでなく、デメリットもあります。導入の失敗を防ぐためにも、あらかじめデメリットもチェックしておきましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
費用が高額になる場合がある
電話代行の料金体系には、主に月額基本料金型と成果報酬型の2パターンあります。月額基本料金型は決められた受電数の中であれば、毎月決まった金額で利用可能です。あらかじめコール数と料金が決まっており、コールオーバー分は別途費用が発生します。
もう一方の成果報酬型は、何件受電したかによってサービス料金が変動します。入電数の少ない企業であればおすすめですが、件数が多いと費用が高額になりやすいため、自社の入電数を確認してからプランを選びましょう。
また、今まで電話対応を社員や契約者自身が業務の合間に行っていた場合、電話対応に追加の費用をかける形になるので、慎重に導入を検討しましょう。
想定外のケースに対応しづらい
電話代行のオペレーターは実際に自社で働いている社員ではないため、決められた回答・事前に共有している内容以外は答えられません。顧客からイレギュラーな問い合わせなどが来た場合は、その場で対応することができないリスクもあります。
オペレーターが直接対応できないことで、顧客への対応が遅れるといった可能性も否定できないので、事前に応対のしかたについてしっかりすり合わせ、対策を打っておきましょう。
オペレーターの対応が問題になることもある
オペレーターはプロとはいえ、何らかの問題が発生する可能性もあります。特にクレーム対応や重要な顧客対応など、印象が大切な場面でミスが起きると、顧客は自社に不信感を抱いてしまいます。
加えて、基本的にはサービス会社の担当者としかやり取りができないため、オペレーターに「もっとこうしてほしい」といった要望を直接伝えるのは難しい点にも注意が必要です。オペレーターに何らかの問題があった場合でも自社で直接指導することはできないことを理解しておきましょう。
情報漏洩のリスクがある
電話対応業務では、お客様の氏名・連絡先・住所・注文内容などの個人情報を扱うことも少なくありません。また、依頼する業務によっては、自社の重要な情報を共有する必要があるため、情報漏洩のリスクは少なからずあります。
万が一情報漏洩が発生すると、顧客や取引先からの信頼を失ったり、顧客離れや売上の減少が起こったりするだけでなく、損害賠償や訴訟に発展するリスクがあります。サービス側もセキュリティには気を配っているとはいえ、こういったリスクを念頭に置いておくことが重要です。
電話代行の利用がおすすめの事業者

電話代行は、業界や業種に関係なく、さまざまな事業者に重宝されています。特に以下のような課題を抱えている場合は、電話代行の導入を検討してみましょう。
専任の事務員がいない
電話対応は事務員が担当することが多いですが、事務員を雇っていない場合は従業員がほかの業務と電話対応をはじめとする事務仕事を兼任することになります。特に従業員の人数が少ない場合は、専任の事務員がいないことも多いです。
こういったケースでは、電話対応のせいでほかの業務がスムーズに進まないなどの問題が発生しやすいので、電話代行に任せられる部分はアウトソーシングすることをおすすめします。
電話の取りこぼしが生じている
従業員全員が同じタイミングで休憩を取る・リモートワークを始めた・営業時間外にも電話がかかってくるといった理由で電話の取りこぼしが生じている場合も、電話代行の導入がおすすめです。
従業員がリモートワークをする日のみ・営業時間外のみなどピンポイントの依頼もできるため、自社に足りていないリソース分だけを追加することができます。
電話代行を比較する際の選び方のポイント

電話代行サービスは数多くあるため、依頼できる内容や料金プランなどを確認しておきましょう。自社のニーズと照らし合わせて、多角的にサービスを比較することが重要です。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
電話代行を比較する際の選び方のポイント
依頼できる業務の範囲
電話代行は、サービス会社やプランによって、基本的な受電業務のみ、予約や注文のみなどなど、対応できる業務範囲が限られている場合があります。自社の課題を効果的に解決するために、まずは依頼できる範囲の確認をしましょう。
また、万が一トラブルが起きた際の対応方法や、応対のしかたなどについてどこまで柔軟にカスタマイズできるかも事前に確認しておきましょう。
料金体系と費用
電話代行を選ぶ際は、自社に適した料金プランを選びましょう。前述のように基本月額料金型と成果報酬型がありますが、入電数が多い場合は基本月額料金型、少ない場合は成果報酬型を選ぶのがベターです。
便利だからと不必要なプランやオプションをつけてしまうと、コストがかさみます。また、同じような料金体系でもサービスによって費用が異なるので、費用対効果の観点から吟味が必要です。
料金の安さだけで電話代行サービスを選ぶのは危険
中には、相場よりも安くサービスを提供する電話代行業者もあります。しかし、安さだけに気を取られて利用を決めてしまうと、かえって顧客満足度の低下を招いてしまうかもしれない点に注意しましょう。
例えば、格安の電話代行サービスでは、自宅などの音質が保証されない環境で業務を行っているケースも少なくありません。また、オペレーターのスキルが十分でないこともあります。
その場合、電話代行を利用していることがバレるリスクもあり、それをよく思わない顧客からの信用性に影響を与える可能性に留意が必要です。
応対品質や情報管理体制
電話対応は会社の顔だと言われるほど、相手に大きな印象を与えます。そのため、できるだけ応対品質の高いサービス業者に依頼することが重要です。トライアルで実際の応対を確認したり、過去に大手企業や有名会社との取り引きがあるか調べておくと良いでしょう。
また、情報管理体制について評価するために、プライバシーマーク(Pマーク)・ISO・ISMSを取得しているかなどをチェックすることをおすすめします。情報管理体制がしっかりしていれば、セキュリティリスクも低減できます。
対応できる時間帯
オペレーターが対応できる時間帯は、平日のみ9時から17時まで、24時間365日対応など代行業者によって異なります。中には土日祝のみ利用できるプランを提供する業者もあるため、平日は自社の従業員で対応できるが、休日対応は難しいという企業におすすめです。
なお、24時間365日対応や夜間対応は、オペレーターの負担も大きくなるため、コストが高額になりやすい点に注意しましょう。費用対効果の高い運用を図るなら、電話が多い時間帯をあらかじめ確認し、利用時間を決めておくのがポイントです。
受電内容の報告方法
オペレーターからの受電内容の報告方法も確認しましょう。メールやチャットツールなどさまざまな報告方法がありますが、普段の業務の中で使用しているツールでの報告に対応している電話代行がおすすめです。
慣れないツールでの報告は確認漏れなども起こりやすく、電話をかけてきた相手とのトラブルに発展する可能性が高まります。
まとめ

電話代行は、受電業務・受注業務・問い合わせ対応などの業務を委託できるサービスです。自社の従業員はコア業務に集中できる上に、電話の取り逃がしによる機会損失を防げるメリットがあります。
料金プランには主に基本月額料金プランと成果報酬型プランがあり、依頼できる業務範囲のほかオペレーターの応対品質などもサービスによって少しずつ異なるため、自社のニーズに合ったサービスを選ぶことが重要です。
本記事で紹介した内容を参考に、電話代行のメリット・デメリット、選び方をしっかり理解し、最適な電話代行サービスを導入しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

