SEO対策におすすめのWordPressアクセス解析ツール11選

WordPressにアクセス解析ツールを導入したいけど、数が多くて何を選べば良いのか分からないという悩みをお持ちの人は少なくないでしょう。
今回は、専門知識が無くても使用できるアクセス解析ツールを11個紹介します。
ユーザーの細かい行動を可視化できるアクセス解析ツールを導入し、更にWordPressで管理しているウェブサイトのアクセスを伸ばしていきましょう。
Googleのアクセス解析ツール
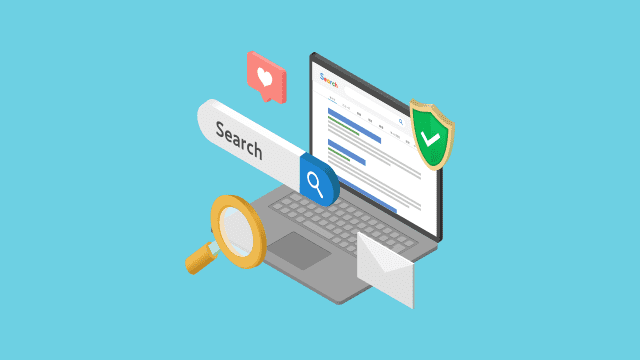
まずは、アクセス解析ツールの基本中の基本であり、他のアクセス解析ツールと連携する機会も多いGoogle Analyticsと、「Googleでどのようなキーワードで検索されたか」を可視化できるGoogle Search Consoleからご紹介しましょう。
Google Analytics
アクセス解析をするなら必須とも言える、ウェブサイトを訪れたユーザーの動きを見える化、データを抽出できるツールです。
Google Analyticsを導入すれば、ウェブサイトのアクセス解析に必要なデータをほぼ全て抽出できます。
単体で優れた分析ツールであると同時に、Google AnalyticsとAPI連携してデータを抽出するタイプのツールがいくつもあります。
利用には、トラッキングコード(ページのアクセス解析に必要なコード)をサイトのヘッダー内に設置する必要がありますが、WordPressでウェブサイトを運営している場合は、プラグインを使うことでトラッキングコードを簡単に設置できます。
Google Analyticsでは、サイトを訪れたユーザーが使用している端末、その他性別や年齢等の非常に細かいデータまで可視化できるため、どのような人がサイトを見ているのかを手に取るように把握できます。
また、アフィニティカテゴリ欄では、ウェブサイトを訪れたユーザーの嗜好やライフスタイルのデータを表示可能で、より詳細なターゲティングが可能になります。
Google Analyticsを使いこなすことで、よりハイレベルで効果的なウェブサイト運営が可能になるでしょう。
Google Search Console
Google Analyticsでは抽出できない「ユーザーがウェブサイトを訪れる前」のデータを可視化できるのがGoogle Search Consoleです。
記事ページへアクセスしたユーザーが、検索エンジンでどんなキーワードで検索して訪れたかを抽出できるので、ユーザーの検索ニーズをより具体的に把握できるようになります。
Google Search Consoleは、Googleの検索画面でのクリック率も把握できます。
検索画面でのユーザーの反応を追跡できる点が特徴で、例えば記事のタイトルやメタディスクリプションが、検索ユーザーにとって魅力的な文章になっているかなどが分かります。
また、検索エンジンの平均掲載順位の変化を正確に調べられるので、公開した記事がどのような順位変動を経て今の順位に居るのかなど細かな動きを確認できます。
さらに、リンク機能からはウェブサイトがどのようなウェブサイトからリンクされているのかを把握できるほか、通常のアクセス解析では気付きにくい、サイトが抱えている問題(インデックス登録されていない、Googleからのペナルティを被っているなど)を確認できる点も重要です。
Google Analyticsと連携するアクセス解析ツール

次に、Google Analyticsと連携し、データ抽出を行うアクセス解析ツールを紹介します。
Google Analytics単体では手間がかかるようなデータ解析、レポート作成などを自動でやってくれる優秀なツールもあるので、ウェブサイト運営者は要チェックです。
Googleデータポータル
Google関連サービスを中心に、BigQueryなどのビッグデータを扱うクラウドデータベースと連携することも可能なデータ統合ツールです。
Google Analyticsのデータからレポートを作成すれば、アクセス解析の結果を好みの形式を指定してグラフ化できます(期間ごと、棒、円グラフなど)。
Google Analyticsのアクセス解析データに加え、Google広告やSNSとも連携してのレポート作成が可能で、SEO以外の運用データを含め統合的に管理できます。
複数データをレポート化してチームに共有、あらゆる角度からの分析が可能です。
AIアナリスト
Google Analyticsとの連携が前提のサービスで、3万5000サイトを分析したノウハウの元、AIがウェブサイト分析してくれるサイト改善ツールです。
Google Analyticsから抽出したデータを元に、ウェブサイトの改善方針を教えてくれます。
データを抽出しただけでは、なかなか具体的な改善に活かし切れないサイト担当者も多いと思いますが、AIアナリストはウェブサイトのアクセス改善はもちろんのこと、広告の改善にも力を発揮します。
目標に対する現状の進歩度も見えるほか、効果検証機能も実装されているので、SEO対策で行き詰っている場合は導入してみて下さい。
Tableau
Google Analyticsと連携して、アクセスや売り上げデータを可視化して、ビジネスの改善に役立つデータとしてまとめるツールです。
Google Analytics等で抽出したデータのみでは施策立案が難しい場合には、TableauのようなBI(ビジネスインテリジェンス)ツールがおすすめです。
主に抽出したデータのビジュアライゼーションに役立つツールで、データを見える化し、あらゆる角度から施策を打てます。
例えば、Google Analyticsでは数字としてしか見えていなかった離脱率などを、動的なデータの推移として表示できます。
数字よりも感覚的に見られるグラフで表示することで、より簡易的にアクセス解析ができます。
GArepo
Google Analyticsと連携してデータを抽出、約3分で解析レポートを作成できるBIツールです。
レポート作成の完全自動化が可能で、例えば毎月日付を指定してレポートを作成するといった用途に活躍します。
手動でのレポート作成は非常に手間がかかり、人為的なミスが起こる可能性も考えられますが、その点レポート作成が極限まで自動化されるのは非常に魅力的です。
日時推移レポートでは過去と現在のデータを比較し、さまざまな施策の結果、どのように改善されているのかを可視化できます。
過去との比較レポートでは、改善が必要な箇所が赤文字で表示されるなど、レポート作成の自動化と同時に、よりスピーディーに改善点を見つけられる機能があります。
コンバージョンレポート機能では新規成約率、リピーター成約率などを集計し、どの部分で改善が必要かを可視化できます。
FARO REPORT
Google AnalyticsやGoogle Search Consoleと連携することで、効率的にレポート作成ができる解析ツールです。
基本的なアクセス解析レポートだけでなく、ECサイトの売り上げ管理にも対応しています。
Google Search Consoleを連携することで、検索キーワード分析レポートを作成可能で、より効率的にユーザーの検索心理を分析し、改善に役立てられます。
単体で使えるアクセス解析ツール
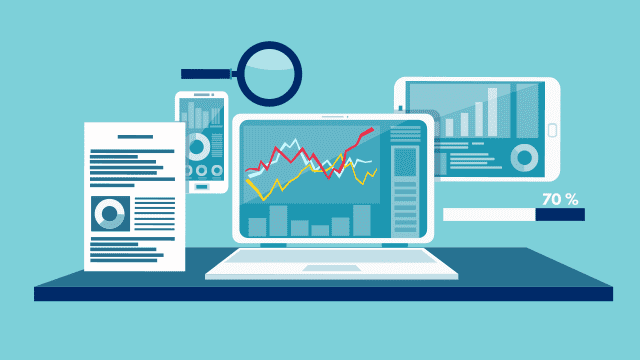
ここでご紹介する解析ツールは、Google Analyticsと連携することなく、単独でアクセス解析ができます。
独自データを利用してユーザーの細かい属性を把握できるツールなどがあります。
Clarity
Windowsでお馴染みのMicrosoftが出している無料ヒートマップツールです。
ウェブサイトにアクセスしたユーザーの行動を、ヒートマップで分かりやすく表示します。
セッション記録では、ユーザーがタップした位置が見えると同時に、ユーザーがどのようにスクロールしたかを把握できるので、読み飛ばされている部分が分かるなどのメリットがあります。
ヒートマップ機能では、ユーザーがよく読んでいる場所に色が付いて表示され、ウェブサイト内でのユーザー行動が可視化されるので、サイト内で特にユーザーにとって魅力的なコンテンツを把握できるでしょう。
また、更に細かいユーザーの動きも可視化可能で、例えば以下のようなデータを出せます。
- ユーザーがクリックして反応がなかった割合
- ユーザーが同じ個所を複数回クリックした割合
- ユーザーがページにアクセス後、元のURLに戻った割合
- 早いスピードでスクロールした(読み飛ばした)割合
詳細なユーザー行動が見えるため、コンテンツ内容の改善だけでなく、サイト構造の見直しにも役立つでしょう。
eMark+
独自データ(PCユーザー20万人・スマホユーザー10万人)を基に、オンライン、オフライン問わずターゲットの詳細な行動を把握できる分析ツールです。
eMark+には4つのサービスラインナップがあります。
- 競合サイト分析
- 検索キーワード分析
- ターゲットユーザー分析
- 特定競合の徹底分析
競合サイトの分析機能が中心ですが、独自データを使ったターゲット分析が可能な点から、単体でのアクセス解析ツールとしても使えます。
ウェブサイトにアクセスしたユーザーが、普段どのようなウェブサイトを見ているのかをランキング形式で表示し、サイトの訪問ユーザーの属性をより詳細に分析できます。
オフラインの行動分析も可能で、例えばウェブサイトを訪れるユーザーが、普段どのような商品を買っているのかも把握できます。
その他、使用アプリなども把握することで、アクセス解析のみでは難しいようなユーザーの細かい心理にアプローチできます。
競合分析機能を使えば、自分のサイトと競合サイトの集客効果などを徹底比較できるなど、競合・ユーザー分析に特化したツールです。
競合サイトを分析できるツール
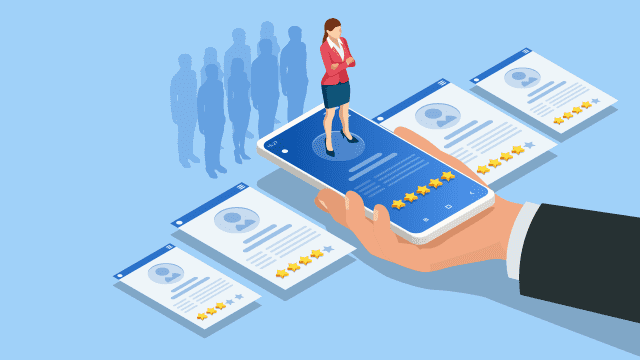
ここでは、検索キーワードにおけるライバルサイトなどを分析できるツールをご紹介します。
SimilarWeb
競合サイトのトラフィック(ユーザー流入数)などをベンチマークで比較できる、競合分析に長けた分析ツールです。
競合のマーケティング戦略を分析し、自分のウェブサイトの成功要因を導き出します。
競合サイトの検索ワードを分析し、自分のサイトが上位表示可能な検索ワードを探り当てたり、検索ボリュームやクリック率などの視点から、今後狙うべきキーワードを特定できます。
アフィリエイトパートナーのモニターも可能で、例えば競合サイトへのアフィリエイト流入を可視化できるため、新たなアフィリエイトパートナーの選定にも役立つツールです。
ANATOMY
Google検索上位20サイトを簡単に把握できる競合分析ツールで、アクセス解析機能も統合的に使えるツールです。
キーワード選定の際、手動で検索を行って上位サイトを確認するのは手間がかかりますが、アナトミーを活用すれば競合サイトを瞬時に判断できます。
Google Search Consoleと連携することで詳細なキーワード分析が可能です。
特定キーワードに対するSEO分析、定期的なスナップショットによる検索順位推移グラフをはじめ、関連キーワード分析までできます。
一つのツールで多くの角度からデータ分析できるツールです。
まとめ
今回はサイトのアクセス解析の際に役立つツールを紹介しました。
ウェブサイトは漠然と運営しているとなかなか課題が見えにくいもので、アクセス解析ツールによる数字の裏付けに基づいた課題の抽出と対策は、極めて重要な施策です。
「分析レポート作成を効率化したい」「より成功要因を出しやすいデータが欲しい」「競合の動向を分析したい」など、現場のニーズに応じて適したツールを導入しましょう。
漠然とした数字として見えていた解析結果も、優れたアクセス解析ツールを介すことでより見やすく、改善に役立つデータになることでしょう。




