Web社内報の導入効果・メリットとは?運用時のポイントも解説

Check!
- Web社内報は、経営理念の浸透やコミュニケーション活性化、社内のDX化などに役立つ
- Web社内報は紙媒体と比べてスピーディーな情報共有が可能で、動画や音声も活用できる
- 閲覧数や読了率などのデータを活かして運用することで、より盛り上げることができる
紙資源の削減や情報共有の円滑化を目的に、Web社内報を利用する企業が増えています。Web社内報はコミュニケーションを活性化できるだけでなく、DX化の推進にも効果的です。本記事では、Web社内報の導入効果やメリット・デメリット、運用時のポイントを解説します。
おすすめ記事
Web社内報でリアルタイムな情報共有を実現

Web社内報とは、インターネット上で配信・閲覧できる社内報です。紙媒体に比べて手軽に作成・配信でき、リアルタイムな情報共有や管理がしやすいことから、近年は紙媒体からWeb社内報に切り替える企業が増えています。
Web社内報の導入により、社内コミュニケーションの活性化やコスト削減、DX化の推進などの効果に期待できます。本記事では、Web社内報の効果やメリット、効果を高めるためのポイントなどを解説します。

Web社内報とは?メリット・デメリット、運営のポイントを解説
Web社内報は、社内報をWeb上で展開することで、作成の効率化・リアルタイムでの情報共有が行えます。テレワークや働き方改革の影響をきっかけに、社内報をデジタル化する企業が増えています。本記事では、Web社内報のメリットやツールの選び方を解説しています。
Web社内報の導入効果
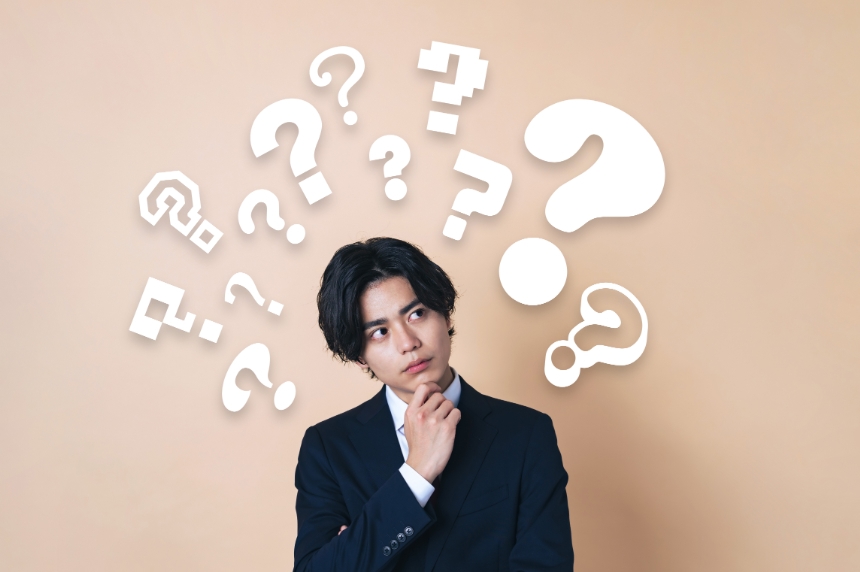
紙媒体からWeb社内報を切り替えることで期待できる効果は多岐に渡ります。ここでは、Web社内報の導入効果について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
Web社内報の導入効果
経営理念やビジョンが浸透する
社内報には、従業員向けに経営理念やビジョンを発信する役割があります。社内報を通じて自社における社会的責任や事業目的を伝えることで、社内の隅々にまで経営者の思想を伝えられます。
特に、Web社内報はインターネットを通じて配信するため、複数拠点や離れた事業所の従業員にもトップメッセージを簡単に繰り返し伝えることが可能です。
定期的な情報発信を繰り返すことで、従業員一人ひとりに理念やビジョンが根付きやすくなり、その達成に向けて自然に行動変容を促せます。
コミュニケーションが活性化される
社内報は社内向けの情報発信媒体ですが、経営層から従業員に対して一方向の情報発信になりやすいのが課題です。しかし、Web社内報の中には、コメントやリアクションといったコミュニケーション機能を搭載したものも多くあります。
これらを活用することで、情報の受信者・発信者間での双方向のコミュニケーションが可能です。通常は交流のない部署同士の関係構築に役立つだけでなく、会社への帰属意識を高めることにもつながります。
また、現場・経営層間でのコミュニケーションが活発化することにより、組織がより深く連携し、経営における透明性の向上といった効果にも期待できます。
従業員のモチベーションが向上する
Web社内報を通じて、効果的に従業員の称賛・評価などを行うことで、モチベーションの向上が見込めます。例えば、同じ会社内であっても「○○部署は何をしているのかよく知らない」といったケースは少なくありません。
社内認知度が低い部署をWeb社内報で紹介し、会社にどのような貢献をしているのかを伝えることで、その部署で働いている従業員の認知度を高めることが可能です。
さらに、日頃からWeb社内報を通じて部門同士の理解を深めておくことで、業務を頼みたいときにもスムーズにコミュニケーションを取れるなど、迅速な連携体制の強化に期待できます。
DX化が推進される
従来まで紙媒体で社内報を発行していた企業では、Web社内報への切り替えによってペーパーレス化とDX化を同時に推進できます。DX化とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、企業としての優位性を保つ取り組みです。
DX化により、紙媒体の社内報では難しかった双方向のコミュニケーションや閲覧率の計測、効果測定が可能になり、社内連携の強化と生産性の向上も見込めます。持続的な組織活性化に加え、企業成長やビジネスの拡大にもつなげられます。
コスト削減につながる
紙媒体からWeb媒体に切り替えることで、紙代・印刷代・製本代といったコストを大幅に削減できます。社内報の保管場所も不要になり、複数拠点を持つ企業における社内報の郵送・保管コストも減らすことが可能です。
また、Web社内報は人的・時間的なコストの削減にもつながります。紙媒体に比べて編集・修正がしやすく、配布の手間もかからないため、社内報の作成から配布にかかる工程をまとめてデジタル化することで、作成担当者は他業務に集中できるようになります。
ナレッジ共有で業務の質が高まりやすくなる
Web社内報は、日々の業務で得た学びや成功事例を手軽に発信できるため、組織内にナレッジを蓄積しやすくなるのが特徴です。紙媒体のように掲載量を気にする必要がなく、現場で生まれた小さな工夫や改善事例も共有しつつ、他部署が参考にできる機会が増えます。
その結果、似た課題へ対応が早まり、業務の質を底上げしやすくなることに加え、部門をまたいだ取り組みへの理解も深まりやすいです。同じ課題を繰り返しにくくなれば、日常的な業務改善にもつながります。
拠点ごとの情報格差が生まれにくくなる
Web社内報により、同じ内容を同じタイミングで従業員全体に届けられるため、多拠点やリモート環境でも情報の偏りが起きにくくなります。スマートフォンやタブレット端末など、各自のデバイスからすぐに閲覧できるのも機会損失の防止に役立ちます。
例えば、本社と支店、オフィス勤務とテレワークなど、働く場所によって生まれがちな認識のずれを減らし、全体的に統一した情報基盤を築きやすいです。情報が均等に届くことで、部署や拠点間でのやり取りがスムーズになり、組織全体の動きも迅速化します。
Web社内報の特徴・メリット

インターネット上で簡単に作成・配信・閲覧できるWeb社内報には、リアルタイムでの情報共有や効果測定がしやすいなど、Webツールならではの特徴があります。ここでは、Web社内報の特徴・メリットについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
Web社内報の特徴・メリット
リアルタイムな情報共有ができる
紙媒体の社内報と異なり、タイムリーに社内で情報を共有できるのがWeb社内報の魅力です。インターネット上ですぐに作成して公開できるため、従業員の手元に届くまでのタイムラグを削減し、情報伝達のスピードが上がります。
有事を含め緊急性の高い場面はもちろん、新商品発売日・イベント開催日といった最新情報もすぐに発信でき、従業員の生産性向上にもつなげられます。発信内容に誤りがあった際も一括で修正できるため、社内における意思統一に役立てることが可能です。
効果測定ができる
紙媒体の社内報は、実際にどのくらいの人に読まれているのかを把握するのが困難です。その点、Web社内報はインターネットを通じて配信・閲覧するため、効果測定が容易です。
具体的には、従業員の閲覧状況をもとに、閲覧数・読了率・平均滞在時間・フィードバックを集計・分析できます。これにより、従業員がどのような記事・見出しに関心や興味を寄せているかがわかり、次回の社内報の改善に活かしやすいです。
効果測定と改善を繰り返すことで、社内報の品質が向上し、Web社内報の導入効果の最大化にもつながります。
動画や音声も投稿できる
Web社内報の中には、文字だけでなく動画・音声といったコンテンツを投稿できるものもあります。動画・音声は文字だけの社内報よりも従業員の関心を引きやすい傾向にあり、閲覧率や読了率の向上に期待できます。
また、文字だけでは伝わりづらい情報でも、視覚・聴覚を活かすことで正確に伝達できるのもメリットです。動画・音声・アニメといった従業員に受け入れられやすいコンテンツを盛り込みながら、オリジナリティのある社内報を作成できます。
スペースに制限がない
紙媒体の社内報は記事を掲載するスペースに制限があるため、記事の内容を吟味しなければなりません。しかし、基本的にWeb社内報にはこのようなスペース制限がなく、ちょっとしたことでもすぐに社内全体で共有しやすいです。
例えば、現場の様子や従業員の本音など、実情から組織改善につながるような情報の掲載も可能です。なお、Web社内報によっては、文字数や容量に制限が設けられている可能性があるため、事前に利用可能な範囲についても確認しましょう。
検索や修正・加筆が簡単にできる
Web社内報は、過去の記事の検索や修正・加筆がしやすいのもメリットです。紙媒体の社内報のように1冊ずつ内容を探すことなく、検索機能を利用して過去の刊行物・記事にすぐアクセスできます。
また、基本的に管理画面から記事を修正・加筆すれば、その内容が各従業員の手元に届いている社内報にも即時反映されます。紙の社内報のように、1冊ずつテープの貼付・ページの差し込み作業をせずに済み、作成担当者の負担軽減にもつながります。
さまざまなデバイスから利用できる
いつどこからでも閲覧できるのも、Web社内報の魅力です。従業員は、手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットなど好きな端末から社内報にアクセスでき、自分の都合に合わせて少しずつ読み進められます。
紙媒体の社内報のように持ち歩く必要がなく、従業員の満足度向上につながるでしょう。外出先や隙間時間でも目を通せるため、社内報の閲覧率向上も見込めます。
セキュリティ性が高い
Web社内報の中には、ユーザーごとのアクセス制限や公開範囲の設定ができるものが多くあります。閲覧してほしい従業員にだけ記事を届けられ、機密性の高い情報の共有が効率化します。
また、紙媒体のように、持ち出した社内報を外出先に忘れてくるといった心配もないため、紛失・盗難による情報漏洩の防止にもつながります。セキュリティ性が高くて管理もしやすいのは、インターネットを利用するWeb社内報ならではの魅力といえるでしょう。
Web社内報のデメリット

Web社内報には、インターネット上での管理によるデメリットが複数あります。導入を検討している場合は、いくつかのデメリットを理解し、あらかじめ対策を講じることが大切です。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
Web社内報のデメリット
デバイス・ネット環境が必要
Web社内報を利用するには、編集・配信用のパソコンやタブレット端末に加えて、ネット環境の整備が必要です。ゼロから環境整備を行う場合は、初期費用がかかります。
また、Web社内報を運用するには、一定のWeb知識・IT知識に加え、動画や音声などのコンテンツを利用するための撮影・編集スキルも必要です。運用開始前にツール操作や編集に関する従業員教育が不可欠であり、総コストについても考慮しなければなりません。
ツール利用にランニングコストがかかる
Web社内報ツールとは、Web社内報の作成を効率化するツールです。初心者が簡単に操作できるツールもありますが、利用には初期費用やランニングコストがかかります。特に、小規模企業などでは、金銭的な負担が大きくなる恐れがあります。
しかし、多くは初心者でも簡単に利用できる仕様であり、Web社内報の作成業務の効率化に期待できます。なお、多くのWeb社内報ツールは月額制であり、文字数やデータ容量によって料金が変動するため、自社の予算と比較したうえで導入を検討しましょう。
社外には共有しづらい
通常、Web社内報にはアクセス制限を設けて、従業員以外が閲覧できないようにします。そのため、紙媒体の社内報を取引先や退職者にも配布している企業では、社外への共有がしづらくなるでしょう。
また、社内報で集客を図っていた企業は、商談機会の損失や売上低下のリスクが否めません。ただし、公開範囲を柔軟に設定できるWeb社内報であれば、社外との共有も従来通り行える可能性が高いです。
長文は流し読みされやすい
一般的に、Web社内報は紙媒体と比べて流し読みや読み飛ばしされやすい傾向にあります。これは、スクロールや見出しジャンプといったWebツールならではの機能により、読者は次々に文章を流せる環境が整っているためです。
主に、Web社内報はスマホでの閲覧率が高いため、長文の記事や見出しは読み飛ばされることが多いです。効果測定機能を活用し、読了率や平均滞在率を計測しながら、多くの人の関心を引くようなレイアウト・文章構成を工夫する必要があります。
Web社内報の導入効果を高めるためのポイント
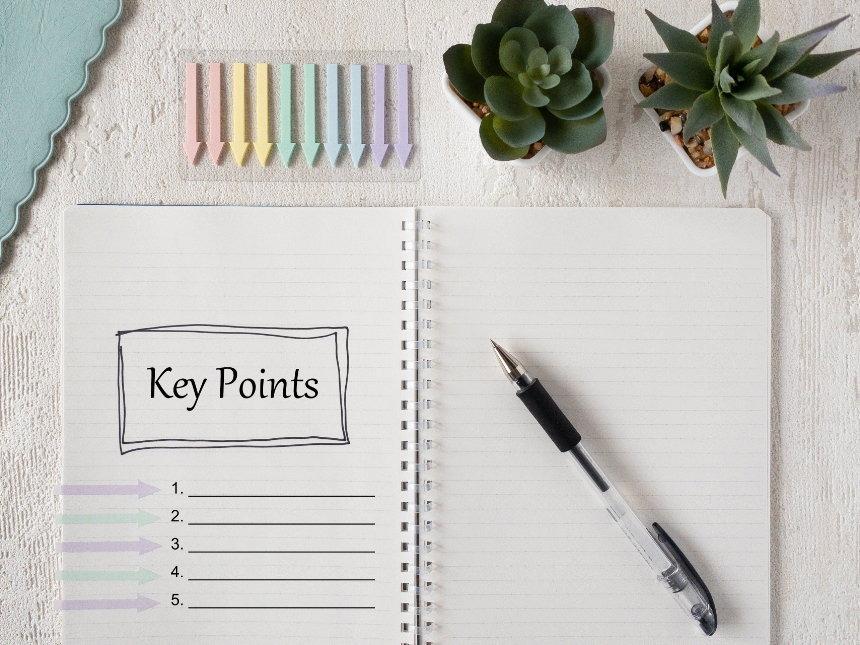
Web社内報にはデメリットも存在し、導入効果を高めるための施策を講じる必要があります。ここでは、Web社内報の導入効果を最大化するためのポイントを解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
Web社内報の導入効果を高めるためのポイント
目的に沿ったコンテンツを作る
Web社内報の導入効果を高めるには、まず情報発信の目的を決めることが大切です。記事の作成方針が定まれば、動画・音声を含めて適切なコンテンツを作成しやすくなります。
例えば、経営層と現場の情報共有が目的であれば、メッセージ動画を配信することで、文字だけの配信よりも人柄や考えを社内に直接伝えられます。
社内コミュニケーションの活性化を目的とする場合は、従業員からの反応が返ってきやすいコンテンツや文章構成が必要でしょう。また、明確な目的を設定すれば効果測定がしやすくなるため、Web社内報の導入効果を高めることにもつながります。
利用ルールを設ける
Web社内報の配信は、作成の手間はもちろん、読む側にも「閲覧」という手間が生じます。また、他のコミュニケーションツールを活用している場合、従業員は複数のツールをまたいで反応を返さなければならず、疲弊する恐れがあります。
作成者・閲覧者の負担を最小限にするためにも、更新頻度や他ツールとの使い分け方などについて明確な利用ルールを設けましょう。コミュニケーションツールを併用している場合は、いずれかに一本化するのがおすすめです。
効果測定を活かして運用する
Web社内報は、社内報ごとの反応を可視化できるのが強みです。この強みを活かして社内報の品質を高めるためには、効果測定の活用が重要です。例えば、過去の配信記事の閲覧数や読了率を比較し、最も読まれた記事の傾向や内容を精査します。
また、同一の刊行物の中で、コンテンツごとの平均滞在時間を比較することも大切です。従業員の閲覧の傾向や興味・関心がわかれば、次回のWeb社内報に反映させられます。
その結果、自社の従業員の指向に適した社内報の作成が実現し、閲覧率・フィードバック率の向上が見込めるでしょう。社内報を通じた情報共有やコミュニケーションの活性化といった導入効果の最大化も見込めます。
画像・動画を活用する
文字のみのWeb社内報は、流し読みや読み飛ばしされやすい傾向にあります。従業員の関心を引くためには、画像・動画・音声といった視覚情報を提供できるコンテンツを積極的に活用しましょう。
それにより、読み飛ばしを防ぎつつ、伝えたい情報をさらにわかりやすく伝達することが可能になります。具体的には、従業員紹介において文字だけでは人柄が伝わらないこともあるでしょう。
動画や音声などの視覚・聴覚情報を付加することで、その人となりをストレートに表現でき、他従業員からの理解も深まります。発信したい情報の内容や重要度に合わせて、適切な発信方法を使い分けることが大切です。
誰でも理解できる内容にする
基本的に、Web社内報は経営層から現場スタッフ、アルバイトなど、会社で働くすべての授業員に向けて発信します。従業員ごとに自社に対する理解度は異なるため、部署・地域・拠点を問わず、誰でも理解できる内容にすることが大事です。
例えば、経営層にしか伝わらないような専門用語は避け、丁寧な説明やかみ砕いた表現を心がけましょう。会社の「誰か偉い人」向けではなく、従業員全員が自分のこととして情報を受け止められるような内容・表現方法が求められます。
また、海外に拠点を持つ企業は、外国人従業員がそれぞれの言語で閲覧できる社内報を作成しなければなりません。Web社内報ツールの中には、多言語翻訳機能を搭載したものもあるため、そちらを検討しましょう。
まとめ

Web社内報とは、インターネット上で作成・配信・閲覧できる社内報です。紙媒体の社内報のように作成・印刷・配布の手間がかからないため、さまざまなコストを削減でき、緊急時にも素早く社内で情報共有が可能です。
紙の社内報では難しかった効果測定を行えるため、Web社内法の品質向上につながります。さらに、動画・音声といったコンテンツの活用で、より閲覧されやすく・伝わりやすい社内報の作成が可能です。
一方、ランニングコストや読み飛ばしといったリスクもあるため、十分に費用対効果を試算したうえで導入を検討する必要があります。Web社内報を簡単に作成するには、専用ツールの利用もおすすめです。
この記事に興味を持った方におすすめ

