社内報のネタをテーマごとに紹介|ネタ探しや読まれる社内報のコツも

Check!
- 社内報のネタは、社内報の作成目的に合ったものを選ぶことが重要
- 社内報におすすめのネタには、社員紹介・全社アンケート・イベント報告などがある
- 読まれる社内報作りには、双方向性のある企画や多様な視点での取材などが有効
社内報は、企業が社員に向けて発行する情報発信ツールです。社員のモチベーション向上などの効果がありますが、作成において、ネタ切れに悩むことも多いでしょう。本記事では、社内報におすすめのネタをテーマごとに紹介し、ネタ探しや読まれる社内報作りのコツも解説します。
おすすめ記事
社内報のネタ切れ時は作成目的に立ち返ろう

社内報の作成時は、ネタ切れに陥ることも少なくありません。その場合は、まずは社内報をなぜ発行しているのかという目的に立ち返ることが重要です。
社内報は単なる読み物ではなく、企業が社員に向けて情報を発信するツールであり、経営方針の共有や社内の一体感の醸成、社員のモチベーション向上などを目的としています。
そのため、面白さだけを追求して一見ウケの良い記事を作っても、目的から外れてしまえば本来の効果は発揮できません。本記事では、社内報におすすめのネタをテーマごとに紹介し、ネタ探しや読まれる社内報作りのコツも解説します。
社内報の目的
社内報の目的は、単なる情報発信にとどまらず、組織全体を活性化させることにあります。まず、経営方針や社内の最新情報を共有することで、社員全員が同じ方向を向いて業務に取り組めるようになります。
また、他部署の事例紹介や専門知識の掲載は、社員のスキルアップを後押しします。さらに、活躍する社員の紹介や成功体験の共有は、モチベーションの向上にもつながります。
つまり社内報は、情報共有・スキルアップ支援・意欲向上の3つの役割を通じて、企業の成長を支える重要なツールなのです。
【テーマ別】社内報におすすめのネタ

社内報は目的に合わせた内容でこそ効果を発揮します。単に面白い記事を載せるのではなく、自社の情報共有や社員のモチベーション向上といった目的に沿ったネタを選ぶことが大切です。
ここでは、社内報に取り入れやすく、かつ社内の一体感や成長を後押しするテーマ別のおすすめネタを紹介します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
部署・社員紹介
部署や社員を取り上げるコンテンツは、普段関わりの少ないメンバーの人柄や仕事ぶりを知るきっかけとなり、社内コミュニケーションを活性化させます。仕事の背景や取り組みへの想いを共有することで、他部署への理解が深まり協力体制を築きやすくなる点も魅力です。
社員の個性や強みが紹介されることで一緒に働く仲間としてのつながりが強化され、組織の一体感が生まれます。以下は、部署・社員紹介のネタ例です。
ネタの例
- 部署ごとの仕事内容や役割の紹介
- 従業員の自己紹介・インタビュー
- 新入社員や異動者へのインタビュー
- 趣味や特技などプライベートの一面紹介
- 上司・部下へのメッセージリレー
- 部署や担当者の1日密着取材や座談会
全社アンケート
全社員を対象としたアンケートは、誰もが参加できる双方向型のコンテンツとして注目を集められます。特に定期的に実施すれば、社員の意識や社内の雰囲気の変化を追えるため、記事としても継続的に面白さを発揮できます。
また、回答を通して他の社員の考え方や価値観を知るきっかけにもなり、共通点の発見や違いを楽しむことで社内の交流が広がります。
テーマ選びを工夫すれば、業務に直結する真面目なものから、気軽に答えられる趣味や嗜好に関するものまで幅広く展開することが可能です。さらに、自分の意見や結果が誌面に反映されることで、社員の関心や参加意欲が高まる効果もあります。
ネタの例
- 好きなランチやお菓子ランキング
- 最近ハマっている趣味・アクティビティ
- 会社の強みや改善してほしい点に関する意見
- 季節ごとの過ごし方や休日の過ごし方
- 好きな社内報コンテンツ
社内・社外イベント
社内や社外で行われたイベントは、多くの社員が直接関わっているため関心度が高い題材です。イベントの様子を報告するだけでなく、参加者の声や舞台裏のエピソードを加えることで、より魅力的で臨場感ある記事になります。
単に開催内容や当日の様子を報告するだけでも一定の効果はありますが、そこに参加者の感想や印象的な場面、運営スタッフの舞台裏での努力などを盛り込むことで、臨場感や新たな発見を読者に提供できます。
こうした記事は単なる記録にとどまらず、参加できなかった社員にとっても社内の一体感を感じられるきっかけになり、会社全体のモチベーション向上につながるのが大きな魅力といえるでしょう。
ネタの例
- 社内研修や表彰式のレポート
- 社員旅行や懇親会のハイライト
- 社外展示会や地域イベント参加の報告
- イベント準備の裏側や担当者インタビュー
- 今だから笑える失敗談
季節・トレンド
季節感や流行を取り入れたネタは、社内報を親しみやすくするだけでなく、社員の会話のきっかけや共感を生みやすいのが特徴です。例えば、春のお花見や夏のイベント、秋の行楽や冬の年末行事など、四季折々のテーマは誰にとっても身近で関心を集めやすい話題です。
また、その時々の流行や業界の最新トピックを盛り込むことで、単なるニュースではなく自社らしい記録として残す価値も高まります。さらに、年ごとのトレンドを振り返る資料として後に読み返す楽しみもあり、社内報をアーカイブとして活用する意味合いも持ちます。
ネタの例
- 季節ごとのおすすめスポット紹介
- 各月の季節ネタ
- 社員の季節行事や休日の過ごし方アンケート
- 業界の最新トレンドや話題ニュースまとめ
- 流行しているアイテム・サービスの紹介
- 新商品や新サービスの紹介
- 今月のお誕生日
お役立ち情報
仕事やプライベートの両面で役立つ情報は、社員にとって実用性が高く、家族と共有できる点も魅力的です。例えば、業務効率化に関する便利ツールの紹介や、健康管理・暮らしの豆知識など、生活を支えるヒントは毎号の楽しみとして定着しやすいコンテンツです。
社員が次も読みたいと思えるような実用的な情報を充実させることで、社内報自体への期待感やリピート率が高まり、継続的な読者とのつながりが生まれます。
また、家庭で役立つ情報を載せることで、家族も社内報を手に取りやすくなり、会社への親しみや理解が広がる効果も期待できます。
ネタの例
- 業務効率化に役立つアプリやツール紹介
- 健康維持や食生活に関する豆知識
- 家計に役立つ節約術やライフハック
- 休日のお出かけ情報やおすすめレシピ
- パパやママの座談会
- 匿名によるお悩み相談
社内報のネタを探す方法

社内報を継続的に発行していく中で、多くの担当者が直面するのが「次に何を書けばよいか」というネタ探しの課題です。
面白さや新鮮さはもちろん大切ですが、単なる娯楽要素だけでは社内報の本来の目的である情報共有やモチベーション向上につながりにくくなります。そのため、効果的にネタを探す方法を意識することが重要です。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
社内報のネタを探す方法
最新トレンドをリサーチする
最新のトレンドや時事ネタを積極的に取り入れることで、読者の関心を引きやすい社内報を作成できます。世の中で話題になっているテーマや業界の最新動向、さらには季節ごとの流行などを反映することで、読者が「今の自分に関係がある」と感じやすくなります。
また、トレンドを紹介するだけでなく、自社との関連性や社員の生活に役立つ切り口を加えることで、単なる情報提供に留まらない有益な記事に発展させられます。
SNSやオウンドメディアを活用
リサーチの方法としては、ニュースサイトやSNSのチェック、業界誌や専門メディアの購読などが効果的です。定期的に最新情報をキャッチアップする体制を整えることで、常に鮮度の高い記事を作成できます。
また、広報担当者同士の情報共有も忘れずにしましょう。SNSやオウンドメディアで見かけた、自社で真似できそうな切り口や発想などの手法も広報担当者内でストックしておくと効果的です。
社内の声を拾う
読者である社員自身の声を反映させることは、親しみやすく双方向性のある社内報を作るために欠かせません。日常的な会話や雑談、またはアンケートや意見募集の仕組みを通じて集めた社員の声を記事化すれば、身近で共感しやすいコンテンツになります。
例えば、「最近ハマっていること」や「仕事で工夫していること」といったテーマを取り上げることで、社員同士の理解を深めるきっかけにもつながります。さらに、社内報が社員の声を反映していると実感できれば、読者が主体的に関わろうとする意識が高まります。
このように社員の声を積極的に拾い上げることは、社内コミュニケーションを活性化し、会社全体の一体感を高める効果をもたらします。
過去の人気記事を参考にする
効率的に社内報を作成するためには、過去に好評だった記事を参考にすることも非常に有効です。人気記事の特徴を分析してその要素を取り入れつつ、新しい切り口を加えることで、再び高い反応を得やすくなります。
社員紹介の記事が特に読まれていたのであれば、別の部署や新入社員に焦点を当てるといった展開が考えられます。また、イベントの裏話や社員の声を集めた企画が人気だった場合、それを定期コーナー化することで安定した読者の関心を維持できます。
過去記事を参考にすることで、ゼロからネタを考える時間を短縮でき、効率的にコンテンツを準備できる点もメリットです。つまり、人気のあった記事を単に再利用するのではなく、その本質的な魅力を分析し、発展させて活かすことが重要です。
パターンを決めておくのも有効
毎回ゼロから考えるのではなく、ある程度パターン化しておくと効率的に社内報を作成できるようになります。例えば、インタビュー形式やアンケート・クイズ・特集といったパターンを決めておくことで、定期的な企画にもつながります。
特に、過去に好評だったシリーズをパターン化しておくと良いでしょう。場合によっては、再編集をして再掲するのもおすすめです。
読まれる社内報を作るコツ

社内報は発行すること自体が目的ではなく、社員にしっかりと読まれて理解や活用されることに価値があります。そのためには「どうすれば読者が関心を持ち、自然と読みたくなるのか」という視点が欠かせません。
ターゲットを明確にする工夫や、社員が参加したくなる企画を取り入れる仕掛け、また新鮮な視点での取材や読みやすい形式の工夫など、いくつかのポイントを意識することが大切です。ここからは、読まれる社内報を作るための具体的なコツを解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
読まれる社内報を作るコツ
ターゲットを明確にする
読まれる社内報にするためには「誰に向けて発信するのか」を明確にすることが重要です。すべての社員に向けた情報は広く伝わる一方で、内容が浅くなりやすく、個々の共感を得にくい場合があります。
そのため、部署や拠点ごと、あるいは若手社員子育て世代などの年齢層やライフスタイルを絞り込み、ターゲットを明確に設定することで、読者に「自分に関係がある記事だ」と思ってもらいやすくなります。
例えば、若手向けにはキャリア形成や先輩社員の体験談、子育て世代には仕事と家庭の両立に役立つ情報を盛り込むといった工夫が効果的です。
広報以外の社員が参加したくなる企画を盛り込む
読まれる社内報に欠かせないのは、社員が「読むだけ」ではなく「参加できる」要素を取り入れることです。アンケートや投票・フォトコンテスト・社員投稿欄などの双方向性の仕掛けを盛り込むことで、自然と社内報への関心を高められるでしょう。
例えば、「次号のテーマ投票」や「社員のおすすめランチ紹介」などは気軽に参加でき、参加した社員にとっては「自分が関わった記事だから読もう」という意識につながります。
また、他の社員の投稿を見ること自体が楽しみとなり、社内報を読む習慣づけにも効果があります。つまり、読者を受け身の立場から能動的に関わらせることで、社内報はより活発に活用されるようになるでしょう。
取材する視点と対象を多様化する
取材の視点や対象を多様化することは社内報のマンネリ化を防ぐ最も効果的な方法です。毎号同じ部署や人物ばかりを取り上げると、読者は新鮮味を失ってしまい「読まなくてもいいか」と感じてしまいます。
そこで、普段は注目されにくい部署や社員、さらには工場やバックオフィスといった現場にスポットを当てることで、新たな発見や意外性を提供できます。
例えば、日常業務の裏側や現場の工夫、普段知ることのない社員の一面を紹介すれば、読者にとって身近さと新鮮さを同時に感じられる記事になります。
このように多角的な視点を持って取材を進めることで、社内報は単なる情報伝達ツールから「新しい魅力を発見できる読み物」へと進化します。
読まれやすい形式を選ぶ
社内報は内容だけでなくどう届けるかも非常に重要です。社内報の配信形式は、社員の環境や習慣に合わせて選ぶことで、読まれやすさが格段に高まります。紙の冊子であれば手に取って読んでもらいやすく、PDF配信なら保存や検索が便利です。
また、スマホアプリや社内ポータルサイトで閲覧できる形式の場合は、通勤時間や休憩中にも気軽に読まれやすくなります。さらに、動画形式を取り入れれば視覚的に楽しむことができ、文章を読むのが苦手な社員にも伝わりやすいメリットがあります。
社内報を作成する際は、コンテンツにあわせた読みやすいデザインになるように気を配るのも有効です。つまり、社内報の目的と読者層の生活スタイルを考慮し、最適な形式を選択することが、実際に「読まれる」社内報につながります。
読まれる社内報作りにはWeb社内報ツールがおすすめ

社内報をより効果的に社員に届けたいなら、Web社内報ツールを導入することがおすすめです。従来の紙媒体やメール形式の社内報では、閲覧率や読まれたコンテンツの傾向を把握することが難しく、改善点を見つけにくいという課題がありました。
しかし、Web社内報ツールを使えば、どのページがよく読まれているのか、どの時間帯にアクセスが多いのかといった閲覧データを分析することができ、次回の企画や内容改善に役立てられます。
また、PCだけでなくスマートフォンやタブレットなど、マルチデバイスに対応しており、出張中や休憩時間など場所を問わず社員が気軽に使えます。つまり、Web社内報ツールの活用は、より多くの社員が社内報を身近な存在として認識できるようになります。
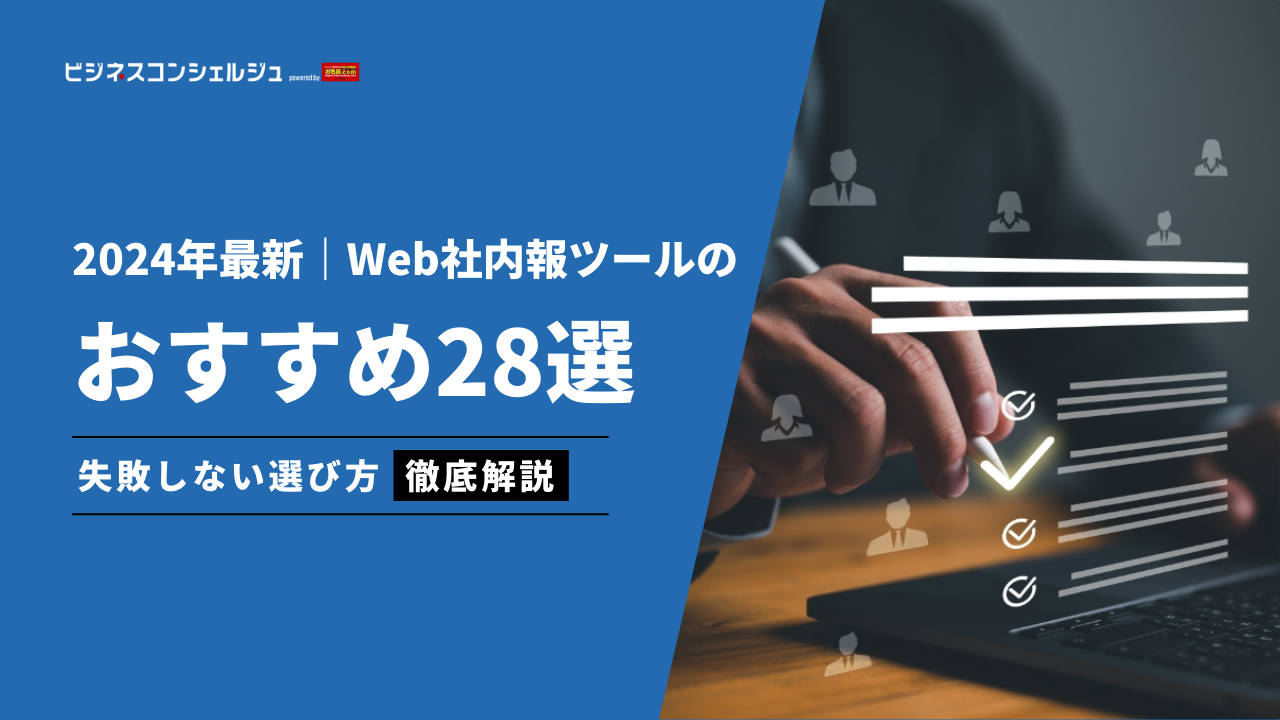
Web社内報ツールおすすめ10選(全28選)を徹底比較!選定のポイントや導入時の注意点を解説
Web社内報ツールとは、システム上で社内報を作成・更新・修正などができるツールです。紙媒体と違って、リアルタイムで共有できて物理コストが発生しないことから、近年多くの企業で社内報のデジタル化が進んでいます。本記事では、徹底比較したおすすめのWeb社内報ツールや選び方などを詳しく解説します。
まとめ

社内報は単なる情報発信にとどまらず、社員のモチベーション向上やスキルアップ支援、さらには企業全体の一体感を高める重要な役割を担っています。
ただし、実際の運用では「どんな内容を書けばよいのか」「社員に読んでもらえるのか」といった悩みが生じやすく、工夫が求められます。そこで効果的なのが、Web社内報ツールを活用した運用です。
閲覧率の分析機能やマルチデバイス対応といった、より実効性のある社内報作りが可能です。本記事を参考に、自社に合った方法で社内報を運用すれば、情報共有の精度が高まり、組織全体の活性化へとつながるでしょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

