ホームページをリニューアルする際の作業工程と注意事項
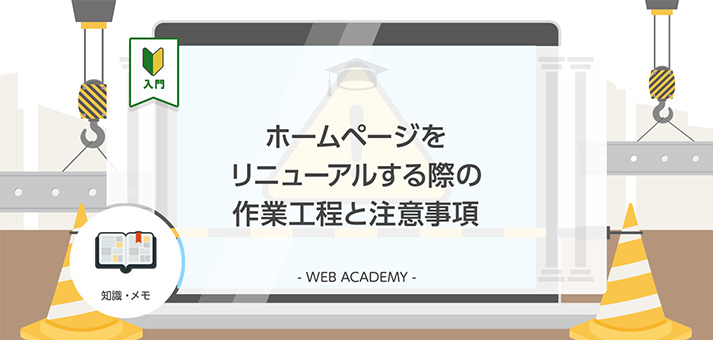
ホームページのリニューアルは、簡単なように思えますが、実はかなり難しいプロジェクトです。
今あるホームページの強みを失わずに、新しいサイトに作り直すのは、緻密なプランが必要になります。
今回はホームページのリニューアルで抑えておくべきポイントを解説しましょう。
実は難易度が高いホームページのリニューアル

企業を中心に、自社のホームページをリニューアルしたいという声は、非常に多くあります。
一見、簡単に見えるホームページのリニューアルですが、実は非常に難易度の高い業務で、安請け合いした担当者が大変な目に遭ったという話は、いくらでも出てきます。
その原因は様々ですが、例えば組織のトップの鶴の一声でリニューアルが決まったものの、どこをどう変えるのかが明確になっていないまま、手探りで改修を進めなければならないといったケースが考えられます。
また、ホームページを作ったときの担当者が既に辞めていたりして、退職した管理者が好き勝手に内部を改造していたりして、どこにどんな問題が潜んでいるのかまるで分からず、引き継ぎ資料やマニュアルもないため、何から手を付けていいのか誰も分からない……というケースもあったりします。
こういった問題含みのリニューアルプロジェクトでは、外注の制作会社に作業を丸投げしても上手く行かないことがほとんどです。
担当者が現在のホームページの状況をまとめ、社内の要望を積極的にヒアリングした上で、プロジェクトの舵取りを行っていく必要があるでしょう。
リニューアルの理由でよくあるものは?
ホームページのリニューアルプロジェクトを任された場合、最初にやるべきは、なぜリニューアルが必要となったのか、その理由を明らかにすることです。
改修の理由をハッキリさせることで、リニューアルで優先すべき事項が見えてきます。
ホームページのリニューアルに踏み切る理由としてよくあるのは次のようなものです。
デザインが古びている
ホームページのデザインには流行があり、毎年のようにトレンドが入れ替わっています。
作ったときには最新のデザインでも、3年もすると新しいサイトに見劣りするようになり、5年も経つと古臭さが漂うようになります。
特に同業他社のホームページと比較したときに、古さが目立つようだとビジネスにおいて致命的でしょう。
ただし、デザインの流行は常に移ろうもので、どんなに最先端の流行を取り入れても、時間の経過と共に古びるのは避けられません。
トレンドに左右されないためには、流行とは距離を置いたスタンダードなデザインを目指すべきでしょう。
モバイル表示に対応していない
現在のGoogle検索では、パソコン版サイトよりも、スマホ向けに作られたモバイル版サイトの方を検索順位の決定において重視しています。
これは2018年のモバイルファーストインデックスの導入以降に鮮明になった傾向なので、それ以前に作られたホームページでは、モバイル版サイトがほとんど顧みられず、パソコン版のおまけのようになっているケースが少なくありません。
また、当時はレスポンシブデザイン(モバイル機器の画面サイズに合わせて変形するデザイン)もそこまで普及していなかったため、モバイル対応が全くなされていないケースもあります。
Google検索からのユーザーの流入を重視するなら、モバイル版のホームページの充実は最優先の課題でしょう。
情報が増えすぎて収まりきらない
長年自社で運用しているホームページに多いのが、情報量が増えすぎてトップページに収まらなくなっているケースです。
後先を考えずに新しい情報を次々に追加したことで、トップページやサイドバーがバナーやリンクだらけになり、訪れたユーザーがどこから見ればいいのか分からない状態になっているホームページが散見されます。
この場合、ホームページのインタフェースの設計をもう一度やり直して、情報の優先順位を整理し直す必要があります。
これもリニューアルが必要な案件ですが、単にデザインを変えるだけでなく、ホームページにある大量の情報の軽重を再検討することになるので、難易度はかなり高いと見るべきでしょう。
こうした時間経過にともない発生した問題点を解消するためのリニューアルの他、ホームページがSSLに未対応なので導入したいという場合や、高性能なサーバーにホームページを移転するついでに作り直したい、といったケースがあります。
いずれの場合も、問題の在り処を明確にして、それを的確に解決するための施策を盛り込めるかが鍵となります。
ホームページのリニューアルで失敗しないポイント

ホームページのリニューアルにおいては、以下の4つのポイントを押さえておくことが重要になります。
- 目的の設定
- 開発者との連携
- 成果物の見極め
- 運用の見通し
ホームページのリニューアルで失敗しないための4つのポイントを解説していきましょう。
リニューアルの目的は明確か
最初の章でも触れましたが、目的が明確でないリニューアルは、失敗する可能性が極めて高くなります。
ホームページのリニューアルは、何らかの目的を達成するために行なうものですが、「とにかくいい感じにして欲しい」「今っぽい雰囲気にしてくれればいいから」といった、曖昧な要望に従って進行することが珍しくありません。
こういったリニューアルは、そのまま進めると「何か思っていたのと違った」というような、やはりハッキリしない理由でNGが出たりします。
リニューアルの迷走を予防するには、リニューアルの目的を明確にし、その達成の度合いによってプロジェクトの成否を図ることが重要です。
開発者との歩調は合わせられているか
ホームページのリニューアルでは、開発者と歩調を合わせられるかが、リニューアルの成否を決定的に左右します。
デザイン制作やインタフェースの設計を任せることになる以上、リニューアルの目的やコンセプトを共有するのは当然ですが、それ以外にも、社内からの要望や懸念点などの情報も可能な限り共有しましょう。
一見、実現が難しそうな要望であっても、優秀な開発者は技術力を背景にした提案能力を持っているため、発注側が想像もしないような問題解決のプランを期待できます。
開発者を味方に付けられるかは、ホームページのリニューアルの鍵を握っています。
派手なデザインや技術に惑わされていないか
ホームページの提案では、派手なデザインが取り入れられたり、先進的な技術が組み込まれたりすることで、分かりやすい「凄さ」が強調されることがよくあります。
確かにデザインや技術はホームページを構成する重要な要素ですが、しかしこれらは必ずしもリニューアルの目的に資するとは限りません。
長く使われるホームページの価値は、表面的なデザインや技術よりも、確実に伝わるメッセージ、分かりやすいインタフェース、飽きの来ないデザイン、メンテナンスのしやすさなどに現れます。
ホームページで本当に重視すべき要素を、デザインや技術に惑わされて見落としていないか充分に注意しましょう。
リニューアル後の運用を視野に入れているか
リニューアルの真価は完成直後ではなく、その後の運用の過程で明らかになります。
例えば、大々的なリニューアルを行ったものの、運用コストが重すぎて定期的な更新を維持できずに開店休業状態になってしまうようでは、そのリニューアルは失敗と言えます。
高品質の画像や動画を大きく取り入れたホームページでは、新しいコンテンツを追加する際にも、その水準の画像・動画を毎回用意しなければならないため、運用班の負荷は大きくなります。
CMSを導入したことで内部がブラックボックス化し、それまで簡単な変更であれば社員が行えていたのに、リニューアル後は制作会社に依頼しないとバナーひとつ追加できない状態になった、といった話もよく聞きます。
ホームページは更新を維持できてこそ真価を発揮します。
リニューアル後のホームページを長期的に運用できるかどうかにも気を配りましょう。
ホームページのリニューアルの手順

企業がホームページのリニューアルを行う場合、通常は外部の制作会社に依頼することになります。
ホームページ制作の工程はソフトウェア開発と同様、進行途中の後戻りが困難なプロセスとなります。
そのため、プロジェクトは段取りを着実にクリアしながら進行しなければならず、途中で段階を飛ばしたり適当に進めたりすると、後で大きな問題に突き当たる可能性が高くなります。
ここでは、ホームページのリニューアルにおける標準的な手順について紹介します。
リニューアルの決定
ホームページのリニューアルを行うという最初の意思決定の段階で、意思決定者は誰か、どのような意図でリニューアルを決めたのか記録を残しておきましょう。
リニューアルの過程で、さまざまな部署から要望や制約が加わったり、会議で方向性が二転三転したり、上層部からの注文が入ったりして、そもそも何を目指してリニューアルしようとしていたのか分からなくなることはよくあります。
その場合は、優先順位を付けて、そこから外れたオーダーは取り入れない判断が必要になりますが、その際に立ち返る起点があれば、錯綜した状況を解きほぐし、取捨選択の理由を論理的に説明するための貴重なヒントになります。
目的の定義と要望の聴取
ホームページを改修する目的を定義します。
リニューアルによって何を改善したいのかはっきりさせないと、以降の目標があいまいになることから、非常に重要です。
リニューアルにあたって実現したい機能を、組織の上層部やホームページに関わる業務の関係者からヒアリングするのもこの段階で行います。
ヒアリングで得られた要望を全てそのまま取り入れていると、まとまりがないホームページになるので、他の機能や予算などの都合を鑑みながら、対応できない要望は断念し、無理や矛盾のない仕様に落とし込みましょう。
提案依頼書の作成
リニューアルの具体的な要望についてまとめた文面が提案依頼書で、
RFP(Request for Proposal)と呼ばれることもあります。
提案依頼書の内容は場合によって異なりますが、以下のような項目が挙げられます。
- 目的
- 背景
- スケジュール
- 必要な機能
- メインユーザー
- 競合
- インフラ環境
- 技術要件
- 品質要件
依頼を受けた制作会社は、この提案依頼書を元に、実装する機能と作業のプロセス、必要な人員と費用を算定します。
提案依頼書は雛形がいくつもウェブで公開されているので活用しましょう。
制作会社の選定
ホームページのリニューアルを依頼する制作会社を選定します。
通常は複数の業者に提案依頼書を元にした見積もりの作成を依頼して条件を比較します。
費用がもっとも安い事業者に依頼するのもいいですが、制作会社が得意とする技術、担当者との意思疎通のしやすさ、アフターケアの充実度なども考慮すべきでしょう。
要件定義書の作成
リニューアルを受注した製作会社は、提案依頼書を元に要件定義書を作成します。
これは提案依頼の内容を、ホームページ上で実際にどのような機能として実現するかをまとめた書類です。
この要件定義書は、ホームページのリニューアルの成否を左右する、極めて重要なプロセスとなるため、ここでしっかりと内容を煮詰めて、抜けや漏れがないようにします。
ワイヤーフレームの作成
ワイヤーフレームとは、ホームページを構成する要素を、線だけで描画したものです。
見出し、本文、画像、ボタンなどの配置をワイヤーによる骨格のみで表すことで、インタフェースの設計が無理のあるものになっていないか、ビジュアルに惑わされずに検討できます。
デザインの仮組み
ワイヤーフレームにデザインやダミーのコンテンツを当てはめて、中身が組み込まれた状態のホームページがどのように見えるかを確認します。
特に重要なのがカラーリングとフォントで、背景やボタンの色が適切か、見出しや本文のフォントが読みやすいかをチェックします。
コーディング
仮組みしたデザインを、コードで記述することにより実際に動作するホームページを作る、コーディングの作業に入ります。
コーディングでは、既に確定しているデザインをウェブサイトに落とし込む作業なので、基本的に全て制作会社の担当となります。
ホームページが完成したら、誤動作やエラーが出ないかのチェックを行って、工程は完了です。
運用、告知
ホームページが完成したら内容を更新していきましょう。
画像に関しては、ホームページのデザインが変わったことで、従来のチョイスや見せ方が合わなくなっている可能性があるので、運用ルールを変えた方がよいかもしれません。
アクセス解析ツールを使って、リニューアルの前と後での数字の変化を測定したり、告知も忘れてはなりません。
SNS、メルマガ、プレスリリースなどでホームページが新しくなった旨を利用者や関係各所に通知しましょう。
上記は標準的なホームページのリニューアルの手順ですが、あくまで一例に過ぎず、必ず同じ工程になるとは限りません。
例えば、ITが苦手な会社の場合、提案依頼書を自力で作成するのが難しいため、制作会社が担当者からヒアリングを行って、ホームページの仕様を提案することもあります。
ホームページのリニューアルにかかる費用と期間は、規模にもよりますが、費用は30万円〜150万円前後、期間は3ヶ月〜半年程度は見ておきましょう。
ホームページを新設する場合と同じですが、これは作業の内容がリニューアルも新設も実質的には変わらないためです。
リニューアルで起こりがちなトラブルとは?

ホームページのリニューアルは、実はかなり難易度の高いプロジェクトです。
既にあるホームページを、その長所を維持したまま作り直すのは、過去の成果と比較されやすいことから、新しくホームページを作るよりもはるかに難しくなります。
また、ホームページは会社の表看板であり、改修に費やす予算も少なくないことから、リニューアルにあたっては組織内部のあちこちから横槍が入りがちです。
さらに、通常リニューアルは数年おきとなるため、前回得た知見が継承されにくいこともあって、作業工程がスムーズに進む方が珍しいくらいです。
ここでは、ホームページのリニューアルで起こりがちなトラブルと、その予防策や解決策について解説します。
デザインが決まらない
リニューアルのトラブルで多いのが、デザインが決定しないまま、ズルズルと納期が伸びるパターンです。
デザインの良し悪しは客観的に測定できないので、最終的には決定権のある人の価値観で決まる傾向があります。
決断力に欠けていたり、判断基準があいまいだったりすると、無意味なリテイクを繰り返したり、途中でやり直しになる可能性があります。
この問題の解決策は、組織の意思決定の最上位者の承認を得ることで、組織内の地位が下位の人間は上位の決定を覆しにくいのを利用して、最上位者の言質を取ることで、デザインをFIX(確定)へと導きましょう。
開発途中で機能が増える
ホームページのデザインや機能が確定し、コーディングが始まった段階になってから、やっぱりこっちのデザインがいい、あの機能を追加したいという要望が出てくることがあります。
時間と労力のロスが大きく、現場のエンジニアが忌避する事態ですが、ホームページ開発に理解のないクライアントは、追加や変更を簡単にできると思い込んで依頼するため、制作会社との関係に溝が生まれることがよくあります。
このトラブルを避けるには、提案依頼書と要件定義書をしっかりと作り込むことで、事前の取り決めから逸脱した作業はプロジェクトの後退を意味するという認識のもと、後で考えればいいという、見切り発車的な要素を徹底的に排除することが重要になります。
アクセス数が激減する
ホームページのリニューアルをしたらアクセス数が激減してしまった、というのは一番怖いトラブルのひとつでしょう。
基本的に検索エンジンはデザインを評価対象にしていないので、ホームページのデザインを変えたことが原因で、検索エンジンの順位が下降し、ユーザーの流入数が減少する事態は起こりえません。
ただし、デザインと合わせてホームページの内部構造を変更した場合はその限りではなく、例えば記事のカテゴリの構成を変えたり、内部リンクを変更したりすると、検索順位に影響が出ることがあります。
また、ホームページを移行する際の手違いで、一部のページのURLが変わっていたり、記事自体がアクセス不能になっていたりする可能性もあります。
アクセス解析ツールの記録から、リニューアル前後でアクセス数に変化のあったページを特定し、以前と変わったところがないかを調べてみましょう。
デザインやUIが利用者層に合っていない
ホームページをリニューアルしたものの、そのデザインやインタフェースがユーザー層に合っていなかったというトラブルです。
これは制作会社に開発を丸投げしたときに起きやすい問題で、発注側が要望を提案依頼書で明確にしていなかったり、ワイヤーフレームやデザインの仮組みの段階で中身をしっかり精査していなかったりするのが原因です。
またよくあるのが、最新流行のデザインを取り入れることに制作会社がこだわり、熱意に押されて発注元もOKを出した結果、使いにくいホームページが出来てしまうトラブルです。
ホームページの利用者像については、制作会社よりも発注側の方が詳しいので、発注側が制作側をコントロールしなければなりません。
ホームページの利用者が何を求めているのかを事前に精査し、それを元にした提案依頼書を時間をかけて作ることが解決策になります。
リニューアル後のコンテンツを忘れる
ホームページのリニューアルを一大プロジェクトとして内外に打ち出している場合、デザインだけでなくコンテンツの刷新も前提となっているケースがほとんどです。
しかし、ホームページのリニューアルに忙殺されてコンテンツのことを失念し、リリース直前になって大慌てで作るハメになるトラブルは意外とよくあります。
ホームページのリニューアルは、あくまで外枠の再構築に過ぎず、ホームページ全体を新しいイメージで打ち出すには、リニューアルと同時に特集的な企画を展開するのがベストです。
もちろんそれには相応の予算と時間と人員の確保が必要になるため、コンテンツの制作に関しては、リニューアルとは担当者を分けて同時並行で進めておくべきでしょう。
まとめ
今回は、ホームページのリニューアルの作業工程や、ありがちなトラブルについて解説しましたが、ホームページの大規模な作り直しは、担当者に大きな負担がかかるプロジェクトです。
社内の要望の取りまとめや制作会社との調整だけでも大変なのに、途中で上司や他部署から横槍を入れられたり、リニューアル後になって苦情が出たりと、内外から様々なトラブルが降ってくる可能性があります。
リニューアルでもっとも重要なのは何かというと、ホームページの存在意義を明確にすることだと言えるでしょう。
ホームページが何のためにあるのか、その理由を定義し、社内で共有できていれば、後から批判に晒されても存在理由から逆算した反論が可能ですし、製作中に意思決定で迷った際にも、合理的な判断を導き出せます。
誰でも10分!WordPressブログの始め方
ブログを始めるには、ライブドアブログやはてなブログといった無料ブログを使う方法、
あるいはWordPressなどを使用する方法があります。
まだWordPressを持っていない人でも、簡単に準備できる方法を以下の記事で解説してます。
初心者でもわずか10分で始められるので、参考にしてみてください。
合わせて読みたい
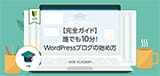
【完全ガイド】誰でも10分!WordPressブログの始め方
アフィリエイトブログを始めるなら「お名前.com」
「お名前.com」は、国内No.1のドメイン登録サービス。独自ドメインと合わせて、WordPressの自動インストールに対応したレンタルサーバーも利用できます。WordPressや独自ドメインを一度も使ったことのない人でも、スムーズに始められるはず。
アフィリエイトに挑戦してみようと考えている方は、以下のリンクから、ぜひご利用ください!




