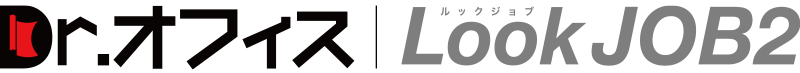裁量労働制とは?概要や注意点、勤怠管理システムの活用方法を解説

Check!
- 裁量労働制には企画業務型と専門業務型の2種類があり、決められた仕事のみ適用される
- 裁量労働制の勤怠管理では、休日・深夜労働における割増賃金の計算や事前承認が重要
- 労働時間を正確に把握する必要がある裁量労働制には勤怠管理システムがおすすめ
裁量労働制は働く時間やタイミングを自分で決められますが、だからこそ従業員一人ひとりが健康に働き続けるための適切な勤怠管理が必要です。この記事では、裁量労働制の細かな違いや勤怠管理の注意点、導入するための条件などについて詳しく解説していきます。
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
裁量労働における勤怠管理の注意ポイント

裁量労働制は支払う賃金が変動しづらいため、勤怠管理は比較的簡単と言えるでしょう。しかし、注意が必要な点もいくつかあります。ここでは、裁量労働制における勤怠管理の注意点を解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
裁量労働制における勤怠管理の注意点
労働時間を正確に把握する
2019年に労働基準法が改正されたことで36協定も内容が変わり、健康福祉確保措置として労働時間の正確な把握が必要となりました。
企業は、労働基準法で定められた限度時間(月45時間・年360時間)より長く労働する従業員に対して、産業医の指導や休暇の取得、深夜労働の回数制限を行うことが義務付けられています。
裁量労働制の従業員においても適用されるため、労働時間の変動がなくても実労働時間は正確に把握しておくことが必要です。
休日・深夜労働の割増賃金を計算する
裁量労働制の従業員でも、休日出勤や深夜労働には手当を支払うことが必要です。また、賃金面に限らず従業員の健康面にも配慮しなければなりません。そのため、裁量労働制においても、みなし労働以外の労働時間を計算しておくことが求められます。
休日・深夜労働を事前承認制にする
休日出勤や深夜労働は事前承認制にすることで、労働時間の把握がしやすくなります。割増賃金の計算や働きすぎている従業員の把握は、人事管理の中でも手間がかかります。事前承認制にすることで、時間外労働の実態がわかりやすくなるでしょう。
そもそも裁量労働制とは

裁量労働制とは、企業と労働者の間であらかじめ契約した時間を労働時間とみなし、その時間分を賃金として支払う制度です。
裁量労働制の特徴は、定められた労働時間を上回っても下回っても、同じ賃金が支払われるということです。例えば労働時間が8時間とされている場合、5時間働いても10時間働いても、同じ賃金が支払われます。
労働時間が一定になることで労務管理の負担が減ったり、働き方の自由度から従業員の満足度が高まるというメリットがあります。一方で、裁量労働制を導入する際には労使委員会の審議など複雑な手続きが必要で、ややハードルが高いです。
企画業務型と専門業務型の違いについて

裁量労働制には、企画業務型と専門業務型があり、対象の職種や導入時の手続き方法に違いがあります。ここでは、それぞれの特徴や該当する業種を詳しく説明します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
企画業務型と専門業務型の違いについて
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、企画や調査、分析など企業の中核を担う職種が対象となります。専門業務型のように職種は定められていませんが、業務の遂行の大部分を労働者の裁量に委ねる業務が該当します。
企画業務型裁量労働制の導入には、労使委員会の5分の4以上の多数の議決を得たうえで、定められた事項の決議内容を管轄の労働基準監督署に提出することが必要です。6ヶ月に1回の定例報告や、有効期間の修了ごとに労働者の個別の同意が求められます。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、デザイナーやコピーライターのようなクリエイティブな仕事や弁護士、会計士などの士業を含めた19の職種が該当します。業務の性質上、遂行するための指示や時間配分が困難な業種とされます。
専門業務型裁量労働制の導入にあたって、労使協定で必要な7つの次項を定めて、管轄の労働基準監督署に提出することが必要です。また、労使協定については従業員に周知されなければなりません。
裁量労働制とフレックスタイム制・高度プロフェショナル制度との違い

以下では裁量労働制と混同されやすい雇用形態について解説します。裁量労働制を正しく理解するために、それぞれ制度との違いを明確にし、整理しましょう。
| 特徴 | 裁量労働制との違い | |
| フレックスタイム制 | 始業・就業時間を自由に決めて働ける | 実労働を元にした賃金支払い所定労働時間は1日8時間・週40時間以内 |
| 高度プロフェッショナル制度 | 特定高度専門業務成果型労働制 | 年収要件がある休日・深夜労働の割増賃金がなし |
| 事業場外みなし労働時間制 | 条件下の「特定の時間」を労働したとみなすことができる制度 | ①対象の従業員に具体的な指揮監督が及ばない ②労働時間の算定が困難いずれをも満たす場合のみ |
裁量労働制を導入するための条件

裁量労働制は企業と労働者の間で労使協定を結び、管轄の労働基準監督署に届け出を行う必要があります。労使協定を結ぶ際には労働組合の代表に合意を得ることが求められます。
裁量労働制に認められるのは、専門性ゆえに労働者の能力にゆだねたほうが効率的に業務が進む職種で、専門業務型においては明確に職種が定められています。
裁量労働制の適切な管理には勤怠管理システムがおすすめ

裁量労働制を適切に管理するためには、勤怠管理システムがおすすめです。自社に所属する様々な働き方の従業員の勤怠管理を、一括で管理できます。
裁量労働制においては従業員がみなし労働時間を超えて働いてる場合にアラートが表示される機能もあるため、労働時間の管理がしやすいです。
特に警備業には適した勤怠管理システムが数多くあるため、様々なサービスを比較検討することが大切です。

勤怠管理システムとは?機能やメリット・デメリット、導入手順も解説
勤怠管理システムは、従業員の出退勤の時間や労働時間を適切に管理できるシステムです。給与計算など他システムとも連携でき、業務の効率化や不正打刻の防止にも役立ちます。本記事では、勤怠管理システムの機能やメリット・デメリット、選び方などを解説しています。
裁量労働制を導入する場合の勤怠管理システムの選定ポイント
勤怠管理システムは、従業員の出退勤を効率的に管理するためのシステムです。裁量労働制を導入する場合は、システムが法令遵守に対応できるかを確認しましょう。
裁量労働制であっても、深夜労働や休日労働は割増賃金の対象となります。これらの時間を正確に把握し、適切に計算できるシステムが必要です。また、36協定で定められた時間外労働の上限規制も適用されるため、時間外労働時間を管理・制御する機能も求められます。
おすすめの勤怠管理システム3選
導入から運用定着までサポート!直感的な操作性で使いやすい「ジンジャー勤怠」
ここがおすすめ!
- 初期設定から定着まで電話・チャット・WEBなどでサポート
- 24時間365日お問い合わせ可能
- スマホアプリ対応で場所を問わず簡単に打刻ができる
- 月末の締め日に見直すだけで簡単に勤怠管理ができる
- 個人だけでなくチーム全体の勤怠管理ができる
ここが少し気になる…
- スマホアプリだと申請や修正画面がわかりにくい
-

⚫︎自社ではエクセル管理からデジタルアプリへの移行だったため出退勤管理の手間や集計ミスの軽減につながり大幅な効率アップができた。 ⚫︎スマホ連携ができることで、営業の直行時や在宅勤務時もリアルタイムで打刻ができるようになった。(後修正の手間が省けた)
-

jinjer勤怠を利用することによって、取り急ぎ問題となっていた「社内システムでは不可能な日付を跨いだ打刻」に関する問題が解決しました。 また、個人個人で日勤・夜勤がバラバラになっているシフト管理も、あらかじめスケジュールを登録できることにより解決しました。現場の責任者からも「シフト表を作る手間が省けた!」と大変好評でした。 労務部の立場としても、無理なシフトになっていないかの連携がリアルタイムにできることは大きなメリットでした。
-

出勤、退勤時にボタンを押して完結することだけでなく、ボタンを押し忘れても簡単に出退勤の入力ができます。振休や有給消化の申請に関してもシンプルでわかりやすいです。通常パソコンから申請をしていますが、アプリも使いやすいです。
小規模や中小企業の人事労務をカバーするなら「freee勤怠管理Plus」

ここがおすすめ!
- 登録人数無制限の定額制勤怠管理システム
- 退社した従業員のアカウントも削除する必要がなく、永久に保持できる
- 雇用形態や従業員数が多い飲食店や、従業員の入れ替わりが多い医療・介護業界にもおすすめ
- 導入時や導入後のサポートが丁寧
- 「奉行シリーズ(OBC)」との連携が可能
ここが少し気になる…
- 導入後1年間は途中解約ができない
- マニュアルやQ&Aが充実しておらず担当者への問い合わせが必要になる
¥0で始めるクラウド勤怠管理システム「スマレジ・タイムカード」
ここがおすすめ!
- 従業員30名までなら無料で使える
- 無料プランを含む4種類のプランで、自社に合わせて最適なプランを選べる
- 笑顔打刻やGPS機能など豊富な打刻方法
- 他事業所へのヘルプ出勤やシフト外出勤などの臨時の勤怠にも対応
ここが少し気になる…
- 対応端末がiOSアプリのみでAndroidには対応していない
-

打刻の際に撮った写真を確認し「今日もいい笑顔だね!」「今日は少し元気ない?」など、遠方ながらも会話のきっかけになりました。また、代わりに打刻するなどの不正も防止できたので助かりました。
-

勤怠の不正ができなくなった事です。 以前は一部のスタッフが、タイムカードの代打ちをしていたり、不正が多かったです。 (残業代をつけるため、残っている別のスタッフに押してもらっていたり、遅刻をしそうな時に電話やメールで『押しといて!』と、する事が多かったので。) 別の部署とも統合することで、当日の出勤一覧で写真が見れるので誰が来てるのか別部署の出勤状況も分かるので良いです。
-

タイムカードを月末に、手作業で勤怠管理する手間がなくなりました。勤怠記録ミスの確認も今までは時間がかかっていましたがリアルタイムで編集できるためミスも減ったように思います。
まとめ

裁量労働制は、企業と労働者の間で労働時間を取り決め、その時間分の賃金を支払う制度です。企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制があり、該当する職種や導入方法、継続方法に違いがあります。
似たような制度にフレックスタイム制がありますが、フレックスタイム制は労働時間より長く働くと残業代が発生することが大きな違いです。
裁量労働制は労働時間のみの賃金を支払うとは言え、休日や深夜の労働には手当を支給しなければなりません。また、従業員の健康状態にも関わるため、実労働時間を正確に把握することは必要不可欠です。
様々な働き方に柔軟に対応できる勤怠管理システムは、裁量労働制とも相性が良いです。自社の働き方に合わせて、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。
勤怠管理をさらに効率化!関連記事はこちら

勤怠管理システムおすすめ16選(全24選)を比較!中小企業向けや無料で使えるものも
従業員の出退勤時間を自動集計し、労働時間の管理や給与計算に役立つ勤怠管理システム。本記事ではおすすめの勤怠管理システムを選び方とともに徹底比較してご紹介。小規模法人や中小企業向け・無料で使える製品など比較一覧表で紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事に興味を持った方におすすめ